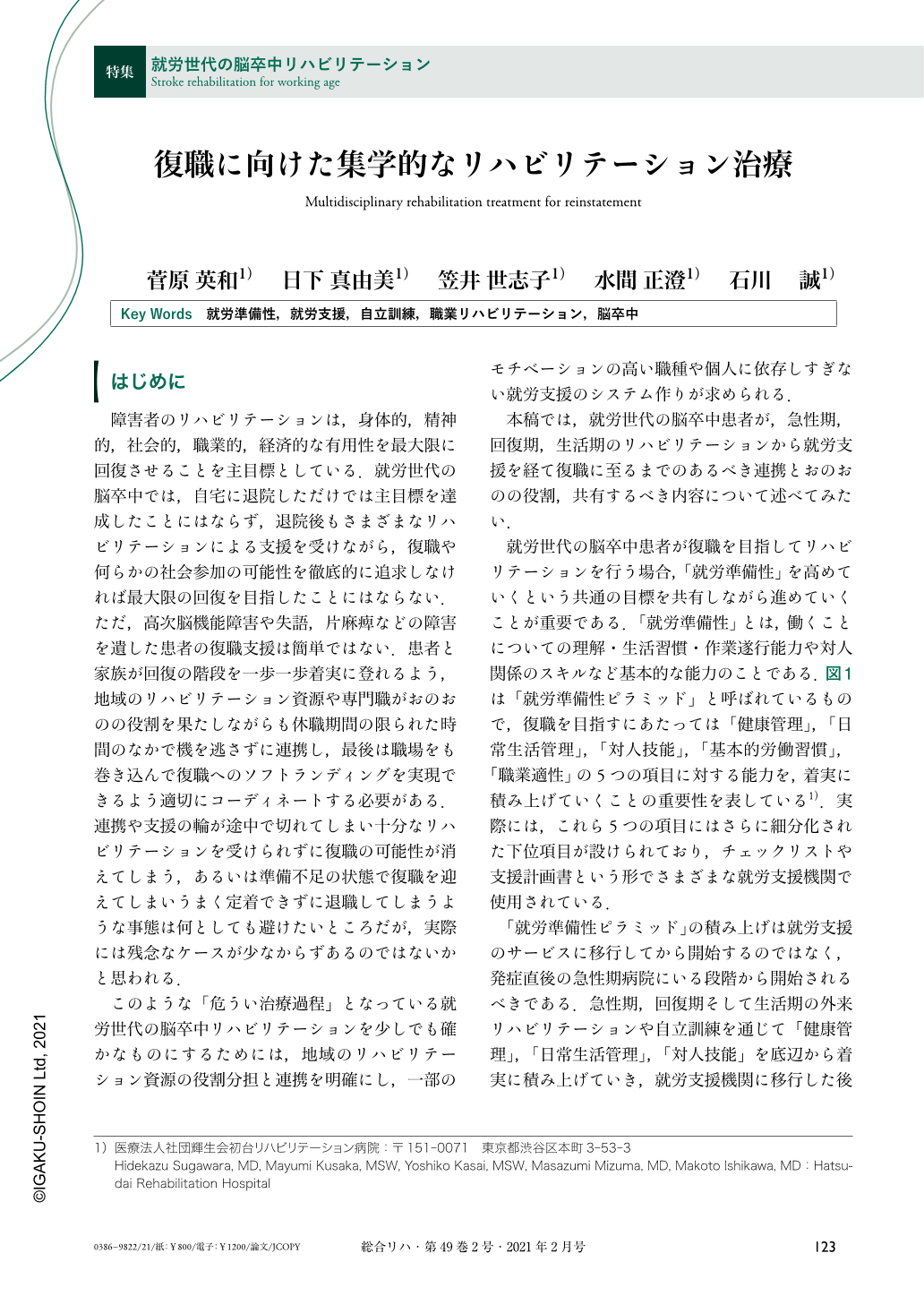1 0 0 0 幕末中央政局における朔平門外の変--その背景と影響について
- 著者
- 町田 明広
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.713, pp.76-92, 2007-10
- 著者
- 遠藤 潤
- 出版者
- 國學院大學研究開発推進機構伝統文化リサーチセンター
- 雑誌
- 國學院大學伝統文化リサーチセンター研究紀要 (ISSN:18836682)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.163-172, 2009-03
1 0 0 0 駿台史學
- 著者
- 明治大學史學地理學會 [編集]
- 出版者
- 明治大學史學地理學會
- 巻号頁・発行日
- 1951
1 0 0 0 IR 8世紀後半日本の対外関係に関する考察--渤海との関係を中心に
- 著者
- 具 蘭憙 中野 高行
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.2, pp.177-200, 2007-12
一 はじめに二 天平宝字~神護景雲年間(七五七~七六九年)三 宝亀年間(七七〇~七八〇)四 延暦年間(七八二~八〇五)五 おわりに論文
1 0 0 0 IR 茂吉の観音さま--歌人 永井ふさ子
- 著者
- 玉井 崇夫
- 出版者
- 明治大学文芸研究会
- 雑誌
- 文芸研究 (ISSN:03895882)
- 巻号頁・発行日
- no.96, pp.119-126, 2005
1 0 0 0 OA 胆汁のpHに及ぼす諸種条件による実験的研究
- 著者
- 神野 正一
- 出版者
- 金沢大学十全医学会
- 雑誌
- 金沢大学十全医学会雑誌 (ISSN:00227226)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.1177-1242, 1958-06-25
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1934年01月08日, 1934-01-08
1 0 0 0 IR 書評 ドミニク・レステル著『肉食の哲学』
1 0 0 0 IR 著作目録(田中煕巳)
1 0 0 0 IR アファナーシエフにおけるзмейをめぐって
- 著者
- 水上 則子
- 出版者
- 国際地域研究学会
- 雑誌
- 国際地域研究論集 (ISSN:21855889)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.53-63, 2015
1 0 0 0 IR 研究生活を回顧して--人との絆に支えられて
- 著者
- 梅本 吉彦
- 出版者
- 専修大学法学研究所
- 雑誌
- 専修大学法学研究所所報 (ISSN:09137165)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.1-27, 2011-03-10
- 著者
- 麻川 武雄 榎本 恵一 高野 正子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.2, pp.59-68, 1993
- 被引用文献数
- 1
Adenylate cyclase is a key enzyme that couples with both the stimulatory and inhibitory G proteins (G<SUB>s</SUB> and G<SUB>i</SUB>). The cyclase has been purified and shown to be a glycoprotein of molecular weight 115, 000-180, 000. Cloning of cDNAs for adenylate cyclase showed that the cyclase is a member of a large family consisting of a variety of subtypes of the enzyme. These subtypes show different responses to calmodulin and G protein βγ subunits, and their distributions in tissues and organs are also different. This suggests that each subtype is involved in a particular physiological function. The general structure of adenylate cyclase is composed of two cytoplasmic domains and two membrane-spanning domains, each of which contains 6 transmembrane spans (12 spans in a molecule). The amino acid sequence of each cytoplasmic domain, which is thought to contain a nucleotide (ATP) binding site, is well-conserved among the various subtypes. This review also focuses on the regulation of adenylate cyclase activity by G protein subunits, particularly on several models for adenylate cyclase inhibition by G<SUB>i</SUB>. As one of these mechanisms, direct inhibition of adenylate cyclase by the βγ subunits recently demonstrated by us will be discussed.
1 0 0 0 IR 事務組織
- 著者
- 熊本大学60年史編纂委員会
- 出版者
- 熊本大学
- 雑誌
- 熊本大学六十年史
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.1158-1232, 2012-10-31
- 著者
- 麻川 武雄
- 出版者
- 診療社
- 雑誌
- 診療 (ISSN:03710092)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.1339-1346, 1970-06
1 0 0 0 IR III. 主権者教育の一環としての模擬選挙の実施II
- 著者
- 隅田 久文 SUMIDA H.
- 出版者
- 名古屋大学教育学部附属中・高等学校
- 雑誌
- 名古屋大学教育学部附属中高等学校紀要 (ISSN:03874761)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.168-172, 2018-03-01
選挙権年齢が満18歳以上へ引き下げられたことにより、学校現場における主権者教育のより一層の充実が求められているが、本校では、昨年度の第24回参議院議員通常選挙における模擬選挙の成果を踏まえ、4月の名古屋市長選挙に合わせて模擬選挙を計画し、実行した。第3部 教科研究・特別研究
1 0 0 0 「あまちゃん」「半沢直樹」のヒット術 常識覆す5つの新法則
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1708, pp.120-123, 2013-09-23
テレビドラマを熱心に見る人たちは女性だ。そのためドラマ制作者は彼女たちの興味を引くように工夫する。だが、「あまちゃん」と「半沢直樹」が視聴率を伸ばした背景には、女性ではなく、中高年男性の支持があった。
1 0 0 0 復職に向けた集学的なリハビリテーション治療
はじめに 障害者のリハビリテーションは,身体的,精神的,社会的,職業的,経済的な有用性を最大限に回復させることを主目標としている.就労世代の脳卒中では,自宅に退院しただけでは主目標を達成したことにはならず,退院後もさまざまなリハビリテーションによる支援を受けながら,復職や何らかの社会参加の可能性を徹底的に追求しなければ最大限の回復を目指したことにはならない.ただ,高次脳機能障害や失語,片麻痺などの障害を遺した患者の復職支援は簡単ではない.患者と家族が回復の階段を一歩一歩着実に登れるよう,地域のリハビリテーション資源や専門職がおのおのの役割を果たしながらも休職期間の限られた時間のなかで機を逃さずに連携し,最後は職場をも巻き込んで復職へのソフトランディングを実現できるよう適切にコーディネートする必要がある.連携や支援の輪が途中で切れてしまい十分なリハビリテーションを受けられずに復職の可能性が消えてしまう,あるいは準備不足の状態で復職を迎えてしまいうまく定着できずに退職してしまうような事態は何としても避けたいところだが,実際には残念なケースが少なからずあるのではないかと思われる. このような「危うい治療過程」となっている就労世代の脳卒中リハビリテーションを少しでも確かなものにするためには,地域のリハビリテーション資源の役割分担と連携を明確にし,一部のモチベーションの高い職種や個人に依存しすぎない就労支援のシステム作りが求められる. 本稿では,就労世代の脳卒中患者が,急性期,回復期,生活期のリハビリテーションから就労支援を経て復職に至るまでのあるべき連携とおのおのの役割,共有するべき内容について述べてみたい. 就労世代の脳卒中患者が復職を目指してリハビリテーションを行う場合,「就労準備性」を高めていくという共通の目標を共有しながら進めていくことが重要である.「就労準備性」とは,働くことについての理解・生活習慣・作業遂行能力や対人関係のスキルなど基本的な能力のことである.図1は「就労準備性ピラミッド」と呼ばれているもので,復職を目指すにあたっては「健康管理」,「日常生活管理」,「対人技能」,「基本的労働習慣」,「職業適性」の5つの項目に対する能力を,着実に積み上げていくことの重要性を表している1).実際には,これら5つの項目にはさらに細分化された下位項目が設けられており,チェックリストや支援計画書という形でさまざまな就労支援機関で使用されている. 「就労準備性ピラミッド」の積み上げは就労支援のサービスに移行してから開始するのではなく,発症直後の急性期病院にいる段階から開始されるべきである.急性期,回復期そして生活期の外来リハビリテーションや自立訓練を通じて「健康管理」,「日常生活管理」,「対人技能」を底辺から着実に積み上げていき,就労支援機関に移行した後は「基本的労働習慣」,「職業適性」の仕上げに専念できるようにしておくのが理想的である.「健康管理」,「日常生活管理」などの基礎が脆弱であると,就労支援へスムーズに移行できなくなるだけでなく,何とか復職できたとしても長期的にはさまざまな部分で綻びが出て働き続けることが難しくなってしまう. 図2は,回復期リハビリテーション病棟に入院するような中等度〜重度の障害を有する就労世代の脳卒中を想定して,発症から復職までにかかわるべき主なリハビリテーション資源と専門職を,急性期,回復期,生活安定期,就労準備期,就労定着期の5つの時期に分けて示したものである.これらの資源は施設面でも制度面でもバラバラに存在しているが,復職を支援する統一体として要所要所で手を結び合って機能していく必要がある.
1 0 0 0 OA 糞便性腸閉塞に対する緊急開腹手術を必要とした消化管アレルギー疑いの1例
- 著者
- 仲谷 健吾 飯沼 泰史 平山 裕 靏久 士保利
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会
- 雑誌
- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.5, pp.1098-1102, 2016-08-20 (Released:2016-08-20)
- 参考文献数
- 17
症例は1 歳女児.急性大腸閉塞の診断で当科に紹介され,腹部膨満と代償性ショックを呈していた.腹部CT では中等量の腹水,直腸とS 状結腸の壁肥厚,下行結腸から回腸の拡張,及びS 状結腸下行結腸移行部の便塞栓を認めた.病歴から消化管アレルギーを疑ったため,開腹手術を回避するために全身麻酔下に大腸内視鏡を行ったが腸閉塞解除は不可能であり,最終的に開腹手術を施行した.S 状結腸下行結腸移行部の腸管壁を切開し便を摘出後,内視鏡を併用して口側腸管の減圧を行った.なお,術中に採取した結腸壁には好酸球浸潤を認め,消化管アレルギーが強く疑われた.経過は良好で術後18 日目に退院した.その3 か月後に再度同原因による腸閉塞を発症したが,保存的治療で容易に改善した.消化管アレルギーの多くは小児科で対応されるが,小児外科医が初期対応を行うこともあり,本症例のような病態に対しては開腹手術が必要になる場合があると考えられた.