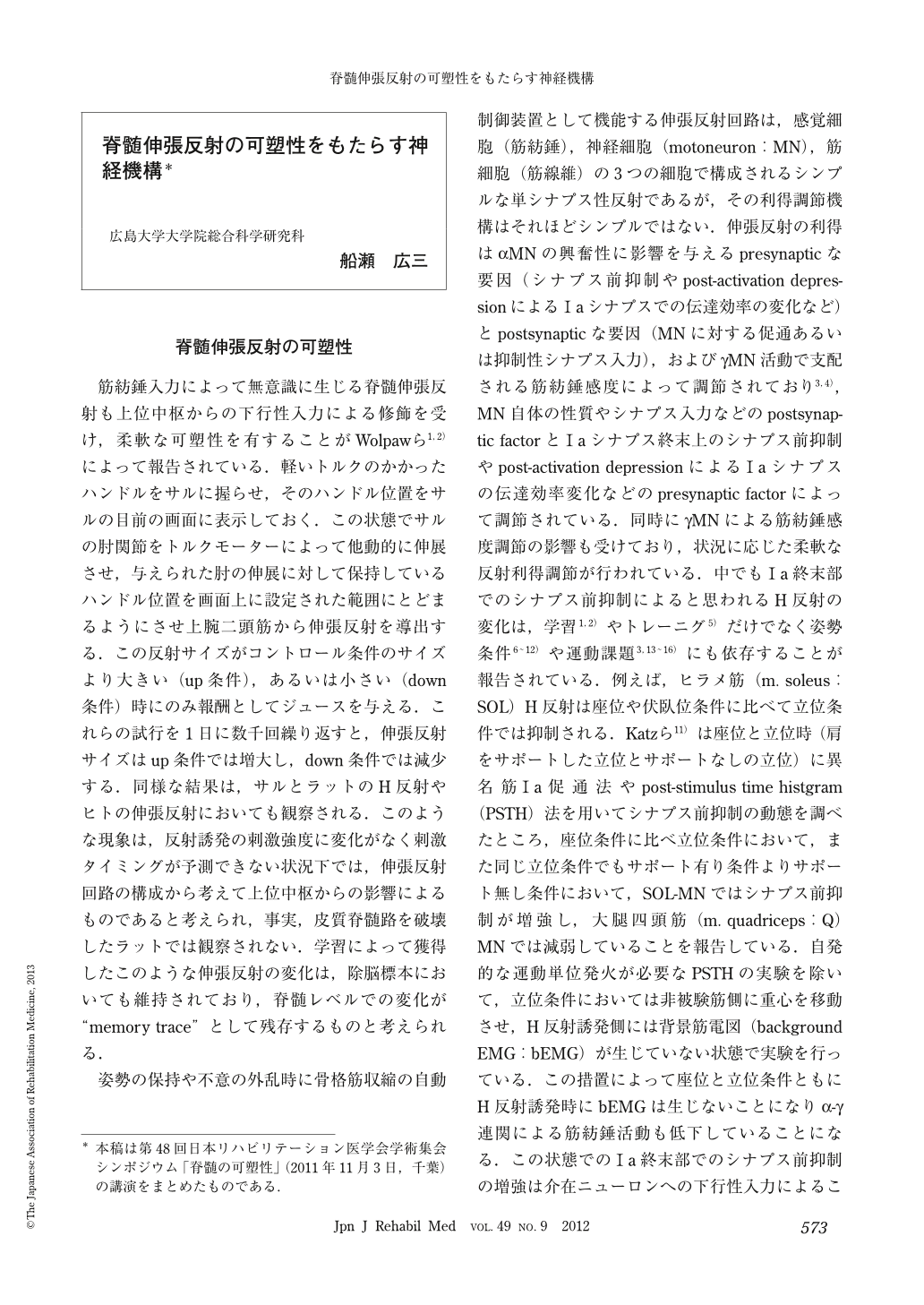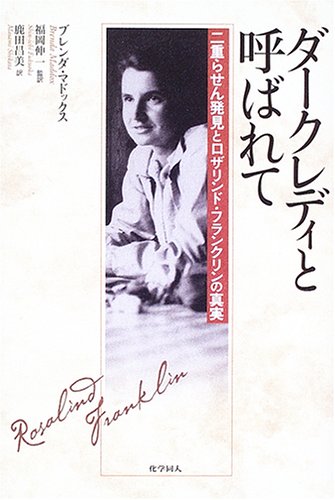1 0 0 0 都市の位相(1)
- 著者
- 水口 憲人
- 出版者
- 立命館大学
- 雑誌
- 政策科学 (ISSN:09194851)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.213-235, 2004-03
1 0 0 0 OA 宇宙ロボットのターゲット捕捉時の衝撃力評価
- 著者
- 吉河 章二 山田 克彦
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.242-248, 1995-03-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 2
Capturing a target by a space robot in space inevitably causes impact forces on the contact points. This paper focuses on such a short contact period and proposes a new approach to model the contact dynamics. It derives equations to estimate the impulse of the contact forces considering the effects of the joint stiffness represented by the joint servo. Using the derived equations, it is shown that the impulse of the contact forces increases with the joint stiffness regardless of its posture. Numerical simulations and hardware experiments are given to validate the proposed approach.
- 著者
- 小野 盛司 吉野 守
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, pp.4Rin107, 2019
<p>将来AI/ロボットが大半の雇用を奪ってしまうと言われている。そのときはベーシックインカムという方法が提案されているが、巨額の財源が必要になる問題と労働意欲の喪失が欠点とされている。その両者を解決するために解放主義社会を提案する。</p>
1 0 0 0 超微小粒子PM0.1の呼吸器疾患へ与える影響の解析
粒径が0.1µm以下のナノ粒子(PM0.1)は肺胞まで到達し、その影響は全身へと波及することから、健康への影響が懸念されている。しかし、PM0.1が喘息の増悪や難治化に及ぼす影響は分かっておらず、本研究ではそれを明らかにする。まず、粒子状物質の分級サンプリングが可能なナノサンプラーⅡ(Kanomax)を用い、2019年2月7日から2月12日の5日間、東京都新宿区において計640.5µgのPM0.1を回収した。次に、マウス喘息モデルの作成およびPM0.1の経鼻投与実験を行った。すなわち、OVA(卵白アルブミン)10µg/匹と水酸化アルミニウム1mg/匹をDay1とDay8に腹腔注射してOVAに感作させたマウスに、PM0.1 10µg/匹とOVA 200µg/匹をDay14,15,16に経鼻投与し、Day17に気管支肺胞洗浄液を採取した(PM0.1群)。OVA群、PBS群では、Day14,15,16にOVAのみ、ないしPBSのみを投与した。気道炎症の評価として気管支肺胞洗浄液の総細胞数、好酸球数の解析をしたところ、PM0.1群およびOVA群ではPBS群に比して有意な上昇を認めたが、PM0.1群とOVA群の間に差を認めなかった。また、上記のPM0.1群とOVA群に対して、Day14, 15, 16の経鼻投与1時間前にステロイド(デキサメタゾン20µg/匹)を腹腔注射する治療実験も行った。ステロイド投与により、PM0.1群、OVA群ともに総細胞数、好酸球数の減少を認めたが、ステロイドへの反応性は2群間で有意な差を認めなかった。上記の結果、PM0.1と喘息の増悪や難治化には関係性がみられない可能性があるが、粒子径の違いにより気道炎症の程度に差が生じる可能性があり、引き続きPM2.5やPM10といった粒径のより大きな物質との比較検討を行う予定である。
1 0 0 0 病院祭4年間の歩み
- 著者
- 畑田 美恵 下村 一寛
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp.155, 2004
【はじめに】<BR> 当院は198床の単科の精神科病院である。昭和41年に開設され、平成13年4月に築35年の古い卍型の旧病棟を取り壊し、誰もが足を踏み入れやすい新築の病棟に建て変わった。著者はこの13年4月に入職し、今年で4年目になる。1年目の秋、これまで行っていた病院行事の運動会の開催が患者層の高齢化により困難となり、代わりに文化的な行事として病院祭を開催することになった。地域の方々に精神科病院を開放し、精神医療への偏見の軽減を図ることを目的として作業療法士が中心となって作業活動の季節行事の一環として開始した。現在ではその枠を越えた病院行事となり、年に2回開催し今春で6回目を迎える。今回この発表の場を借りてこれまでの経過を振り返り、今後の課題等を報告する。<BR>【経過】<BR>[第1回カメリア祭(平成13年10月)および第2回カメリア祭(平成14年5月)]<BR>行事内容:1.イベントとしては、地域で活躍されている太鼓のグループ、パントマイムショーの実演。2.院内各病棟・部署からバザーの出店および作業療法活動の作品の展示・販売を行った。実施時間は午前中のみ行い参加者は院外参加者のほとんどが患者の家族を占め70名程度であった。<BR>[第3回カメリア祭(平成14年10月)]<BR> 第1回・第2回は作業療法士と病棟の作業レクリエーション委員が中心に行なったが、今回から各部署より委員を選出し実行委員会という形で運営した。パフォーマンス・バザー・展示・広報・学術という各グループを作り、実行委員長と各グループのリーダーは作業療法士が行った。実施時間は1日で午前中に外部講師によるシンポジウムを行い、午後からパフォーマンスを行った。行事内容:1.地域の保育園児の太鼓、2.高校生のブラスバンド演奏、3.院内患者様のカラオケ大会も行った。<BR> 各グループで仕事を分担したことで、広報の幅も広がり、地域へのポスター掲示、市政だより、無料広告への掲載依頼等も行い、一般の方の来場は約300名であった。<BR>[第4回カメリア祭(平成15年5月)]<BR> これまで正面玄関前の広場を会場として行ったが、この広場を一般の方にフリーマーケットの会場として開放し、祭りの主会場を施設内の庭園に移した。大きなステージを市から借りパフォーマンスのプログラムも午前、午後を通して行った。出演者も地域の方々に多数出演していただき、これにより一気に地域の方の来場が増え、約800名になった。また院内から出していたバザーも地域活動所や施設に依頼し一般の飲食店の方の出店もあった。<BR>[第5回カメリア祭(平成15年10月)]<BR> 第4回と同様の形式に加えて、前夜祭として長崎の音楽団による演奏を行った。パフォーマンス部門では各病棟からの患者の出し物が増え、また患者のステージに上がる場面や行事に参加する頻度が増えた。展示では作品展示に加えて陶芸などの作業活動体験コーナーを設けた。一般の方の参加も出店者、出演者を含め1000名になった。<BR>[第6回カメリア祭(平成16年5月開催予定)]<BR> 今回は前日の前夜祭に加え、病院外の施設を利用し特別講演としてパネルディスカッションを行う予定である。広報はポスター掲示の範囲も広げ、TVCM等を利用することによって多くの方に参加していただけるようさらに企画を立案している。<BR>【考察】<BR> 著者が入職した平成13年からカメリア祭を開催して今年で4年目になる。これまでの経過を振り返ると当初の患者の家族中心の参加から、現在では回を重ねるごとに一般の来場者が増えており地域の方々がより身近に精神科病院を感じていただけるような地域に開かれたお祭りに移行してきていると感じている。パフォーマンスの出演やフリーマーケット、バザーの出店の参加を地域の方々に呼びかけることで患者と地域の方が時間を共にする場作りにもなったことが考えられる。来場された一般の方のアンケートによると、新病棟になったことで施設面での偏見は少ない印象もある。しかし、精神科の病気に対する偏見が減ってきているかということに関してはわからないところが多い。患者の中には第4回開催の頃からカメリア祭を目標に継続した作品作りが行われるなどカメリア祭を楽しむものから一緒に参加し作っていくものとの意識の変化が見え始めた。現在実行委員は職員で編成しているが、患者も企画の段階から参加する方法を取り入れ、ともに作っていくカメリア祭を目指したい。そして祭りの中で患者と一般の方が直接にふれあう機会を増やす内容などの検討が必要と考える。当日は終了している第6回および第7回のカメリア祭の報告も含めて発表する。
1 0 0 0 脊髄伸張反射の可塑性をもたらす神経機構
- 著者
- 船瀬 広三
- 出版者
- 日本リハビリテーション医学会
- 巻号頁・発行日
- pp.573-578, 2012-09-18
脊髄伸張反射の可塑性 筋紡錘入力によって無意識に生じる脊髄伸張反射も上位中枢からの下行性入力による修飾を受け,柔軟な可塑性を有することがWolpawら1,2)によって報告されている.軽いトルクのかかったハンドルをサルに握らせ,そのハンドル位置をサルの目前の画面に表示しておく.この状態でサルの肘関節をトルクモーターによって他動的に伸展させ,与えられた肘の伸展に対して保持しているハンドル位置を画面上に設定された範囲にとどまるようにさせ上腕二頭筋から伸張反射を導出する.この反射サイズがコントロール条件のサイズより大きい(up条件),あるいは小さい(down条件)時にのみ報酬としてジュースを与える.これらの試行を1日に数千回繰り返すと,伸張反射サイズはup条件では増大し,down条件では減少する.同様な結果は,サルとラットのH反射やヒトの伸張反射においても観察される.このような現象は,反射誘発の刺激強度に変化がなく刺激タイミングが予測できない状況下では,伸張反射回路の構成から考えて上位中枢からの影響によるものであると考えられ,事実,皮質脊髄路を破壊したラットでは観察されない.学習によって獲得したこのような伸張反射の変化は,除脳標本においても維持されており,脊髄レベルでの変化が“memory trace”として残存するものと考えられる. 姿勢の保持や不意の外乱時に骨格筋収縮の自動制御装置として機能する伸張反射回路は,感覚細胞(筋紡錘),神経細胞(motoneuron:MN),筋細胞(筋線維)の3つの細胞で構成されるシンプルな単シナプス性反射であるが,その利得調節機構はそれほどシンプルではない.伸張反射の利得はαMNの興奮性に影響を与えるpresynapticな要因(シナプス前抑制やpost-activation depressionによるⅠaシナプスでの伝達効率の変化など)とpostsynapticな要因(MNに対する促通あるいは抑制性シナプス入力),およびγMN活動で支配される筋紡錘感度によって調節されており3,4),MN自体の性質やシナプス入力などのpostsynaptic factorとⅠaシナプス終末上のシナプス前抑制やpost-activation depressionによるⅠaシナプスの伝達効率変化などのpresynaptic factorによって調節されている.同時にγMNによる筋紡錘感度調節の影響も受けており,状況に応じた柔軟な反射利得調節が行われている.中でもⅠa終末部でのシナプス前抑制によると思われるH反射の変化は,学習1,2)やトレーニグ5)だけでなく姿勢条件6~12)や運動課題3,13~16)にも依存することが報告されている.例えば,ヒラメ筋(m. soleus:SOL)H反射は座位や伏臥位条件に比べて立位条件では抑制される.Katzら11)は座位と立位時(肩をサポートした立位とサポートなしの立位)に異名筋Ⅰa促通法やpost-stimulus time histgram(PSTH)法を用いてシナプス前抑制の動態を調べたところ,座位条件に比べ立位条件において,また同じ立位条件でもサポート有り条件よりサポート無し条件において,SOL-MNではシナプス前抑制が増強し,大腿四頭筋(m. quadriceps:Q)MNでは減弱していることを報告している.自発的な運動単位発火が必要なPSTHの実験を除いて,立位条件においては非被験筋側に重心を移動させ,H反射誘発側には背景筋電図(background EMG:bEMG)が生じていない状態で実験を行っている.この措置によって座位と立位条件ともにH反射誘発時にbEMGは生じないことになりα-γ連関による筋紡錘活動も低下していることになる.この状態でのⅠa終末部でのシナプス前抑制の増強は介在ニューロンへの下行性入力によることが示唆される.興味深いことにSOL-MNとQ-MNとでシナプス前抑制が逆の効果を示しており,足関節伸筋では伸張反射利得を減弱させ関節可動性を増して下行性調節を行いやすくし,膝関節伸筋では逆に伸張反射利得を増強して膝関節を固定する方向に作用していることが考えられる.また,同じ立位姿勢でも,通常の歩行時より走行時13,14,16),より難易度が高い線上歩行時ではSOL-bEMGとH反射の関係を示す回帰直線の傾きが低くなることが報告されている3).この回帰直線の傾きの低下は,随意運動時のαMN活動が同程度であってもⅠaシナプスを介したH反射誘発時に活動するαMN数は異なっていることを示しており,Ⅰa終末部のシナプス前抑制が増強していることを示唆している.
1 0 0 0 OA 特殊繊維塗料を用いた組積造構造物の耐震補強に関する実験的研究
- 著者
- 山本 憲二郎 沼田 宗純 目黒 公郎
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.561-564, 2014-11-01 (Released:2015-01-15)
- 参考文献数
- 2
世界の約6割もの人々が組積造構造物を住宅として使用している.組積造構造物の問題点は,地震に対する脆弱性が非常に高い点にあり,これまでに発生した地震による組積造構造物の崩壊で,世界中で多くの人的被害が出ている.組積造構造物の耐震性能を向上させるために,多くの技術的方法が開発されてきた.しかし,それらの方法は,実際の組積造構造物に適用する際,多くの時間と労力を必要とし,更に,多くの方法は新築の組積造構造物に対してのみ適用できる技術である.これらの問題は,技術を普及する上での妨げとなっている.そこで本研究では,既存・新築の組積造構造物の両方に適用でき,更にこれまでの方法と比較して,圧倒的に施工が簡単な耐震補強方法を提案する.この方法に使用する材料は,「SG-2000」というガラス繊維を混ぜ込むことにより強化された特殊繊維塗料である.本稿では,この材料の組積造構造物の耐震補強への適用可能性と効率的な塗布方法に関する実験的な検証結果を紹介する.
- 著者
- 美那川 雄一 Yuichi Minagawa
- 出版者
- 同志社大学文化学会
- 雑誌
- 文化學年報 = Bunkagaku-Nempo (Annual report of cultural studies) (ISSN:02881322)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.1-30, 2017-03-15
井上雅夫先生 退職記念論文集
1 0 0 0 OA Millonの人格障害構造仮説にかかわる10PesTに関する研究
- 著者
- 中澤 清 Kiyoshi Nakazawa
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.35-42, 2006-02-10
- 著者
- 鈴木 幹雄
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.197-212, 2011
本論稿では,J・イッテンの出身校,シュトゥットガルト芸術アカデミーでヘルツェル教授の下に学び,ナチズム崩壊後,シュトゥットガルト芸術アカデミー教授(1946-55年)となったW・バウマイスターの芸術教育と芸術教育観について基本的な輪郭を描こうと試みた。筆者の知る限りそれはわが国ではこれまで先行研究で解明されることのなかった領域で,バウハウス系譜の芸術教育学とは異なるもう一つの芸術教育観であった。バウマイスターは,ワイマール共和国の時代,フランクフルト市芸術学校の教師として招聘を受け(1927-33),1946年には,シュトットガルト芸術アカデミー装飾油彩画の教授として招聘された。そして1949年には,同アカデミーに改革提案を提出すると同時に,現代の造形表現理論と新しい時代の芸術教育学の基本的精神を若い世代に伝えようとした。それは,内的亡命に耐えてきた一老教授によって用意された,フランス,スイスと国境を接する南西ドイツの戦後芸術大学改革コンセプトであった。
1 0 0 0 ロザリンド・フランクリンとDNA : ぬすまれた栄光
- 著者
- アン・セイヤー [著] 深町真理子訳
- 出版者
- 草思社
- 巻号頁・発行日
- 1979
1 0 0 0 動的交通均衡配分理論の近年の進展
- 著者
- 和田 健太郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.5, pp.I_21-I_39, 2021 (Released:2021-04-20)
- 参考文献数
- 83
本稿では,動的交通均衡配分モデルの解析理論の近年の進展について解説する.渋滞の時空間進展と利用者行動の相互作用から生じる,複雑な交通ネットワーク流の見通しのよい解析を可能とする移動座標系アプローチに対象を限定し,車両を流体近似する伝統的なモデルと最近進展している粒子型のモデルを対比的に紹介する.その中で得られる,それぞれのモデルの特徴や関係,均衡解の数理特性に関する成果を踏まえ,双方の優位性を活かした今後の発展の方向性について述べる.
- 著者
- ブレンダ・マドックス [著] 鹿田昌美訳
- 出版者
- 化学同人
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 IR 分析的マルクス主義と置塩理論--リカード派マルクス主義から新古典派マルクス主義へ
- 著者
- 三土 修平
- 出版者
- 愛媛大学経済学会
- 雑誌
- 愛媛経済論集 (ISSN:09116095)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.1-18, 1999-03
1 0 0 0 戦後日本の階級構造:空想から科学への階級研究の発展
- 著者
- 橋本 健二
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.164-180, 1999
- 被引用文献数
- 3
戦後日本では, 大橋隆憲らを中心に階級構成研究が独自の発展を遂げたが, 彼らの研究は, 資本家階級と労働者階級への2極分解論や, 労働者階級=社会主義革命勢力という規定など, きわめて非現実的な想定に立っていたこと, また特定の政治的立場を前提とした政治主義性格のために, 階級研究に対する数多くの誤解を生みだし, このことが日本における階級研究を衰退させる結果をもたらしてしまった。いま必要なことは, 階級研究からこうした理論的・政治的バイアスを取り除き, これを社会科学的研究として再構築することである。理論的には, 1970年代半ば以降の, 構造主義的階級理論から分析的マルクス主義に至る階級研究の成果を生かしながら, フェミニズムの立場からの階級研究批判に答えうる階級構造図式と階級カテゴリーを確立することが求められる。実証的には, 社会階層研究の豊かな蓄積を模範としながら, 計量的な研究のスタイルを確立する必要がある。本稿はこうした階級研究の発展のための基礎作業である。<BR>以上の目的のため, 本稿はまず, 現代日本の階級構造を, 資本主義セクターと単純商品セクターの節合関係を前提として, 資本家階級・新中間階級・労働者階級・旧中間階級の4階級からなるものとして定式化し, さらに各職業の性格のジェンダー差を考慮して, 実証研究に適用可能な階級カテゴリーを構成する。次に, 階級構成の変化を概観するとともに世代間階級移動量の趨勢を検討し, 近年の日本では世代間階級移動への障壁が強まりつつあることを明らかにする。最後に, 階級所属と社会意識の関係を検討し, 階級所属が社会意識の形成に第一義的な重要性を持ち続けていることを明らかにする。
1 0 0 0 IR 分析的マルクス主義の社会システム論(3・完)
- 著者
- 松井 暁
- 出版者
- 富山大学経済学部
- 雑誌
- 富大経済論集 (ISSN:02863642)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.101-171, 1997-07
1 0 0 0 IR 分析的マルクス主義の社会システム論(2)
- 著者
- 松井 暁
- 出版者
- 富山大学経済学部
- 雑誌
- 富大経済論集 (ISSN:02863642)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.159-194, 1996-07
1 0 0 0 IR 分析的マルクス主義の社会システム論-1-
- 著者
- 松井 暁
- 出版者
- 富山大学経済学部
- 雑誌
- 富大経済論集 (ISSN:02863642)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.p353-383, 1995-11
1 0 0 0 IR 分析的マルクス主義への招待
- 著者
- 松井 暁
- 出版者
- 富山大学経済学部
- 雑誌
- 富大経済論集 (ISSN:02863642)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.p45-75, 1995-07