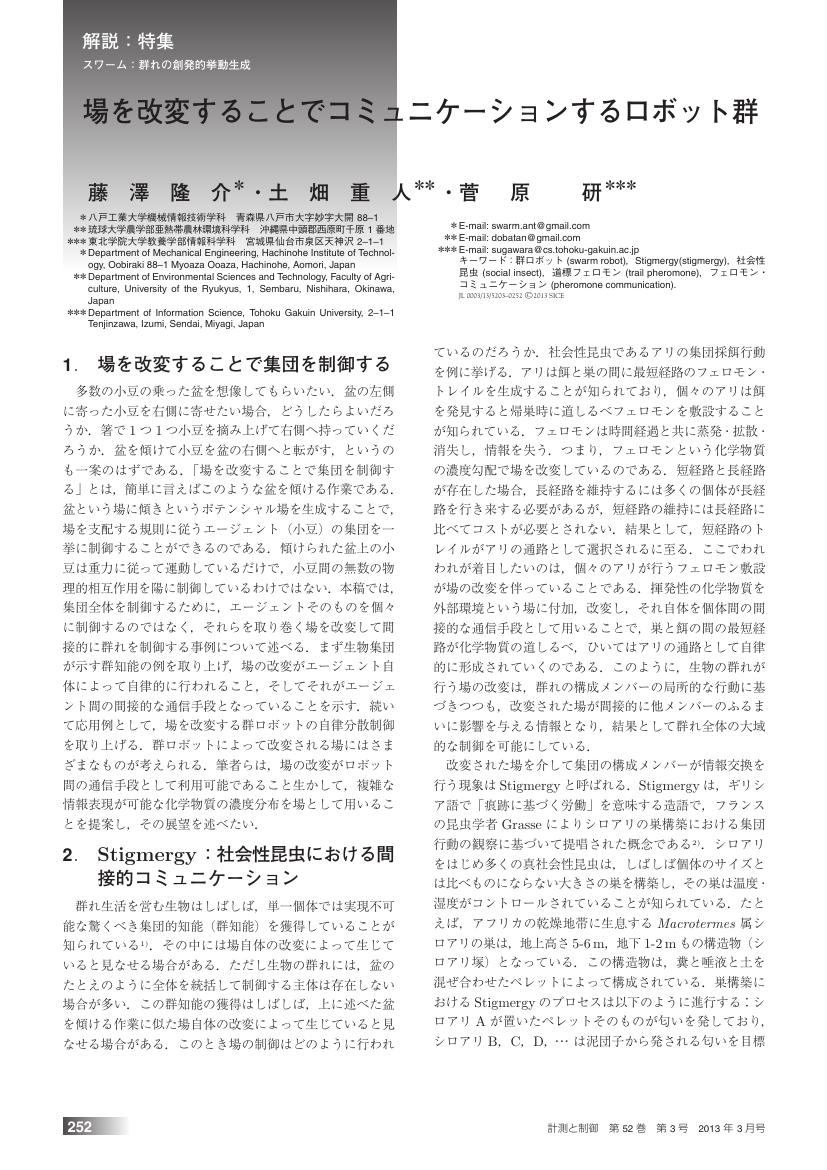1 0 0 0 OA 下肢筋の機能解剖と歩行
- 著者
- 安藤 徳彦
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.213-218, 1999-07-01 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
立脚相に股関節では大殿筋と大内転筋が伸展位を保持し, 中殿筋, 大殿筋上部, 大腿筋膜張筋が左右側方向の支持性を確保する. 膝関節は屈曲位で踵接地して床からの衝撃を吸収し, 体重を支える. この機能は大腿広筋が果たす. 踵接地期の足関節背屈筋群の強い収縮も衝撃吸収の意義が大きい. 全足底接地後にひらめ筋, 続いて腓腹筋の活動が足関節の底屈速度を制御する. 立脚相終期では大腿直筋が膝関節を伸展位に維持して股関節を屈曲させ, 下腿三頭筋が強く収縮して前足部を中心に下肢全体を前方に移行させる. 遊脚相に向けて股関節屈曲には腸腰筋, 長内転筋, 大腿直筋, 縫工筋, 薄筋が活動する. 大腿直筋は蹴り返し期に膝伸展位で股関節を屈曲させる. 縫工筋と薄筋は内・外転, 内・外旋中間位に保って股関節を屈曲させる. 遊脚相後半にハムストリングは股関節の屈曲と膝関節の伸展を制御するために活動する.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.999, pp.185-188, 1999-07-12
今年5月、横浜市中区のある老舗ホテルが71年におよぶ歴史の幕を静かに下ろした。観光名所として知られる山下公園や元町商店街からほど近い、新山下地区の「バンドホテル」だ。日本初のナイトクラブを開設したり、往年のヒット曲「よこはま・たそがれ」の歌詞に取り上げられたことなどで全国的にも名を馳せた。
1 0 0 0 ハワイの「日本の歌」とナイト・クラブ
- 著者
- 中原 ゆかり
- 出版者
- 日本ポピュラー音楽学会
- 雑誌
- ポピュラー音楽研究 (ISSN:13439251)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.35-44, 2004
本稿の目的は、1950年代はじめから1970年代後半までのハワイで日本のポピュラー音楽の演奏を行っていたナイト・クラブについて報告することにある。これらのナイト・クラブは、1950年代はじめから1960年前後までが数も多く、生演奏の他に日本舞踊やストリップ・ショー等もあり、ドアの外で客たちが並ぶほどであった。その後1960年代から1970年代へと時代が下るにつれて数も減り、演奏する曲目もアメリカのポピュラー音楽の占める割合が増えて、1970年代後半には姿を消した。<br>ナイト・クラブの状況から、全く日本のポピュラー音楽のみを好んでいたのはごく一部の二世までであり、三世以降の日本のポピュラー音楽の愛好者はアメリカのポピュラーも愛好していると推察できる。
1 0 0 0 IR 世界におけるナイトライフ研究の動向と日本における研究の発展可能性
- 著者
- 池田 真利子
- 出版者
- 地理空間学会
- 雑誌
- 地理空間 (ISSN:18829872)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.67-84, 2017
東京五輪開催(2020)に始まる都市観光活性化の動きのなか,ナイトライフ観光への注目が高まりつつある。本研究は,プレ五輪,ポスト五輪における東京の夜間経済や夜間観光の発展可能性を視野に,世界のナイトライフ研究・ナイトライフ観光研究の動向とその具体性に関して展望を行った。その結果,同研究は2010年代以降増加しつつあるが, アジア圏と欧米圏とでナイトライフの語義が異なり,前者はより広義であるのに対し,後者ではナイトクラブやバーといった特定の観光資源を意味する点,また飲酒やパーティ等の観光行動と結び付くため若者集団に特徴的な観光形態として広く認知されている点,観光地域により観光形態は個人・ツアー観光など多様である点等が明らかとなった。プレ五輪における風営法改正や,ポスト五輪のMICE観光振興・IR推進法成立の背景には観光を巡る都市間競争の熾烈化も窺え,東京のナイトライフ観光は今後より一層変化を遂げる可能性がある。
- 著者
- 山田 真広
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2013
コンビニ・スーパー・通信販売といった様々な小売業態の登場に伴う消費者購買行動の多様化,規制緩和やモータリゼーションの進展などに伴う大型店の売場面積拡大と郊外化の進展などにより,地方都市における中心商業地の求心力低下が問題となっている.その結果,日用食料品の入手に困難をきたす「買物難民」層の出現や,都市の個性がない画一的な景観の出現といった問題が発生している.本研究は,人口10万規模の地方都市である静岡県三島市を事例に,地方都市内部における消費者購買行動を時系列で分析し,その変化の要因を明らかにすることを目的とした.その研究手法として,三島市の中心市街地・市街地縁辺部・郊外部に居住する高齢者を対象に,食料品(鮮魚)と買い回り品(革靴)についての購買行動を,40年前・20年前・現在の3時期別に尋ねることにより把握した.アンケートの内容は,普段利用している(いた)店舗とその利用理由や,店舗までの交通手段などについてとした.得られた結果からは地域別・商品別に,購買先・購買距離・交通手段の変化などを把握した.購買距離についてはGISにより,道路距離解析を用いて算出した.さらに,利用店舗の場所を目的変数,居住地・交通手段・店舗の利用理由などを説明変数として数量化2類による分析を行い,各時期別・商品別にみた,店舗の選好理由を導き出した.研究で分かった事実を要約すると,食料品(鮮魚)については,①購買距離は中心市街地・市街地縁辺部・郊外部の3地区とも時代とともに増大し,中心市街地に比べて郊外部の方が3.6~6.8倍増大している.②買物先を規定する要因には,居住地域や交通手段(徒歩・公共交通機関・自家用車)が大きくかかわっていることから,店舗への近接性が重視されている.それに加えて中心市街地の店舗の利用者は,サービスの質や顔なじみかどうかなどが重視されている ことなどが明らかになった.買い回り品(革靴)については,①購買距離の地域的差異は日用品ほどは認められず,消費者の多くが40歳代~60歳代であった時期(20年前)の購買距離が最も長かったことから,居住地や購買距離よりも消費者の年齢や職業といった個人属性が購買先を規定していると考えられる.②三島市内の店舗か市外の店舗(沼津市・静岡市・東京都など)を選択する要因は,以前は利用する交通手段や品質・サービスの良さが,現在は価格や顔なじみかどうかが大きく関わっていると考えられる.さらに,三島市内の中でも中心市街地の店舗を選択する場合も,同様の要因が関わっている ことなどが明らかになった.
- 著者
- 佃 陽子
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター
- 雑誌
- アメリカ太平洋研究 (ISSN:13462989)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.142-159, 2009-03
論文Articlesカリフォルニア州サンフランシスコ市のジャパンタウンは20 世紀初頭に日本人移民の集住地域として誕生した。現在の日系人人口は郊外など各地に分散しているが、日系アメリカ人の多くにとってジャパンタウンはエスニシティの象徴として今なお重要とされている。本論文は近年の人文地理学の空間理論を援用し、1990 年代末から活発化したジャパンタウンの保護運動が日系アメリカ人のアイデンティティ形成に果たす役割を考察した。2006 年、一日本企業の撤退に伴いジャパンタウンのショッピング・モールやホテル等が一度に売却されることになった。これに危機感を募らせた日系コミュニティの指導者たちはサンフランシスコ市行政委員の支援を受けてロビー活動を展開し、ジャパンタウンを「Special Use District (SUD)」という土地利用が制限される特別地区に指定することに成功した。SUD制度は「場所」の境界線を定め、場所のアイデンティティを「日本・日系アメリカ文化」に限定した。本論文は場所の永続性と開放性という対照的な観点から、SUD制度の利点と問題点を指摘した。場所を永続的なものとみなした場合、SUDにより場所の境界とアイデンティティを再定義することはジャパンタウンの求心力低下に直面しているコミュニティ指導者たちにとって喫緊の問題であり、SUDの熱心なロビー活動は当然の行動だったといえる。SUDはジャパンタウンの経済的・文化的な発展を促すばかりでなく、多文化都市サンフランシスコの観光産業にも利益をもたらす可能性がある。しかし、場所を開放的なものとみなした場合、SUDはジャパンタウンに居住する非日系人グループらを周縁化し、「我々」と「他者」の境界を益々強固にするという危険性も孕むといえるであろう。
1 0 0 0 地方都市の中心市街地における大型店撤退とその跡地利用の課題
- 著者
- 箸本 健二
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, 2012
地方都市の中心市街地における大型店の撤退問題は,1990年代の半ばから顕在化するようになり,その後,全国的に拡大しつつある.こうした店舗の廃店・撤退は,小売業やその経営に深く参画する金融資本の立場からすれば致し方のない事業縮小であり,経営の合理化のために不可避と位置づけられている.しかし,地方都市の視点に立てば,中心市街地のランドマークであり,集客施設の核となってきた大型店の撤退は,中心市街地の求心力低下をもたらすだけでなく,小売販売額の争奪をめぐる都市間競争からの脱落に直結しかねない.このため,大型店の跡地問題は,深刻な商店街の地盤沈下と相俟って,地方都市が直面する喫緊の課題となっている.本研究は,このような状況をふまえ,地方都市における大型店撤退の実態を整理するとともに,跡地利用が直面している課題や行政の政策的対応を明らかにすることを目的とする. 本研究では,中心市街地に大型店が立地する可能性を持つ市町村合併前(1995年)人口20,000人以上の自治体(もしくはこれらを含む合併自治体)を対象に,1)1995年~2011年の間の大型店撤退事例の有無,2)事例ごとの撤退経緯の詳細,3)撤退跡地の現況,4)大型店撤退・跡地利用に関する政策的対応,5)国の中心市街地活性化政策との連携,などを主な質問項目とするアンケート調査を実施した.アンケート調査は,平成24年2月に全国849市町村を対象として郵送留置方式で実施し,626自治体から有効回答を得た(回収率73.7%).分析の結果,1)中心市街地に大型店が立地する自治体の約半数で大店法規制緩和(平成2年)以降に大型店の撤退が見られること,2)大型店の撤退が中心市街地の吸引力低下に直結する事例が多いこと,3)複雑な権利関係や負債の影響で撤退跡地の再利用が遅れる事例が多く,中心市街地の活性化に深刻な影響を与えていることなどが明らかとなった.口頭発表では,より詳細な調査結果に基づき,大型店撤退の実態と跡地利用が直面する課題を検討する.
- 著者
- 脇田 和美 福代 康夫
- 出版者
- 日本沿岸域学会
- 雑誌
- 沿岸域学会誌 = Journal of coastal zone studies (ISSN:13496123)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.59-69, 2020
1 0 0 0 OA 場を改変することでコミュニケーションするロボット群
- 著者
- 藤澤 隆介 土畑 重人 菅原 研
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.252-257, 2013-03-10 (Released:2019-05-08)
- 参考文献数
- 26
- 著者
- 井出 友洋
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1, 2006
【はじめに】 変形性股関節症に対しての保存療法の希望者に対しての装具などの選択に難渋する経験もあると思います。今回、末期変形性股関節症の症例について、既存の股関節サポーター以外の工夫による除痛の効果を得た2症例について報告する。<BR>【症例1】 70歳女性、平成16年12月7日初診、右変形性股関節症と診断、平成17年10月13日装具採型、股関節機能判定(以下JOA)右44/100点、X線像の評価判定0・20/100点、末期股関節症、同年12月6日痛みの軽減、平成18年2月7日(装具装着117日目)JOA60/100点で、+16点。<BR>【症例2】 75歳女性、平成16年1月28日初診、左変形性股関節症と診断、平成17年10月27日装具採型、JOA35/100点、X線像の評価判定0・20/100点、末期股関節症、同年11月26日痛みの軽減、平成18年2月18日(装具装着114日)JOA左36/100点で、+1点。<BR>【結果】 症例1のJOA変化は疼痛10→20点、立ち上がり・しゃがみこみ・車バス乗り降りが2→4点、計16点増加、症例2のJOA変化は可動域80→50度でー3点、腰掛2→4点、しゃがみこみ0→2点、計1点増加。<BR>【装具内容】 既存の関節サポーターにプラスチックにて股関節前面から後面まで包み、臼蓋への求心力を高められるものをつくり、サポーターに付属させた。<BR>【考察】 JOA判定基準やX線像評価において本2症例は末期股関節症であり、手術適応例であるが、本人希望により、保存療法を試み、痛みの軽減目的で装具療法となった。X線より、大腿骨骨頭変形も著明であり、股関節周囲筋力低下による歩行時痛が有り、歩行時の大腿骨骨頭求心力低下が痛みの原因と考え、これを補助するよう装具を考慮し、股関節の不安定性の減少により、痛みの軽減につながったと考えられる。また、症例1については可動域等の変化はないが、疼痛とADL面の改善が高く、これによる効果は高いと思われる。しかし、症例2においてはJOA変化は少なく、股関節屈曲可動域の減少はあったが、ADL面での改善があることから、今回の装具考案については良好な結果が得られたと思われる。<BR>【まとめ】1.末期変形性股関節症の2症例の装具検討による工夫について。2.装具内容において既存の股関節サポーターにプラスチックを付属させ、 大腿骨骨頭の求心力を高め、股関節の不安定性軽減により痛みの軽減とJOA変化につながったと考えられる。3.今後も既存の装具による工夫により、痛みやADLの改善を図りたい。
1 0 0 0 OA ヘーゲル哲学と弁証法
1 0 0 0 OA 帝国陸軍史
- 著者
- 田辺元二郎, 荒川銜次郎 著
- 出版者
- 帝国軍友会
- 巻号頁・発行日
- 1909
1 0 0 0 イカナゴはなぜ砂に潜るのか:行動の制御機構と高水温耐性
イカナゴ属魚類は,沿岸生態系の食物連鎖を支え,水産資源としても重要な魚類である.一方,日本各地で資源が激減しており,禁漁措置がとられているにも関わらず回復の兆しが見られないことが深刻な問題となっている.そこで,イカナゴ属の特徴的な行動である潜砂に着目し,本属魚類の再生産を阻む要因を探ることを目的とした.まず(1)北海道南部から瀬戸内海までを網羅した複数の地点に分布するイカナゴ属を用いた飼育実験を行い,潜砂行動の制御機構を明らかにする.続いて,(2)夏季の数カ月間にわたって砂に潜る夏眠について,潜砂により獲得される高水温耐性の分子機構を解明する.
- 著者
- 加藤 ゆかり 小室 譲 有村 友秀 白 奕佳 平内 雄真 武 越 堤 純
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, 2018
1.研究背景と目的<br>地方中心市街地では,店主の高齢化や後継者不在による求心力低下に伴い,その打開策として自治体主導の中心市街地活性化に向けた方策が講じられている。他方,近年の地方移住の背景には,充実した「移住・定住促進策」を背景に,進学や就業を機に大都市圏に流出したUターン者や多様な理由で移住するIターン者が存在する(作野,2016)。本報告では,こうした開業者による店舗開業や社会ネットワーク形成が商店街の新たな持続性となり得るのかを長野県伊那市中心市街地における事例から検討する。<br><br>2. 結果と考察<br>1) 新規開業者による店舗展開<br>長野県伊那市は,行政主導による空き店舗活用促進や移住者に対する創業支援のための補助金交付事業が講じられている。その結果,中心市街地において新規店舗の開業が相次いだ(図1)。開業者は主に市内出身のUターンや大都市圏出身のIターンであり,移住前の就業経験などを通じて得られた経験や知見を基に,新たな業種・業態の店舗を展開している。<br><br>2) 開業者ネットワークの形成<br>前述の新規開業者の一部は,強力なリーダーシップの基,と中心市街地活性化に向けた自らの方策を基に,賛同する近隣店舗にに共有することで,中心市街地内において社会ネットワークを形成している。例えば,「ローカルベンチャーミーティング」では,創業塾の開催を通じて近隣地域内店舗の経営方策や新規店舗開業について支援している。また,「いなまち朝マルシェ」においては発案者の緻密な計画の下,近隣の開業者が自らの技術,経験を集約することで運営に携わり,近隣の地域内店舗が出店する新たな集客機会を創出している。これら2つの社会ネットワークが中心市街地の持続性に向けた,新たな基盤となっている。<br><br>3) 持続性の考察<br>前述の開業者ネットワーク成立の背景には,行政の創業支援体制や商工会主体の既存店舗間ネットワークが関連している。また,これらのネットワークへの関与は活動指針に賛同する近隣地域店舗住民により構成されるものの,中心市街地の持続性へ寄与していることが指摘できる。それらの個別の開業者ネットワークの事例については,当日報告する。<br><br>文献 作野広和 2016.地方移住の広まりと地域対応――地方圏からみた「田園回帰」の捉え方.経済地理学年報62: 324-345.
1 0 0 0 OA プラグマテイズム
- 著者
- エフ・エス・シー・シラー 著
- 出版者
- 早稲田大学出版部
- 巻号頁・発行日
- 1916
1 0 0 0 OA 近代思想十六講
- 著者
- 中沢臨川, 生田長江 著
- 出版者
- 新潮社
- 巻号頁・発行日
- 1916