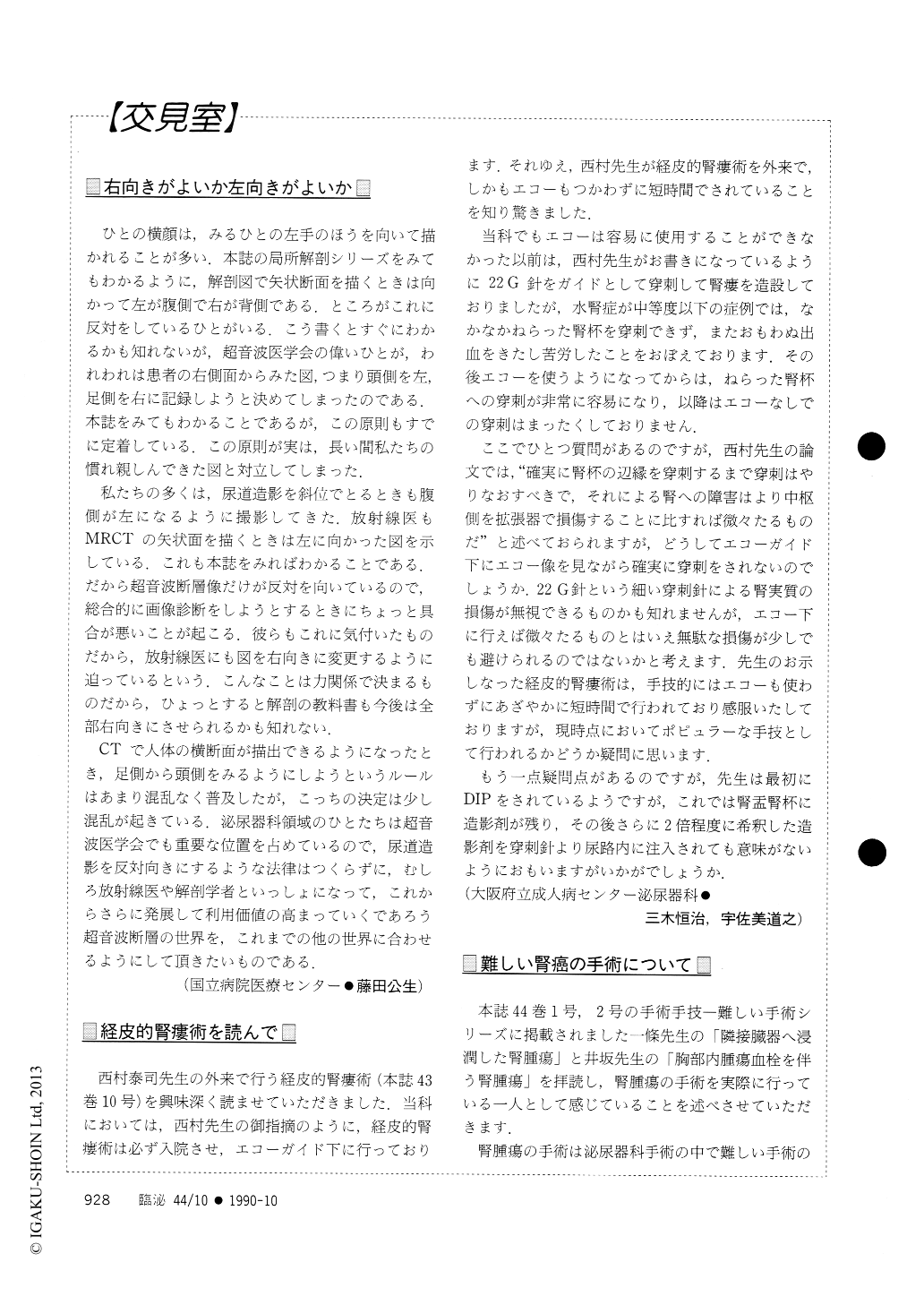- 著者
- 稲垣 絹代
- 出版者
- 日本地域看護学会
- 雑誌
- 日本地域看護学会誌 (ISSN:13469657)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.75-80, 1999-03-15
研究目的 戦後最大の不況のもとで,大阪市内では野宿生活者の増加がみられ,その健康問題の深刻さが予想されていた.野宿生活者への健康相談を通じて,健康問題の実態を明らかにすることを目的として,炊き出し公園で健康相談活動を実施した.研究方法1996年の8月から1997年1月までの毎日曜日の午後1時〜3時ごろまで,釜ヶ崎の四角公園で炊き出しが始まる時刻に机と椅子を置き,1人ずつ約15分面接した.調査項目は体温,脈拍,血圧測定し,現在の健康状態,相談内容,既往歴,居住地,栄養状態,就労状況,野宿の期間や原因などを質問した.その後,必要な援助を実施し,結果は項目ごとに統計的に分析した.結果と考察 相談日数は合計14日,相談件数は合計174件,1回平均12件であった.相談者は男姓150人,女性1人である.年代別にみると,50歳台後半から60歳台前半が合わせて56.9%にも達する.九州出身者が34%と多い.野宿をしている人が69.5%で,その期間は1週間以内から2年以上とさまざまである.半数以上がほぼ失業状態で,栄養摂取状況の不良な者は59%である.体温測定では夏季は発熱者が多く,秋から冬では低体温が多い.脈拍では48.1%が90以上の頻脈であり,血圧測定では収縮期血圧の異常が70.7%あり,拡張期血圧の異常も39.3%あった.相談内容としては循環器系,脳神経系,筋骨格系,呼吸器系の症状の訴えが多く,既往歴は呼吸器系,循環器系,筋骨格系が多い.特に結核は7人に1人,高血圧は8人に1人の割で発症していた.無料の医療機関への紹介,救急車での搬送,相談と指導の援助を行った.仕事に就けないことが,野宿せざるを得ない状況になり,栄養状態の悪化を招く結果になっている.結論 野宿と栄養障害が原因による健康障害の重篤性が明らかになり,対策が求められてる.
1 0 0 0 OA FEC療法とDOC療法併用による術前化学療法を受ける乳がん患者の栄養状態の変化
- 著者
- 新貝 夫弥子 横内 光子 国府 浩子
- 出版者
- 一般社団法人 日本がん看護学会
- 雑誌
- 日本がん看護学会誌 (ISSN:09146423)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.43-54, 2008 (Released:2017-01-19)
- 参考文献数
- 12
要 旨本研究は,乳がんの術前化学療法を受ける患者の栄養状態の変化を明らかにすることを目的とした.2004~2007年に初回術前化学療法を受けた乳がん患者50名を対象とし,診療記録の栄養指標となるデータについて統計的に分析した.全対象者の平均年齢は48.7(SD±9.0)歳で,DOC療法―FEC療法の順に治療を受けたレジメンⅠ群が31名(62%),FEC療法―DOC療法の順に治療を受けたレジメンⅡ群は19名(38%)であった.分析の結果,対象者全体で化学療法後のBMIは有意に増加していた.2元配置の分散分析では,体重,血清アルブミン,血清総蛋白では交互作用が認められ,レジメンによってこれらの変化のパターンが異なることが示された.レジメンⅠ,Ⅱ群いずれも前半化学療法後に,血清総蛋白と血清アルブミン値の有意な低下が認められたが,レジメンⅠ群では後半化学療法後にいずれも有意な増加があり,改善傾向がみられた.レジメンⅡ群では,後半化学療法後にも血清アルブミンと血清総蛋白の有意な低下と体重の有意な増加が認められており,浮腫や体液貯留による体重増加の可能性が考えられた.血清総コレステロールは,化学療法前後で両群とも有意な上昇が認められた.以上から,従来の症状と食事量の減少に対する指導のみならず,過剰な食事摂取の予防や,浮腫の助長を予防する食事や生活の注意を含めた指導の必要性が示唆された.
1 0 0 0 IR 大鏡と今昔物語集との関係--平田氏説批判
- 著者
- 国東 文麿
- 出版者
- 早稲田商学同攻会
- 雑誌
- 早稲田商学 (ISSN:03873404)
- 巻号頁・発行日
- no.144, 1960-01
1 0 0 0 OA 河口部の水理現象と関連する諸問題
- 著者
- 土木学会水理委員会河口部の水理現象小委員会
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1985, no.363, pp.47-60, 1985-11-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 111
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA デスフルラン麻酔のトラブルシューティング─各種トラブルに対する対処法─
- 著者
- 山口 重樹
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.606-609, 2016-09-15 (Released:2016-11-05)
- 参考文献数
- 7
デスフルランを用いた麻酔管理で遭遇する問題点は,気道刺激に伴う咳嗽,喉頭痙攣,気管支収縮,交感神経刺激による頻脈,高血圧である.そのため,デスフルラン吸入開始時には細心の注意が必要である.デスフルランの吸入濃度が1MACを超えると,気道刺激や交感神経刺激の危険性が高まる.Golden roleと呼ばれる「新鮮ガス総流量×デスフルランの設定濃度」の値が18を超えないようにデスフルラン吸入を設定することが望ましい.デスフルランによる気道刺激,交感神経刺激の予防にオピオイド鎮痛薬の併用が有効である.その他,低流量麻酔の問題点として,麻酔中の気化器再充填,二酸化炭素吸収材の劣化などの問題がある.
1 0 0 0 OA 危機に於ける人間の立場
1 0 0 0 OA より自由でより没入感の高いイマーシブメディア:編集にあたって/概要
イマーシブメディアは,映像空間内を移動し自由な視点からの全方位映像を見ることができ,あたかもその空間に入り込んだような体験ができる高臨場感メディアである.家庭でも360度カメラやヘッドマウントディスプレイが用いられるようになり,映像・音響の両面から現実世界の映像空間を自由に移動して見ることができるイマーシブメディアに向けた研究開発が積極的に行われている.本特集では,「超高臨場感ライブ体験の開発と標準化」,「イマーシブメディアに向けた音響技術 -放送とMPEGを中心に-」,「自由視点テレビFTVの原理」,「MPEGが規格化に取り組む映像システム技術~新たな映像体験に向けて~」の4件の解説を頂く.
1 0 0 0 霞ヶ浦漁業に関する一文書
- 著者
- 法学部法史学研究室 旧慣調査班
- 出版者
- 明治大学法律研究所
- 雑誌
- 法律論叢 (ISSN:03895947)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.90-96, 1952-11
1 0 0 0 OA 中庭型の建築および都市空間の構成原理とその展開
- 著者
- 鈴木 隆
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.482, pp.135-145, 1996-04-30 (Released:2017-01-28)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2 2
The composition of different types of architectural and urban spaces with a courtyard can be identified and explained by what we call the "principle of association of MA(Japanese meaning a room space)" based on two neccessary conditions : an opening for light and air of the MA and an efficient utilization of the site. 1) Different plans of houses with a courtyard result from the principle applied to the sites of various forms. 2) The principle permits to assimilate the galeries to the architecture with a courtyard. 3) The housing estates composed around a courtyard on large sites are a planning choice rather than the necessity of the principle. 4) A block of houses with a courtyard can be reorganized by the rearrangement according to this principle.
1 0 0 0 OA スコラ学派の貨幣論
- 著者
- ヨハンネス・ラウレス 著
- 出版者
- 有斐閣
- 巻号頁・発行日
- 1937
- 著者
- 高橋 統一
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第45回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.S4-2, 2018 (Released:2018-08-10)
非臨床毒性試験に用いられる正常実験動物と,実際に薬剤を服用するヒトでの薬剤(化学物質)への反応性の違いは数多く報告され,このような違いが生じる大きな要因として薬剤を服用するヒトの個体差(人種・性別・年齢・生活環境・生活習慣・疾患の有無など)が報告されている。これらのヒトにおける個体差のうち,非臨床毒性試験で評価・対応可能な要素として生活習慣(疾患の素因)や病態(化学物質誘発あるいは自然発症病態モデル動物)があり,多くの研究者がヒトの病態に類似した実験動物を作出して化学物質の安全性や毒性発現機作を調べている。これらの研究で判明した知見,すなわち正常実験動物と病態モデル動物の化学物質への反応性の違いやその理由を,新たな薬剤の開発のために実施される非臨床毒性評価に生かす努力がなされているが,選択する病態モデル動物によって同一薬剤でも異なる結果が得られる等,病態モデル動物を利用した毒性試験の評価系確立には,さらに知見の収集や解析が必要と考えられる。このような背景から,我々はヒトの糖尿病と表現型が類似したSDTラットやSDT fattyラットを安全性評価に用いる試みを続けている。SDT fatty(SDT.Cg-Leprfa/JttJcl)ラットはSDTラット(自然発症の非肥満2型糖尿病モデル)に肥満遺伝子Leprfaを導入した肥満2型糖尿病モデル動物である。SDT fattyラットの糖尿病性合併症やその病態プロファイルは特に慢性病態において他の糖尿病モデルラットよりもヒトの病態に類似性が高いことが報告されている。さらに,SDT fattyラットでは糖尿病発症による栄養学的な修飾により,正常動物と比較し薬物代謝も異なる可能性があり,糖尿病に関連した研究に最適な病態モデル動物の1つであると考えている。我々はこれまでにいくつかの薬剤や化学物質について肝臓を中心に病態モデル動物における毒性修飾を調べており,これらの結果は非臨床安全性評価の向上に寄与するものと考える。
1 0 0 0 右向きがよいか左向きがよいか,他
ひとの横顔は,みるひとの左手のほうを向いて描かれることが多い,本誌の局所解剖シリーズをみてもわかるように,解剖図で矢状断面を描くときは向かって左が腹側で右が背側である.ところがこれに反対をしているひとがいる.こう書くとすぐにわかるかも知れないが,超音波医学会の偉いひとが,われわれは患者の右側面からみた図,つまり頭側を左,足側を右に記録しようと決めてしまったのである.本誌をみてもわかることであるが,この原則もすでに定着している.この原則が実は,長い間私たちの慣れ親しんできた図と対立してしまった. 私たちの多くは,尿道造影を斜位でとるときも腹側が左になるように撮影してきた.放射線医もMRCTの矢状面を描くときは左に向かった図を示している,これも本誌をみればわかることである.だから超音波断層像だけが反対を向いているので,総合的に画像診断をしようとするときにちょっと具合が悪いことが起こる.彼らもこれに気付いたものだから,放射線医にも図を右向きに変更するように迫っているという,こんなことは力関係で決まるものだから,ひょっとすると解剖の教料書も今後は全部右向きにさせられるかも知れない.
- 著者
- 小野 勇一 伊澤 雅子 岩本 俊孝 土肥 昭夫 NEWSOME Alan KIKKAWA Jiro
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1988
代表者らのグル-プは,森林に起源を持つといわれている食肉目の社会進化を明らかにするために、これまでネコ科、特に小型種について研究を進めてきた。特に小型ネコ科の社会形態とその維持機構を、様々な環境で野生化したイエネコの研究によって明らかにしてきた。すなわち、小型ネコ科の社会の適応性は生息環境の資源量と強い関連性を持つことが示唆された。この適応性についての試論は国内では野生種の小型ネコ、イリオモテヤマネコとツシマヤマネコの調査によって、すでに検討を始めている。ネコ科の社会進化を論ずる上で、イエネコの人間社会と完全に隔離された自然状態での社会形態と、その起源種である野生種の小型ネコの社会形態と比較することは重要なポイントとなる。しかしながら、わが国において野生化したイエネコの生息域とその中の資源量は、ほとんどの地域で人間生活との関連が深く、完全に自然状態で野生化したイエネコの生息域はない。本研究では、オ-ストラリア大陸内部に人間社会の影響がほとんどない地域で野生化したイエネコを対象にして、その社会生態と環境資源利用の調査を実施した。オ-ストラリアには西洋人の入植以来200年間にイエネコが野生化し、現在では大陸のほとんどの地域に分布している。人間生活の影響をまったく受けない森林地帯・半乾燥地帯・砂漠などに生息している野生化したイエネコは、その始原種であるヤマネコと同様に、ハンティング(狩り)によって生活をしている。一方、この野生化したイエネコは、オ-ストラリア固有の貴重な動物相に重要な影響を及ぼしている。これらの固有種の保護のために、野生化したイエネコの生態学的調査も本研究の重要な課題のひとつである。調査は、ニュ-サウスウェルズ州のヤソン自然保護区で行った。この保護区内に調査地を設け、1988年と1989年の2年間に約12ヶ月間滞在して資料を収集した。調査地内のネコの大部分を補獲し、発信機あるいは耳環を装着して個体識別し、テレメトリ-法と直接観察によって行動が追跡された。この地域の野生化したイエネコは、年中ほとんどの餌を野生化したアナウサギに依存していることが明らかになった。このことから、2年目にはアナウサギの生態学的調査も行った。調査の結果は、完全な自然条件のもとで野生化したイエネコの社会形態の基本型は、小型ネコの野生種とほとんど変わらないこと、また生息地の資源量がその基本型の変異に強い影響を持つことが明らかとなり、研究グル-プの試論が証明される大きな成果が得られた。2年間に渡る継続した資料が得られたことから、調査地内のネコの定住性と分散過程の資料が得られ、哺乳類に頻繁に見られる「雄に偏よった分散」を実証でき、またその分散の要因が、定住雄の繁殖活動によることが観察によって明らかにされた。さらに分散が確められた個体の分散過程の資料も得られた。これらの結果は、ネコ科の社会形態の維持機構解明に重要な手がかりを与えるものである。次にこの地域の野生化したイエネコは年間の餌の大部分をアナウサギに依存していることから、単純な食う=食われる関係のもとに成り立っていた。このことからネコのホ-ムレンジの大きさは、餌資源の季節的な変化に対応して決定されること、またネコの繁殖も餌の利用しやすい時期と同調していることを用いて、食う=食われる関係のシュミレ-ションモデルが導かれた。また、保護区の鳥類相の調査も平行して行い、ネコによる被食の程度は、主な餌であるアナウサギの個体数が最も少なくなる厳冬季にはかなりの程度補食されていることが明かとなった。このことから、小型哺乳類の生息が少ない地域や季節には、野生化したネコのオ-ストラリア固有動相への影響は大きいことが示唆された。本研究で得られた研究結果は各分担者ごとにサブテ-マごとに論文として公表され、また全体的には報告書の形でまとめられた。この研究成果は、特にオ-ストラリアでこれまで大きな問題となっていた野生化したイエネコについて多くの新しい知見を与えるもので野生動物保護管理のうえで貢献するものと期待される。
1 0 0 0 渋谷定輔とタラス・シェフチェンコ : 比較文学的試み・覚書き
- 著者
- 村井 隆之
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 近代 (ISSN:02872315)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.77-150, 1983-01