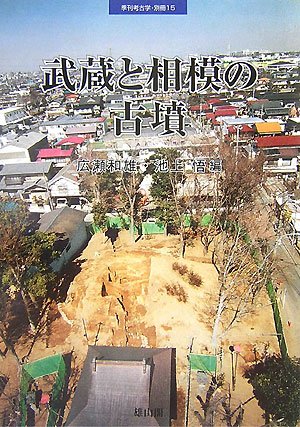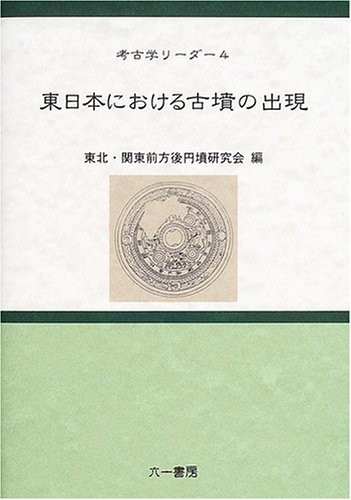1 0 0 0 OA 食塩について
- 著者
- 橋本 壽夫
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.1, pp.7-15, 2004-01-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 25
塩の専売法が廃止されてから, 様々な塩が販売されるようになった。しかし, 現在でも, 製塩や塩に関する情報は少なく, マスメディアや特殊製法塩の製造業者の多くは, 科学的根拠が乏しかったり, 無いにも拘らず, ある種の塩を誇大に宣伝して, 消費者に誤った認識を与えていると言われる。塩についての判断基準となる「塩の科学」の著者であり, 前に本誌に「食塩と高血圧との関係」についての解説もいただいた著者に, 改めて今回は, 製塩法と塩の品質, 食塩の安全性, ナトリウム以外のミネラル, 食塩と健康問題等について詳細に解説いただいた。
1 0 0 0 OA 「新コモンウェルス」と南アフリカ共和国の脱退 (一九六一年) -拡大と制度変化-
- 著者
- 小川 浩之
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.136, pp.79-96,L10, 2004-03-29 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 63
The purpose of this paper is to examine how the Commonwealth has experienced enlargement and changes after the Second World War. In this attempt, particular attention is paid to South Africa's withdrawal from the Commonwealth in 1961. The Government of the Union of South Africa under H. F. Verwoerd made an application to remain within the Commonwealth as a Republic, but eventually decided, or was virtually forced, to withdraw the application as a result of strong criticism against apartheid mainly from Afro-Asian member countries. Therefore, the Republic of South Africa was established on 31 May 1961 outside the Commonwealth. As increasing number of newly-independent states joined after 1947 (when both India and Pakistan became independent and then joined as new members), the Commonwealth which had been originally formulated by Britain and six ‘white’ Dominions was transformed into a multi-racial institution. The major character of the ‘old Commonwealth’ was that the member states maintained traditional ties among the peoples of British origin and did not regard each other as ‘foreign’, while, at the same time, the mutual recognition of internal and external autonomy was the central raison d'étre. However, as newly-independent non-white countries joined one after another and the norm of racial equality was strengthened, both the old intimacy and the conventional principle of mutual non-interference were increasingly faced with strong pressure.In those changes which the Commonwealth has experienced, the disputes about apartheid among the Commonwealth countries and the departure of South Africa marked a crucial turning point. Firstly, the departure of white-dominated South Africa clearly demonstrated that the principle of noninterference in domestic affairs of member states was increasingly under pressure from the norm of racial equality. Secondly, the often uncontrollable and open rows over South Africa's racial policy symbolized the fact that the old intimacy had been largely curtailed as newly-independent members added ‘alien’ elements into the Commonwealth. Thirdly, the sequence of events culminated in South Africa's departure made some of the original members such as Britain and Australia feel increasingly discontent with the ‘new Commonwealth’ and therefore facilitated the centrifugal forces working in the Commonwealth relations. Britain's attempts to accede to the European Economic Community (EEC) and the European Community (EC) in the 1960s and the early 1970s were noticeable examples of the centrifugal tendencies. However, at the same time, the inter-Commonwealth disputes on racial issues such as South Africa's apartheid in 1960-61 and the Unilateral Declaration of Independence (UDI) by the Smith regime of Rhodesia (today's Zimbabwe) in the mid-1960s can also be considered as inevitable hurdles which the Commonwealth had to tackle in the process of becoming a truly multi-racial association.
1 0 0 0 OA 井上円了における現象即実在論
- 著者
- 新田 義弘
- 出版者
- 東洋大学井上円了研究会第二部会
- 雑誌
- 井上円了と西洋思想
- 巻号頁・発行日
- pp.79-102, 1988-08-10
1 0 0 0 OA 神経痛と心身症 : アレキシシミアをめぐって
- 著者
- 池見 酉次郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.193-199, 1980-06-01 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 4
1 0 0 0 OA 深層学習を用いた画像変換に基づく会話からの音声抽出
- 著者
- 髙市 晃佑 片上 敬雄 黒澤 義明 目良 和也 竹澤 寿幸
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)
- 巻号頁・発行日
- pp.3Rin231, 2019 (Released:2019-06-01)
近年盛んである深層学習を用い音源を分離することを目的とする.ネットワークを用い通常の会話から特定の人間の声を抽出することを試みる.画像変換を行うpix2pixに注目する.そのアルゴリズムは純粋な画像変換の手続きに基づくため,追加の手続きとして音声を一度スペクトログラムに変換する必要がある.その後,人間の声を分離するためにネットワークを学習し、特に同性と異性の違いに注意して抽出を行う.この観点から、本稿では男女の声を重ねた音声を使って2つの実験を行った.SSIMとカラーマップを評価の基準に使用した.結果として,女性の声が良く抽出できていることを確認した.ところが,女性同士の発話から抽出はできなかった.今回,分離はうまくいかなかったという結論に至った.しかしながら,生成された音声は自然に再生されたと思われる.今後の課題は,こうした人間の判断を客観的に判定することである.
- 著者
- 伊藤 貴雄 Takao ITO
- 出版者
- 創価大学人文学会
- 雑誌
- 創価大学人文論集 (ISSN:09153365)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.37-58, 2009
1 0 0 0 OA ベトナムの習慣と信仰を古典文学に探る
- 著者
- グエン ティ オワイン
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 巻号頁・発行日
- pp.1-35, 2012-09-20
会議名: 日文研フォーラム, 開催地: ハートピア京都, 会期: 2012年1月17日, 主催者: 国際日本文化研究センター
1 0 0 0 OA 証拠標本の保存の重要性 : あなたが発表した論文の内容が後世で無視されないために
- 著者
- 広瀬 義躬
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.28-31, 2012-01-05 (Released:2018-09-21)
1 0 0 0 OA 日本語大規模SNS+Webコーパスによる単語分散表現のモデル構築
- 著者
- 松野 省吾 水木 栄 榊 剛史
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)
- 巻号頁・発行日
- pp.4Rin113, 2019 (Released:2019-06-01)
本稿では,筆者らの構築したTwitterをはじめとしたSNS上に存在する日本語の文章に対応する単語分散表現モデルを紹介する. 本モデルはSNSデータ,Wikipedia,Webページといった複数カテゴリを媒体とした日本語大規模コーパスから作成される.作成した単語分散表現モデルに対し,Speamanの順位相関係数を評価指標とした単語類似度算出タスクによる評価を実施したところ,wikipediaのみを学習コーパスとして用いたモデルと比較して7ポイント程度良い性能を得られた.本稿で紹介した単語分散表現モデルはWebサイトを通じて公開する予定であり,本モデルが活用されることで,SNSデータを対象とした自然言語処理研究が一層盛んになることを期待したい.
1 0 0 0 OA 成長期の野球肘と肩関節機能の関連性について
- 著者
- 岸本 進太郎 辛嶋 良介 近藤 征治 杉木 知武 川嶌 眞之 川嶌 眞人
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- pp.25, 2016 (Released:2016-11-22)
【はじめに】 近年,野球肘に関しても投球肩障害と同様に,肩後方タイトネスやScapula Dyskinesiaなどの存在を指摘する報告がされている.今回,成長期の選手における野球肘と肩関節機能の関連性ついて調査したので以下に報告する.【対象と方法】 対象は,2015年9月から2015年12月の期間に当院を受診し,野球肘と診断され加療を行った7例(内側型4例,外側型3例)とした.全例男性,右利き,右投げであり,平均年齢12.3歳(10?17歳)であった.なお,投球時の一発外傷例は除外した.方法は,肩関節機能の理学所見を原テスト11項目で評価し陽性率を調査した.評価内容は以下のとおりである.①Scapula-spine distance(以下SSD),②Combined abduction test(以下CAT),③Horizontal flexion test(以下HFT),④下垂時外旋筋力テスト(以下ISP),⑤下垂時内旋筋力テスト(以下SSC),⑥下垂時外転筋力テスト(以下SSP),⑦Elbow extension test(以下EET),⑧Elbow push test(以下EPT),⑨Loosening test(以下loose),⑩Hyper external rotation(以下HERT),⑪Impingement test(以下impingement).また,内側型野球肘4例(平均年齢10.5±0.6歳)を内側群,外側型野球肘3例(平均年齢14.7±2.5歳)を外側群とし11項目の陽性率を2群間で比較した.統計学的検討にはχ2検定を用い,いずれの検定も有意水準5%未満とした.【結果】 原テスト正常項目は平均6.6(5?8)項目であった.陽性率は,SSD:100%,CAT:57.1%,HFT:71.4%,ISP:14.3%,SSC:42.9%,SSP:42.9%,EET:71.4%,EPT:28.6%,loose:0%,HERT:0%,impingement:14.3%であった.2群間の比較では,SSCは内側群75%,外側群0%で有意に内側群が高かった(p<0.05).CATは内側群25%,外側群100%で有意に外側群が高かった(p<0.05).SSD,HFT,ISP,SSP,EET,EPT,loose,HERT,impingementの陽性率は有意な差を認めなかった.【考察】 可知らは中学・高校野球選手に対する投球時の肘痛と肩関節機能について調査し,肘痛を有する野球選手の原テスト正常項目は6.3項目であったと報告していた.本調査も平均6.6項目とほぼ同様の結果であった.自験例から,肩甲骨位置異常,肩後方タイトネスを示す項目の陽性率が高い傾向にあり,成長期の野球肘において,肘関節に加え肩関節機能の評価と治療が重要だと考えられた.また,coking phaseからacceleration phaseの野球肘が発生しやすい投球相で,骨頭を求心位に保つ腱板に機能不全を起こしている可能性が示唆された.両群間でSSCとCATに差が認められたが,これは受診時の年齢の違いに起因する問題が原因として考えられた.内側群は平均年齢が低く,筋機能の未発達な時期に投球負荷が加わり,腱板機能にimbalanceを起こすと思われた.一方,外側群は平均年齢が高く,無症候性に病態が進行するため,障害発生の危険因子として特徴的な肩後方タイトネスが顕著となったと思われた.本調査の限界として,症例数が少なく今後も調査を継続していきたい.【倫理的配慮,説明と同意】 本調査はヘルシンキ宣言に沿った研究であり,当院倫理員会の承認を得て実施した.また研究の実施に際し,対象者に調査内容について説明を行い同意を得た.利益相反に関する開示事項はない.
1 0 0 0 OA 呼吸器疾患の理学療法
- 著者
- 林 積司 上西 啓裕 吉富 俊行 成川 臨
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法のための運動生理 (ISSN:09127100)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.209-216, 1989 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 10
胸部外科における心肺疾患患者の肺理学療法目的は、術前、術後の呼吸機能低下が原因で出現する種々の合併症予防と換気効率低下改善にある。術前において最も重要なことは、患者及び家族教育であり、呼吸訓練の重要性を理解してもらうことは肺理学療法の目的達成のポイントとなり得る。次は、術前、術後の全身状態が非常に異なることを念頭に置き、患者が普段から意識しなくても腹・胸式呼吸パターンが行える様に指導する。最後に、術前、術後の呼吸音を聴診することで、これは術後背臥位期間中の外側肺底区・後肺底区の聴診は異常呼吸音の早期発見につながるからである。
- 著者
- 松沢 裕作
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.741, pp.124-127, 2010-02
1 0 0 0 長柄・桜山第1・2号墳 : 測量調査・範囲確認調査報告書
- 出版者
- 神奈川県教育委員会 : かながわ考古学財団
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 長柄・桜山第1・2号墳 : 新発見の大形前方後円墳の概要
- 著者
- かながわ考古学財団編集
- 出版者
- 神奈川県教育委員会 : かながわ考古学財団
- 巻号頁・発行日
- 2000
- 著者
- 東北・関東前方後円墳研究会編
- 出版者
- 六一書房
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 シンポジウム前期古墳を考える : 長柄・桜山の地から : 記録集
- 出版者
- 葉山町教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 2004