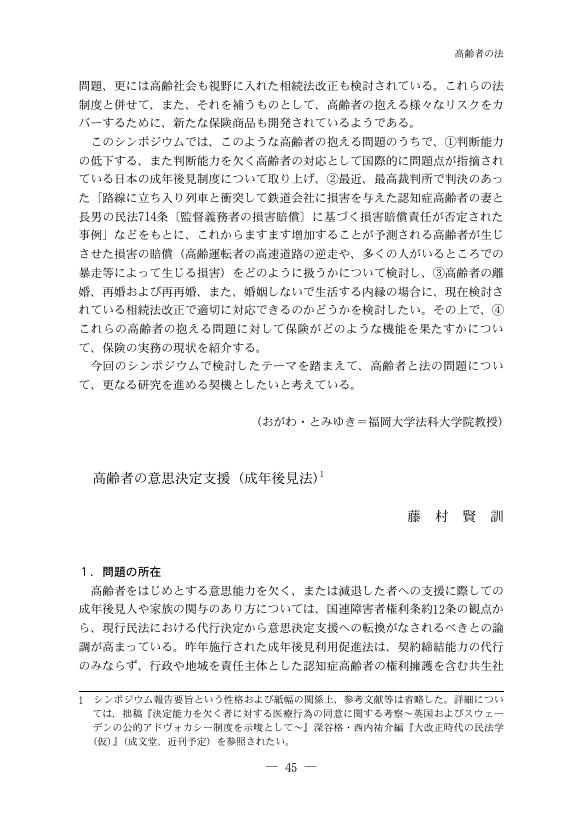1 0 0 0 かんしょの需要変化と品種の動向
- 著者
- 狩谷 昭男
- 出版者
- 農畜産業振興機構調査情報部
- 雑誌
- 野菜情報 = Vegetable information
- 巻号頁・発行日
- vol.152, pp.46-55, 2016-11
1 0 0 0 サツマイモブームの現状と展望
- 著者
- 狩谷 昭男
- 出版者
- 大日本農会
- 雑誌
- 農業 = Journal of the Agricultural Society of Japan (ISSN:02880105)
- 巻号頁・発行日
- no.1624, pp.29-36, 2017-04
1 0 0 0 でん粉のあれこれ さつまいもでん粉産業の変遷(1)
- 著者
- 下野 公正
- 出版者
- 農畜産業振興機構調査情報部
- 雑誌
- でん粉情報
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.17-21, 2011-07
- 著者
- 小巻 克巳
- 出版者
- 大日本農会
- 雑誌
- 農業 = Journal of the Agricultural Society of Japan (ISSN:02880105)
- 巻号頁・発行日
- no.1631, pp.26-38,図巻頭1枚, 2017-11
- 著者
- ダグダンプレブ スミヤクハンド 光鎬 孫 重人 阿部 岳巳 松井
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.162, 2017
<p>2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行を機に,世界中の空港では赤外線サーモグラフィによる発熱チェックシステムが導入された.しかし,感染の疑いのある渡航者も解熱剤服用時には検出が困難であり,サーモグラフィの有用性を疑問視する報告までも散見される.これらの検疫における課題を克服するために,本研究では,現在空港検疫で使用されている赤外線・CMOSカメラを用いて,非接触でバイタルサインである呼吸数・心拍数・体温を測定し,画像処理により感染症をスクリーニングするシステムの開発を提案する.その有用性を検証するため,2015年高坂クリニックのインフルエンザ患者16名と対象群の22名の健常者に対してスクリーニングを行った.本システムの精度は,感度87.5%,特異度91.7%であった.</p>
1 0 0 0 OA グリセリン浣腸により直腸穿孔と溶血をきたした一症例
- 著者
- 島田 能史 松尾 仁之 小林 孝
- 出版者
- 新潟医学会
- 雑誌
- 新潟医学会雑誌 = 新潟医学会雑誌 (ISSN:00290440)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.1, pp.17-20, 2004-01
症例は60歳女性.右乳癌の診断にて入院した.手術当日グリセリン浣腸施行中に強い疼痛を訴え,その後も強い肛門部痛と嘔吐が持続した.臀部は腫脹し,肛門内から少量の出血を認めた.直腸診で直腸粘膜の欠損を触知し,浣腸時の直腸穿孔およびグリセリン液の管腔外注入が考えられた.浣腸後から自尿は無く,約10時間後の導尿では少量の血尿が得られた.補液と強制利尿にも反応無く,翌日急性腎不全と診断し,血液透析を開始した.計3回の血液透析で,腎機能は利尿期を経て約2週間後に正常に回復した.臀部の発赤,腫脹も受傷10日目には自然に消失し,直腸周囲での膿瘍形成も無かった.本症例は高濃度のグリセリン液が血中に入ったことにより,赤血球の膜障害と溶血が起こり,急性腎不全を引き起こしたと考えられた.以前より高濃度のグリセリンが血中に入ると溶血を起こすことは広く知られている.グリセリンが溶血を起こす機序については,赤血球の膜障害による高度の溶血が原因として推測されている.溶血が起こると大量の遊離ヘモグロビンが発生し,尿細管上皮内に再吸収されヘムとグロビンに分解される.ヘムは細胞毒として作用するため腎不全が発生するとされている.腎不全発生を予防するためには,遊離ヘモグロビンの除去が重要とされる.遊離ヘモグロビンは大分子物質であるため,その除去には血漿交換が有効と考えられている.また,遊離ヘモグロビンと結合し肝臓に運び処理するハプトグロビン投与も有効とされている.グリセリン浣腸時に患者が疼痛や気分不快および強い疼痛等を訴えた場合には,浣腸による直腸粘膜の損傷や穿孔の可能性がある.さらに腸管外へのグリセリン液注入は溶血から急性腎不全を発症する場合もあり,注意深い観察と迅速な対応が必要である.
1 0 0 0 OA 高齢者の意思決定支援(成年後見法)
- 著者
- 藤村 賢訓
- 出版者
- 九州法学会
- 雑誌
- 九州法学会会報 九州法学会会報 2017 (ISSN:24241814)
- 巻号頁・発行日
- pp.45-49, 2017 (Released:2018-02-05)
1 0 0 0 デモクリトスにおける感覚と思惟
- 著者
- 西川 亮
- 出版者
- 日本西洋古典学会
- 雑誌
- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.28-38, 1969
トラシュロスがデモクリトスの作品を四部作に分類して配列した目録の中に,認識論的傾向のものを扱ったとおもわれる若干の作品名が残されているが,その内容に至ってはほとんど知られない.もしそれについて考察を試みようとすれば,セクストス・エンペイリコスやガレノスによって引用された断片や,アリストテレスやアエティオスなどの記録,さらに諸感覚についてのテオプラストスのかなり詳細な記述などによらなければならない.しかし皮相的にみれば,これらの資料間における齟齬が,統一的見解を阻んでいるかのように見做される.むろんデモクリトスのいわゆる認識論についての資料の処理にすでにかなりの努力が払われてきた.ここでは,それらの諸資料を三区分し,その間の差異を検討して,デモクリトスのいわゆる原子思想における認識論的問題の一端にふれてみたい.
- 著者
- 戸塚 七郎
- 出版者
- 日本西洋古典学会
- 雑誌
- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.118-121, 1973
- 著者
- 工藤 秀明
- 出版者
- 千葉大学経済学会
- 雑誌
- 経済研究 (ISSN:09127216)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.165-192, 1996-03
In this paper, we analize the second volume of Marx's doctoral dissertation. As important branches of naturphilosophy are ones of atom, time, and heavenly bodies, Marx examines Demokritos' and Epikuros' views on each of these branches in detail. Sympathiz
1 0 0 0 パトグラフィ(4)精神医学史探訪(3)笑うデモクリトス
- 著者
- 酒井 明夫
- 出版者
- 科学評論社
- 雑誌
- 精神科 (ISSN:13474790)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.44-48, 2004-01
1 0 0 0 IR デモクリトスとクローンの問題
- 著者
- 森 一郎
- 出版者
- 東京女子大学
- 雑誌
- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.1-28, 2004-09
- 被引用文献数
- 1
Die Begrenztheit menschlichen Lebens bedeutet nicht nur das Sein zum Tode, sondern auch das Geborensein. Zur Frage der Existenz gehoren gleichursprunglich die Moglichkeit des Todes und der Zufall der Geburt. Und dennoch kann niemand aus sich allein - in einem Akt der Monogonie - geboren sein, im Gegensatz zum Tod durch die eigene Hand. Die Geburtlichkeit hat mehr mit der Bedingtheit durch Pluralitat zu tun als die Sterblichkeit. Das Ereignis der Geburt bedeutet immer eine zufallige Begegnung zweier unabhangiger Wesen: eines Kindes und seiner Welt. Dafiir ist es aber auBerdem notwendig, dass ein Mann und eine Frau zusammentreffen und ein Paar werden, sie beide ein Kind zeugen und die Frau es gebiert. Die geschlechtliche Fortpflanzung ist eine Art "Poiesis" durch eine ganz eigene Art der "Techne". Hier stellt sich nun die Frage, inwiefern das Generieren neuen Lebens als ein kunstliches Herstellen verstanden werden kann. Mein Essay versucht diese Frage von einem aktuellen Aspekt her zu klaren, namlich im Hinblick auf das Problem des Klonens. Als Leitfaden wahle ich die uralte Empfehlung eines Weisen. Demokritos (Fragment B277) sagte namlich zu uns, "Wer irgend eine Notigung hat, sich ein Kind zu verschaffen, tut dies, wie mir scheint, besser durch Adoption eines Freundeskindes. Dieser wird dann ein Kind bekommen, so wie er es wiinscht. Denn er kann es sich auswahlen, wie er es will. [...] Zeugt man es aber sich selbst, so sind viele Gefahren dabei: denn man muss doch mit dem, das gerade geboren wird, vorlieb nehmen. "Da die Erzeugung eines Kindes etwas Zufalliges und Unvorsehbares ist, mussen die Eltern und das Kind selbst dieses groBe Risiko auf sich nehmen. Wenn das Kind einmal geboren worden ist, dann kann das Faktum seiner Geburt nicht mehr riickgangig gemacht werden. Deshalb hielt der klassische Atomist die "Adoption eines Freundeskindes" besser als die Selbstzeugung. Die Adoptiveltern konnen sogar ihr Kind gewissermaBen auswahlen. Anstelle Demokrits' Verfahren der versicherten Kindesbeschaffung ist man heute dabei, eine andere Methode der Adoption zu erfinden: die gentechnische Anwendung des Klonens auf die Menschenproduktion. Es ist eine groBe Ironie, dass durch diese neue Adoptionskunst, die die Zufalligkeit des Geborenwerdens ausraumen will, gerade die Unwiderruflichkeit der faktischen Geburt noch groBere Gefahren erzeugen wird.
- 著者
- 山下 尚一 ヤマシタ ショウイチ Shoichi Yamashita
- 出版者
- 駿河台大学教養文化研究所
- 雑誌
- 駿河台大学論叢 (ISSN:09149104)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.25-43, 2015
1 0 0 0 OA プレゼンテーションの技法 日本語報告から英語報告まで
- 著者
- 佐藤 嘉倫
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.307-312, 2012 (Released:2013-08-12)
1 0 0 0 IR トランプ大統領の英語を添削する
- 著者
- 星野 三喜夫
- 出版者
- 新潟産業大学経済学部
- 雑誌
- 新潟産業大学経済学部紀要 = Bulletin of Niigata Sangyo University Faculty of Economics (ISSN:13411551)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.11-22, 2019-01
トランプ米国大統領の英語を主要歴代大統領や彼と大統領選で戦った候補と比較すると、文法は小学校5年から6年生レベル、語彙は8年生に届かない低いレベルである。また彼の英語には、繰り返しや口語的な誇張表現の多用が見られ、スラングや上品でない言葉も含まれる。トランプ大統領が自ら認めたと思われる、2018年5月24日付けの北朝鮮金正恩労働党委\n員長に宛てた首脳会談の「中止」を告げる書簡をチェックすると、語法や言い回しにおいて指摘すべき点が多々ある。英語を母語とする人が、たとえ米国の大統領であったとしても、必ずしも相応しい英語を書く訳ではなく、時には間違った、あるいは望ましくない英語を書いている。トランプ大統領がSNS等で書く英語は子供っぽく、また誇張表現や感情表現が多いが、スピーチライターが慎重を期して書き、トランプ大統領がゆっくり発している大統領選勝利演説や大統領指名受諾演説、一般教書演説等は英語学習において有用である。英語学習者はその点を踏まえて彼の英語を活用するのが良い。
1 0 0 0 OA 下水からのトータルりん回収システムの提案
- 著者
- 天本 優作 明戸 剛 今井 敏夫 三浦 啓一
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第24回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.321, 2013 (Released:2014-01-21)
下水の水からリンを回収する技術は,HAP法,MAP法などが実用化されている.しかしながら,これらの方法で回収することができるリンは,全体の30%にとどまる.一方,下水汚泥焼却灰に炭酸カルシウムを添加して焼成すると,特性の優れた肥料が得られることが判明している.両者の技術を併用すれば,下水の中のリンの90%以上が,肥料として有効に再資源化できる.
1 0 0 0 OA 定理証明支援系Coqにおける手続き的証明から宣言的証明への変換
定理証明支援系Coqにおける証明は、一般に手続き的証明と呼ばれる形式で記述される。これは対話的証明を前提としており、自然言語による証明記述と大きく異なるため、可読性が高いものではない。この問題を解決するためにCoq用宣言的証明言語C-zarが開発された。宣言的証明は可読性が高く、また外部ツールを導入し易い。しかし、C-zar は手続き的証明に対して記述量が多い上に柔軟性が低く、Coq ユーザに受け入れられなかった。本研究では、Coq の手続き的証明からC-zarの証明を生成することで、両者間の橋渡しを行う。一般に手続き的証明から宣言的証明への変換手法としては、証明項や証明木のような中間表現を経由する方法が考えられ、既に定理証明支援系Matitaでは証明項を経由する手続き的証明から宣言的証明への変換が存在する。しかし、中間表現は元の証明と比べて詳細かつ巨大になり、元の手続き的証明1ステップに対して数百ステップの宣言的証明が生成されてしまう場合もある。一方で、C-zar は手続き的証明で用いられるタクティックと呼ばれるコマンドを利用することができ、これによって手続き的証明の1ステップは、多くの場合C-zarの数ステップと対応させることができる。本研究では、元の手続き的証明と証明項の両方を用いて変換を行うことで、元の証明に近い粒度の宣言的証明の生成を実現する。
1 0 0 0 OA 前賢故実
- 著者
- 菊池容斎 (武保) 著
- 出版者
- 郁文舎
- 巻号頁・発行日
- vol.巻第6, 1903