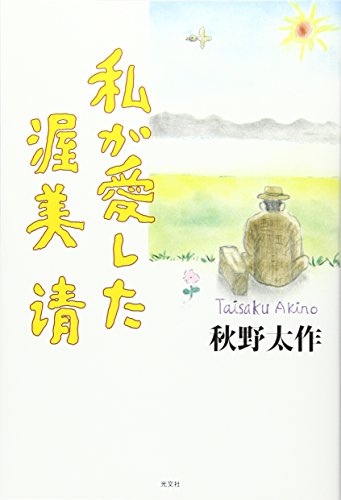1 0 0 0 OA 長期間未整備の都市計画道路をめぐる都市計画訴訟に関する研究
- 著者
- 川崎 興太 大村 謙二郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.43.3, pp.271-276, 2008-10-25 (Released:2017-01-01)
- 参考文献数
- 23
本研究は、長期間未整備の都市計画道路をめぐる都市計画訴訟、具体的には都市計画制限に基づく建築不許可処分の取消訴訟及び都市計画制限に対する損失補償訴訟の判例について考察することを目的とするものである。都市計画の存立基盤は、原理的には、長期的安定性・継続性と可変性・柔軟性との緊張関係の上にありながらも、実際には建築自由の原則を尊重する観念の反対論理として、ひとたび都市計画決定を行って財産権に制限を課したならば、その後の都市計画の運用は慎重に行うべきだとの思考に固執するあまりに時間の観念が稀薄になり、いかに社会経済情勢や環境諸条件等が変化しようとも、既決のものは所与不変の事実として自明視され、適切に見直しが行われなかった場合が少なくなかったように思われる。これは、本質的には都市計画の効力が持続することについての実体的かつ手続的な合理性の問題だと考えられる。本研究では、こうした観点から、今後の都市計画道路の整備及び見直しを進める上での検討課題として、都市計画変更義務の的確な遂行と事業期間明示型都市計画制度の導入、都市計画基礎調査の内容の充実、都市計画提案制度の活用要件の拡充を提起している。
1 0 0 0 OA 準都市計画区域の指定実績と法制度上の問題点
- 著者
- 川崎 興太
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.50-61, 2012-04-25 (Released:2012-04-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
本研究は、平成12年に創設された市町村指定の準都市計画区域と平成18年の法改正後における都道府県指定の準都市計画区域の実績を分析し、都道府県の準都市計画区域制度等に関する認識を明らかにした上で、九州北部3県による構造改革特区の提案とこれに対する国土交通省の回答をもとに準都市計画区域に関する法制度上の問題点について考察することを通じて、準都市計画区域の指定実績と法制度上の問題点に関する知見を得ることを目的とするものである。本研究を通じて、(1) 市町村指定の準都市計画区域は、4区域(4市町村)の実績にとどまったが、都道府県指定の準都市計画区域は大規模集客施設の立地制限を主たる目的とするものを中心として44区域(9道県)となっていること、(2) 都道府県は、少なからず「土地利用規制が課されるばかりで、都市計画事業が行われないことなどから、住民の理解を得ることが困難であること」や「用途や規模の違いにかかわらず接道義務規定等の集団規定が一律的に適用され、既存不適格建築物などが発生すること」などを準都市計画区域制度のデメリットとして認識していること、(3) 準都市計画区域に関する法制度上の問題点は、(1)都市計画区域外における原初的な都市的土地利用規制の不在、(2)市街地外において緩くなる都市的土地利用規制の論理構成、(3)都道府県の全域を対象とした都市計画に関する基本方針の欠如にあることが明らかになった。
1 0 0 0 IR 木下広次の「在仏雑記」と木下助之宛書簡(1876年7月22日)
- 著者
- 冨岡 勝
- 出版者
- 近畿大学教職教育部
- 雑誌
- 近畿大学教育論叢 (ISSN:18809006)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.59-74, 2012
- 著者
- 七戸 克彦 Shichinohe Katsuhiko
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナー (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.10, pp.64-66, 2009-10
1 0 0 0 IR 資料解説・目録 木下広次関係資料
- 出版者
- 京都大学大学文書館
- 雑誌
- 京都大学大学文書館研究紀要 (ISSN:13489135)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.79-127, 2005-03-25
1 0 0 0 OA 〈史料紹介〉木下広次の「在仏雑記」と木下助之宛木下広次書簡(1876年7月22日)
- 著者
- 冨岡 勝
- 出版者
- 近畿大学教職教育部
- 雑誌
- 近畿大学教育論叢 = The research journal of the Department of Teacher Education, Kinki University (ISSN:18809006)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.59-74, 2012-11-01
1 0 0 0 IR 京都帝国大学と報徳主義 : 岡田総長退職事件をめぐって
- 著者
- 並松 信久
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.46-73, 2005-03
- 被引用文献数
- 1
京都帝国大学は,わが国で二番目の帝国大学として創設される。その創設以来,沢柳事件・河上事件・瀧川事件というように,大学の自治をめぐる事件が数多く起こっている。しかしながら,総長人事や教授人事に関する問題は,これらの事件が発生する以前に,すでに起こっている。その先駆的な事例が岡田総長退職事件である。第二代総長となる岡田良平は,その在任期間が約10 カ月と短く,しかも総長退職をめぐって教授側と文部省との対立をみている。 岡田良平は幼い頃から報徳主義の影響を受け,文部官僚となった後も,この思想をモデルとすることがしばしばみられる。岡田良平は文部官僚だけでなく,第一高等学校教授,山口高等中学校校長などの教職も歴任する。報徳主義の影響と教職の経験によって,岡田は自らの教育理念をつくっていくが,それを創設後約10 年を経過していた京都帝国大学において実践する。岡田良平の就任時の京都帝国大学は,創設期における独創性を失い,その研究教育体制の構築において苦悩していた時期である。したがって,文部省から送り込まれた官僚である岡田良平の実践は,教授側の猛反発を招く。 岡田良平の総長退職は,岡田良平の文部次官と総長の兼任をきっかけに,急速に展開する。結果的に山県有朋の判断で,岡田良平は総長を退職して文部次官専任となるが,それはもちろん京都帝国大学が新たな研究教育体制を構築したからではない。岡田良平が突きつけたのは,大学のあり方に関する問題であるが,京都帝国大学はそれに答えることなく,大学自治の問題が,主要な課題となっていく。つまり大学の問題は,研究教育体制の確立ではなく,自治の問題へと転化している。一方,岡田良平は総長退職後に文部大臣となり,現在の高等研究教育制度の基礎となる大学令の公布に大きな役割を果たす。この大学令には,岡田良平の報徳主義や京都帝国大学での経験による成果がみられる。 1.はじめに 2.京都帝国大学の創設期 3.岡田良平の経歴 4.岡田総長の大学運営 5.岡田総長退職後の展開 6.結 語
1 0 0 0 OA さくんたら姫 : 梵劇
- 著者
- Kennichi Kakudo Yanhua Bai Zhiyan Liu Yaqion Li Yasuhiro Ito Takashi Ozaki
- 出版者
- The Japan Endocrine Society
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.1-12, 2012 (Released:2012-01-31)
- 参考文献数
- 73
- 被引用文献数
- 16 52
We propose a new classification of thyroid follicular cell tumors which is correlated with patient’s prognosis. It is unique as to two new categories: borderline malignancy between benign and malignant, and moderately differentiated adenocarcinoma (MDA) as a differentiation classification to stratify tumor aggressiveness. As to diagnostic criteria, we recommend invasiveness (capsular and vascular invasion) to separate benign and malignant and it should not be based on presence or absence of papillary thyroid carcinoma (PTC) type nuclear features (PTC-N). Thus borderline malignancy in our new classification includes some of the formerly malignant tumors and they are 1) papillary microcarcinoma, 2) encapsulated conventional PTC (EncPTC), 3) encapsulated follicular variant PTC (EnFVPTC), 4) well differentiated tumor of uncertain malignant potential (WDT-UMP), 5) follicular tumors of uncertain malignant potential (FT-UMP), and 6) capsular invasion only follicular thyroid carcinoma (FTC). Review of the literature revealed that those thyroid tumors have consistently excellent outcome. Well differentiated follicular cell adenocarcinoma (WDA) in our classification includes common type PTC and low-risk follicular carcinoma (FTC). They are invasive (diffuse infiltrative) common type PTC and minimally invasive type FTC with less than 4 foci of angioinvasion. Moderately differentiated follicular cell adenocarcinoma (MDA) includes FTC with angioinvasion (more than 4), aggressive variants of PTC, such as tall cell, columnar cell, solid, loss of cellular polarity/cohesiveness (hobnail) variants and encapsulated carcinoma with high grade histology. Poorly differentiated carcinoma (PDC) includes PDC of WHO definition, insular carcinoma, tumors with minor anaplastic transformation and tumors with distant metastasis at presentation.
- 著者
- Toru Hifumi Hayato Yoshioka Kazunori Imai Toshihiro Tawara Takashi Kanemura Eiju Hasegawa Hiroshi Kato Yuichi Koido
- 出版者
- The Japanese Society of Intensive Care Medicine
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.607-610, 2011-10-01 (Released:2012-03-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
The cases of intake of organophosphate pesticides reported in Japan are mainly due to oral ingestion associated with attempted suicides. We report a case of organophosphate pesticide poisoning in which percutaneous absorption was suspected to be the cause. A 61-year-old woman was brought to our hospital because of consciousness disturbance. She was found lethargic, lying in the bathroom, by her husband. She had a significant medical history of hypertension. On admission, her Glasgow coma scale (GCS) score was 14/15. Her vital signs were as follows: body temperature, 35.3°C; blood pressure, 185/102 mmHg; heart rate, 106 /min; and respiratory rate, 23 /min. Her oxygen saturation was 100%. Her pupils were 2 mm in diameter, equal in size, round, and reactive. The rest of the examination was unremarkable. Chest X-ray, head CT, and head MRI were performed, but failed to identify the cause of the consciousness disturbance. Three hours after arrival, her oxygen saturation level had fallen and diaphoresis, miosis, and lacrimation had developed, while she was intubated under sedation. Prior to tracheal intubation, we asked her whether she had taken any organophosphate agent, which she denied. No organophosphate smell was detected from the endotracheal tube. Nine hours after arrival, her cholinesterase level was reported to be 11 IU/l, and we could finally confirm the diagnosis. Pralidoxime and atropine therapy was accordingly started. Seventeen hours after arrival, her family brought bottles of pesticide (smithion®) to the hospital. It transpired that she had handled this organophosphate pesticide without wearing gloves, and that earlier she had received abrasions to her hands. Therefore, it was assumed that the organophosphate was easily absorbed through her skin. Critical care physicians should bear in mind that whenever they see patients with consciousness disturbance, percutaneously absorbed organophosphate poisoning could be one of the causes.
1 0 0 0 可変磁力メモリモータの原理と基本特性
- 著者
- 堺 和人 結城 和明 橋場 豊 高橋 則雄 安井 和也 ゴーウッティクンランシー リリット
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌. D, 産業応用部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. D, A publication of Industry Applications Society (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.1, pp.53-60, 2011-01-01
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 4 27
A reduction in the power consumed by motors is required for energy saving in the case of electrical appliances and electric vehicles (EV). The motors used for operating these apparatus operate at variable speeds. Further, the motors operate with small load in stationary mode and with large load in start-up mode. A permanent magnet motor can operate at the rated power with a high efficiency. However, the efficiency is lower at small load or high speed because the large constant magnetic force results in substantial core loss. Furthermore, the flux-weakening current that depresses voltage at high speed leads to significant copper loss. Therefore, we have developed a new technique for controlling the magnetic force of permanent magnet on the basis of the load or speed of the motor. In this paper, we propose the novel motor that can vary magnetic flux and we clarify the principle.
1 0 0 0 OA 出水一件
- 巻号頁・発行日
- vol.第118冊, 1000
1 0 0 0 OA 高安定セラミックコンデンサの20年間にわたる経年変化特性の実測
- 著者
- 齋田 貢 吉江 達夫 山名 法明 奈良井 啓一 村守 清
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.6, pp.779-784, 1995-05-20 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
The authors started studying and developing a new capacitor used for a 1.5 MHz highly-stable LC tuning circuit in 1963. The high-stability of capacitor was severely required under the conditions that the signal voltage is from 1.4 to 9.2 V, the temperature is from -30 to 65°C and the period is for 20 years. The aging characteristics of the ceramic capacitors available 20 years ago were ΔC/C=±0.1%/year or so, but the requirements was ΔC/C=(-0.01±0.08)%/20 years. In addition, no design method to satisfy the requirements was established.Therefore, the authors developed a ceramic capacitor housed in a low-humidity metallic case using a paraelectric (MgTiO3) element, considering the stability of aging characteristics for 20 years.It could be assumed during the study that the aging characteristics would change almost linearly with the logarithm of time under the influence of humidity. So, the authors proposed the characteristics change for 20 years could be expected based on the data for 10 days of the specimen. To confirm that the proposal was correct, they measured the aging characteristics for 20 years, and found that the measurement value was within the specified value of ΔC/C which was (-0.01±0.08) %/20 years.
1 0 0 0 OA 緜考輯録
- 著者
- [小野景湛] [等編]
- 巻号頁・発行日
- vol.第56冊, 1000
1 0 0 0 IR 『大日本紡績聯合会月報』収録中国関係記事目録(1889~1943年)
- 著者
- 金丸裕一
- 雑誌
- 近代中国研究彙報 / Kindai Chugoku Kenkyu Iho
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.43-93, 1994
- 著者
- 仁科 エミ
- 出版者
- 放送大学
- 雑誌
- 研究報告 (ISSN:09152202)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.20-36, 1996-12