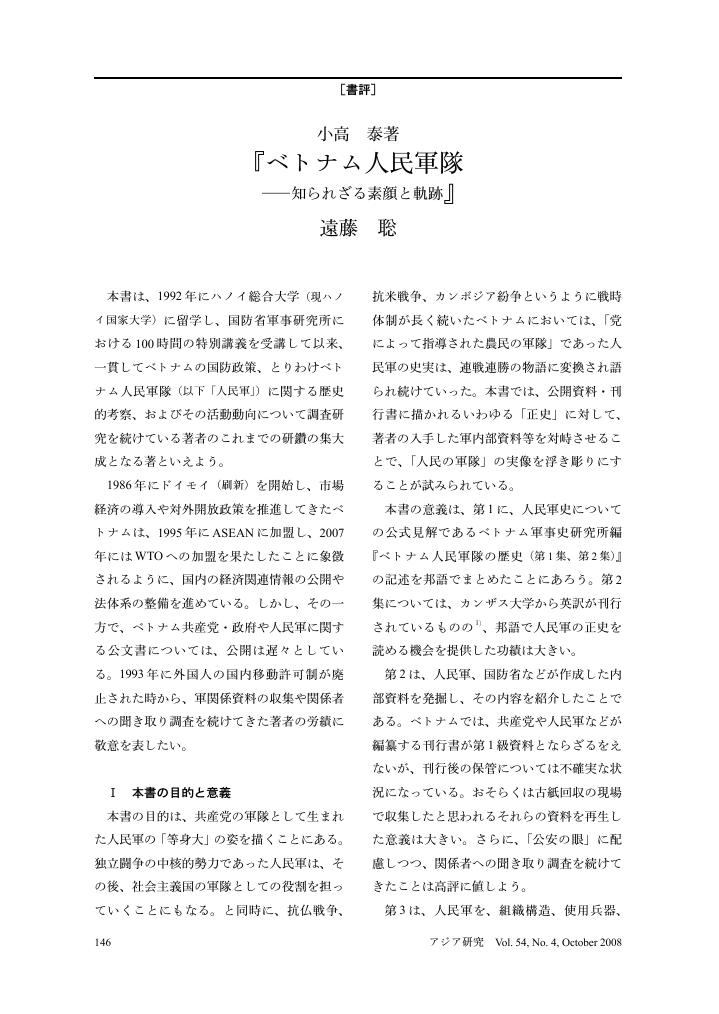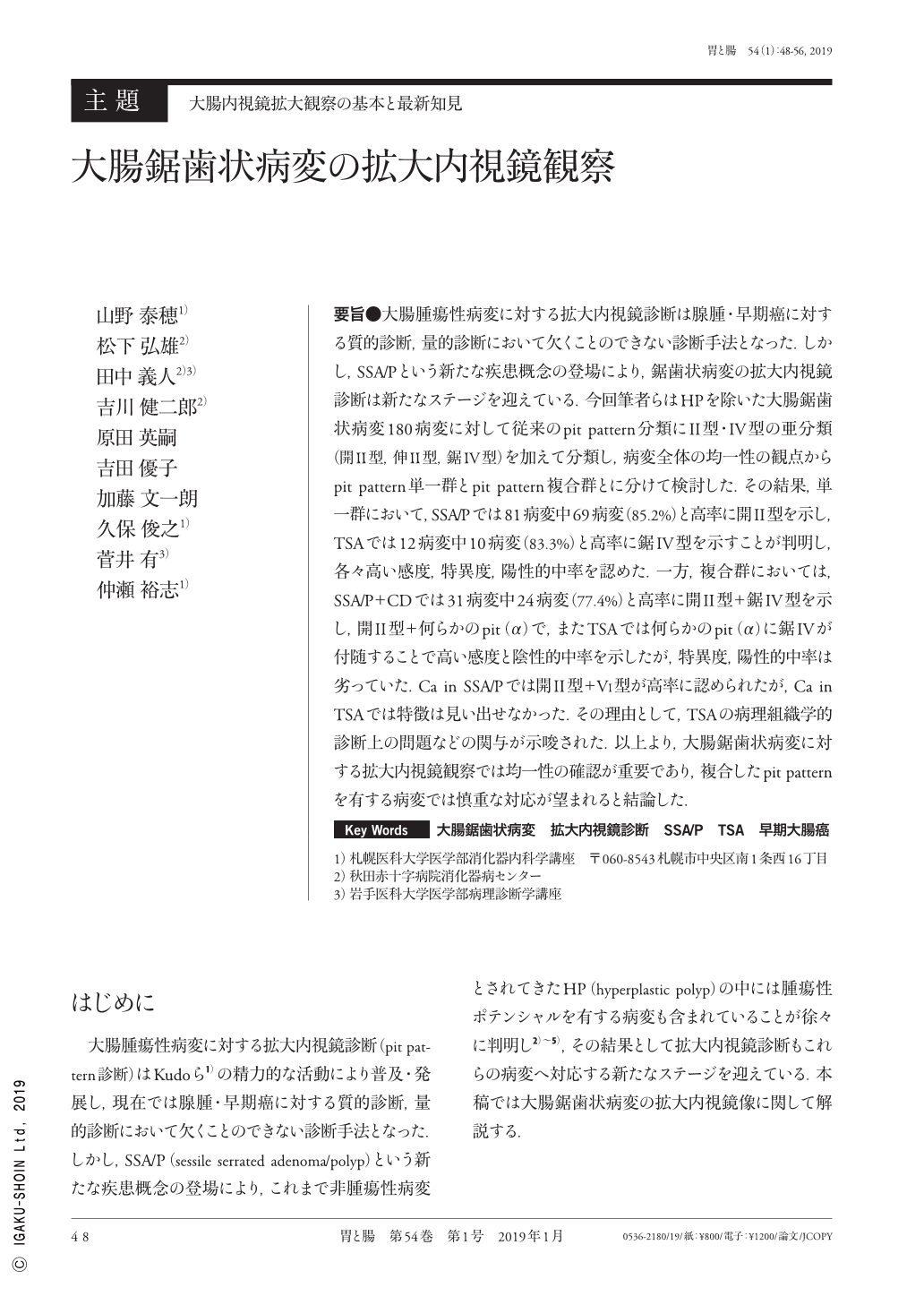- 著者
- 青木 学一 小田 さつき 久保田 聡 齋藤 栄 横田 訓男 柴﨑 淳 渋谷 清 酒向 孫市 尾鳥 勝也
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.1, pp.125-133, 2021-01-01 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
The immunosuppressant azathioprine (AZA) is classified as a hazardous drug. AZA contamination during tablet-splitting increases exposure risk. However, there is no study on contamination and exposure during AZA tablet splitting and dispensing. AZA tablet splitting and dispensing methods were classified based on whether tweezers are used during splitting and packaging. In Dispensing Method (1), no tweezers were used in either step. In Dispensing Method (2), no tweezers were used during tablet splitting, but were used during packaging. In Dispensing Method (3), tweezers were used in both steps. After AZA half-tablet split-dispensing, we quantified the adherent AZA removed from the tools, packaging machines, and dispensing counters by three consecutive wipings with water-dampened polypropylene cloths. A large amount of AZA adhered to the gloves used in Dispensing Methods (1) and (2), wherein tablets were placed with gloved hands, compared with Dispensing Method (3), wherein tablets were held with tweezers. Thus, the gloves must be replaced before touching the packaging paper during the final step. After three consecutive wipings, AZA was not detected at most of the sites in the third round. Thus, we recommend that (1) AZA tablet splitting should be performed while wearing gloves, (2) the gloves should be changed before packaging the half tablets, and (3) the tools, packaging machines, and dispensing counters should be wiped twice or thrice with a water-dampened cloth after dispensing.
5 0 0 0 OA 潜在記憶現象としての単純接触効果
- 著者
- 生駒 忍
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.113-131, 2005-08-31 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 175
- 被引用文献数
- 7 2
ある対象への反復接触がその対象への好意度を高めるという単純接触効果は古くから知られている現象である.単純接触効果は潜在記憶現象であり,実験変数,被験者変数,推計学的独立性において顕在記憶から乖離を示す.一方で,単純接触効果と直接プライミング効果との間には相違も見られる.知覚的流暢性誤帰属説の妥当性,古典的条件づけとの関係,構造的単純接触効果の位置づけ,個人差といった論点について概観し,今後の研究の方向性について論ずる.
5 0 0 0 山陽新幹線・JR神戸線に見るコンクリート構造物の被害と復旧
- 著者
- 北後 征雄
- 出版者
- MATERIALS LIFE SOCIETY, JAPAN
- 雑誌
- マテリアルライフ (ISSN:09153594)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.22-27, 1996-01-25
- 著者
- 山本 真司 ヤマモト シンジ Yamamoto Shinji
- 出版者
- 東京外国語大学語学研究所
- 雑誌
- 語学研究所論集 (ISSN:13419846)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.151-160, 2010
- 巻号頁・発行日
- 1944
5 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1932年02月16日, 1932-02-16
5 0 0 0 漢代「天下の母」考
- 著者
- 石井 和志
- 出版者
- 立命館東洋史學會
- 雑誌
- 立命館東洋史學 = The journal of Ritsumeikan East Asian History Studies (ISSN:13451073)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.47-84, 2021
5 0 0 0 OA 小高 泰著 『ベトナム人民軍隊―知られざる素顔と軌跡』
- 著者
- 遠藤 聡
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.146-150, 2008-10-31 (Released:2014-09-15)
5 0 0 0 OA 前頭連合野のしくみとはたらき
- 著者
- 渡邊 正孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.1-8, 2016-03-31 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3 1
高次機能の中枢としてヒトで最も発達した前頭連合野は, 外側部, 内側部, 腹側 (眼窩) 部に区分される。外側部は行動の認知・実行制御, 内側部は心の理論・社会行動, 腹側部は行動の情動・動機づけ制御, に重要な役割を果たす。また前頭連合野内でより前方の部位はより抽象的かつ高次な情報処理を担う。前頭連合野の腹内側部 (内側部と腹側部の前部) は, 情動・動機づけに基づく意思決定に関わる。前頭連合野の最前部 (前頭極) の特に外側部はヒトに特有な脳部位であり, 複雑, 抽象的な認知操作に重要な役割を果たす。サルを用いた私たちの研究において, (1) 競争における勝ち負けを捉えるような社会行動に関係する前頭連合野ニューロンがあること, (2) PET で調べると, 前頭連合野内側部において, 安静時に活動性が増すこと, (3) 前頭連合野ドーパミンは認知課題遂行中に比して安静時に前頭連合野外側部では減少し, 内側部では増加すること, が示された。
- 著者
- 長島 和幸
- 出版者
- 日本スポーツ教育学会
- 雑誌
- スポーツ教育学研究 (ISSN:09118845)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.13-26, 2020-01-31 (Released:2020-05-20)
- 参考文献数
- 28
The aim of this study is to establish Ichiro Hatta’s “konjo” theory through analysis of his criticism of this trending term, “konjo”, along with his “training” concept, both terms he used during the 1960s. The first analysis identifies Hatta’s definition of “takeyari konjo” and “makeinu konjo” in his criticism. These definitions condemned training methods as “irrational”. Athletes and coaches who were supposed to aim at winning, yet focused on cultivating just a “mental” side without accessing “authentic strength”. Therefore Hatta defined any victories as mere coincidences. Hatta’s concept of “konjo” was grounded in the importance of both the “physical strength and mental strength” components of athletic ability. The second analysis of this research clarifies Hatta’s focus on consistent victory by targeting athletes’ “physical strength and mental strength” under seven types of “training” provided in his coaching. In essence, this study finds Hatta’s “konjo” theory was different from the popularized notion during the 1960s. We can characterize his perspective as being “physical strength and mental strength”. As will be outlined, his theory was embodied in his coaching.
5 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1912年10月28日, 1912-10-28
5 0 0 0 大腸鋸歯状病変に対する臨床現場での実情
- 著者
- 山野 泰穂 田中 信治 菅井 有 松下 弘雄 斎藤 彰一 三澤 将史 堀田 欣一 竹内 洋司 佐野 寧 永田 信二 河野 弘志
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.1648-1669, 2020-12-25
Introduction山野 本号は「大腸鋸歯状病変の新展開」ということで,本誌ではしばしば鋸歯状病変に関して特集されていますが,大腸鋸歯状病変,さらにはSSA/P(sessile serrated adenoma/polyp)に関しては概ね市民権を得ており,多くの内視鏡医が知っている病変であると思います.SSA/PはMSI(microsatellite instability)陽性大腸癌の前駆病変であろうと分子生物学的にも解析が進んでおり,adenoma-carcinoma sequence,de novo pathwayに次ぐ第三の発癌ルートserrated neoplastic pathwayとしてmalignant potentialも高いのではと考えられています. 一方,実臨床では鋸歯状病変,特にSSA/Pは本当に悪性度が高いのかという疑問があります.これまで長い間,SSA/Pは過形成性ポリープと見分けがつかず,非腫瘍として扱われ放置されてきた歴史,むしろadenomaのほうが前癌病変として問題であると考えられてきた歴史があります.
5 0 0 0 大腸鋸歯状病変の拡大内視鏡観察
- 著者
- 山野 泰穂 松下 弘雄 田中 義人 吉川 健二郎 原田 英嗣 吉田 優子 加藤 文一朗 久保 俊之 菅井 有 仲瀬 裕志
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.48-56, 2019-01-25
要旨●大腸腫瘍性病変に対する拡大内視鏡診断は腺腫・早期癌に対する質的診断,量的診断において欠くことのできない診断手法となった.しかし,SSA/Pという新たな疾患概念の登場により,鋸歯状病変の拡大内視鏡診断は新たなステージを迎えている.今回筆者らはHPを除いた大腸鋸歯状病変180病変に対して従来のpit pattern分類にII型・IV型の亜分類(開II型,伸II型,鋸IV型)を加えて分類し,病変全体の均一性の観点からpit pattern単一群とpit pattern複合群とに分けて検討した.その結果,単一群において,SSA/Pでは81病変中69病変(85.2%)と高率に開II型を示し,TSAでは12病変中10病変(83.3%)と高率に鋸IV型を示すことが判明し,各々高い感度,特異度,陽性的中率を認めた.一方,複合群においては,SSA/P+CDでは31病変中24病変(77.4%)と高率に開II型+鋸IV型を示し,開II型+何らかのpit(α)で,またTSAでは何らかのpit(α)に鋸IVが付随することで高い感度と陰性的中率を示したが,特異度,陽性的中率は劣っていた.Ca in SSA/Pでは開II型+VI型が高率に認められたが,Ca in TSAでは特徴は見い出せなかった.その理由として,TSAの病理組織学的診断上の問題などの関与が示唆された.以上より,大腸鋸歯状病変に対する拡大内視鏡観察では均一性の確認が重要であり,複合したpit patternを有する病変では慎重な対応が望まれると結論した.
5 0 0 0 IR 戦争記憶の形成 : 中学校国語教科書の分析
- 著者
- ユルマズ フィリズ 溝上 智恵子
- 出版者
- 「図書館情報メディア研究」編集委員会
- 雑誌
- 図書館情報メディア研究 (ISSN:13487884)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.51-60, 2013
5 0 0 0 IR 「問わず語り」の背後に潜むもの--『口述の生活史』成立の謎に迫る
- 著者
- 武笠 俊一 Mukasa Shunichi
- 出版者
- 三重大学人文学部文化学科
- 雑誌
- 人文論叢 (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.17-27, 2009
一九七七年に刊行された『口述の生活史 - 或る女の愛と呪いの日本近代』は、中野卓の最初の生活史研究である。この本において、中野は話者の主体性を最大限に尊重するという調査法を提示しその有効性を実例をもって示そうとした。中野の提唱した新しい調査法は、若手研究者の一都に強く支持され、その後の社会学における生活史研究の興隆のきっかけとなった。しかし、この方法を採用したからといって、ただちに優れた生活史研究が生み出されるという保証はない。では、良い生活史を生み出す話者の側の条件とはどのようなものか。インタビューにおける話者の主体性の尊重がなぜ優れた生活史の前提条件となるのか。本稿では、この二つの問題を『口述の生活史』の再検討によって明らかにしたい。中野卓がこの生活史の語り手と出会う四〇年前に、彼女は一通の長い手紙を書いている。それは、中野が聞き取った口述生活史の原型ともいうべき「自伝的な手紙」であった。しかし不思議なことに、話者の内海松代は幾度か行われたインタビューの中でこの手紙についてほとんど語っていない。どのような事情によってこの手紙は書かれたのか。その内容はどんなものだったのか - 語られなかった事実に注目することによって、この生活史に秘められた「話者の強い思い」が見えてくる。語られなかったことがらに対する徹底的な再検討という作業をすることによって、中野の調査法の意義が明らかになると思われる。
5 0 0 0 OA ストロマトライト研究の歴史と今後の展望
- 著者
- 山本 純之 磯﨑 行雄
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.5, pp.791-806, 2013-10-25 (Released:2013-10-31)
- 参考文献数
- 86
Ever since the term stromatolith was first coined by Kalkowsky in 1908, research studies on stromatolites have continued for more than a century. This article reviews the study history of living and fossil stromatotelites. The history is divided into two parts by the discovery in 1961 by Logan of living stromatolites in Shark Bay, Western Australia, because this determined the subsequent main trend of studies on both living and fossil stromatolites. Major contributions during the last three decades include documentation of (1) a worldwide bloom of stromatolites in Proterozoic low-middle lateral shallow seas, and (2) oxygen-producing cyanobacterial activity related to stromatolites from the 1990s, resulting in various new aspects being clarified, which include in-vitro cultivation gradually revealing cyanobacterial calcification and dome-formation. Future studies will be directed towards reconciling morphological disparities and formation mechanisms among fossil, living, and cultured stromatolites.
5 0 0 0 OA 美術館における絵画鑑賞者類型の析出と類型帰属要因の識別
- 著者
- 与謝野 有紀 林 直保子
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.73-104, 2018-03-31
本稿では、絵画鑑賞のために美術館に行くという行為を大衆的な贅沢消費行為として位置づけ、美術鑑賞後の感想や一般的な美術鑑賞態度に関するデータから、美術鑑賞行為の類型の析出を試みた。ここで用いたものと同一のデータから、林・与謝野(2017)は、共分散構造分析をもちいて、美術館に行く人々がいくつかの類型に分けられる可能性を指摘しているが、その分析手法では類型を直接に識別することはできない。ここでは、クラスタ分析と潜在クラス分析という異なる分析視野をもった手法を並行で用い、計量社会学的にこの課題にアプローチした。クラスタ分析では、感想について2 つのクラスタが、態度については6つのクラスタが析出された。また、潜在クラス分析では、感想、態度ともに3つの潜在クラスが識別された。さらに、それぞれの類型に属する要因を、性別、年齢、美術館に行くきっかけ、他者に話す程度、メディアや権威への追従傾向を説明変数とするロジスティック回帰分析および回帰分析で検討した。これらの検討の結果、クラスタ分析と潜在クラス分析の両者で、「積極的評価型」と「消極的評価型」の二つの類型が共通に析出された。さらに、態度に関する潜在クラス分析の結果からも、感想と対応するような「能動的鑑賞型」と「受動的鑑賞型」の二つの類型が析出された。また、「積極的評価型」、「能動的鑑賞型」の類型の人々は、要因分析の結果、大衆的贅沢消費をしている人々と見做しうる特徴を示した。一方、「消極的評価型」、「受動的鑑賞型」の人々では、大衆的贅沢消費や誇示的消費概念だけでは理解することが難しく、その行為の背後にある意図の解明が今後の課題となっている。
5 0 0 0 OA Lunar-related maturation and spawning migration in the honeycomb grouper, Epinephelus merra
- 著者
- Ryosuke Murata Takafumi Amagai Daisuke Izumida Yuji Mushirobira Ryo Nozu Kiyoshi Soyano
- 出版者
- The Japanese Coral Reef Society
- 雑誌
- Galaxea, Journal of Coral Reef Studies (ISSN:18830838)
- 巻号頁・発行日
- pp.G2021_S4R, (Released:2021-11-05)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 5
To better understand the eco-physiological characteristics of reproduction in the coral reef small honeycomb grouper, Epinephelus merra, we investigated their spawning migration using biotelemetry, in addition to reproductive physiology analysis. Histological observations indicated that final ovarian maturation was not completed in honeycomb grouper collected from the coral reef pond (CRP), even during their spawning season. Additionally, our visual observations revealed that fish numbers decreased in the CRP after a full moon, which is thought to be their spawning time, suggesting their spawning migration. Next, we investigated the migration of honeycomb grouper during their spawning season using biotelemetry. Our investigations indicated that honeycomb grouper migrated from the inside of the CRP to the outside after a full moon, and then back to the inside again a few days later. These results strongly suggested that honeycomb grouper migrate to spawning sites located outside of the CRP, attain final ovarian maturation, and spawn after a full moon in the spawning season.