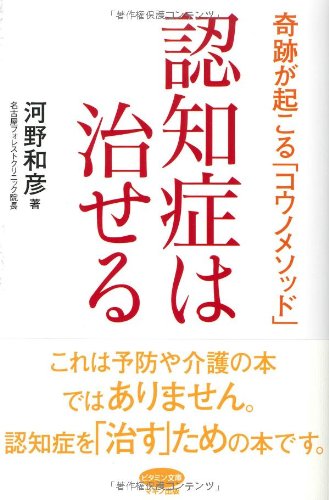1 0 0 0 OA 「文化侵略」か,「人間解放」か : 新しい英語教育の課題
- 著者
- 高島 敦子
- 出版者
- 青山学院女子短期大学
- 雑誌
- 青山學院女子短期大學紀要 (ISSN:03856801)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.97-117, 1995-12-10
1 0 0 0 複数解探索のための離散粒子群最適化アルゴリズム
- 著者
- 久保田 将史 斎藤 利通
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. NLP, 非線形問題 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.335, pp.15-19, 2010-12-06
基本的な離散型粒子群最適化アルゴリズム(DPSO)を提案する。同アルゴリズムでは、連続値探索空間を格子点によって離散化し、目的関数を標本化する。そして、離散探索空間に候補解基準を設ける。候補解が見つかった場合は、各候補解の近傍に新たな離散探索空間を生成し、それを細分化して、近似解を探索する。複数の最適解を探索する基本的な問題に対する数値実験を行い、アルゴリズムの有効性を検証する。
1 0 0 0 OA 精神薄弱児における発見型授業と説明型授業との比較研究
- 著者
- 田口 則良
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.12-22, 1978-03-30
現在および将来の社会生活を過ごすために「学び方能力」の育成は必須である。この能力は,特にBrunerが提唱した「発見学習」によって獲得させることができる。発見学習とは基本的内容を観察-予想-実験(発見)・検証のプロセスで学習者自身に発見させる仕方である。 この授業スタイルは抽象能力や既有知識,先行経験の乏しい学習者には適用が難しいとされている。しかし,授業は指導内容,方法との相対的関係で成立するものであるから,能力に合った指導内容を設定して,学習者の自発性だけに頼らず,授業者が積極的に働きかけたり,援助したりするならば,これらの学習者にも必ずしも適用が不可能ではないと思われる。 本研究はこのような観点から構築された発見型授業が精神薄弱児に適用可能かどうかを検討するものである。対比される授業スタイルとして説明型授業を構成する。これは観察-示範-実験・確認のプロセスで進められる授業者主導型スタイルである。 被験者は小学校特殊学級27名で,I.QとL.Aが釣合わされた2グループに分けられ,発見型と説明型授業を受ける。授業者は2名で始めにひとりは1グループの半数に発見型授業を,もうひとりは他のグループの半数に説明型授業を次に残りの半数にもう1つの型の授業をそれぞれ行う。指導内容は理科教材で「磁石」を取扱い,第3時までを2授業スタイルにより,第4時は共通の授業スタイルによりおもちや作りの作業課題をする。評価に関しては4名が授業の事前,直後,事後(1か月後,6か月後)にわたって知識,転移テストを聴取,授業中の意欲,探究的思考スタイルを評定する。 結果は次のとおりである。 (1) 授業者の発言内容は両授業スタイルの特徴を示す方向で異なる。発見型に多いカテゴリーは,ヒントを与える,課題意識を持たせる質問,考え方を受容する,であり,説明型に多いカテゴリーは,知識を与える,確認する,である。 (2) 知識問題の習得率(直後テスト/事前テスト)では両授業スタイル間に差が見出されない。しかし,1か月後の把持率(1か月後の事前テスト/直後テスト)では発見型が顕著によい。その効果は6か月後では消失している。 (3) 転移問題の習得率(直後テスト/事前テスト)は両授業スタイル間に差はない。これは転移問題と知識問題が類似していたためである。 (4) 自発発言数は第1時より,第2,3時で発見型が増加している。 (5) 第4時の授業中に測定された探究的思考スタイルは種々の観点から分析されたが,どれも差は見出せない。 (6) 習得された知識と矛盾する事例を観察させてその反応から信念を分析したところ,両授業スタイル間に差は見出されない。
テキストマイニングとは,テキストデータの特徴ベクトルにもとづくクラスタリングや自動分類を行うことであり.その中核となる技術として,特徴ベクトルの抽出やクラスタリング,パターン認識,情報推薦などがあげられる.これらの技術を様々なストリームデータに適用し,新たな知見を得ることが本研究の目的であり,それに関連する今年度の研究実績は大きく3つに分けられる:1.平成15年度の音楽データに続き,平成16年度では,クリックストリームデータ(ユーザがWebページ間で遷移する履歴)のマイニングを試みた.クリックストリームデータから,ユーザの情報探索行動のパターンを発見するために,同じ話題に関するWebページ間での移動回数など,独自な特徴ベクトルを用いた分析手法を提案した.この分析手法を,個人のウェブサイト,企業の公式ウェブサイト及びポータルサイトのクリックストリームデータに適用し,ユーザの行動パターンを明らかにすることによって,Webサイト運営の担当者が直観的に感じていたことを裏付けるとともに,Webサイト改善の方向に示唆を与えることができた.(文献1)2.マイニング技術を利用した情報推薦システムで試みされてこなかった「意外性」のある情報の推薦に注目し,利用者の新しい発見に繋がる情報,言い換えると意外性のある情報を推薦するために,マイナーグループと呼ぶ推薦者のグループを構成し,このグループから情報提供を受ける推薦システムを提案し,実装を行った.実装したシステムを利用し,学生を被験者として,映画作品推薦の実験を行った結果,意外性があり,且つ興味・関心を持て情報を提供できることを確認できた.(文献2)3.2001年から2003年に新品種として登録された272品種のバラの52週間の売上データを対象に,各週の売上を特徴ベクトルとして用いてクラスタリングを行った結果,バラ新品種が市場で受け入れられていく4種類のパターンを明らかにすることができた.(文献3)
- 著者
- 伊藤 仁之
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.341-343, 2001
回転群表現の2価性の説明モデルとして知られるDiracのひも付きハサミやFeynmanのワインダンスを検討し,これらが2価性の説明になっていないことを明らかにする。
1 0 0 0 認知症は治せる : 奇跡が起こる「コウノメソッド」
1 0 0 0 OA ウイーン市財政事情
- 出版者
- 東京市政調査会資料課
- 巻号頁・発行日
- 1924
1 0 0 0 日満華興亜団体会合記録
- 著者
- 蘆田 裕史
- 出版者
- 東レ経営研究所
- 雑誌
- 繊維トレンド (ISSN:13462970)
- 巻号頁・発行日
- no.101, pp.59-61, 2013-07
- 著者
- 蘆田 裕史
- 出版者
- 東レ経営研究所
- 雑誌
- 繊維トレンド (ISSN:13462970)
- 巻号頁・発行日
- no.100, pp.47-49, 2013-05
1 0 0 0 OA 千葉大学病院において生体部分肝移植手術を実施した8症例
- 著者
- 小林 進 落合 武徳 堀 誠司 宮内 英聡 清水 孝徳 千葉 聡 鈴木 孝雄 軍司 祥雄 島田 英昭 岡住 慎一 趙 明浩 大塚 恭寛 吉田 英生 大沼 直躬 金澤 正樹 山本 重則 小川 真司 河野 陽一 織田 成人 平澤 博之 一瀬 正治 江原 正明 横須賀 收 松谷 正一 丸山 紀史 税所 宏光 篠塚 典弘 西野 卓 野村 文夫 石倉 浩 宮崎 勝 田中 紘一
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 千葉医学雑誌 (ISSN:03035476)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.6, pp.265-276, 2004-12-01
千葉大学医学部附属病院において2000年3月から,2003年8月まで8例の生体部分肝移植手術を施行した。5例が18歳未満(7ヶ月,4歳,12歳,13歳,17歳)の小児例,3側が18歳以上(22歳,55歳,59歳)の成人例であった。2例(7ヶ月,4歳)の小児例は左外側区域グラフトであるが,他の6例はすべて右葉グラフトであった。2側が肝不全,肺炎のため移植後3ヶ月,2ヶ月で死亡となったが他の6例は健存中であり,元気に社会生活を送っている。第1例目は2000年3月6日に実施した13歳男児のウイルソン病性肝不全症例に対する(ドナー;姉22歳,右葉グラフト)生体部分肝移植である。現在,肝移植後4年3ヶ月が経過したが,肝機能,銅代謝は正常化し,神経症状も全く見られていない。第2例目は2000年11月23日に実施した12歳男児の亜急性型劇症肝炎症例である(ドナー;母親42歳,右葉グラフト)。術前,肝性昏睡度Vとなり,痛覚反応も消失するほどの昏睡状態であったが,術後3日でほぼ完全に意識は回復し,神経学的後遺症をまったく残さず退院となった。現在,術後3年7ヶ月年が経過したがプログラフ(タクロリムス)のみで拒絶反応は全く見られず,元気に高校生生活を送っている。第3側目は2001年7月2日に実施した生後7ヶ月男児の先天性胆道閉鎖症術後症例である。母親(30歳)からの左外側区域グラフトを用いた生体部分肝移植であったが,術後,出血,腹膜炎により,2回の開腹術,B3胆管閉塞のためPTCD,さらに急性拒絶反応も併発し,肝機能の改善が見られず,術後管理に難渋したが,術後1ヶ月ごろより,徐々にビリルビンも下降し始め,病態も落ち着いた。術後6ヵ月目に人工肛門閉鎖,腸管空腸吻合を行い,現在,2年11ケ月が経過し,免疫抑制剤なしで拒絶反応は見られず,すっかり元気になり,精神的身体的成長障害も見られていない。第4例目は2001年11月5日に行った22歳男性の先天性胆道閉鎖症術後症例である(ドナー:母親62歳,右葉グラフト)。術後10日目ごろから,38.5度前後の熱発が続き,白血球数は22.700/mm^3と上昇し,さらに腹腔内出血が見られ,開腹手術を行った。しかし,その後敗血症症状が出現し,さらに移植肝の梗塞巣が現れ,徐々に肝不全へと進行し,第85病日死亡となった。第5例目は2002年1月28日に行った4歳女児のオルニチントランスカルバミラーゼ(OTC)欠損症症例である(ドナー;父親35歳,左外側区域グラフト)。肝移植前は高アンモニア血症のため32回の入院を要したが,肝移植後,血中アンモニア値は正常化し,卵,プリンなどの経口摂取が可能となり,QOLの劇的な改善が見られた。現在2年5ヶ月が経過したが,今年(2004年)小学校に入学し元気に通学している。第6例目は2002年7月30日に行った17歳女性の亜急性型劇症肝炎(自己免疫性肝炎)症例である(ドナー:母親44歳,右葉グラフト)。意識は第2病日までにほぼ回復し,第4病日まで順調な経過をたどっていた。しかし,第6病日突然,超音波ドップラー検査で門脈血流の消失が見られた。同日のCTAPにて,グラフトは前区域を中心とした広範囲の門派血流不全域が示された。その後,肝の梗塞巣は前区域の肝表面領域に限局し,肝機能の回復が見られたが,多剤耐性菌による重症肺炎を併発し,第49病日死亡となった。第7例目は2003年3月17日に行った59歳男性の肝癌合併肝硬変症例(HCV陽性)症例である(ドナー:三男26歳,右葉グラフト)。Child-Pugh Cであり,S8に4個,S5に1個,計5個の小肝細胞癌を認めた。ドナー肝右葉は中肝静脈による広い環流域をもっていたため,中肝静脈付きの右葉グラフトとなった。術後は非常に順調な経過をたどり,インターフェロン投与によりC型肝炎ウイルスのコントロールを行い,移植後1年3ヶ月を経過したが,肝癌の再発も見られず順調な経過をとっている。第8例目は2003年8月11日に行った55歳男性の肝癌合併肝硬変症例(HBV陽性)症例である(ドナー;妻50歳,右葉グラフト)。Child-Pugh Cであり,S2に1個,S3に1個,計2個の小肝細胞癌を認めた。グラフト肝は470gであり過小グラフト状態となることが懸念されたため,門脈一下大静脈シヤントを作成した。術後はHBV Immunoglobulin,ラミブジン投与により,B型肝炎ウイルスは陰性化し,順調に肝機能は改善し合併症もなく退院となった。現在移植後10ヶ月が経過したが,肝癌の再発も見られず順調な経過をとっている。ドナー8例全員において,血液及び血液製剤は一切使用せず,術後トラブルもなく,20日以内に退院となっている。また肝切除後の後遺症も見られていない。
1 0 0 0 カンキツ新品種「大分果研4号」の特性
- 著者
- 楢原 稔 若月 洋 佐藤 祥子
- 出版者
- 大分県農林水産研究センター
- 雑誌
- 大分県農林水産研究センター研究報告 農業編 (ISSN:18819206)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.69-73, 2009-03
1.「大分果研4号」は、1995年に大分県柑橘試験場津久見分場(現大分県農林水産研究センター果樹研究所津久見試験地)において高糖系温州「大津八号」にタンゴール「天草」の花粉を交配して育成した早生カンキツで、2007年3月に種苗法に基づき品種登録を申請し、2009年3月6日に品種登録された。2.樹勢は中程度で、樹姿は開張性である。枝梢の太さは細く、長さは短く、密度はやや密である。結実し始めると樹勢が落ち着き、枝に発生していた短いトゲはほぼ消失する。3.単生花序を形成し、花弁は5枚で白色の紡錘形。花糸の分離程度は一部合一で、花糸の数は少なく、花粉が少しある。4.果実の形は扁球形で、果形指数は115。果頂部の形は陥没しており、凹環は不明瞭。果梗部は球面で、放射条溝は無である。果実の重さは170g程度で、果皮の色は濃橙。油胞の大きさは中で、果面の粗滑は滑〜中、果皮の厚さは中で、はく皮は易である。じょうのう膜は軟らかく、さじょうの形・大きさはともに中である。5.果汁は多く、12月中旬の果実品質は、果汁歩合85%、糖度(Brix)12.0、クエン酸0.82%と、酸切れの早い品種である。香気は中程度のオレンジ香がある。種子は中程度入るが、他家受粉がなければ少となる。6.収穫適期は、果皮が完全着色となり、クエン酸が0.8%程度となる11月下旬頃から12月中旬までである。7.着花は良好で、隔年結果性は低い。また、果皮が弱く、果肉が軟らかいので、収穫時期の果実の取り扱いには注意が必要である。8.温州ミカンの栽培可能な地域であれば栽培は可能であるが、減酸が早く年内出荷が可能な早生カンキツとしての特性を十分に発揮させるためには、比較的土壌が浅く、排水、日照が良好な緩傾斜地での栽培が望ましい。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.323, pp.53-55, 2003-03-14
鳥取市の市街地を流れる天神川は,護岸がぜい弱で河道の断面積も不足しているので,鳥取県が改修工事を進めてきた。天神川に架かる立川大橋を境にして,下流側は2000年度までに工事が完了しており,上流側の約100mの区間を2001年度から施工し始める計画だった。 鳥取県は2001年3月6日,護岸改修の詳細設計や用地測量,用地調査について指名競争入札を実施。
1 0 0 0 OA 市民練成 : 紀元二千六百年記念東京市民練成道場建設概要
- 出版者
- 東京市記念事業部
- 巻号頁・発行日
- 1942
1 0 0 0 沖縄県八重山諸島で記録された両生類・爬虫類
- 出版者
- 近畿大学農学部
- 雑誌
- 近畿大学農学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Agriculture of Kinki University (ISSN:04538889)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.163-169, 2011-03
日本の豊かな生物相に対する理解を深めることを目的に、2010年2月28日から3月6日の7日間、近畿大学農学部生態調査班を中心としたメンバーで八重山諸島の石垣島と西表島にて両生類、爬虫類の調査・観察を行った。調査地を含む琉球列島は、地理的変遷から多くの固有種や固有亜種の生息地として知られている。今調査の結果として、全体では両生類が4科6種、爬虫類が5科8種確認され、このうち固有種が7種、固有亜種が3種、国の天然記念物が2種記録された。島ごとでは石垣島で両生類が3科4種、爬虫類が4科4種、西表島では両生類が3科3種、爬虫類が5科8種それぞれ記録された。
1 0 0 0 初一国民学校全科指導記録
- 著者
- 三苫正雄, 田中豊太郎 著
- 出版者
- 厚生閣
- 巻号頁・発行日
- 1942
1 0 0 0 OA 大学受験評論文における既有知識活用方略の認知
- 著者
- 古居 美香
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 : 別冊 (ISSN:13402218)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.1-12, 2010-03-30 (Released:2016-11-23)
1 0 0 0 OA 独逸自動車国道 : 技術的基本問題
- 著者
- ドイツ自動車国道管理局 編
- 出版者
- 都市土木
- 巻号頁・発行日
- 1942