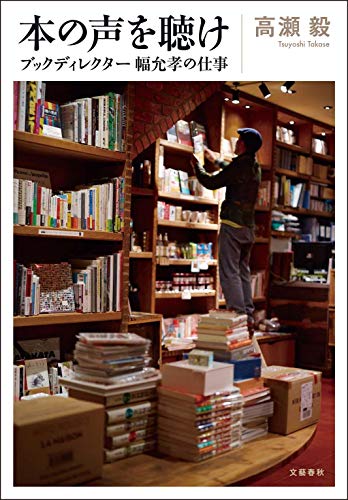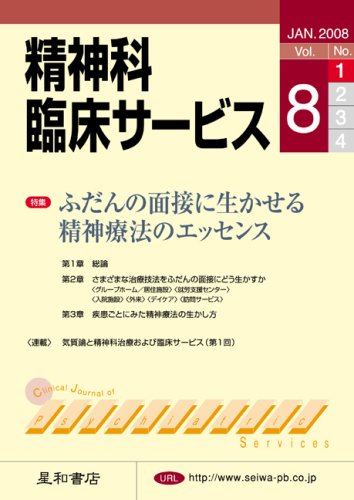- 著者
- Kensaku Aihara Tomohiro Handa Sonoko Nagai Kiminobu Tanizawa Kizuku Watanabe Yuka Harada Yuichi Chihara Takefumi Hitomi Toru Oga Tomomasa Tsuboi Kazuo Chin Michiaki Mishima
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.11, pp.1157-1162, 2011 (Released:2011-06-01)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 8 37
Objective We identified the prognostic relevance of pneumothorax in interstitial lung disease (ILD) patients and evaluated the efficacy and safety of autologous blood-patch pleurodesis. Methods We retrospectively reviewed 59 occurrences of pneumothorax in 34 ILD patients identified over a 12-year period. Results Air leakage ceased in 16 of 22 (72.7%) episodes after blood pleurodesis and in 11 of 14 (78.6%) episodes after chemical pleurodesis. Both the cure ratio and recurrence ratio in the cure episodes were comparable with those in the chemical pleurodesis group (p=0.99 and 0.99, respectively). In addition, there were no harmful events associated with blood pleurodesis. The median survival time after the first episode of pneumothorax was less than 9 months in patients with idiopathic interstitial pneumonia (IIP) and only around 3 years in the patients with other types of ILD, which have essentially favorable outcomes. Kaplan-Meier survival estimates were significantly worse in the patients with concomitant pneumomediastinum than in those without (p<0.05). A multivariate Cox regression analysis identified that the number of episodes of pneumothorax, IIP diagnosis and concomitant pneumomediastinum were independent predictors of death. Conclusion Autologous blood-patch pleurodesis is safe and worth considering as a first-line treatment for pneumothorax secondary to ILD. However, despite treatments, the prognosis after the onset of pneumothorax in ILD patients was found to be poor. In addition, concomitant pneumomediastinum may further worsen the prognosis.
- 著者
- Na Kyung Lee Sung Min Son Seok Hyun Nam Jung Won Kwon Kyung Woo Kang Kyoung Kim
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.10, pp.1235-1237, 2013 (Released:2013-11-20)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3 10
[Purpose] The purpose of this study was to investigate the effect of progressive resistance training (PRT) integrated with foot and ankle compression on the gait ability of post-stroke patients. [Subjects and Methods] Participants were randomly allocated to two groups: the PRT group (n=14) and the control group (n=14). Subjects in the PRT group received training for 30 minutes, five days per week, for a period of six weeks. Gait ability was evaluated using the RsScan system. [Results] Use of PRT integrated with foot and ankle compression resulted in significant improvements in temporal parameters (gait velocity, step time, and double limb support) and spatial parameters (step length, stride length, and heel-to-heel base of support). [Conclusion] Progressive resistance training integrated with foot and ankle compression improved the gait ability of stroke patients. These results suggest the feasibility and suitability of integration of PRT with foot and ankle compression for individuals with stroke.
- 著者
- Joong-Chul Lee Ji Youn Kim Gi Duck Park
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.12, pp.1595-1599, 2013 (Released:2014-01-08)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2 5
[Purpose] To examine changes in the knee joint’s isokinetic muscle functions following systematic and gradual rehabilitation exercises lasting for 12 weeks for male and female patients who underwent anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. Differences in muscle functions between the uninvolved side (US) and the involved side (IS) before surgery, differences in muscle functions between US and IS after rehabilitation exercises lasting for 12 weeks, and changes in muscle functions on US and IS between before and after surgery were analyzed to examine the effects of accelerated rehabilitation exercises after ACL reconstruction. [Subjects] The study subjects were 10 patients, five females and five males, who underwent ACL reconstruction performed by the same surgeon. [Methods] As a measuring tool, a Biodex Multi-joint system 3pro (USA), which is an isokinetic measuring device, was used to examine the flexion and extension forces of the knee joint. During isokinetic muscle strength evaluation, the ROM of US was set to be the same as that of IS for consistency of measurement. [Results] At 60°/s, the isokinetic muscle functions of the females did not show any significant change between before and after surgery in any of the variables on both US and IS. At 60°/s, the isokinetic muscle functions of the males did not show any significant change between before and after surgery in the peak torque, average power, and entire work done on US. In extension, peak torque on IS did not show any significant change.
1 0 0 0 OA ユニットケア実施施設における認知症高齢者への安全なケア提供に関する研究
認知症高齢者を対象としてユニットケアを実施している施設における安全なケア提供についての実態を知るため、2009年度に施設スタッフおよび管理者を対象にインタヴュー調査を実施した。2010年度は2009年度の調査で得られた結果をもとに質問紙を作成し、無作為抽出した全国の高齢者施設の管理者・看護師・介護士に対し、質問紙調査(郵送法)を実施した。因子分析を行った結果、「安全なケア提供への工夫と困難」として、"全入居者の安全確保因子"、"職員の資質向上因子"、"多職種間での情報共有・支援因子"などの25の因子が抽出できた。さらに、施設群ごとの因子得点(平均値)を多重比較したところ、ユニットケア実施施設と非実施施設間における有意差は認めなかった。しかしながら、各因子を構成する項目ごとには有意差を認めるものがあるため、今後さらに分析を進め、認知症高齢者を対象としてユニットケアを実施している施設でのケアの特徴を見出す必要がある。
- 著者
- 新井将之
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経エレクトロニクス (ISSN:03851680)
- 巻号頁・発行日
- no.795, pp.139-143, 2001-05-07
- 被引用文献数
- 1
騒がしい水音を打ち消すように,男の叫び声が響き渡った。どうやら声の主はシャワー・ルームにいるらしい。 「これだよ,これ。忘れないうちにメモしとかなきゃ,と言ってもここはシャワー・ルームだしなぁ。いつもこうだ。だれか濡ぬれても使えるノートを発明してくれよ」 彼の名はMichael Farmwald(図1)。友人は彼を「アイデア・マン」と呼ぶ。
1 0 0 0 OA ヘテロな分散環境用makeの実装と大規模自然言語処理ワークフローの実行
- 著者
- 関谷 岳史
- 出版者
- 大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻
- 巻号頁・発行日
- 2008-03
報告番号: ; 学位授与年月日: 2008-03-24 ; 学位の種別: 修士 ; 学位の種類: 修士(情報理工学) ; 学位記番号: ; 研究科・専攻: 情報理工学系研究科電子情報学専攻
1 0 0 0 環極北文化の比較研究
平成3年度から継続して、平成4年度にも2回の研究集会を札幌と網走で開催し、研究会は計4回を数えた。その間に、代表者をふくめて、研究分担者全員が、順次研究発表を行ったが、研究集会以外にも、北海道立北方民族博物館で毎年秋に開かれるシンポジウムにも、半数以上の研究分担者が参加し、研究発表や討論を通じて、情報や意見を交換する機会をもった。平素は、別々の研究機関に促し、それぞれ独立に調査研究に従事している代表者および分担者は、2年間に、かなりな程度までお互いの研究成果を知ることができ、このようにして得た広い視野に立って、最終的な研究報告をまとめる段階に到達した。研究報告書は10篇の論文から構成され、アイヌ文化に関するもの2篇、北西海岸インディアン2篇、イヌイト(エスキモー)1篇、サミ(ラップ)1篇、計7篇は文化人類学に視点をおくものである。その他に、東南アラスカの現地の人類学者による寄稿1篇が加えられている。その他の2篇は、言語学関係のもので、北欧のサミと、北東アジアのヘジェン語を主題としている。研究報告書には、シベリア関係の論文がほとんど掲載されていないが、平成4年5月に刊行された「北の人類学一環極北地域の文化と生態」(岡田、岡田編、アカデミア出版会」に代表者および分担者による8論文のうち、3篇はシベリア原住民に関するものである。平成4年度未に刊行される研究報告書は、上記の「北の人類学」と一対をなすものであり、両者を総合することによって、わが国の環極北文化の研究は確実に一歩前進したと見ることが可能であろう。論文に掲載されなかった資料やコピー等は、北海道大学と北海道立北方民族博物館に収集、保管し、今後の研究に役立てたいと考えている。
1 0 0 0 食品安全5法施行に対応するための家畜飼養管理基準の構築
2年間の研究期間中の研究対象地域は、1)愛知県(名古屋大学農学部付属農場周辺)、2)千葉県(農業共済家畜診療部門管轄地域、3)北海道(十勝支庁周辺)の3箇所であった。研究最終目的は、生産から販売までの「食の安全」の輪を、農家(生産者)レベルで確実なものとするための家畜飼養管理基準の構築である。しかし、農家毎に問題の種類も程度も異なるので、一律な家畜飼養管理基準での現場への対応は実践的ではない。そこで、この課題では、パイロット研究として、生産者のニーズを的確に把握し、その解決策を家畜保健所などの公共機関の職員(外部者)と農家が一緒になって探る過程が、問題の解決、ひいては生産性の向上へとつながることを提示することが重要な役割を持つ。共同研究者である堀北氏が所属する千葉県農業共済家畜診療部門との連携が十分に機能し、数々の事例を分析することができた。具体的には、2年目の後半に取り組んだ家畜保健所・コンサルタント事業を利用した活動では、参加型手法を使い、従業員全員で問題点を明確にし、解決策を提案し実践したところ、2ヶ月間という短期間に、搾乳頭数が増加し乳量が目的に達成したのに搾乳時間,は短くなり、乳房炎などの疾病発生数が減少し、仕事の連携が改善したという事例を生み出した。薬などの有害物質や資金を使わずに、農場内のコミュニケーション不足、獣医学的知見の一方的な指導、関係機関間の不十分な連携という問題点を改善したことによる成果である。つまり、「食の安全」に関連した健康的な管理飼養問題の解決方法の一例が提示できたわけである。千葉農業共済では上記の活動を平成18年度より正式な業務と認めた。今後は、堀北氏を中心にさらなる事例研究を全国レベルに拡大する。「ポジテイブ制度」など規制が増える昨今、生産者との協力関係を軸とした飼養管理基準の構築が急がれる。
1 0 0 0 本の声を聴け : ブックディレクター幅允孝の仕事
1 0 0 0 OA 名所江戸百景 亀戸天神境内
1 0 0 0 OA 酢酸菌ナノビルダー : 酢酸菌はナノの大工さん?(レーダー)
- 著者
- 近藤 哲男
- 出版者
- 社団法人日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.9, pp.412-413, 2010-09-20
1 0 0 0 ふだんの面接に生かせる精神療法のエッセンス
- 出版者
- 星和書店
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 OA 地震・火山月報 : 防災編
- 出版者
- 気象庁
- 巻号頁・発行日
- vol.平成22年, 2010-03
1 0 0 0 OA 実用和英会話活法 : 最新案速成
1 0 0 0 Císařovy nové šaty
- 著者
- [Ken Kaikó přeložil Ivan Krouský]
- 出版者
- Svoboda
- 巻号頁・発行日
- 1983
1 0 0 0 OA 2005年総選挙後における政策決定過程の変容
- 著者
- 上川 龍之進
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.54-68,195, 2007-02-28 (Released:2009-01-27)
- 参考文献数
- 11
本稿は,2005年総選挙以後の小泉政権において,政策決定過程がどのように変化したのかを論じる。第1に,小泉首相が政権発足直後に打ち出したものの,与党や省庁の反対にあって頓挫していた政策が,総選挙以降,小泉のリーダーシップによって次々と決められていったことを示す。第2に,2005年末以降,「官邸主導」による政策決定を可能にしてきた経済財政諮問会議の役割が変質し,自民党•官僚主導の政策決定が復活したという見解に対し,歳出•歳入一体改革の決定過程は依然として「首相主導」であったことを明らかにする。第3に,2006年の通常国会では重要法案が軒並み成立しなかった。これも,会期延長を求める与党の声を無視した「首相主導」の結果であると論証する。総選挙での大勝によって小泉の自民党内での影響力が飛躍的に高まった結果,政策決定過程が先述したように変化したというのが本稿の主張である。
- 著者
- 食見 文彦
- 出版者
- スピノザ協会 ; 1999-
- 雑誌
- スピノザーナ : スピノザ協会年報 (ISSN:1345160X)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.79-97, 2011
1 0 0 0 OA 75.岐阜県中部地震-1969年9月9日による被害調査報告
- 著者
- 伯野 元彦
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大学地震研究所彙報 (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.6, pp.1287-1294, 1971-02-27
The following features are pointed out concerning the damage of structures by the recent Sept. 9, 1969 earthquake in the Gifu Prefecture in Japan. i)It is supposed that the acceleration of the ground motion is more than 350 gals, due to the behavior of gravestones, however, the damage of structures is not so severe. The reason might be the fact that the epicenter of the earthquake is in the mountainous region, so the frequency content of the ground motion concentrations in a higher frequency domain. ii)The damage of the following structures are severe, A)Road, highway going through the slope of mountains, B)Masonry retaining wall, C)Failure of the forest area, iii) Almost no damage was found in Wooden Houses.