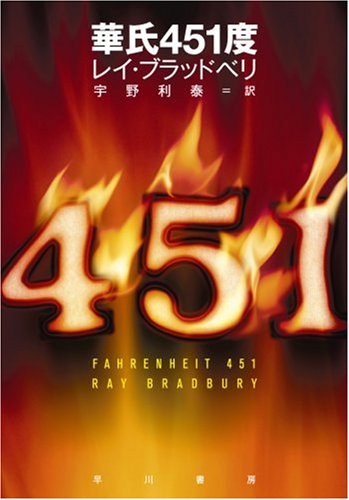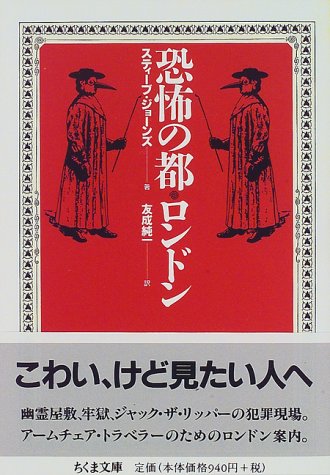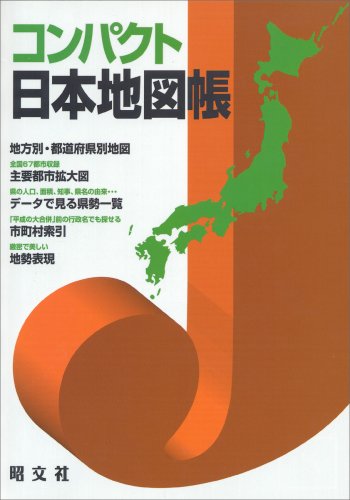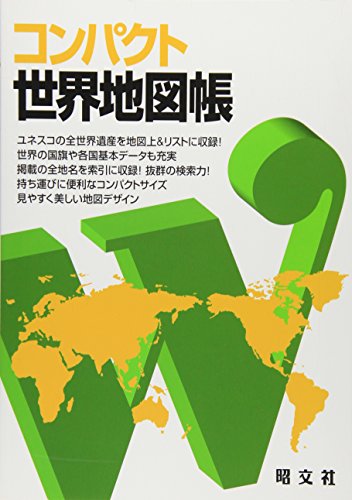- 著者
- 原田 勇治 西尾 正則 坂本 祐二
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SAT, 衛星通信 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.256, pp.131-134, 2010-10-21
- 参考文献数
- 3
ハヤト(KSAT)は2010年5月21日に、HIIA17号機の相乗り衛星として打ち上げられ、高度300kmの円軌道に投入された。衛星は1辺10cmの立方体の形状で、重量は1.43kgである。軌道投入当初、衛星からの信号を捉えることができなかったが、6月1日より6月7日までの7日間、信号受信に成功した。その後、再び信号を捕らえることが困難となり、7月14日に大気圏に突入・消滅したと思われる。衛星の地上管制システムの概要と追跡方法および追跡結果について報告する。また、受信結果から想定される衛星の動作状態の解析結果についても報告する。
- 著者
- 喜連川 優 牧野 二郎
- 出版者
- 社団法人人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会誌 (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.621-627, 2010-09-01
- 被引用文献数
- 1
- 出版者
- 日刊工業出版プロダクション
- 雑誌
- ISOマネジメント (ISSN:13459384)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.5, pp.64-66, 2010-05
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1914年10月02日, 1914-10-02
- 著者
- Ikusaku AMEMIYA
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Imperial Academy (ISSN:03699846)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.7, pp.284-286, 1929 (Released:2008-03-19)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 43
1 0 0 0 OA 膜交通における選別輸送の分子機構の解明と植物の高次システムへの展開
1 0 0 0 OA ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判(中) : 中間考察
- 著者
- 山本 啓
- 出版者
- 山梨学院大学
- 雑誌
- 山梨学院大学法学論集 (ISSN:03876160)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.1-55, 2012-03-30
1 0 0 0 OA 福祉国家論の理論的基盤に関する批判的考察 : 社会契約論-国民国家論の視点から
- 著者
- 伊藤 新一郎
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.81-98, 2012-03
1 0 0 0 OA 福祉国家と正義論 (藤澤益雄教授退任記念号)
- 著者
- 保坂 哲哉
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 三田商学研究 (ISSN:0544571X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.37-49, 1996-08-25
本論はアメリカ,イギリスにおける正義論の最近の発展と論点,福祉国家とその政策への含意を論ずる。取り上げだのはJ.ロールズ,B.アッカーマン,R. ノージック,D. D.ラファエル,A.ブラウン,A.マッキンタイアの正義論である。とくに注目に値すると筆者が考えたのは,アリストテレスが『ニコマコス倫理学』で展開した徳論,善理論および正義論を基礎とするブラウンとマッキンタイアの正義論である。道徳的自然主義に立ち,人間の本性とその社会性の特質から出発して正義論を導出する内在主義的アプローチは,ブラウンによって実践的合理性によって整序された基礎財リストの提案を導く。しかしこれらの正義論討議から引き出せる実践的指針は,概して一般的性質のものであり,福祉国家正統化の根拠についての一般的合意形成には直接役立たない。その点にかんしてのマッキンタイアの言明,アリストテレス的道徳性の伝統は近代の組織的政治を拒絶すべきである,はきわめて厳しい批判と言わなければならない。
1 0 0 0 華氏451度
- 著者
- レイ・ブラッドベリ著 宇野利泰訳
- 出版者
- 早川書房
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 恐怖の都・ロンドン
- 著者
- スティーブ・ジョーンズ著 友成純一訳
- 出版者
- 筑摩書房
- 巻号頁・発行日
- 1997
本研究の目的は、沖縄で語られている植民地台湾の記憶と、沖縄地上戦の記憶、さらに戦後の米軍占領と今日まで継続する米軍駐留をめぐる政治、社会運動、文化状況との相関関係を明らかにすることである。今年度は、5月と12月に台湾にそれぞれ約1週間ずつ滞在し、中央研究院や国立台湾大学などで資料調査を実施した。また研究関心を共有する研究者と面会して助言をもらうことができた。また年度末の3月には米国サンディエゴで開催されたアジア研究学会で研究報告を行った。また研究者だけが集う国内の研究会だけでなく、一般市民向けの会合(「沖縄クラブ」)で自分の研究の成果を還元できたのは有意義だった。研究の成果は国際的に高い評価を得ている学術雑誌(査読有り)のCultural StudiesとInter-Asia Cultural Studies上で学術論文というかたちで発表した。また年度内に出版できなかったが、本科学研究費で実施した研究の成果は平成25年度に3冊の共著書(和文)上で発表されることが決定している。さらに年度中に執筆した和文の学術論文が平成25年5月現在、査読審査中で、審査を通過すれば8月頃に出版される予定である。以上のように、平成24年度は前半はおおむね順調に調査と執筆活動を行うことができたが、後半は就職活動のために精神的にも時間的にも消耗してしまい、当初計画していたほどには研究を進めることができなかったことを残念に思っている。
1 0 0 0 OA CADの現状と今後の進展 : CAD特訓セミナの提案と日本放射線技術学会会員への期待
- 著者
- 土井 邦雄
- 出版者
- 公益社団法人日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術學會雜誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.318-320, 2000-03-20
- 被引用文献数
- 6
1 0 0 0 コンパクト日本地図帳
- 出版者
- 昭文社
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 キリストの十字架と栄光 : イエスをもとめて(最終講義)
1 0 0 0 コンパクト世界地図帳
- 出版者
- 昭文社
- 巻号頁・発行日
- 2007
- 著者
- 門野 泉
- 出版者
- 英米文化学会
- 雑誌
- 英米文化 (ISSN:09173536)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.111-127, 2010-03-31
Thomas Middleton's A Game at Chess provoked a scandal when it was first performed at the Globe Theatre in 1624. Due to the severe sarcasm it directed against Count Gondomar, former Spanish ambassador, and Catholic Spain, the play was banned by the Privy Council after 9 consecutive performances because it was considered that the King's Men had flouted the commandment that no contemporary Christian monarchs should be represented on stage. It seems certain that there were much more serious reasons why this play would have offended James I, who ordered an investigation into the offensive performances with the intent of making a severe example of the offenders. After strict interrogations, the Master of Revels and individual actors were found not guilty. After being given a stern warning, the King's Men were ordered to pay a light fine, and only Middleton was jailed in the Fleet prison. The decisions of the Privy Council appeared to be politically motivated and unfair. However, careful reading of the comedy reveals that the playwright portrayed James I as having innocent foolishness, lack of confidence, lacking both leadership and insight into human nature, and many other weaknesses as a king, in comparison with the Machiavellian Count Gondmar's superb political ability, sharp insight and brilliant tactics. There can be no doubt that the members of the Privy Council realized that Middleton's satire was focused not only on Spain but also on the King of England and his court. This would seem to explain why he received the heaviest sentence. Although this was an unfortunate outcome for him, when viewed from another angle, the punishment was a positive evaluation of his sharp satirical comedy, and therefore can be considered a "just reward" for his brilliant talent and sharp insight into human nature.
1 0 0 0 文法論 : 陳述論の誕生と終焉
- 著者
- 尾上 圭介
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 國語と國文學 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.1-16, 1990
1 0 0 0 文核と結文の枠:「ハ」と「ガ」の用法をめぐって
- 著者
- 尾上 圭介
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1973, no.63, pp.1-26, 1973
The present paper is an attempt to describe and reorganize the usage of Japanese particles <I>wa</I> and ga and to give it a theoretical interpretation.<BR>The author maintains that two elements are involved for sentence formation, i. e. Sentence Kernel and Sentence Frame. <I>Wa</I> is one realization of the Sentence Frame and thus completes sentence formation. <I>Ga</I> is only a component of the Sentence Kernel. A Sentence Kernel has the semantic function as a dictum, i. e. the core material of a Sentence. It is shown that the special constraint on the usage of "near-sentences"containing <I>ga</I> but not any Sentence Frame follows from this hypothesis.
1 0 0 0 文核と結文の枠:「ハ」と「ガ」の用法をめぐって
- 著者
- 尾上 圭介
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1973, no.63, pp.1-26, 1973
The present paper is an attempt to describe and reorganize the usage of Japanese particles <I>wa</I> and ga and to give it a theoretical interpretation.<BR>The author maintains that two elements are involved for sentence formation, i. e. Sentence Kernel and Sentence Frame. <I>Wa</I> is one realization of the Sentence Frame and thus completes sentence formation. <I>Ga</I> is only a component of the Sentence Kernel. A Sentence Kernel has the semantic function as a dictum, i. e. the core material of a Sentence. It is shown that the special constraint on the usage of “near-sentences”containing <I>ga</I> but not any Sentence Frame follows from this hypothesis.