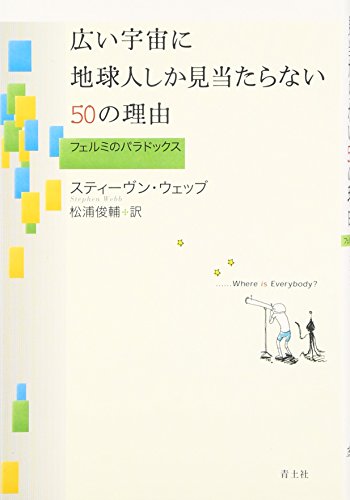1 0 0 0 伝小野通女筆《豊臣秀吉像》について
- 著者
- 中村 玲
- 出版者
- 筑波大学大学院人間総合科学研究科
- 雑誌
- 芸術学研究
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.142-133, 2010
1 0 0 0 RNA研究の21世紀への展開
近年のRNA研究の大きな発展を支えた背景には、国内のRNAの基礎研究に関して10年余の間継続して実施されてきたRNAに関係する重点・特定領域研究が果たした役割が大きい。このようなRNA研究に対する熱意は、特に若い研究者の間に大きなうねりとなって現れ、平成11年に日本RNA学会が組織された(初代会長:志村令郎・生物分子工学研究所長)。本基盤研究(C)においては、「RNA研究の21世紀への展開」のために推進すべき課題についての調査と討論を重ね、平成13年度発足特定領域研究(A)「RNA情報発現系の時空間ネットワーク」を申請するに至った。その過程で、本基盤研究(C)に参加し、同時に新特定領域研究の総括班に予定するメンバーは、平成12年に開催されたRNA関連の国際研究集会「tRNA Workshop」(4月、ケンブリッジ)、「RNA Society年会」(5月、マジソン)、FASEBシンポジウム「Posttranscriptional Control of Gene Expression:The Role of RNA」(7月、コロラド)、「Ribosome Biogenesis」(8月、タホ)、「Structural Aspects of Protein Synthesis」(9月、アルバニ)に参加し、最新情報の調査・討論を行った。これらの調査討論に基づき新特定領域研究の申請を準備するとともに、平成13年2月には、国外から12名の研究者を招聘して国際シンポジウム「Post-Genome World of RNA」(開催責任者:東京大学医科学研究所教授中村義一)を東京で開催し、本研究領域に関する最新の発表・討論を実施した。
1 0 0 0 RNA情報発現系の時空間ネットワーク
- 著者
- 中村 義一 坂本 博 塩見 春彦 饗庭 弘二 横山 茂之 松藤 千弥 渡辺 公綱 野本 明男 谷口 維紹 堀田 凱 京極 好正 志村 令郎
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 特定領域研究
- 巻号頁・発行日
- 2001
本特定領域研究では、「原子→分子→細胞→個体」と階層的に研究を推進し、それらの連携によって「RNAネットワーク」の全体的かつ有機的な理解を深めることを目的にした。これらの研究成果は、RNA研究にとどまらず、広く生命科学に対する貢献として3つに集約することができる。・第一の貢献は、構造生物学と機能生物学を連携駆使した研究によって、RNAタンパク質複合体やRNA制御シグナルの動的な作動原理に対する学術的な理解を深めたことである。・第二の貢献は、micro RNAを始めとするタンパク質をコードしない「小さなRNA」に関して先導的な研究を推進できたことである。ノンコ-ディングRNA(ncRNA)は本特定領域の開始時には全く想定されていなかった問題だが、ヒトゲノム・プロジェクトの完了によって、ヒトのRNAの98%をも占める機能未知な「RNA新大陸」として浮上した。今後の生命科学の最優先課題といっても過言ではないこの新たな問題に対して、本特定領域はその基盤研究として重要な貢献をすることができた。・第三の貢献は、本特定領域の研究が、意図するとしないとに係らず、RNAの医工学的な基盤の確立に寄与したことである。本特定領域研究では、実質的研究が開始された平成14年度から年1回の公開シンポジウムを開催し、平成15年と平成18年には各々30名程度の海外講演者を含めた国際シンポジウム(The New Frontier of RNA Science[RNA2003 Kyoto]; Functional RNAs and Regulatory Machinery[RNA2008 Izu])を開催した。これらのシンポジウムは、学術的、教育的、国際交流的に実り豊かな第一級の国際会議となった。又、特定領域研究者のみならず社会とのコミュニケーションを目的として、RNA Network Newsletterの年2回発行を継続し、各方面からの高い評価と愛読を頂戴して全10冊の発行を完了した。なお、事後評価においては「A+」と評価され、本プログラムはその目的を十分に達成することができた。
1 0 0 0 RNAの動的機能発現の分子機構
本総合研究(B)は、「RNAの動的機能発現」に関する重点領域研究の設定をその主要な目的として企画されたものである。しかしながら、平成4年度から新重点領域研究「RNA機能発現の新視点」が発足することに決定し、その研究内容がほとんど重複するため、当初の趣旨での本総合研究(B)班からの重点領域申請はやむなくとりやめた。その上で、本研究班の活用を計るため他の関連研究組織との連携を検討することとし、平成4年1月17ー18日に研究集会「RNA合成における分子間コミュニケ-ション」を東京において開催した。本総合研究(B)班からの5名を含めた12名が参加し、多角的に当該分野の研究を協議した結果、石浜明国立遺伝学研究所教授を代表者として、「転写装置における分子間コミュニケ-ション」を重点領域研究として申請することで合意し、申請を行なった。本総合研究課題に関する国内研究の活性化を計るために、平成3年12月に行なわれた日本分子生物学会において、シンポジウム「RNAシグナルによる翻訳制御」を開催した。国内から4人の演者に加えて、ミュンヘン大学からセレノシステイン研究で有名なA.Bo^^¨ck教授を招聘して活発なシンポジウムを行なうことができた。
1 0 0 0 mRNA研究の展開
本基盤研究は、mRNAの誕生から終焉に至る動態と多元的な制御プログラムについて、国際的な調査及び研究討論を実施し、総合的な討論に基づいて重点領域研究の設定を検討する目的で企画採択されたものである。その研究実績を要約する。1.研究領域の調査結果:転写後の動的な制御プログラムは、広範囲の生物系で重要不可欠な役割を担うことが明らかになりつつあり、mRNAを骨格とする基本的な諸問題を体系的に正攻法で研究すべき時期にある。本研究の成果は、発生・分化・応答等の高次な細胞機能の解明や、RNAダイナミズムの創成、あるいは蛋白質工学やmRNA臨床工学等の次世代バイオテクノロジーの基盤となりうる。mRNA研究に関連する重点領域の推進が必要かつ急務である。2.国際研究集会における学術調査と討議:平成8年11月10〜14日、本基盤研究代表者が中心となってmRNA研究に関する国際研究集会「RNA構造の遺伝子調節機能(“Regulatory Role of RNA Structure in Gene Expression")」を開催した(日本学術振興会王子セミナー/於箱根)。本研究集会には、申請領域の第一戦で活躍する欧米の研究者約40人が参加し最新の研究成果の発表、討論、交流を行った。その機会を利用して、国際的な視点からmRNA研究の展望と研究振興の方策を議論した。3.出版企画:上記国際研究集会に関連した学術刊行物を、学術誌Biochimieの特集号としてElsevier社(仏パリ)から出版することとなり、本基盤研究代表者が監修し平成9年3月に出版の予定である。4.重点領域の設定:本基盤研究の目的をふまえて、重点領域研究「RNA動的機能の分子基盤」(領域代表・渡辺公綱、平成9〜12年)の実施が決定された。
1 0 0 0 遺伝子発現の転写後調節:mRNA分解と翻訳制御の分子機構
- 著者
- 中村 義一 饗場 弘二 HERSHEY John BOCK August COURT Donald ISAKSSON Lei SPRINGER Mat
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1992
遺伝子発現の転写後調節をつかさどるRNAシグナルの構造・機能・制御タンパク質との相互作用を明かにする目的で行なった研究成果を以下に整理する。1.ペプチド鎖解離因子の研究:大腸菌では、終止コドンUGAにおける翻訳終結はペプチド鎖解離因子RF2を必要とする。我々はin vivoでRF2と相互作用している因子に関する知見を得ることを目的として高温感受性RF2変異株から6種類の復帰変異株を分離した。その内、4株が遺伝子外サプレッサー変異であった。それらは、90分(srbB)と99分(srbA)の2つのグループに分けられた。この解析に並行して、新たにトランスポゾン挿入(遺伝子破壊)によりUGAサプレッサーとなるような突然変異を分離し、tosと命名した。遺伝学的分析とDNAクローニング解析の結果、tos変異はsrbA変異と同一の遺伝子上に起きた突然変異であることが明かとなった。この結果から、tos(srbA)遺伝子は、その存在が1969年に予言されていながら何の確証も得られず放置されていたRF3蛋白質の構造遺伝子である可能性が示唆された。そこでTos蛋白質を過剰生産、精製し、in vitroペプチド鎖解離反応系で活性測定を行なった結果、RF3蛋白質の活性を完全に保持することが明かとなった。この解析により、四半世紀の謎に包まれていたRF3因子の存在、機能、構造を遺伝学的、生化学的に実証することが出来た。この成果は今後、終止コドン認識の解明にとって飛躍的な原動力となるものと自負する。2.リジルtRNA合成酵素遺伝子の研究:大腸菌は例外的に、2種類のリジルtRNA合成酵素を持ち、構成型(lysS)と誘導型(lysU)の遺伝子から合成される。その生理的な意味は依然不明であるが、我々は本研究によってlysU遺伝子の発現誘導に関してその分子機構を明かにすることができた。その結果、lysU遺伝子の発現はLrp蛋白質(Leucine-Responsive Regulatory Protein)によって転写レベルで抑制されており、ロイシンを含めた各種の誘導物質によるLrp蛋白質の不活化を介して転写誘導されることを明かにした(Mol.Microbiol.6巻[1992]表紙に採用)。さらに、lacZとの遺伝子融合法により翻訳レベルの発現制御を解析した結果、翻訳開始コドン直下に“downstream
- 著者
- 渡辺 公綱 横川 隆志 河合 剛太 上田 卓也 西川 一八 SPREMULLI Li SPREMULLI Linda lucy LINDA Lucy S SPREMULL Lin
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1991
本国際学術共同研究は、動物ミトコンドリアにおける暗号変化(UGA;普遍暗号では終止暗号がトリプトファンに、AUA;イソロイシンがメチオニンの暗号に、AGA/AGG;アルギニンが殆どの無脊椎動物ではセリン、原索動物ではグリシン、脊椎動物では終止暗号に変化、など)の分子機構をin vitro翻訳系を構築して、解明する目的で始められた。このような研究は、ミトコンドリア(mt)からその細胞内量から見ても、生化学的な研究に十分な試料を調製することが大変困難なこと、翻訳に関わるタンパク性諸因子がかなり不安定で単離が困難なことなどが主な障害となって世界的にも殆ど手がつけられていなかった。我々は特異構造を持つmt・tRNA(殆どのmt・tRNAではL型立体構造形成に関わっているDループとTループ間の塩基対を欠いていたり、DループやTループが欠落したものも見つかっている)と変則暗号解読の因果関係を探る目的で、mt・tRNAの大量調製法を確立し、その構造と性質を調べていたが、翻訳系の構築に必要な活性のある因子の調製ができなかった。国外共同研究者であるSpremulliのグループは、活性あるmtリボソームと翻訳系諸因子の調製に成功していたが、mt・tRNAの単離ができなかった。このような状況においてお互いのグループで開発したシステムと技術を合体させることにより、mtのinvitro翻訳系を構築し、暗号変化の分子機構を解明するという目的で平成3年度から本研究がスタートした。研究はかなり順調に進んできたが、本格的な展開はこれからであり、やっとその基礎が固まったという現状である。以下に年度を追ってその成果を述べる。[平成3年度]1)tRNAの特定配列に相補的な合成DNAプローブを用いたハイブリダイゼーション法を開発し、mt・tRNAの0.2-0.5mgオーダーの調製が可能になった。2)UCN(N=A,U,G,C)のコドンに対応するウシmt・セリンtRNAを単離、精製し、それが従来の遺伝子から推定されていた配列から、実際の構造がずれていること、アンチコドン・ステムは一塩基対長く、アミノ酸ステムとDステムの間が一塩基しかない、異常な2次構造をとること、この構造は哺乳動物mtに共通であることを明らかにした。3)ウシ肝臓から活性のあるリボソーム、開始因子(IF-2)、伸長因子(EF-Tu/Ts、EF-G)、アミノアシル-tRNA合成酵素(ARS)の調製方法を確立し、それらの性質を検討した。[平成4年度]1)AGY(Y=U,C)のコドンに対応する、Dアームを欠くセリンtRNAのセリルtRNA合成酵素(SerRS)による認識部位を決定する目的で、このtRNA遺伝子からT7RNAポリメラーゼによる転写物を調製し、種々の塩基置換を導入したtRNA変異体のSerRSによるセリン受容能を測定した結果、アンチコドンは認識に無関係だが、Tループが重要であり、中でもよく保存されたループ中央のA44の置換が決定的であることが分かった。2)ウシ・mtでポリ(U)依存ポリ(フェニルアラニン)合成系を初めて構築し、大腸菌の系との構成成分の互換性を検討したところ、mtのPhe-tRNA^<Phe>は大腸菌のEF-TuとGTPとで3者複合体を形成するが、そこからリボソームA部位への転移過程が働かないことを明らかにした。3)ウシ・mtのメチオニンtRNAの塩基配列を再検討し、アンチコドンの一字目に、5-ホルミルシチジンという新規修飾塩基が存在することを明らかにした。4)ウシ・mtフェニルアラニンtRNAの修飾塩基を含む塩基配列を決定し、RNaseや化学試薬への感受性からその立体構造を推定したところ、Dループ、Tループ相互作用はないが、Dアームとバリアブルループ間の3次元的な塩基対形成によってL型に近い構造をとっていることを見出した。[平成5年度]1)ポリ(U)依存ポリ(Phe)合成系の効率化の条件を検討し、1mMスペルミン存在下で大腸菌の系の約1/2のレベルまで合成効率を上昇させることに成功した。2)AUAがメチオニンの暗号であることを証明するために、AUAを含む人工mRNAを用いて、AUAに依存したメチオニル-tRNAのリボソームへの結合、ポリペプチドへのメチオニンの取り込みを調べたが、現在までのところまだ肯定的な結果は得られていない。3)ウシmtからホルミルトランスフェラーゼを精製し、fMet-tRNAを作成し、EF-TuとIF-2の結合をMet-tRNAと比較したところ、fMet-tRNAはIF-2と、Met-tRNAはEF-Tuとそれぞれより高い親和性を示した。これは単一tRNAがホルミル化によって開始と伸長の両反応に使い分けられる可能性を支持するものである。
1 0 0 0 RNA機能構造の新視点
本年度は,これまでの4年間の研究成果をとりまとめ,9月24日の第6回公開シンポジウムにおいて広く公表した.また,4年間の班員の成果をまとめた最終報告書を作成した.また,本重点領域研究と関係の深いシンポジウムが8月27日の日本分子生物学会大会中に行われ,これにおいても研究成果が公表された.第6回公開シンポジウムでは,第1項目「RNA機能の発現機構」の研究成果として,オルタナティブ・スプライシングの制御に関与するRNA結合タンパク質,精密なtRNA分子識別を行うクラスIアミノアシルtRNA合成酵素,および特異な二次構造を持つ動物ミトコンドリアtRNAについての立体構造解析の結果が示された.また,グループIイントロンRNAの活性化,リボソームRNAの機能あるいはタンパク質によるtRNAの分子擬態についての研究成果も報告された.第2項目「RNA新機能の検索」については,新規に発見された低分子量RNAによるTrans-translationの機構,リボソームRNAにおける2つのドメイン間のcommunication機構,あるいはミトコンドリアtRNAによるショウジョウバエの生殖細胞形成機構についての研究成果が発表された.また,第3項目「RNAの起源と進化」については,アミノアシルtRNA合成酵素の起源と進化のメカニズム,およびウイルス由来のリボザイムやミトコンドリアtRNA遺伝子変異によるミトコンドリア病についての研究成果が発表された.
- 著者
- 林 尚之
- 出版者
- 青木書店
- 雑誌
- 歴史学研究 (ISSN:03869237)
- 巻号頁・発行日
- no.869, pp.18-35, 2010-08
1 0 0 0 「ファシズム論争」と十五年戦争期研究
- 著者
- 河島 真
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- no.576, pp.68-79, 2010-08
1 0 0 0 「日本ファシズム論争」再考
- 著者
- 平井 一臣
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- no.576, pp.50-67, 2010-08
1 0 0 0 RNA高次機能の分子基盤
ミトコンドリアtRNA病の発症機序の分子機構解明とそれを基礎とした治療法の開発が行われた。太田と渡辺公綱は共同で、ミトコンドリア病の原因である変異ミトコンドリアtRNAを精製し、修飾塩基を含む構造解析をし、ミトコンドリア病のふたつの病型(MELASとMERRF)の原因の3種類の変異ミトコンドリアtRNA(tRNA-LysとtRNA-Leu(UUR))では共通にアンチコドンの塩基修飾が欠損していることを明らかにした。さらに、渡辺はこの塩基の修飾にはタウリンが結合していることを明らかにした。すなわち、3つの変異tRNAには共通にアンチコドンにタウリンが結合していない。この塩基修飾の欠損によって、mRNAのコドンへの親和性が低下してミトコンドリア内の蛋白合成が停止することによって発症することを明らかにした。変異tRNAの構造解析、機能解析を基礎として疾患の治療法の基礎が開発されたので、一連の研究の社会的意義はきわめて大きい。小林はミトコンドリアrRNAが生殖細胞の形成に普遍的に必要であること、生殖細胞形成期の細胞ではミトコンドリアrRNAを含むミトコンドリア型(原核細胞型)のリボソームが形成されていることを明らかにした。この研究によって、ミトコンドリア型の翻訳系が生殖細胞の形成に必要であるという独創的な概念を提出した。この概念は、類する研究がないほど新しい分野をきりひらいたという意味で極めて重要である。渡辺嘉典は減数分裂に必要なRNAであるmeiRNAの機能を明らかにした。すなわち、meiRNA結合蛋白が核と細胞質をシャトルさせるためにRNAが必要であるという新しい概念を打ち立て、証明した。武藤はmRNAとtRNAの双方として機能するmtRNAの役割ドメインを決定し、その分子機構を解明した。
- 著者
- スティーヴン・ウェッブ著 松浦俊輔訳
- 出版者
- 青土社
- 巻号頁・発行日
- 2004
1 0 0 0 金属錯体を不斉中心とする光学活性ポリマーの開発
当研究室では生体中での酵素系の作用機序を念頭において、アミノ酸や糖質などの生体関連物質と遷移金属イオンとの相互作用に対して配位立体化学的に詳細な検討を行い、それらに高度な立体化学制御機能を賦与することを目指し研究を進めてきた。本研究では、我々のこれまでの蓄積を基盤にして、分子識別能を有する金属錯体を設計し立体化学制御に関する知見を広げ、さらに当研究室で独自に開発した金属錯体の化学修飾法を用いて金属錯体を機能素子とする高分子錯体等の高機能性複合系の開発を目指し研究を行った。まず光学活性なポリアミンとエチレンジアミン二酢酸型配位子の混合配位Co(III)錯体の立体化学制御機構について詳細に検討した。その結果複数個の配位窒素原子に対するアルキル基の位置選択的置換により金属錯体の絶対配置を高度に制御できることを明らかにした。また分子間の水素結合を介する分子識別能を有する金属錯体の設計を目指して、二糖のNi(II)グリコシルアミン錯体の合成とキャラクタリゼーションを行った。良好な結晶が得られたD-マルトース錯体についてX線結晶構造解析を行った。その結果、二糖分子内での水素結合が見られた他、錯体分子が糖ユニットの水酸基間での水素結合を介して二量化していることが判明し、金属錯体による分子識別能の発現にとって重要な知見を得た。さらに非配位の水酸基を有するポリアミノポリカルボン酸を配位子とする陰イオン性Co(III)錯体に対し、当研究室で独自に開発したクリプタンド可溶化法を用いる各種酸無水物との反応により錯体の非配位の水酸基を反応点とするエステル化に成功した。脂肪酸無水物の場合には水中でミセル形成能を示す金属錯体をヘッドグループとする新規界面活性剤の開発に成功した。さらに高分子化可能なクロトン酸およびメタクリル酸残基が連結した錯体の合成にも成功した。以上の知見を基に金属錯体の高電子化について検討している。
- 著者
- Kanako Ueno Hideki Tachibana
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.156-161, 2005 (Released:2005-03-01)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 3 5 18
In order to investigate the effect of a hall response on music players, we have made various experimental studies up to now. In order to develop this research, one of the most important subjects is to understand the musicians’ perception of the acoustic effects of halls. Musicians generally perceive the acoustic properties of a concert hall by keeping their performing action and by adjusting their playing technique subconsciously. This kind of interactive relationship between musicians and acoustic environment is really important when considering the acoustic values of concert halls for musicians. In this study, musicians’ awareness of concert halls was investigated through interview survey and the cognitive psychological phenomena of musicians were interpreted by applying the “tacit knowing” theory. Then the process to extract the musicians’ perception in experimental studies on concert hall acoustics is discussed.
1 0 0 0 OA 生活習慣病と食育
- 著者
- 尾立 純子
- 出版者
- (社)大阪生活衛生協会
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.372-377, 2006 (Released:2006-10-19)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
The report “Healthy Japan 21” sets out Japanese public health targets for the year 2010. Under the item of “Nourishment/eating habits”, detailed numerical values are given for the whole human lifespan. For adult women, in particular, the pregnancy period is important, as poor nourishment and bad habits can sow the seeds of lifestyle-related disease. It is important to lay the foundations for healthy eating habits and dietary education activity early on. Now, the Dietary Education Law, enforced in 2005, has provided backing for such activity, and dietary education activities specific to each region are being developed. By teaching children the value of home cooking, it is important to nip lifestyle-related disease in the bud.
1 0 0 0 アニメ『わんぱく王子の大蛇退治』と原典『古事記』の比較と考察
- 著者
- 村瀬 学 谷本 由美
- 出版者
- 同志社女子大学教育・研究推進センター
- 雑誌
- 同志社女子大学学術研究年報 (ISSN:04180038)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.167-178, 2011
- 著者
- 広渕 崇宏 中田 秀基 伊藤 智 関口 智嗣
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌コンピューティングシステム(ACS) (ISSN:18827829)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.248-262, 2010-09-17
- 被引用文献数
- 3
ポストコピー型の仮想マシン再配置機構は仮想マシンの実行ホストを素早く切り替えられるため,データセンタの運用効率を向上させるうえで有用な技術であると考えられる.しかしながら,今日一般的に利用できるまでには至っていない.先行研究におけるポストコピー型再配置機構は,既存の仮想マシンモニタ(VMM)への変更が大きく,ゲストOSの改変も必要になる点に問題がある.そこで我々は,既存VMMのへ拡張が単純でゲストOSの改変も不要な,新たなポストコピー型ライブマイグレーション機構を提案する.メモリアクセスのトラップ処理とメモリページのコピー処理をVMMの外部で実装することで,VMMへの変更量を抑えながらポストコピー型再配置を実現する.再配置性能を検証するため,SPECweb2005を用いて評価実験を行った.負荷の高いウェブサーバを実行するVMであっても,1秒以内に実行ホストを切り替えることができた.実行ホスト切替え後の性能低下は限定的であった.プレコピー型再配置に比べて,VMのすべての状態を移動する時間も短縮できた.Post-copy-based VM migration is considered a promising technology for next-generation datacenters; memory pages are transferred after a VM restarts at a destination host, thereby minimizing the time of switching the execution host. Post-copy-based migration mechanisms, however, have not yet been available in industry. Prototype implementations in prior work need major modifications to existing virtual machine monitors (VMMs), and also require special software support in guest operating systems. In this paper, we propose a simple and plain implementation of post-copy-based migration, which is implemented as a lightweight extension to KVM. It supports any guest operating systems without their modifications. The RAM of a migrated VM is mapped to a special character device, which transparently transfers memory pages on demand. Experiments were conducted by using the SPECweb2005 benchmark. A running VM with heavily-loaded web servers was successfully relocated to a destination within one second. Temporal performance degradation after relocation was alleviated by pre-caching memory pages. In addition, for memory intensive workloads, our migration mechanism moved all the states of a VM faster than a pre-copy-based migration mechanism.
- 著者
- 沼尻 晃伸
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社會經濟史學 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.1, pp.3-23, 2011-05-25
本稿は,兵庫県尼崎市を事例とし,戦時期〜戦後改革期における組合施行土地区画整理事業の考察を通じて,農村の側から市街地形成の特質を明らかにすることを課題とする。本稿が明らかにした点は,以下の3点にまとめられる。第1に,戦時期の耕地についてである。地主は小作農民に対し土地区画整理実施前に離作料を支払ったが,戦争末期に事業は滞ったため小作農民による耕地利用が継続された。第2に,戦後改革期における地主・小作農民間の対立についてである。仮換地は小作地の移動や減少を伴うとする組合側の主張に小作農民は反対したため,地主と小作農民は激しく対立したが,政府の方針に沿っていた組合(地主)の主張が通ることとなった。第3に,形成された市街地の特質についてである。土地区画整理の実施により公共用地が創出される一方で,耕作面積の減少を賃耕等によって補った小作農民によって,農地が維持される場合もあった。このような小作農民による農地利用を農業委員会も承認し,農地が残存する市街地が土地区画整理地区内に形成された。