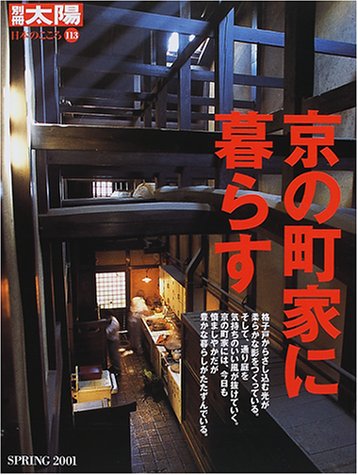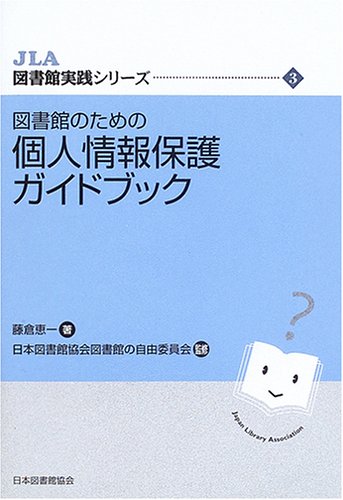1 0 0 0 OA 有機化學反應性の電子論的解釋に就いて
1 0 0 0 OA 水星の日面通過を利用した黒点の温度測定(第5回科学部研究報告)
- 著者
- 中江 祥平 和田 泰治 近藤 直弥 大島 功也 小松 紀由 近藤 涼介 堀江 麗 竹内 彰継
- 出版者
- 米子工業高等専門学校
- 雑誌
- 米子工業高等専門学校研究報告 (ISSN:02877899)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.22-26, 2008-01-01
1 0 0 0 OA 金星の太陽面通過(2012年)を理科教育教材に
- 著者
- 竹内 彰継
- 出版者
- 米子工業高等専門学校
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2005
本研究の目的は市販の光学機器だけを用いて安価に太陽の彩層の速度場を観測する望遠鏡を製作し、それを太陽プロミネンスの振動・波動現象の研究などに利用することにある。本望遠鏡は口径8cmの屈折望遠鏡の後に半値幅0.3AのHαフィルタと冷却CCDカメラを取り付けたもの3本を同一架台に搭載したものから構成される。Hαフィルタは設定温度を変えると透過波長帯をずらすことができるので3本の望遠鏡でHα線の線中心、短波長側ウィング、長波長側ウイングの光の強度を観測し、Hα線のドップラーシフトの2次元情報を得て、彩層速度の2次元分布図を作ることができるというのが本望遠鏡の特長である。次に、望遠鏡の性能の検定を行うため国立天文台三鷹キャンパスの分光器を利用してHαフィルタの分光・温度特性の測定を行い、各フィルタの波長λ(A)-温度T(℃)関係を求めた。続いて、京都大学理学研究科附属花山天文台のシーロスタットと水平分光器を利用してHαフィルタの透過波長帯のムラの有無を調べ、ムラの影響はほとんど無く精度良く太陽彩層の速度場が測定できることを示した。最後に、太陽表面上のジェット現象「サージ」や太陽表面に新しい磁束演浮き上がってくる「浮上磁場領域」の観測を行い、速度分布の2次元分布図(ドップラーグラム)を製作した。また、2006年11月9日の水星の日面通過を観測し、そのとき太陽面上に存在した黒点の温度の精密測定を行った。太陽プロミネンスの振動の研究については、本研究期間では充分なデータが蓄積できなかったが、今後とも本望遠鏡で研究を継続しその物理の解明に寄与して行きたい。
1 0 0 0 惑星科学 〔2004年〕6月8日を見逃すな 金星の太陽面通過
- 著者
- Dick Steven J.
- 出版者
- 日経サイエンス
- 雑誌
- 日経サイエンス (ISSN:0917009X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.7, pp.28-36, 2004-07
金星の太陽面通過(日面通過)は地球から見て金星が太陽の真ん前を横切る現象で,243年間に4回だけ起きる珍しいイベントだ。それが来る6月8日,121年半ぶりに起こる。
- 著者
- 竹原 直希 高橋 栄一
- 出版者
- 特定非営利活動法人日本火山学会
- 雑誌
- 日本火山学会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, 2007-11-18
1 0 0 0 並列プログラミング用事例ベースの構築
- 著者
- 山崎 勝弘 松田 浩一 安藤 彰一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. CPSY, コンピュータシステム
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.34, pp.1-6, 1996-05-16
類似した並列プログラムの構造を極力再利用して並列プログラミングの負担を軽減させる方法について述べる。並列アルゴリズムは一般的に、分割統治法、プロセッサファーム、プロセスネツトワーク、繰り返し変換に分類される。各クラス毎に並列プログラムを作成して、並列プログラミング用事例ベースを作成する。事例はインデックス、スケレトン、プログラム、並列効果、及び履歴から成る。スケレトンにはタスク分割、同期、相互排除、並列化手法、スレッド使用法など並列プログラムの最も重要な部分が含まれる。インデックスは並列プログラムの特徴を示し、並列効果は速度向上を示す。新たな問題に対して、類似したスケレトンを事例べースから検索し、それを自動/手動で修正して並列プログラムを生成する。
1 0 0 0 パルメニデスに於ける「存在」概念の研究
パルメニテスの「存在」概念を明かにする為に挟み撃ち作戦をとった。一つはパルメニデス以前のイオニア派中ピュタゴラス派の根底にある,アルケーやプシューケーの概念を明かにすることにより,パルメニデスが不生不滅,不変不動,不可分であり,完全球によそえられるとした「存在」概念を解明する試みである。他の一つはパルメニデス以後の哲学者達による批判的継承過程を通じて「存在」概念を明かにする試みである。前者については,哲学以前のギリシア人の心情,宗教的感情の中でその核となる,生き生きと同一性を保ち働きつづける何かへの信仰の要素まで溯ることによって,アルケーやプシューケー概念が理解可能となるとの知見を得た。具体的には,人間が生存する為には犠牲となり葬られ,しかも複活再生してくるディオニュソス神に象徴される力への信仰及びアキレウスの怒りに見られる他とは置き換えられぬ自己という考え方が,ギリシア人の根底にあるということである。後者についてはエンペドクレス,アナクサゴラス,デモクリトス達の所謂自然哲学,更にプラトンのイデア論ばかりではなく,ソクラテスか死を賭して示した生き生きとした同一性,特に人格の同一性の問題とつなげることによって,パルメニデス理解が可能になるとの見通しを得た。以上の成果をふまえてパルメニデスの残存断片の整理,編集 一行一行についてに翻訳,註釈の作業を試みた。特にパルメニデスは「真理の道」で恩惟によってとらえられるとした「存在」が「ドクサの道」で感覚世界に如実に働きかけている,その働きかけの様相を明かにすべく努めてること,「序歌」はその「存在」のもつ生き生きとした同一性を保ち働きつづける力を詩を通じて感得させると共に,「存在」理解の連続性と段階性を示すものであり,二つの道をつなぐ要となっていることを示すことに努めた。
1 0 0 0 祇園精舎圖とアンコル、ワット
- 著者
- 伊東 忠太
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.313, pp.10-41, 1913-01-25
- 著者
- 北浦 かほる 谷 みや子 岡田 奈美枝 靜木 美絵 延与 祐三子
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会近畿支部研究報告集. 計画系 (ISSN:13456652)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.361-364, 1996-07-03
1 0 0 0 大規模な異種データ解析のための情報基盤
近年、Hadoopなどの大規模のデータを分散処理するフレームワークが<br />普及したことにより、蓄積された大量のデータを分析する<br />データマイニングが盛んに行われている。<br /><br />しかしながら、複数の異なる種類のデータを組み合わせた分析では、<br />各々のデータフォーマットが異なるため、分析処理が複雑になってしまう。<br /><br />そこで我々は異なる種類のデータを組み合わせた分析を容易にするために、<br />様々なデータをある一定の形式に変換可能な情報基盤を構築した。<br />具体的には、すべてのデータを分析処理が容易なXML<br />または構造を持ったテキスト形式に変換する。<br /><br />構築した基盤を用いて、<br />各種センサー・医療用データ・天候データ<br />を組み合わせたデータマイニングの結果も含めて報告する。
1 0 0 0 OA 貿易財の階層化と関連づけたアジア地域の貿易構造の研究と欧州地域との比較
1 0 0 0 ホタルイカの分類学 (特集 海の宝石 ホタルイカ)
- 著者
- 土屋 光太郎
- 出版者
- 生物研究社
- 雑誌
- 海洋と生物 (ISSN:02854376)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.247-252, 2009-06
1 0 0 0 OA マウス大脳皮質バレル領野構築に関わる細胞・分子機序の解明
本研究は、生後間もないマウス大脳皮質の接線軸方向に沿ってユニークな発現様式を示すシナプス・細胞間接着分子カドヘリン遺伝子群に着目し、それら発現制御機構や領野形成に果たす役割を探索することから、これまで不明であった大脳皮質機能領野個々の発生に関わる細胞・分子機序に迫ることを主目的とした。その結果、生後1週間の短期間に視床からの入力やバレルIV層神経細胞自身の活動に依存してカドヘリンサブクラスの発現動態が精妙に調節され、各サブクラスのもつ選択的な接着特異性が動的かつ協同的に神経細胞体の配置や樹状突起の配向性を制御することによってバレル領野特異的な組織構築様式を表出することが明白となった。
1 0 0 0 図書館のための個人情報保護ガイドブック
- 著者
- 小山 憲司
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.102-112, 2010
- 被引用文献数
- 3
利用者の学術情報ニーズを補完する図書館間相互貸借(ILL)に注目し,それを取り巻く環境を概念モデルとして提示,検討することで,学術雑誌の電子化が学術文献の需給にどのような変化を与えているかを分析した。その結果,利用者の量的・質的変化,文献の発見可能性の高まりなど,文献需要を押し上げる要因が複数確認される一方で,ビッグ・ディール契約に基づく電子ジャーナルの導入や機関リポジトリを通じた一次資料の電子化など,電子的入手可能性の増大によるILLの減少が明らかとなった。学術雑誌の電子化が学術情報へのアクセス環境を改善したが,予算確保,未電子化文献への対応といった課題も認められた。オープン・アクセスの進展とともに,ILLという互助制度が今後も求められると考えられる。