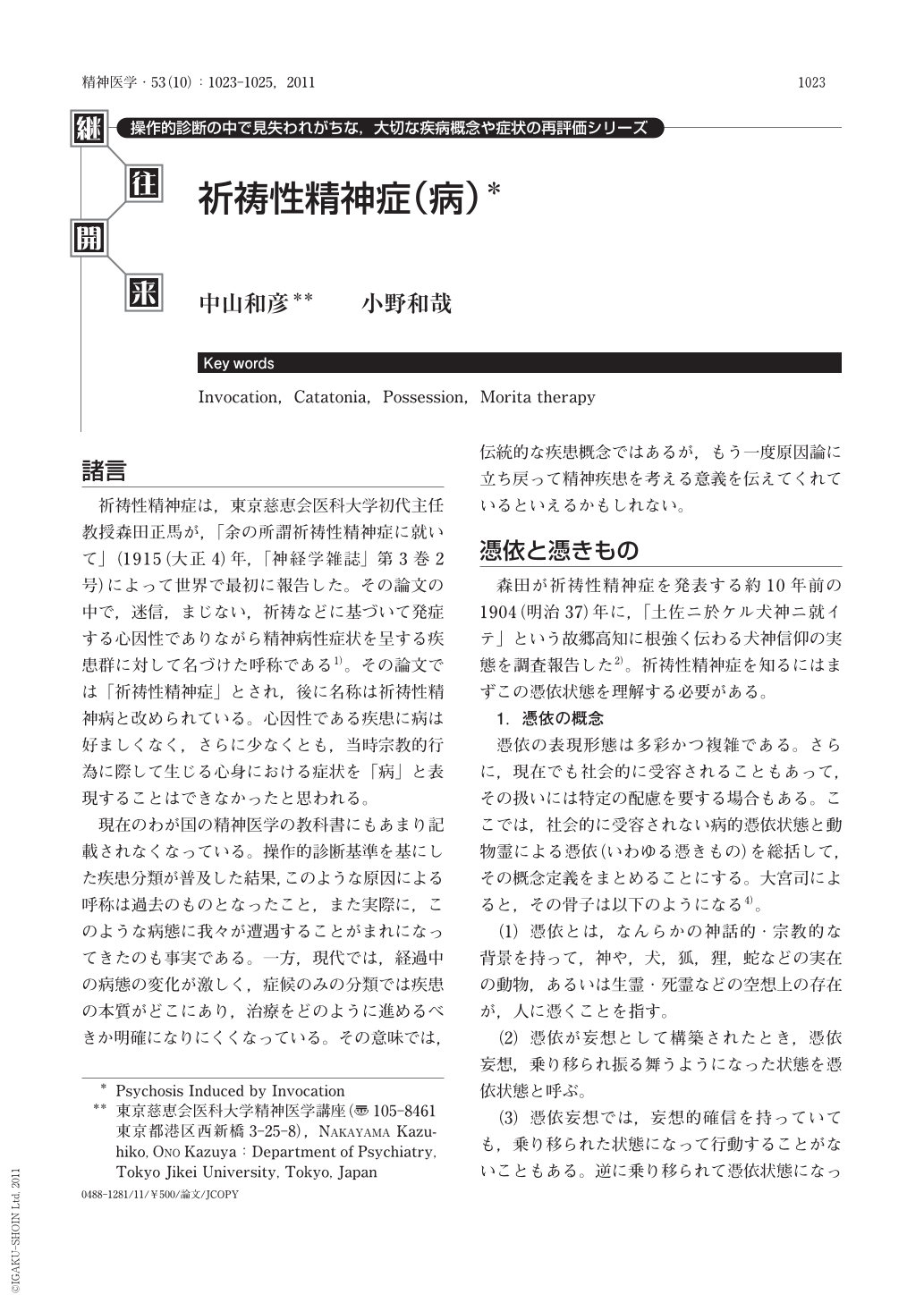2 0 0 0 OA 設備投資に対する固定資産税の実証分析
- 著者
- 小林 庸平 佐藤 主光 鈴木 将覚
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.172-189, 2020 (Released:2022-01-19)
- 参考文献数
- 18
地方財政のテキストにおいて固定資産税は「望ましい地方税」の代表例としてあげられる。ただし,その前提は土地に対する課税であることだ。しかし実際のところ,日本の固定資産税は土地に加えて,家屋や機械設備等,償却資産をその対象に含む。とくに償却資産に対する課税は,固定資産税に法人税とは異なる形での資本課税の性格を与えてきた。そこで本稿では資本税としての固定資産税の経済効果を検証する。具体的には工業統計調査および経済センサス活動調査(経済産業省・総務省)の事業所別パネルデータを用いて,固定資産税の償却資産課税が設備投資(有形固定資産の形成)に及ぼす影響について実証した。推定結果からは,固定資産税が設備投資を損なっている(マイナス効果が有意になっている)こと,とくに流動性制約に直面している(キャッシュフローが負の)企業に対するマイナス効果が高いことが明らかになった。
2 0 0 0 OA 三位一体改革が地方自治体の歳出行動に与える影響
- 著者
- 鈴木 崇文
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.132-155, 2017 (Released:2021-08-28)
- 参考文献数
- 23
本稿では,2000年代に行われた三位一体改革が地方自治体の公共サービス歳出にどのような影響を与えたか分析する。まず自治体の歳出意思決定モデルを構築し,消費者需要の推定に広く用いられているAlmost Ideal Demand System(AIDS)を適用して変数の内生性を考慮したうえで行動パラメータの推定を行う。次に推定したパラメータを用いて,三位一体改革が行われなかった場合の歳出水準をシミュレートする。シミュレートした歳出水準と実際の歳出水準を比較することにより,改革が歳出に与えた影響を分析した。目的別歳出の分析からは,改革によって自治体は民生費,教育費およびその他の費目で相対的に大きい歳出の削減を行っていた。民生費は特定補助金の削減と税源移譲およびそれに伴う交付税調整の両者を原因として歳出が減少していた一方で,教育費とその他では前者の影響は小さく,主に後者の影響によって歳出の減少がもたらされたことが明らかになった。また,農林水産費,商工費および土木費では前者と後者の歳出に与える影響は相殺する方向に働いていた。
2 0 0 0 OA わが国における財政競争 ―市町村・歳出分類別の分析
- 著者
- 山本 航
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.145-163, 2018 (Released:2021-08-28)
- 参考文献数
- 38
近年,自治体間の財政競争・相互依存関係に関する研究がわが国においても注目を集めてきた。自治体間の財政競争・相互依存関係には,大別して,①便益のスピルオーバー,②資本や住民の移動,③情報のスピルオーバーによる模倣という理論的背景が考えられるが,これら理論間では政策的含意が必ずしも一致しないため,実証結果を解釈する際は理論的背景への意識が不可欠となる。この点に関し,Hayashi and Yamamoto(2017)は推定において類似団体区分制度を活用することで,自治体の1人当たり総歳出についてヤードスティック競争が適合するとの結論を得ている。しかし,1人当たり総歳出に関する「平均的」な記述としてヤードスティック競争を用いるのが適当であるという結論を得ることができたとしても,その結果が個別の歳出項目についても当てはまる保証はない。そこで本稿では同論文を拡張し,個別の歳出項目を分析対象とした場合にも同論文の結論が成立するのかを実証的に検証する。
2 0 0 0 OA 「オランダモデル」と財政改革
- 著者
- 島村 玲雄
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.198-217, 2017 (Released:2021-08-28)
- 参考文献数
- 23
本稿は,1982年のワセナール合意を契機とする「オランダモデル」による経済回復において,財政制度がどのように変化し,どのように「成功」に寄与したのか,財政の視点から再検討するものである。政労使の政策協調による雇用政策として知られるオランダモデルに対し,財政再建が課題であったルベルス政権,コック政権の2つの政権がいかなる財政改革を行ったのか,制度の視点から明らかにした。その結果,両政権の財政再建策の手法は異なるものであったが,その後の経済回復への貢献は大きいものであった。またオランダモデルとして理解される新たな雇用制度が単独で機能したというわけではなく,政府による抜本的な財政改革によって実現したと理解されるべきものであった。
- 著者
- 石田 三成
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.224-241, 2014 (Released:2021-10-26)
- 参考文献数
- 8
本稿では北海道内の市町村を対象として,①市町村が銀行等引受債を起債するにあたり,地域金融機関同士の競争環境が弱いと,地域金融機関の交渉力が強くなるため,銀行等引受債の金利スプレッド(対財政融資資金貸付金利)が上昇する,②公的資金のウェイトが高い地域では,公的資金が地域金融機関の競合相手として機能するため,地域金融機関による寡占の弊害が小さくなり,銀行等引受債の金利スプレッドも低下する,という2つの仮説を定量的に検証した。その結果,2つの仮説がともに支持された。主要な結論は以下のとおりである。まず,入札や見積合わせに参加する地域金融機関数が多くなるほど,銀行等引受債の金利スプレッドは低下することが明らかとなった。次に,非競争的な随意契約であっても指定金融機関以外の金融機関から資金を調達することで,わずかに金利スプレッドを引き下げることが可能である。最後に,公的資金のシェアが高い地域ほど銀行等引受債の金利スプレッドが低くなる傾向が確認され,公的資金は地域金融機関による寡占の弊害を軽減していることが示唆された。
2 0 0 0 OA 消費税の税収変動要因の分析 ―産業連関表を用いた需要項目別の税額計算
- 著者
- 上田 淳二 筒井 忠
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.248-266, 2013 (Released:2021-10-26)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
日本の消費税について,毎年度の税収対GDP比やVRR(VAT Revenue Ratio)の値をみると,必ずしも一定で推移しているわけではなく,GDPに対する税収弾性値も変動している。本稿では,消費税収の対GDP比が変動してきた要因を明らかにし,将来の消費税収の対GDP比の大きさを考える際に考慮しなければならない要因を検討する。そのために,産業連関表を用いて,非課税取引を考慮した需要項目別の課税ベースの大きさを考えたうえで,毎年度の「理論的税収」の値を計算することによって,GDPに対する民間消費や住宅投資,一般政府総固定資本形成の比率の変化が,消費税収の変動に大きな影響を与えてきたことを示す。さらに,理論的税収と徴収ベースの消費税収の差として,「税制要因」による税収変動の大きさを把握し,2003年度の税制改正における中小事業者への特例措置の変更によって,税制要因の規模が大きく縮小したことを示す。
- 著者
- 吉弘 憲介
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.200-217, 2006 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 39
1980年代以降,アメリカの州財政は新連邦主義の影響からその役割が強調され注目が集まっている。その中で,90年代を通じて州所得税改革が相次いで行われたとされる。本稿で取り上げるニューヨーク州は90年代以降,州個人所得税を中心に減税政策を展開するが,その過程で州内経済の変化によって生じた貧困問題などへの対応から勤労所得税額控除などの還付可能な税額控除を増額していく。このとき,各ブラケットでの限界税率の引き下げや基礎控除の引き上げなど従来行われてきた減税政策に加えて,還付可能な税額控除により低所得者層で実効税率が急速に引き下げられていく。本稿ではこうした変化を分析することで,90年代に各州で積極的に導入されていった還付可能な税額控除の影響を,ニューヨーク州のケーススタディを通じて明らかにしていく。
2 0 0 0 OA フランス 高等教育進学制度の改革
- 著者
- 安藤英梨香
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 275-2), 2018-05
2 0 0 0 昭和38年度総合防衛図上研究(三矢研究)の基礎研究抜粋と資料
- 出版者
- 統裁部
- 巻号頁・発行日
- 1963
2 0 0 0 SFマガジン・ベスト
2 0 0 0 SFマガジン・ベスト
- 著者
- 亀山 晶子 樫原 潤 山川 樹 村中 昌紀 坂本 真士
- 出版者
- 産業・組織心理学会
- 雑誌
- 産業・組織心理学研究 (ISSN:09170391)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.165-177, 2021 (Released:2022-04-29)
Recently, a case of depression called “modern-type depression” (MTD), which has different characteristics from melancholic or traditional-type depression (TTD), has been discussed. At the workplace, it has been suggested that employees with MTD are regarded as a problem, so this study examined the characteristics of impressions and attitudes toward MTD compared to those regarding TTD among supervisors and coworkers. Survey participants were 245 managers and 208 non-managerial employees from Japan. They read two vignettes that described fictitious employees with either TTD or MTD, and completed items regarding their impressions and attitudes toward these employees. Results indicated the following: (a) both managerial and non-managerial employees recognized there were employees similar to those described in the MTD vignette in society, especially among the youngest generations; (b) both managerial and non-managerial employees had more negative impressions and attitudes toward employees with MTD compared to those regarding employees with TTD; and (c) managers were more likely to attribute the cause of MTD to the employee’s personality and have lower sense of familiarity and understanding toward MTD characteristics. It is suggested that there are less understanding and support for MTD in the workplace and countermeasures for these problems are required.
2 0 0 0 OA 小腸の自己免疫機構:クローン病の病態とサイトカイン
- 著者
- 金井 隆典 渡辺 守 日比 紀文
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.1, pp.39-45, 2002 (Released:2003-01-28)
- 参考文献数
- 34
最近,潰瘍性大腸炎とクローン病の分子免疫学的な病態メカニズムが徐々に明らかにされるにつれ,従来の治療法とは異なった,より病態に特異的な治療法,サイトカインや免疫担当細胞に着目した治療法が開発,研究されるようになった.特に,抗TNF抗体によるクローン病治療に代表されるように,実際の臨床現場に応用され,優れた成績が報告されつつある.潰瘍性大腸炎とクローン病といった生涯にわたり治療を余儀なくされる疾患に対して,副作用が問題となる長期副腎皮質ステロイド投与に替わる,より効果的な治療法の開発は本病が若年で発症することを考え合わせ,社会的にも重要な問題である.免疫学の進歩の恩恵を受け,数年後の炎症性腸疾患治療は従来とは全く異なった新たな局面からの治療法が開発されることも考えられている.本稿では,現在までに明らかとされた炎症性腸疾患の免疫学的病態と,サイトカインに関連した知見に基づいた治療法の開発状況について概説した.
2 0 0 0 運動と視覚フィードバックの空間的一致性が操作体験に与える影響
- 著者
- .*田中 拓海 今水 寛
- 雑誌
- 日本心理学会第86回大会
- 巻号頁・発行日
- 2022-07-29
2 0 0 0 祈祷性精神症(病)
諸言 祈祷性精神症は,東京慈恵会医科大学初代主任教授森田正馬が,「余の所謂祈祷性精神症に就いて」(1915(大正4)年,「神経学雑誌」第3巻2号)によって世界で最初に報告した。その論文の中で,迷信,まじない,祈祷などに基づいて発症する心因性でありながら精神病性症状を呈する疾患群に対して名づけた呼称である1)。その論文では「祈祷性精神症」とされ,後に名称は祈祷性精神病と改められている。心因性である疾患に病は好ましくなく,さらに少なくとも,当時宗教的行為に際して生じる心身における症状を「病」と表現することはできなかったと思われる。 現在のわが国の精神医学の教科書にもあまり記載されなくなっている。操作的診断基準を基にした疾患分類が普及した結果,このような原因による呼称は過去のものとなったこと,また実際に,このような病態に我々が遭遇することがまれになってきたのも事実である。一方,現代では,経過中の病態の変化が激しく,症候のみの分類では疾患の本質がどこにあり,治療をどのように進めるべきか明確になりにくくなっている。その意味では,伝統的な疾患概念ではあるが,もう一度原因論に立ち戻って精神疾患を考える意義を伝えてくれているといえるかもしれない。
- 著者
- ⼤串 敦
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.50, pp.152-156, 2021 (Released:2022-06-11)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 「東方シフト」のなかの方向転換:米ロ対立下のロシアの東方政策と地域秩序へのインパクト
- 著者
- 加藤 美保子
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.48, pp.1-18, 2019 (Released:2020-05-30)
- 参考文献数
- 40
The Ukraine crisis and subsequent Western sanctions have accelerated Russia’s economic dependence on China. Since the annexation of Crimea, scholars and analysts of Russia’s Asia policy have focused on Russia’s pivot to China and disregarded any preceding diversification policies throughout the Asia-Pacific region. This paper has two purposes. First, the paper aims to explain geopolitical changes in Russia’s Asia pivot policy over the last 20 years by analyzing not only Moscow’s strategic thinking towards major Asian powers―including the US, China, Japan, and South Korea, ―but also the restoration of its relationship with former Soviet partners such as India, Vietnam, and North Korea―. Second, this paper examines the impact of the Russia-US confrontation and the emerging friendship regime between Russia and its traditional partners in light of a Eurasian security order.The first section explains Russia’s strategic thought and policies towards the Asia-Pacific region from 2000 to 2012 by focusing on two factors: 1) The Asia-Pacific region as an emerging political and economic centre in a multipolar world vis-à-vis a US-led unipolar world. 2) The Asia-Pacific region where Russia needs to overcome isolation by restoring traditional diplomatic relations with China, India, Vietnam, and North Korea. The second section explains Russia’s aspiration as a Euro-Pacific power under the third Putin administration before the escalation of the Ukrainian crisis. In this period, Russia’s diversification policy in the Eastern direction expanded to the Pacific region including US allies. The third section describes how Russia accelerated its economic dependence on China under the deterioration of relations with the US by analysing energy and military cooperation with China. The fourth section evaluates the impact of the Russia-US confrontation at the global and regional levels as well as the Russia-China quasi-alliance in a newly emerging order in Eurasia.In conclusion, this paper reveals three findings. First, Russia’s geopolitical direction in its “Pivot to the East” policy developed in three steps: 1) the restoration of relations with former soviet partners to overcome isolation in the region (2000–2012); 2) regaining self-confidence as a great power and seeking aspiration as a Euro-Pacific power (2012–2014); 3) deterioration of relations with the US and subsequent economic dependence on China. This paper reveals that Russia has barely retained its multi vector foreign policy by developing and utilizing relations with former Soviet partners such as India and Vietnam even after March 2014, whereas Russia has accelerated its China-centred foreign and economic policy since the annexation of Crimea, as indicated in other research. Second, while Russia’s “pivot to China” policy is inherently based on economic incentives, Russian leadership views relations with China largely through the lens of US-Russia relations. Currently, as Moscow does not anticipate an opportunity to improve its relations with the US, Russia is unlikely to review its China-centred policy in the short and medium term. Third, the Russia-China strategic partnership is becoming a quasi-alliance in terms of military cooperation. For Russia, the only constructive means to remain a great power in Eurasia is to actively engage in both military cooperation and China-led regional order such as the “Belt and Road Initiative (BRI)”, to prevent further isolation in Eurasia. Meanwhile, its strengthened strategic partnerships with traditional Asian partners―the sole achievement of its early “Asia pivot” policy―will serve well to balance relations with China.
- 著者
- 富樫 耕介
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.47, pp.81-97, 2018 (Released:2019-10-08)
- 参考文献数
- 30
Chechnya is important in terms of issues related to the nature of the state and minorities in the Russian Federation. When considering the Chechen problem, one notices that it has a dual structure. First, as a minority in Russia, the Chechen people have been affected by changes in the Russian state. Most extant research on this issue has examined the Chechen problem by focusing on the Chechens’ relationship with the Russian state.However, there is also another aspect—the form and nature of the “state” sought by the Chechen people has had an impact on both themselves and the Russian side. Existing research has mainly studied the kinds of tensions that “the state” sought by the Chechen people has caused in Russia. Thus, the effects of this “state” on the Chechens themselves have not been adequately studied.This article seeks to consider the Chechen problem by focusing on the nature of the “state” sought by the Chechen people. In particular, it seeks to clarify the kind of influence exerted by the changes in the nature of the “state” advocated by a minority group on that minority group itself. Further, it also considers the current situation and problems in the Chechen Republic.To achieve these aims, this article undertakes two tasks. First, it considers whether the form of the Chechen “state” governed by Ramzan Kadyrov is adequately accepted by its residents. In Chechnya, there have been terrorist activities and revolts by independence-seeking and radical Islamic groups, who do not recognize the legitimacy of the Kadyrov regime. This article analyzes the GTD (Global Terrorism Database) to assess whether the incidents of terror and rebellion have decreased over time to the present.The second task is to consider issues related to the nature of the “state” under the incumbent Kadyrov regime. Terrorism and rebellion are reactions against the government that can be easily observed externally, but there are also cases where these are subdued through strict crackdowns by the government. However, issues that concern the form and legitimacy of the state are often raised during the process of moving toward a stable statehood. Based on a fieldwork conducted in August 2018 and by considering the relationship between the Chechen general public and the “state,” particularly from the dual perspectives of history and public opinion, this article reveals the current problems relevant to the Chechen “state.”In conclusion, the number of terrorist activities in Chechnya as well as in North Caucasus has declined, and the Chechen republic is stable at present. Under the Kadyrov regime, it is difficult to research modern Chechen history because of the loss of research materials due to war and political issues preventing objective research. Therefore, especially the history and experience under the Chechen separatist “state” (1991–2000) are beginning to be forgotten in the current Chechen society. The Kadyrov regime emphasizes the legitimacy of its own “state” by comparing it with the Chechen separatist “state,” which it has labeled as a symbol of chaos, destruction, and destabilization. However, there are differences between the government and the people in Chechnya since the Kadyrov regime ignores the general public. Consequently, this would lead people to doubt the legitimacy of Kadyrov’s “state.”