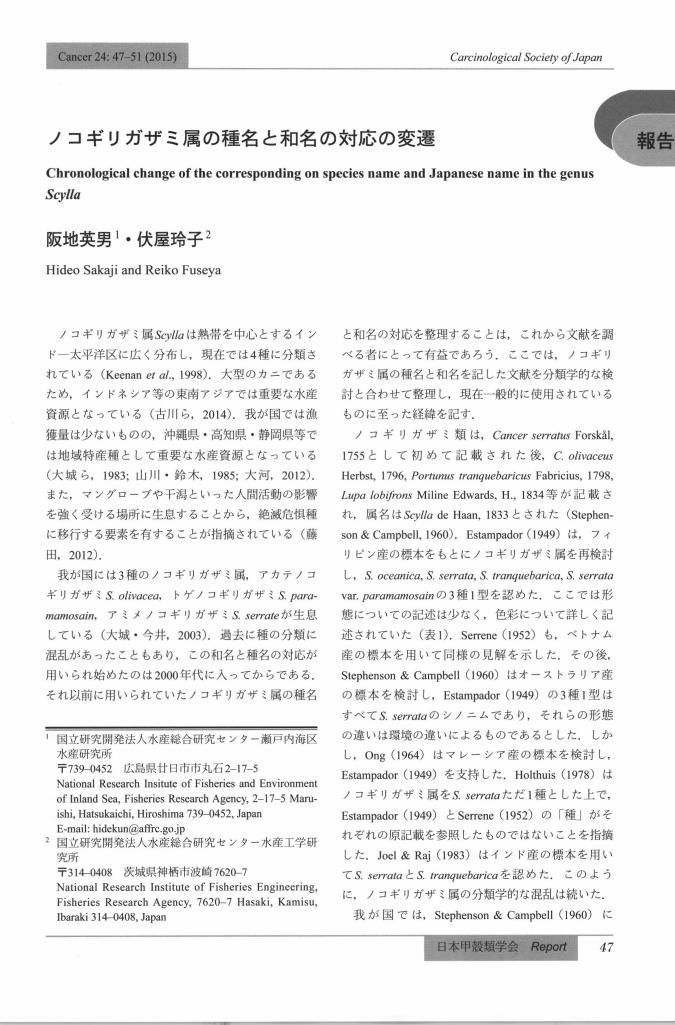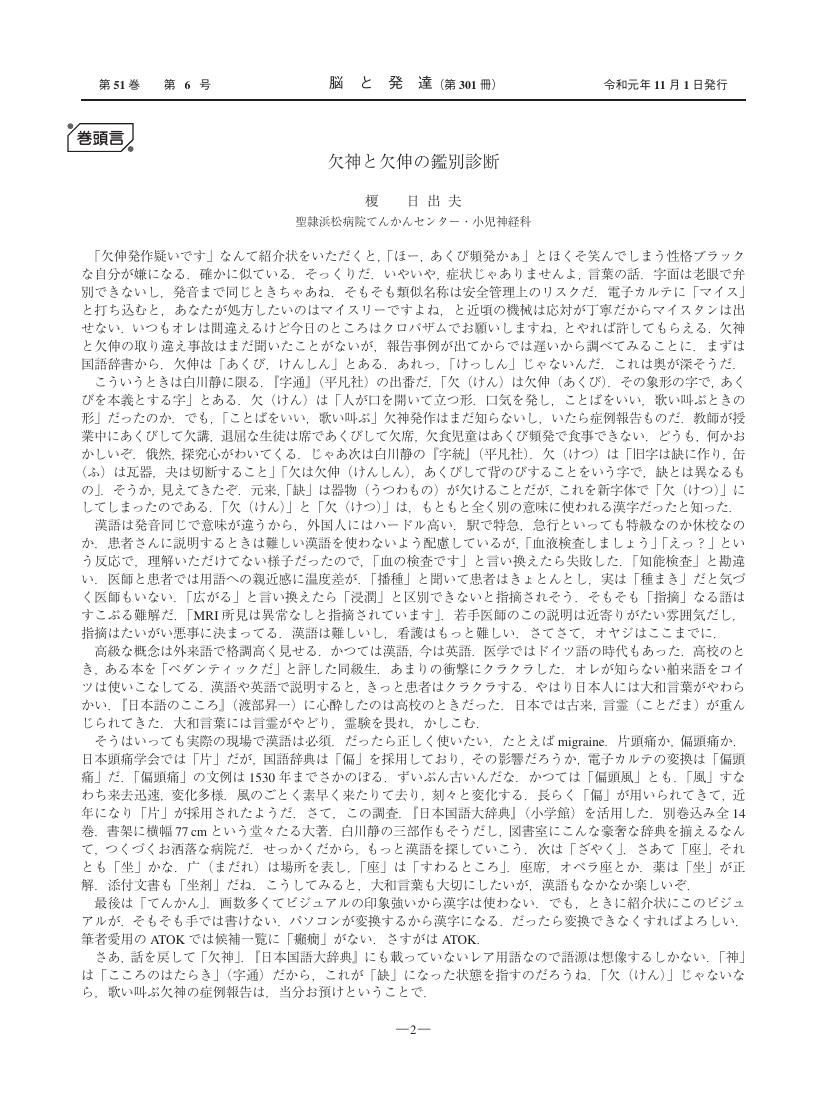- 出版者
- ノートルモンド社
- 巻号頁・発行日
- 2010
2 0 0 0 OA The Increasing Trend of Intense Precipitation in Japan Based on Four-hourly Data for a Hundred Years
- 著者
- Fumiaki Fujibe Nobuo Yamazaki Mitsugi Katsuyama Kenji Kobayashi
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.41-44, 2005 (Released:2005-04-21)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 78 86
Long-term changes of precipitation intensity were analyzed using a dataset which was recently compiled by the Japan Meteorological Agency (JMA). After some quality check, data of four-hourly, daily, and hourly precipitation at 46, 61, and 8 stations, respectively, were used for the period 1898-2003 on the condition that data for at least 80 years were usable in each month. As the measure of precipitation intensity, ten categories were defined so as to equate the total precipitation amount in each month at each station. The result is characterized by increase of precipitation in high categories, namely intense precipitation, and decrease in low categories. The linear trend for the highest and lowest categories is ±20-30% per century. This feature is found invariably for four-hourly, daily, and hourly precipitation, and qualitatively for all the seasons and regions.
2 0 0 0 簗田家文書 : 会津の商人司、簗田家の軌跡
- 著者
- 福島県立博物館友の会古文書愛好会編
- 出版者
- 福島県立博物館友の会古文書愛好会
- 巻号頁・発行日
- 2008
2 0 0 0 幹部政策の基本問題
- 著者
- 国民文庫編集委員会 編訳
- 出版者
- 国民文庫社
- 巻号頁・発行日
- 1954
2 0 0 0 関節リウマチによる拘縮肘に対する人工肘関節置換術の治療成績
- 著者
- 安間 英毅 寺島 照雄 岡 義春 坂野 真士 加藤 文彦
- 出版者
- 中部日本整形外科災害外科学会
- 雑誌
- 中部日本整形外科災害外科学会学術集会 抄録集
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.378, 2005
【目的】関節リウマチの肘関節の骨障害に伴う関節痛と可動域障害に対しては、骨破壊が進行した例では人工関節置換術が適応となる。関節リウマチによる拘縮肘に対する人工肘関節置換術の治療成績を検討したので報告する。【対象および方法】術前の肘関節可動域のArcが30゜以下の10症例10肘を対象とした。症例は男性2例、女性8例、平均年齢51歳(31_から_71歳)であった。機種はKudo Elbow 6肘、JACE型 1肘、Coonrad-Morrey型 3肘であった。Campbell法にてアプローチし、術中骨棘の切除や軟部組織の解離操作を十分に行った。これらの症例の日本整形外科学会肘機能評価法(JOA score)、X線所見、合併症を検討した。【結果】術後経過観察期間は平均37ヶ月(5_から_65ヶ月)であった。JOA scoreは術前平均38点から術後平均72点に改善した。疼痛は全例で消失し、肘関節の屈曲/伸展は術前平均81゜/_-_56゜から術後平均124゜/_-_28゜、Arcは術前平均22゜(10゜_から_30゜)から術後平均96゜(80゜_から_106゜)に改善した。全例で洗顔、摂食動作が困難であったが術後いづれも改善した。尺骨神経領域のしびれ、関節の不安定性、X線所見でのlooseningを生じた症例はなかった。【考察】関節リウマチによる拘縮肘に対し人工肘関節置換術を施行したが、十分な肘関節の可動域が獲得され、ADLの大幅な改善が得られた。
2 0 0 0 OA 毛髪への香料の付着に及ぼすカチオン性高分子と界面活性剤のコアセルベートの影響
- 著者
- 兼井 典子 児玉 達哉 張谷 友義
- 出版者
- 日本化粧品技術者会
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.311-316, 2017-12-20 (Released:2017-12-27)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
シャンプーの主成分であるアニオン界面活性剤はカチオン性高分子との相互作用により,シャンプー希釈時のある濃度領域において,コアセルベートと呼ばれる水に不溶の複合体を形成する。コアセルベートは毛髪に付着してコンディショニング効果を付与することが知られており,コアセルベートの性質がシャンプーの使用感に影響を及ぼすことが報告されている。一方,香料はシャンプーに配合されており,香り立ちや残香は重要である。コアセルベートは毛髪に付着することから,香料の香り立ちや残香はコアセルベートの影響を受けるものと考えられる。そこで,本研究では毛髪への香料の付着に及ぼすコアセルベートの影響について検討した。コアセルベート有/無シャンプー水溶液の上澄み液中の香料量を比較した結果,香料はコアセルベート中に取り込まれる傾向にあることが明らかとなった。さらに,コアセルベート有/無のシャンプーを用いて洗髪した毛髪への香料の付着量をガスクロマトグラフィーにより定量した結果,コアセルベート有の方が無よりも香料の付着量は増加することが確認された。これは,コアセルベート形成時に香料が取り込まれて毛髪へ付着するためと考えられる。
2 0 0 0 OA 輪状軟骨切開術後に切開孔を閉鎖しえた4症例
- 著者
- 小針 健大 鹿野 真人 佐藤 廣仁 髙取 隆
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会
- 雑誌
- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.227-233, 2016-10-30 (Released:2016-11-17)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 2
輪状軟骨切開術は,輪状軟骨前方部分の鉗除を行う気道確保術であり,皮膚から気管までの距離が短く甲状腺の操作も必要としないため,安全性の高い術式である。われわれは,前頸部膿瘍,出血傾向,短頸および上気道狭窄の緊急度が高く通常の気管切開術が困難な4症例に対し輪状軟骨切開術を施行し,術後に切開孔を閉鎖しえた。これまで輪状軟骨の損傷は肉芽形成の可能性があり推奨されていなかったが,全例で声門下の肉芽増生はなく経過している。輪状軟骨切開術は,手術リスクの高い症例に対しても安全に行える術式であり,また術後に切開孔を閉鎖する場合でも必ずしも肉芽形成による気道狭窄などの理由とはならず,有効な術式であると考えられた。
2 0 0 0 OA 輪状軟骨鉗除による気管孔形成術の実際と適応
- 著者
- 鹿野 真人
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.9, pp.1254-1256, 2019-09-20 (Released:2019-10-02)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA ノコギリガザミ属の種名と和名の対応の変遷
- 著者
- 阪地 英男 伏屋 玲子
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.47-51, 2015-08-01 (Released:2017-07-05)
2 0 0 0 OA 大山町史細見 : 一村一品運動のモデルはいかにして形成されたか
- 著者
- 足立 文彦 Fumihiko Adachi
- 出版者
- 金城学院大学
- 雑誌
- 金城学院大学論集. 社会科学編 = Treatises and Studies by the Faculty of Kinjo Gakuin University. Studies in Social Sciences (ISSN:1880036X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.8-23, 2014-09-30
2 0 0 0 IR 武士から士族へ : 社会層としての変容と学校教育利用
2 0 0 0 OA 欠神と欠伸の鑑別診断
- 著者
- 榎 日出夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.364, 2019 (Released:2020-01-17)
2 0 0 0 OA 2.組織細胞化学シリーズ(若手研究者へのヒント) 最近の免疫組織化学賦活法(6)
- 著者
- 並松 茂樹 杉崎 祐一 土屋 眞一
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.178-184, 2010 (Released:2010-11-09)
- 参考文献数
- 15
Current antigen retrieval techniques include the use of citrate buffer, Tris-HCl containing 5% urea, and EDTA solutions combined with heating in a microwave oven or autoclave. These methods must be adjusted for a given tissue or antigen. To improve the efficiency of antigen retrieval for immunohistochemical staining, we developed a new method using citraconic anhydride. We describe this new antigen retrieval method using 0.05% citraconic anhydride solution of pH 7.4 and heat. This antigen retrieval method produced satisfactory staining results for a wide variety of antigens.
2 0 0 0 工業立地論
- 著者
- アルフレート・ヴェーバー 著
- 出版者
- 大明堂
- 巻号頁・発行日
- 1966
2 0 0 0 地形の説明的記載
- 著者
- W.M.デービス 著
- 出版者
- 大明堂
- 巻号頁・発行日
- 1969
- 著者
- 武智 研志 古手川 明里 千石 莉音 西隅 勇翔 谷川 愛采 和田 真志 本橋 直人 高取 真吾 柴田 和彦 難波 弘行
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.8, pp.875-882, 2022-08-01 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 21
We investigated a situation of passive smoking and its damaging effects among high school students. Urine cotinine concentration was measured and quantified. Additionally, we evaluated the awareness of passive smoking and smoking regulations in high school students, and the educational effect on passive smoking using a questionnaire survey and educational videos produced by high school students. We conducted a self-reporting questionnaire survey with high school students before and after watching the video produced by the high school students. We gathered the scores of the Kano Social Nicotine Dependence Questionnaire (KTSND) and awareness of smoking restrictions. Consent was obtained through the questionnaire before watching the video and collecting urine samples. Urine cotinine concentrations from 54 samples were evaluated and indicated within the low value. The KTSND score significantly decreased for those who responded to both questionnaires, after watching the video. Furthermore, analysis of the KTSND questionnaire items showed a significant decrease in scores for lifestyle, stress, and smoking location. This suggests that the video produced in this study has a certain amount of educational effect on passive smoking and that the student-led educational method is effective. The survey using the KTSND revealed that there were some students who were not exposed to passive smoking, but instead had high smoking tolerance. Going forward, it will be necessary to promote education on passive smoking and smoking prevention by incorporating the video lecture and urine cotinine concentration was measured, as in this study, to encourage behavior that decreases passive smoking among high school students.
2 0 0 0 OA 日本の医療分野における規制改革の動き
- 著者
- 森下 竜一 隅藏 康一 齋藤 裕美
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.68-73, 2015-08-31 (Released:2017-10-19)
The environment of business development on regenerative medicine in Japan was drastically changed by the Pharmaceuticals and Medical Devices, etc. Act and the Regenerative Medicine Act that were enforced on November 25th, 2014. In parallel, the situation surrounding health and medical innovation in Japan is also changing. In this article we interviewed Professor Ryuichi Morishita, a member of the Council for Regulatory Reform, to discuss the trend of medical regulatory reform in Japan.