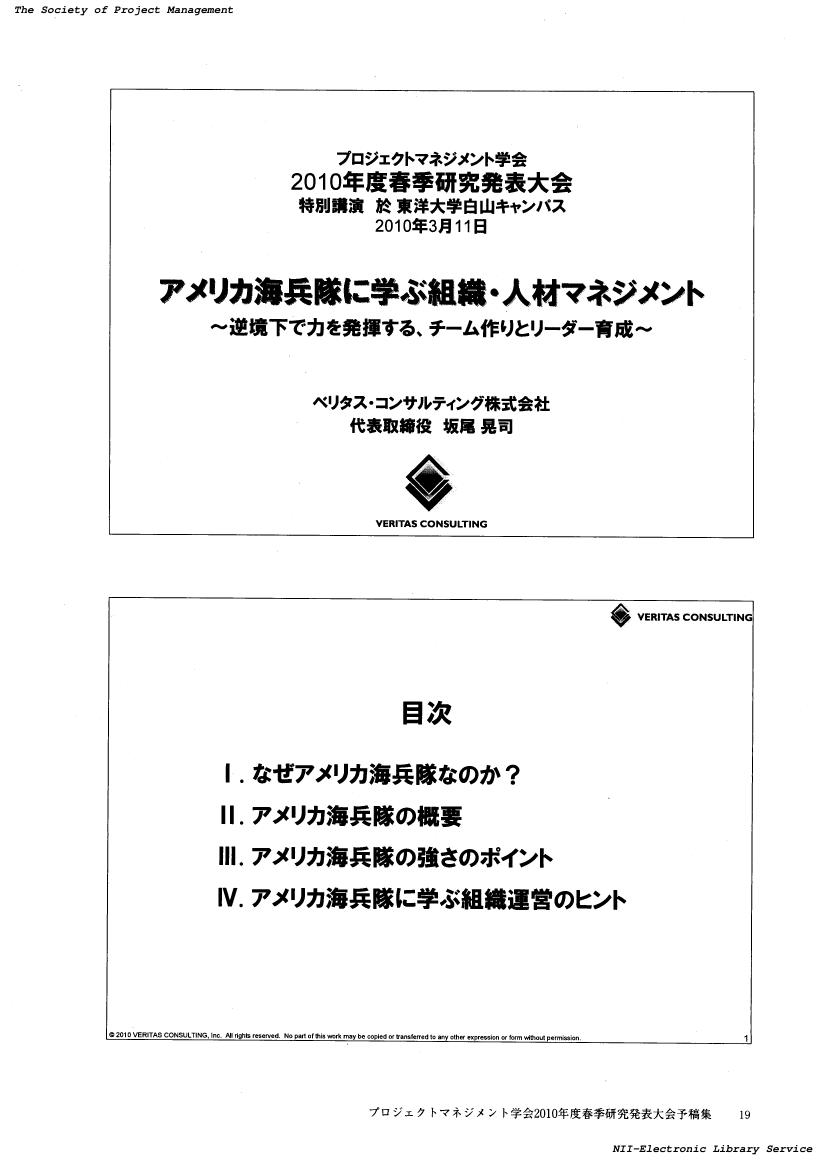2 0 0 0 OA 河畔におけるごみのポイ捨て対策
- 著者
- 中俣 友子 阿部 恒之
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会誌 (ISSN:18835864)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.304-308, 2018-07-31 (Released:2019-07-31)
- 参考文献数
- 24
本論は,著者が過去に行ったごみのポイ捨て対策のための研究 (実験室実験・現場実験) を紹介し,海洋ごみ対策に関してささやかな提言を試みたものである。実験室実験では,スライドを提示して一対比較でごみの捨てやすさを判断してもらった。現場実験では,宮城県仙台市と名取市の間を流れる名取川河畔に看板を設置し,ごみの量を実際に比較した。両実験とも,監視カメラの有無,先行ごみの有無,景観の違い (草むら・更地・花壇),看板の違い (無・目の絵・監視カメラ撮影画像) の 4 要因を検討した。その結果,監視性の確保,記述的規範への配慮,領域性の確保,情緒的ブレーキが有効なごみ対策になりうることが明らかになった。海洋ごみについても同様の対策が有効であると推測されるが,対策の対象地がごみに悩む現場にとどまらず,海の向こうにまで広がっていることが問題を複雑化している。
2 0 0 0 OA スカイダンサーつきゴミ箱によるポイ捨て防止
- 著者
- 木村 友哉 松村 真宏
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.4D3GS1203, 2020 (Released:2020-06-19)
電源が入ると人形が踊りだす屋外式エアー看板の一種「スカイダンサー」が人々の行動を変えるかを定量的に測定した。その結果、スカイダンサーに対し積極的な反応を示した人数は通行量の2.0%から4.9%に増加したほか、視認率は4.6倍になった。この装置を応用し、イベント会場のゴミ箱に併置してポイ捨ての量を減らすことを試みたところ、イベント翌日に拾得されたゴミの量が前年比で約半分になった。
2 0 0 0 OA 浅野侯爵御講話速記録
- 出版者
- 大阪芸備会
- 巻号頁・発行日
- 1936
2 0 0 0 OA e-Sportsにおける動画コンテンツを用いた戦略思考分析手法に関する検討
- 著者
- 梶並知記
- 雑誌
- 研究報告デジタルコンテンツクリエーション(DCC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013-DCC-4, no.14, pp.1-7, 2013-06-20
本稿では,e-Sports の一種である対戦型格闘ゲームに関する,プレイ技能向上支援の方法について検討する.近年,対戦型格闘ゲームの競技会は世界各国で行われており,その模様は動画コンテンツとして配信されている.本稿では,対戦型格闘ゲームのプレイが知的なものであり,またプレイヤーが競技者 (Athlete) でもあり観戦者 (Audience) でもあると仮定し,動画コンテンツを用いて,ゲームプレイにおける戦略・戦術に関する創造活動を支援するための枠組みについて述べる.
2 0 0 0 OA 「「蜘蛛の糸」仕事をしたのはカンダタの筋力か?」へのコメント
- 著者
- 吉岡 大二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.9, pp.650, 2016-09-05 (Released:2017-01-09)
- 参考文献数
- 1
会員の声「「蜘蛛の糸」仕事をしたのはカンダタの筋力か?」へのコメント
2 0 0 0 OA 食品中の脂質の酸化生成物による風味変化
- 著者
- 高村 仁知
- 出版者
- 公益社団法人 日本油化学会
- 雑誌
- オレオサイエンス (ISSN:13458949)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.6, pp.231-235, 2007-06-01 (Released:2013-06-01)
- 参考文献数
- 9
脂質に含まれる多価不飽和脂肪酸は構造的に酸化されやすく, 食品においては調理加工や保存の過程などで酸化をうける。その結果, 生じた脂質酸化生成物には食品の風味を損なう, 毒性を有するなど, 食品の品質に悪影響をもたらすものがある。大豆においては, リノール酸がリポキシゲナーゼによって酸化されて生成するリノール酸13S-ヒドロペルオキシドから豆臭の主成分であるヘキサナールが生ずる。大豆種子に存在する3種のリポキシゲナーゼアイソザイムのうち, L-2アイソザイムがヘキサナール生成に最も寄与し, L-3アイソザイムは逆にヘキサナール生成に寄与せず, 逆にヘキサナール生成を抑制する。一方, 魚においては, 従来, トリメチルアミンが魚臭の主成分であるとされてきたが, イコサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸などの酸化劣化に由来する多くのカルボニル化合物が存在すること, これらの化合物はさまざまなにおいを有しており, これらのにおいが相まって魚臭となっていることが明らかとなった。
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1916年09月18日, 1916-09-18
- 著者
- 坂本美紀 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1997
2 0 0 0 OA 南部方言集 : 教育適用
2 0 0 0 OA 記録技術 (第8回) 2. 磁気記録 (VII)
- 著者
- 小西 達夫 角井 良治 沼澤 潤二
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.495-502, 1981-06-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 日本におけるミツバチのアカリンダニ寄生の現状
- 著者
- 前田 太郎
- 出版者
- 日本ダニ学会
- 雑誌
- 日本ダニ学会誌 (ISSN:09181067)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.9-17, 2015-05-25 (Released:2015-06-25)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 6 9
アカリンダニAcarapis woodiはミツバチ成虫の気管内に寄生して体液を吸汁する.アカリンダニの寄生はミツバチコロニーに深刻なダメージを与え,セイヨウミツバチApis melliferaにおけるアカリンダニの分布はヨーロッパから南北アメリカを中心に全世界に広がっている.日本におけるセイヨウミツバチへの寄生報告は2010年に初めて行われ,同年ニホンミツバチA. cerana japonicaにおいてもアカリンダニの寄生が確認された.その後,農林水産省のアカリンダニに関する記録によると,2012年までわずか4件の記録がニホンミツバチであるだけで,セイヨウミツバチにおける寄生記録はない.しかし,実際のアカリンダニ被害件数はこの記録よりもはるかに多いと考えられた.そこで,全国のニホンミツバチ350コロニーと,セイヨウミツバチ50コロニーについてアカリンダニ寄生の現状を調査した.アカリンダニ寄生の診断は,顕微鏡下でミツバチを解剖して行った.その結果,ニホンミツバチでは東日本を中心にアカリンダニの寄生が確認された.一方,セイヨウミツバチではアカリンダニの寄生は発見されなかった.セイヨウミツバチへのアカリンダニ寄生率が,ニホンミツバチに比べてはるかに低い原因について現在調査中である.
2 0 0 0 OA 下腿外側鍼刺激の眼循環動態に及ぼす影響
- 著者
- 水上 まゆみ 矢野 忠 山田 潤
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.201-212, 2006 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 21
We previously reported the possibility that acupuncture stimulation to the Guangming (GB37) increased retinal blood-flow volume. In this study, we examined whether this reaction was peculiar to GB37 by measuring the blood-flow velocity and pulsatility index (PI) of the central retinal artery (CRA) with Color Doppler imaging. The points to be stimulated were the Waiqiu (GB36), GB37, the Yangfu (GB38) or the non-meridian point on the outside of the crus. Acupuncture stimulus was applied to one point on the right side with a needle for 15min. Seven measurements were made at intervals of 7.5min during a 45-minute period while the subject (control group n=35, stimulus group n=89) was in the sitting position. Patterns of the change in blood-flow velocity and PI with time differed significantly between the five groups. An increase in retinal blood-flow volume occurred in the GB37 group only suggesting there was a peculiarity related to the meridian point. The reaction patterns of the right and left eyes were not significantly different. Blood pressure and heart rate exhibited no significant differences either. These results suggest the relevance of choosing GB37 for improving or maintaining the retinal blood-flow volume.
2 0 0 0 OA 沈約『宋書』謝靈運傳について
- 著者
- 森野,繁夫
- 出版者
- 広島大学文学部中国中世文学研究会
- 雑誌
- 中国中世文学研究
- 巻号頁・発行日
- no.55, 2009-03-27
2 0 0 0 OA 上肢および上胴に着目したテニスサーブにおける回転の打ち分け
- 著者
- 村田 宗紀 藤井 範久
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.413-430, 2014 (Released:2014-12-20)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 9 4
The purpose of this study was to investigate the relationship between motion and ball spin in tennis serves. Ten male university tennis players participated. The three-dimensional coordinates of the players performing flat, kick and slice serves were collected using a motion capture system with 8 cameras (250 Hz). Similarly, the three-dimensional coordinates of reflective markers on the ball were also collected (500 Hz). The primary variables computed were: racquet face velocity and direction at impact, velocity and angular velocity of the ball after impact, hitting point, angles of the upper limb joints, and segment angles of the upper trunk. The differences in racquet face velocity among flat, kick, and slice serves were divided into the following terms: 1) ΔVposture: A difference in velocity resulting from a change in upper trunk posture, 2) ΔVswing: A difference in velocity resulting from a change in arm swing (kinematics of the upper limb), 3) ΔVutrk: A difference in velocity resulting from a change in upper trunk translational and rotational motion. Repeated measures ANOVA (p<0.05) with Bonferroni multiple comparison was used to evaluate the effects of changes in form (with differences in ball spin) on each parameter. The findings are summarized as follows.1) The impact point and swing direction were mainly controlled not by a change in arm swing motion, but by a change in upper body posture.2) To generate ball spin, it is necessary to avoid a head-on collision between the ball and the racquet (a normal vector of the racquet face is parallel to the racquet face velocity vector). Therefore, players decreased the amount of upper trunk leftward rotation in kick and slice serves at the point of impact so as to swing the racquet more laterally.3) It is necessary to swing the racquet more vertically in order to lean the rotation axis of the ball. Therefore, players controlled the upper trunk leftward-rightward and forward-backward leaning in a kick serve at the point of impact.4) Changes in upper body posture cause changes in the direction the racquet faces. Therefore, players mainly controlled their elbow pronation-supination angle in order to maintain a racquet face direction that satisfies a legal serve.
2 0 0 0 OA 新しいゴキブリ忌避効力評価法および天然精油のチャバネゴキブリに対する忌避性
- 著者
- 稲塚 新一
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.133-143, 1982-05-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4 4
チャバネゴキブリに対する嗅覚的忌避性を評価しうる新しい方法として, 試験管法とビーカー法の2法を考案した. 試験管法は, チャバネゴキブリの排泄物の付着した汚染濾紙を誘引源に利用し, 試験管中で供試化合物を処理したペーパーディスクに対するゴキブリの忌避反応の有無により検定する方法である. ビーカー法は供試化合物を含む試料を処理し, ビーカー中のゴキブリ数の変動により, 空間的な侵入防止効果および追い出し効果の有無を検定する方法である. これらの方法を用いて, 公知のゴキブリ忌避物質および天然精油の嗅覚的忌避性について検討した.α-naphthoquinone, 2, 3, 4, 5-bis (Δ2-butenylene) tetrahydrofurfral, 2-hydroxyethyl-n-octylsulfide および naphthalene の公知の忌避物質は, 試験管法では, 低濃度で忌避効果を示したが, ビーカー法では2-hydroxyethyl-n-octylsulfide が弱い忌避効果を示したのみで, 他の化合物には有効な忌避性が認められなかった.一方, 天然精油では, Japanese mint oil および spearmint oil (native type と Scotch type) が顕著な嗅覚的忌避効果を示した. また, 蚊に対し強い忌避性を有すると報告されている citronella oil などの天然精油には強いゴキブリ忌避性が認められなかった. calamus oil など数種の天然精油に性別による忌避性の差異が認められた.
2 0 0 0 OA 日本画の水簸絵具とその美術教育における活用法に関する考察
- 著者
- 早川 陽 Yo Hayakawa
- 雑誌
- 學苑 = GAKUEN (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- vol.896, pp.2-18, 2015-06-01
In the field of Japanese art education, the pigments employed in traditional Japanese paintings are rarely used, though using them in an educational context could be very valuable in imparting an understanding of Bijutsu Bunka(art culture)currently required in curriculum guidelines. In an attempt to explore how they can be adopted in today's art education, this paper explores two Japanese traditional painting technique books from the Taisho Period and highlights the common characteristics of the pigments described in the books and compares them with pigments that have survived from those times, or have been more recently developed for use in traditional-style paintings. The origins of various Japanese pigments are organized in such a way that they can be used as educational material. In order to provide background for this research, the first chapter considers how Japanese traditional paintings are created, displayed and enjoyed today. Also the significance of Bijutsu Bunka, which was newly specified in curriculum guidelines, is discussed. The second chapter, focusing on the refinement and elutriation of pigments used in Japanese traditional paintings, categorizes and organizes the features of the pigments used. The third chapter refers to the above two books and considers the changes made since then in the types of the pigment. The final chapter summarizes the characteristics of the pigments and gives a general view of how they were traditionally used and concludes that the pigments, many of which have been refined by elutriation, can be utilized effectively in the field of art education today. The author believes that intercourse between the past and present, and understanding and appreciating traditional art, offer new possibilities in the future of art education.
- 著者
- 坂尾 晃司
- 出版者
- プロジェクトマネジメント学会
- 雑誌
- プロジェクトマネジメント学会研究発表大会予稿集 2010年度春季
- 巻号頁・発行日
- pp.19-33, 2010-03-11 (Released:2017-06-08)
2 0 0 0 IR 日本の公立ろう学校教員の労働負荷から見た日本手話受容の問題
- 著者
- 加藤 晃生
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 応用社会学研究 (ISSN:03876756)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.53-64, 2010-03-25
2 0 0 0 鴎外・森林太郎のキャリアへの一考察
- 著者
- 谷光 太郎
- 出版者
- 大阪成蹊大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:13489208)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.27-60, 2005
鴎外森林太郎の(1)軍医としての官界生活には、青春時の海外留学、日清・日露両戦役への出陣、軍医界での昇進、左遷、同期生上役との軋轢、斯界大ボスから受け続けた冷遇に屈ぜずの精進、といったいつの時代にもある宮仕えの哀歓があった。(2)家庭生活では、権門家子女との初婚の破綻、二度目の妻と母との尋常ならざる不和、先妻が産んだ嫡男と後妻との対立等、困惑の多いものだった。(3)文人としての鴎外の経歴には汗牛充棟の研究書がある。鴎外のキャリアを論ずるにはこの(1)、(2)、(3)からの分析が必要であるが、紀要としての紙数の制限もあり、本論文は(1)に限るものとした。キャリア・デベロップメントや、キャリア・デザインに関心のある諸賢のご高覧を得れば幸である。