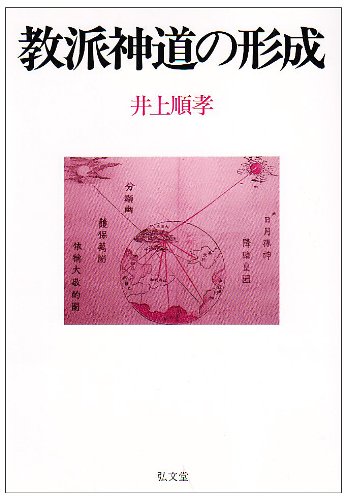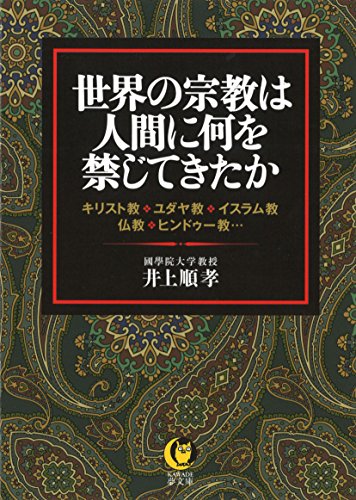12 0 0 0 OA <新新宗教>概念の学術的有効性について
- 著者
- 井上 順孝
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.3-24, 1997-06-14 (Released:2017-07-18)
- 被引用文献数
- 1
新新宗教という用語は広く用いられるようになったが、学術的概念としては、問題点も少なくない。とくに1970年代以降に「台頭した」新宗教をすべて新新宗教に含める議論が、とくに問題である。新新宗教論は、新宗教の変化を社会変化との対応においてみる視点から出てきた議論であり、その重要性は十分理解できるが、それだけに緻密な理論構成が求められる。新新宗教という概念は、かなり幅広い意味で用いられているのが現状であるので、まずこの概念が提起された経緯、及び主な使用法について整理を試みる。そして、この概念にどの程度必然性があったかを考察する。最後に、新新宗教といった概念を提起するならば、その前提としてどのような研究が蓄積されていなければならないかについて私見を述べる。とくに、1970年代以降の社会変化とは何か、運動の個性、発展段階という問題、外来の新宗教と日本の新宗教についての比較の視点の必要性について触れる。
10 0 0 0 OA がん患者に対する自主トレ指導のポイントと注意点
- 著者
- 井上 順一朗
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.421-426, 2022-12-20 (Released:2022-12-20)
- 参考文献数
- 20
6 0 0 0 OA がん領域のリハビリテーション医療のエビデンスと今後の課題
- 著者
- 井上 順一朗 酒井 良忠
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.35-40, 2022-12-26 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 33
がん患者では,がんそのものやがん治療に伴う有害事象や合併症により,体力低下や身体的・精神的な機能障害が生じ,日常生活動作(ADL)や生活の質(QOL)が低下してしまうリスクが高い.そのため,がん種や病巣部位,進行度を考慮したリハビリテーション治療や,がん治療後に生じることが予測される合併症や機能障害を治療開始前から予防するリハビリテーション治療を行うことが重要となる.また,がんの進行に伴い機能障害の増悪や二次障害が生じるため,それらへの適切な対応も必要となる.近年,がん領域のリハビリテーション医療においては,身体的・精神的な機能障害の改善だけでなく自宅療養や社会復帰支援,治療と就労の両立支援などの社会的な側面をも考慮したがん患者のライフステージに応じたサポートを行うことが求められている.これらのリハビリテーション治療やケアを行う際には医学的エビデンスに基づいたアプローチが必要である.
4 0 0 0 現代日本における教団の総合調査
- 著者
- 田丸 徳善 石井 研士 後藤 光一郎 孝本 貢 井上 順孝 柳川 啓一 島薗 進 浜田 哲也 金井 新二 ヤン スインゲドー 西山 茂 藤井 健志 林 淳
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 総合研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 1986
昭和61年度と昭和62年度の二年間にわたり, 現代日本における教団の総合調査を行った. 対象教団は, 神社神道, 仏教教団(浄土真宗本願寺派, 日蓮宗, 臨済宗妙心寺派, 曹洞宗, 真言宗智山派), キリスト教(日本キリスト教団, カトリック)および新宗教教団(金光教, 天理教等)である. これらに関してはできる限り統計処理の可能な資料を収拾し統計分析を行った. これに関しては報告書に掲載されている. また, 地域における教団組織と教勢を把握するために, 銀座と大阪梅田を選び, 都市化の問題をも含めた総合調査を行った. 神社神道は, 既成教団として, 変動がないように考えられてきたが, 内容は大きく変化しているように思われる. とくに都市化が神社神道に及ぼした影響はとくに顕著である. 仏教教団に関しても, 都市と農村の寺院の格差は著しく, 根底から寺院の質を変えようとしている. 都市化が都市と農村の寺院の経済的基盤に変化を与えており, そのことが寺院の世襲化を生む土壌となっている. キリスト教団は, これらに対して比較的変動のない歴史を送っている. そのことは同時に大規模な発展のなかったことをも意味している. 新宗教教団は, 通常の認識では最も変化の激しく, 現代社会に適応した形態をとっていると考えられるが, 実質的にはかなりの程度既成化が進み, 社会的認識との間にはずれがある. この点に関しては, 新宗教教団の詳細な歴史年表を作成することによって, 新宗教教団の歴史的経緯も考察した. 地域研究では, 都市化の顕著な銀座と大阪梅田の比較調査を行うことによって, 各宗教教団の組織的問題を考察した. また, 各教団の製作しているビデオテープを収拾し, 映像に関する考察をも取り入れた.
- 著者
- 井上 順一朗 牧浦 大祐 斎藤 貴 秋末 敏宏 酒井 良忠
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.155-161, 2022 (Released:2022-04-20)
- 参考文献数
- 27
【目的】筋筋膜性疼痛症候群を生じた進行性卵巣癌患者に対して,運動療法と経皮的電気刺激治療の併用により疼痛の緩和,オピオイド鎮痛薬使用量の減量,身体活動・身体機能・QOL の改善を認めた症例を経験したので報告する。【症例紹介】卵巣癌術後再発,肝転移,遠隔リンパ節転移,腹膜播種を有する40代の女性であった。再発・転移に対する化学療法中より頸部から殿部にかけて筋筋膜性疼痛症候群を認めた。【治療プログラムと経過】頸部から殿部にかけての筋筋膜性疼痛症候群に対して,運動療法に加え,疼痛部位に対する経皮的電気刺激治療を施行した。【結果】疼痛は理学療法開始後より経時的に緩和した。疼痛緩和に伴いオピオイド鎮痛薬使用量も経時的に減量した。また,身体活動,身体機能,QOL にも改善が認められた。【結論】運動療法と経皮的電気刺激治療の併用は,がん患者の筋筋膜性疼痛症候群に対する治療・サポーティブケアのひとつとなる可能性が示唆された。
2 0 0 0 食道癌患者における倦怠感と心理状態およびQOLに関する検討
- 著者
- 本山 美由紀 小野 玲 井上 順一朗 牧浦 大祐 三輪 雅彦 黒坂 昌弘 宇佐美 眞 黒田 大介
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.711-715, 2010
〔目的〕本研究の目的は食道癌患者の術前と退院時における倦怠感,心理状態,QOLの変化について検討し,さらに倦怠感と心理状態およびQOLの相互関係について検討することである。〔対象〕食道再建術を施行した食道癌患者20名。〔方法〕倦怠感,心理状態(抑うつ,自覚ストレス),QOLについて質問紙を用いて評価した。術前と退院時の比較についてpaired t testを用い,倦怠感と心理状態およびQOLとの相互関係についてはPearsonの積率相関係数を用いて検定した。〔結果〕倦怠感は術前から退院時かけて強くなっていた。抑うつ,ストレス,QOLに関しては術前から退院時まで有意な変化が認められなかった。相互関係については,倦怠感と自覚ストレス,倦怠感とQOLに相関関係が認められた。〔結語〕倦怠感,心理状態,QOLを評価することは,患者の状況を十分に把握し,心理面に配慮したリハビリテーションを実施する上で重要であると考えられる。<br>
1 0 0 0 OA 術前の消化器がん患者における睡眠障害と筋肉量低下の関連
- 著者
- 奥村 真帆 福田 章真 斎藤 貴 牧浦 大祐 井上 順一朗 酒井 良忠 小野 玲
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1453, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】がん患者における術前の筋肉量低下は,術後の合併症や,生存率に影響を及ぼすと報告されている。近年,一般高齢者において筋肉量低下に関連する因子の一つに睡眠障害が注目されている。がん患者は高い確率で睡眠障害を発症するため,睡眠障害が筋肉量低下に関連していることが予測されるが,現段階ではこれらの関連は明らかとなっていない。本研究の目的は,術前の消化器がん患者における睡眠障害と筋肉量低下との関連性を調査することである。【方法】本研究の解析対象は,2016年6月から2016年9月の間に手術施行予定の患者の中で,術前に評価可能であった胃がん,食道がん,大腸がん患者40名(年齢70.5±7.5,男性31名)とした。筋肉量低下の診断は,Asian Working Group for Sarcopeniaの基準に従い,男性:骨格筋量指標<7.0kg/m2,女性:骨格筋量指標<5.7kg/m2から診断した。筋肉量の測定には,インピーダンス測定機器Inbody430(バイオスペース社製)を用いた。睡眠障害の評価には,日本語版Pittsburgh Sleep Quality Index(PSQI)を用いた。睡眠の質,入眠時間,睡眠時間,睡眠効率,睡眠困難,眠剤の使用,日中覚醒困難の7つの各項目を0-3点の4段階に分類した。また,PSQIの各項目の総合得点が6点以上を睡眠障害有とした。その他に,年齢,性別,身長,体重,教育歴,同居人の有無,CRP,アルブミン,ヘモグロビン,performance status,がん種,合併症(Carlson Comorbidity Index),喫煙,飲酒,clinical stage,身体活動量(International Physical Activity Questionnaire),認知機能(Mini-Mental State Examination),抑うつ(Geriatric Depression Scale短縮版),栄養状態(Mini Nutritional Assessment-Short Form)を測定した。筋肉量(低下群vs.維持群)の比較は,Fisherの正確確率検定,t検定,Mann-Whitney U検定を用いた。PSQIに関しては,各下位項目と睡眠障害の有無のそれぞれについて検討した。p値が0.1未満であった項目を独立変数とし,筋肉量を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った。すべての検定において,有意水準は5%未満とした。【結果】対象者の12名(30%)が筋肉量低下群であった。筋肉量低下群は,筋肉量維持群と比較して,体重が軽く(51.79±7.44kg vs. 65.60±9.83kg,p<0.05),入眠時間が長かった(p=0.03)。体重,入眠時間に加え,単変量解析にてp<0.1であった栄養状態を投入し,多重ロジスティック回帰分析を行った結果,体重(オッズ比0.79,95%信頼区間0.68-0.93)と入眠時間(3.23,1.08-9.68)が術前の筋肉量低下に関連していた。【結論】本研究では,睡眠障害のうち入眠時間が,消化器がん患者における術前の筋肉量低下と関連していることが示唆された。術前に入眠時間を評価・管理することが,筋肉量低下の進行を予防する可能性がある。今後は,睡眠障害と筋肉量低下の因果関係について検討する必要があると考える。
- 著者
- 松本 雄宇 岩崎 優 細川 恵 鈴木 司 井上 順 重村 泰毅 高野 克己 山本 祐司
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- pp.NSKKK-D-22-00090, (Released:2023-02-17)
腎臓病患者の治療食として使用されている低タンパク米の製造工程で生じるERPの脂質代謝改善効果を検討した. 高脂肪食を与えた肥満モデルマウスにERPを摂取させたところ, 体重および精巣周囲脂肪重量の増加が抑制された. また, ERP摂取により糞中TG量が増加した. さらに, 血中ALT活性と肝臓中脂質量の結果から, ERP摂取は高脂肪食に起因する肝障害を抑制することが示された. 興味深いことに, ERP摂取によりインスリン抵抗性に関連するCerS6の発現量低下も観察された. ERPは主にペプチドと遊離アミノ酸から構成されていること, また一部の血中遊離アミノ酸濃度と精巣周囲脂肪重量との間に負の相関関係が認められたことから, 本研究で観察された効果はペプチドと遊離アミノ酸のどちらかないし両方を介していると考えられる. これらの結果から, ERPは抗肥満食品として有用な素材であることが示唆された.
1 0 0 0 OA グローバル化・情報化時代における宗教教育の新しい認知フレーム(<特集>宗教の教育と伝承)
- 著者
- 井上 順孝
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.2, pp.347-373, 2011-09-30
一九九〇年代に急速に進行したグローバル化・情報化と呼ばれる社会変化は、宗教教育に関する従来の議論に介在していると考えられる認知フレームに加え、新しい認知フレームを導入することを要請している。日本における宗教教育についての戦後の議論は、宗教知識教育、宗教情操教育、宗派教育という三区分を前提とするものが多い。このうち宗教情操教育が公立学校において可能かどうかをめぐる議論が大きな対立点となってきた。その理由には、近代日本の宗教史の独自の展開が関わっている。しかし、近年は国際理解教育の一環としての宗教に関する教育、多元的価値観の共存を前提とした宗教教育、そして宗教文化教育などと、新しい認知フレームに基づくとみなせる研究が増えてきている。これは、宗教教育に関する規範的視点とは別に、全体社会の変化に対応して形成されたものであり、従来の多くの議論とは異なる新しいフレームが加わった結果であると考える。
- 著者
- 斎藤 貴 杉本 大貴 中村 凌 村田 峻輔 小野 玲 岡村 篤夫 井上 順一朗 牧浦 大祐 土井 久容 向原 徹 松岡 広 薬師神 公和 澤 龍一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, 2016
【はじめに,目的】近年がん医療においては疾病の早期発見,治療法の発展により生存率が向上している一方で,治療による副作用が問題視されている。化学療法の副作用の1つに化学療法誘発性末梢神経障害(chemotherapy-induced peripheral neuropathy,以下,CIPN)があり,その好発部位から「手袋・靴下型」と称されている。リハビリテーション実施場面においても,化学療法実施中の患者にはしばしば見られる症状である。CIPNは多様な感覚器の障害様式を呈するが,その評価は医療者による主観的な評価が中心であり,どのような感覚器の障害様式なのかはについて詳細な評価はなされていない。本研究の目的は感覚検査の客観的評価ツール用い,CIPNを縦断的に調査し,その障害様式を明らかにすることである。【方法】本研究は前向きコホート研究であり,任意の化学療法実施日をベースラインとし,フォローアップ期間は3ヶ月とした。本研究の対象者は,2015年2月から7月までの期間内に,神戸大学医学部附属病院の通院治療室にて,副作用としてCIPNが出現する化学療法を受けているがん患者35名であり,脊椎疾患を有する者,フォロー不可能であった者,欠損値があった者を除く18名(63.7±11.3歳,女性11名)を解析対象者とした。CIPNの評価は下肢末端を評価部位とし,客観的評価として触覚検査,振動覚検査,主観的評価としてしびれについて検査を行った。触覚検査はモノフィラメント知覚テスターを用い,母趾指腹,母趾球,踵部,足首の四カ所の触覚を測定し,測定方法にはup and down methodを用いた。振動覚検査は音叉を用い,内果の振動覚を測定し,測定方法はtimed methodを用いた。しびれの主観的検査はVisual Analog Scale(以下,VAS)を用い前足部,足底部,足首の三カ所の主観的なしびれを評価した。測定はベースライン,フォローアップ時ともに化学療法実施日に行い,薬剤の投与前に上記評価を完了した。統計解析は対応のあるt検定およびWilcoxonの符号付順位検定を用い,それぞれの評価項目におけるベースライン時からフォローアップ時の値の変化を検討した。【結果】触覚検査では踵部のみに有意な変化がみられ,フォローアップ後に有意に触覚が低下していた(<i>p</i><0.01)。振動覚検査においてはフォロー後に有意に増悪がみられた(<i>p</i><0.01)。下肢末端のしびれの主観的検査においては前足部,足底部,足首部ともにフォロー後に有意差は見られなかった。【結論】三ヶ月のフォローアップ調査により,CIPNの障害様式は主に踵部の触覚低下および振動覚の低下であることが明らかとなった。一方で,主観的なしびれは変化がなく,客観的評価ツールで足底した触覚や振動覚の方が鋭敏に神経障害を反映しており,患者が障害を認知する前から感覚障害が生じていることが示唆された。
1 0 0 0 OA 宗教研究は脳科学・認知科学の展開にどう向かいあうか
- 著者
- 井上 順孝
- 出版者
- 宗教哲学会
- 雑誌
- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.28-46, 2018-03-31 (Released:2018-05-11)
Neuroscience and cognitive science have undergone explosive advances since the 1990s, the effects of which have even been felt on religious studies. I will explore here what new perspectives these developments might generate by looking at two specific issues. The first is that of what concepts of kami (deity), imi (taboo) and kegare (pollution) exist in modern Shinto. The second is connected to research concerning the debate over the nature of the founders of new religions and the process by which people adopt those faiths. The question of what is distinctive about the kami concept in Shinto can be seen as part of the broader question of what leads the human mind to conceive of gods and deities in the first place. Similarly, such common Shinto ideas as imi and kegare come under the broader topic of why humans establish taboos for certain acts and behaviors. While discussing prior research, I also stress the need to study these new perspectives. Max Weber’s theory of charisma is widely used in discussions regarding the founders of new religions, but I believe that the phenomenon of people becoming entranced with a certain person can be examined from a broader perspective that incorporates neuroscience. The same may be said for the conversion process.
1 0 0 0 「探す」ことのデザイン:情報探索のためのインタフェースデザイン
- 著者
- 井上 順子 小山内 靖美
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.211, 2006
現在インターネットや携帯電話等における情報検索サービスが発展し、誰もが必要な情報を入手できるような基盤が整ってきている。探すことのデザインには、大別すると2種類のタイプがある。あらかじめ目的がはっきりしている「検索」と目的が曖昧もしくは無い「探索」である。ネットワーク上の情報を活用するためには、「探索」を目的とした情報空間のデザインの必要性が高まると考えられる。本研究では、Webサイトでの情報探索のかたちを発想する手がかりとして、人が日常空間で情報を探す活動を調査した。その活動から情報探索サービスの提案を行った。日常空間における情報探索の調査、インタフェースのデザインプロセスについて報告する。
1 0 0 0 世界の宗教は人間に何を禁じてきたか
- 著者
- 井上順孝著 夢の設計社企画・編集
- 出版者
- 河出書房新社
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 インフォグラフィックスデザインの教育実践(3)
- 著者
- 井上 順子 平野 北斗 豊嶋 哲志
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.62, 2015
本研究では、インフォメーショングラフィックス表現の拡張性として、情報の立体化、立体表現の可能性について報告する。 インフォメーショングラフィックスは、情報を効果的・魅力的に伝える手法として注目が高まっている。見る人に印象強さや関心を与える力を持つことから、簡素で明快かつ魅力的な表現が模索されている。モーショングラフィックスに加え、最近では情報を立体的に表現しようとする傾向も見られる。 オマーンの新聞社「Times of Oman」が制作した「ON THE BALL, An in-depth look at the 32 national teams」では、情報を立体模型に再構成するアイデアを適用している。この事例は、インフォグラフィックスにおける立体的表現の可能性を確認できる好例である。インフォメーショングラフィックスの新たな視覚体験を提供できるアプローチとして、情報の立体化に着目し「情報に触れる体験」が理解とコミュニケーションを向上させる可能性について探求した。その結果、情報を立体化することで見る人の意欲的・知的欲求を引き出す特性を指摘することができた。
- 著者
- 井上 順孝
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.139-140, 2016-06-11 (Released:2018-07-20)
1 0 0 0 新宗教事典
- 著者
- 井上順孝 [ほか] 編
- 出版者
- 弘文堂
- 巻号頁・発行日
- 1990
- 著者
- 井上 順子
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史學 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.1, pp.51-75, 2015-07
文学部創設125年記念号(第2分冊)論文 東洋史