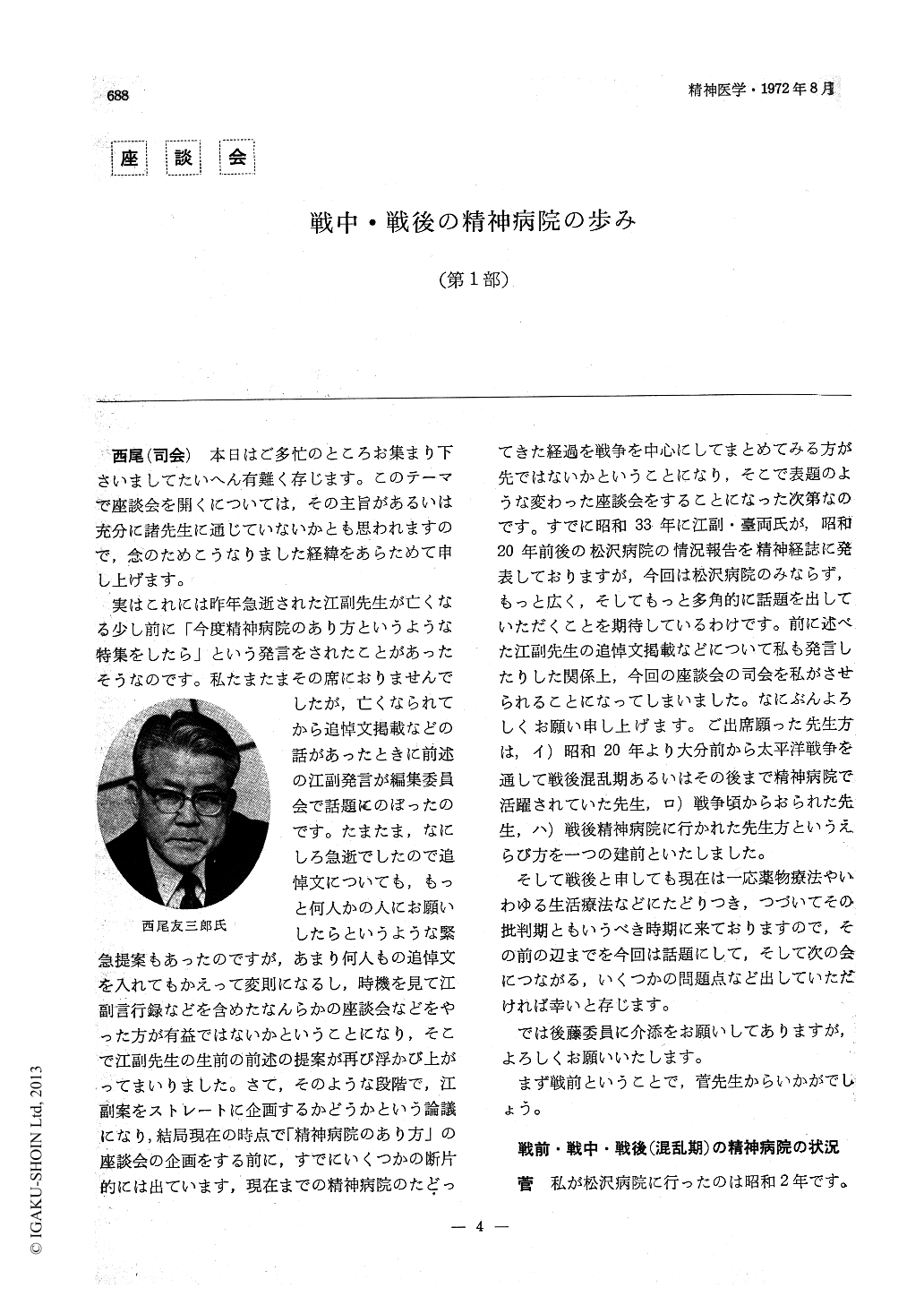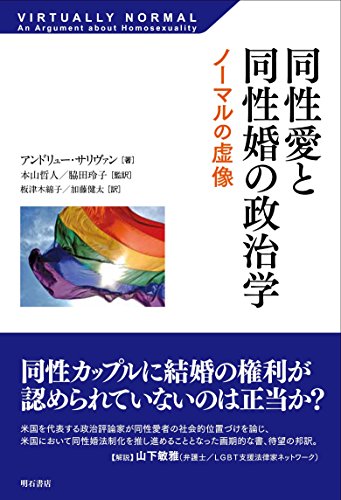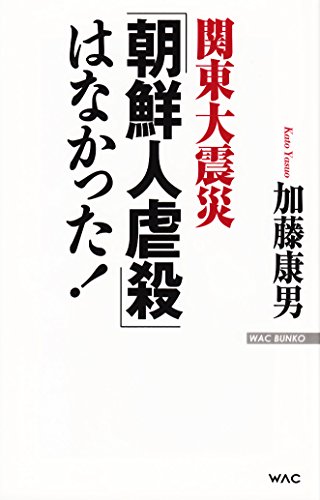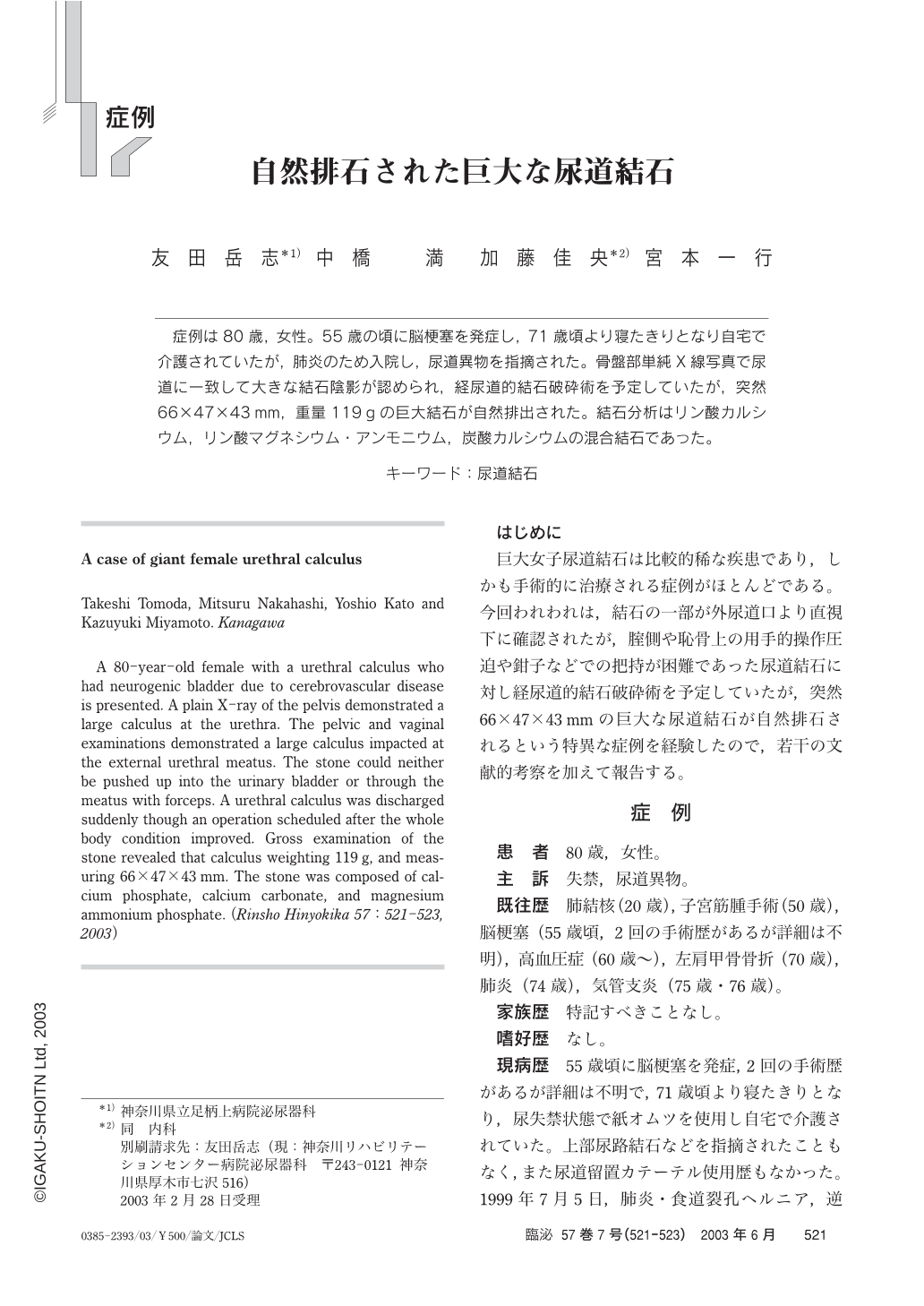6 0 0 0 OA 地域在住前期高齢者に対する運動プログラムの転倒予防に焦点をあてた費用対効果分析
- 著者
- 加藤 剛平 倉地 洋輔
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11734, (Released:2020-08-04)
- 参考文献数
- 45
【目的】本邦における健常な地域在住前期高齢者に対する運動プログラムによる転倒予防の費用対効果を明らかにした。【方法】公的医療・介護の立場から分析した。質調整生存年数(Quality Adjusted Life Years:以下,QALY)を効果,医療費と介護費を費用に設定した。マルコフモデルを構築して,65 歳の女性と男性の各1,000 名を対象に当該プログラムを実施した条件における10 年後の増分費用対効果比(Incremental Cost-Eff ective Ratio:以下,ICER)を シミュレーション分析した。費用対効果が良好とするICER の閾値は5,000,000 円/QALY 未満とした。【結果】女性,男性集団のICER は順に1,550,900 円/QALY,2,277,086 円/QALY であった。【結論】本邦において,当該プログラムの費用対効果は良好である可能性が高いことが示唆された。
6 0 0 0 OA 希少種ユメユムシ(環形動物門:ユムシ綱:ミドリユムシ科)の四国からの初記録
- 著者
- 後藤 龍太郎 邉見 由美 Jonel Mangente Corral 塩﨑 祐斗 加藤 哲哉 伊谷 行
- 出版者
- 日本ベントス学会
- 雑誌
- 日本ベントス学会誌 (ISSN:1345112X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.79-82, 2018-03-31 (Released:2018-04-19)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
Ikedosoma elegans (Ikeda, 1904) (Annelida: Echiura: Thalassematidae) is a rare, large deep-burrowing spoon worm that has been observed only in Japan. This species was first described based on the specimens collected from Misaki, Sagami Bay (Kanagawa Prefecture), eastern Japan, in 1902. Since the first description, this species has not been collected until the recent studies, which reported that I. elegans was collected from Hamana Lake (Shizuoka Prefecture), Boso Peninsula (Chiba Prefecture), and probably Amakusa, Ariake Sea (Kumamoto Prefecture). Furthermore, the specimen collected from Takasu, Seto Inland Sea (Okayama Prefecture) in 1975 was identified to be I. elegans. In this study, we present a new locality of this species in Japan. We collected a large individual of I. elegans with a probably commensal scale worm (Polynoidae: Polynoinae) by using a yabby pump in a mud flat in the Doki River Estuary, which is facing the Seto Inland Sea, in Marugame (Kagawa Prefecture), northern Shikoku Island. To the best of our knowledge, the present study is the first record of I. elegans from Shikoku Island and the second record from the Seto Inland Sea, following a 42-year-old record from Takasu, Okayama.
- 著者
- 上田 拓 山谷 里奈 尾形 良彦 加藤 愛太郎
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
On June 18, 2019, a Mj6.7 earthquake occurred at Yamagata-oki. The source region of this earthquake is adjacent to that of the Mj7.5 earthquake which occurred on June 16, 1964, and in this region, there are few aftershocks right after the 1964 earthquake, and the seismicity rate in recent years is extremely low (Earthquake Research Committee, 2019). This observation suggests that the source region of the 2019 Yamagata-oki earthquake was not ruptured by the Niigata earthquake, but the cause has not been revealed. In order to elucidate the relationship between these two areas, this study compared the characteristics of seismicity between the two areas.We used the JMA catalog constructed by Japan Meteorological Agency (the Preliminary Determination of Epicenters). We applied HIST-ETAS (Hierarchical Space Time Epidemic Type Aftershock Sequence) model (e.g., Ogata, 2004) considering the spatial dependence of each parameter of the Space Time ETAS model (e.g., Ogata, 1998), to the hypocenter catalog (M1.8) from 1998 through 2019 in order to estimate the spatial distribution of background seismicity rate μand number of aftershock occurrences K. As a result, we find that μ-value is higher and K-value is lower in the source region of Yamagata-oki earthquake than in that of Niigata earthquake.In addition to these differences, we find that the b-value, which is one of the characteristics of the seismicity, is lower in the source region of Yamagata-oki earthquake than in that of Niigata earthquake. Moreover, comparing the seismic wave velocity structure obtained by Matsubara et al. (2019), the P wave velocity is lower in the source region of Yamagata-oki earthquake than in that of Niigata earthquake.The difference in seismic wave velocity and characteristics of seismicity between these two areas suggests that the macroscopic behavior in the source region of Yamagata-oki earthquake is more ductile than in that of Niigata earthquake. In more ductile area, microfracture is likely to proceed and it decreases seismic wave velocity. In addition, background seismicity rate (μ) decreases in more ductile area because of low brittleness. Moreover, the results of rock experiments and numerical simulation by Amitrano (2003) imply the increase in aftershock productivity (K) and the decrease in b-value in more ductile area. Focusing on the short-wavelength component of the linear strain rate distribution in the east-west direction (Meneses-Gutierrez and Sagiya , 2016), the different response for the 2011 off the pacific coast of Tohoku earthquake between the source regions of Yamagata-oki earthquake and Niigata earthquake is appeared. These differences may reflect different deformation styles between the two regions.
6 0 0 0 OA 地震波干渉法によるマントル不連続面での反射P波検出に向けて
- 著者
- 加藤 翔太 西田 究
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
地震波干渉法は2観測点で観測された地震波形記録の相互相関関数を計算することにより、片方を仮想的な震源とし、もう片方を観測点とした場合の観測波形を推定する手法である(e.g. Snieder et al., 2013)。地震波干渉法解析では、地震波動場がランダムかつその強度分布が等方・均質であることを仮定する。ランダムな波動場として海洋波浪起源の脈動を解析に用いる場合には、周期5-20 sの帯域で表面波が卓越することが知られている。そのため、脈動を用いた地震波干渉法は地殻・上部マントルの3次元構造の推定に適している(e.g. Shapiro et al., 2005)。近年では、表面波だけではなく実体波の抽出が試みられている。その一例として、マントルの410/660 km不連続面からの反射P波の抽出が報告されている(Poli et al., 2012, Feng et al., 2013)。しかし、これらの反射P波を抽出した先行研究の対象地域は大陸に限られていた。本研究の目的は、防災科学技術研究所Hi-netの上下動記録に地震波干渉法を適用することにより深さ410/660 km不連続面からの反射P波を抽出し、日本列島下の不連続面をイメージングすることである。本研究では以下の手順で各観測点ペアに対する相互相関関数を計算した。用いた波形記録は防災科学技術研究所Hi-net観測点のうち西南日本に存在する240点の上下動記録(2007年-2018年)である。まず、Hi-netの上下動記録を2 Hzにダウンサンプリングした。その上で各観測点について翌日の観測波形との差を計算して元の観測波形の代わりに用いた(高木ほか、2019)。これは、Hi-netの機器ノイズ(Takagi et al., 2015)の相互相関関数への影響を抑えるためである。次に、得られた1日長の波形を1024 sの時間窓に分割し、周期5-10 sおよび10-20 sの平均2乗振幅によって時間窓を選択した。選択した時間窓について周波数領域で白色化を行い、周期1-10 sの成分について全観測点ペアの相互相関関数を計算した。まず4-th root vespagramを全観測点ペアに対する相互相関関数について計算した(Rost and Thomas 2002)。その結果、410 km不連続面の反射P波がオフセット距離0-300 kmで見られ、660 km不連続面の反射P波はオフセット距離50-100 kmで見られた。また、660 km不連続面の反射P波は410 km不連続面の反射P波に比べて弱いことがわかった。次に、得られた反射P波を不連続面の深度に変換するため、Common Middle Point (CMP)重合を行った(e.g. Stein and Wysession, 2003)。具体的には、オフセット距離が500 km以内の各観測点ペアについて反射点の位置でグループ分けを行い、各グループに対して不連続面が水平と仮定しCMP重合を行った。速度構造はJMA2001(上野ほか、2002)を用い、深度推定は410 km不連続面についてのみ行った。その結果、地域ごとに410 km不連続面深度の変動が見られ、特に東経134°-135°北緯33°-36°に反射点を持つグループでは不連続面が上昇している結果が得られた。これは、従来の地震波を用いた不連続面深度に関する研究(Tonegawa et al., 2005, Tono et al., 2005)と整合的である。本研究では地震波干渉法により西南日本の410 km不連続面深度の推定を行った。今後は用いる観測点を増やして対象領域を日本全国へと拡大するとともに、今回扱わなかった660 km不連続面の推定も行う予定である。謝辞:本研究では防災科学技術研究所のHi-netの上下動記録を用いました。記して感謝いたします。
6 0 0 0 戦中・戦後の精神病院の歩み—第1部
西尾(司会) 本日はご多忙のところお集まり下さいましてたいへん有難く存じます。このテーマで座談会を開くについては,その主旨があるいは充分に諸先生に通じていないかとも思われますので,念のためこうなりました経緯をあらためて申し上げます。 実はこれには昨年急逝された江副先生が亡くなる少し前に「今度精神病院のあり方というような特集をしたら」という発言をされたことがあったそうなのです。私たまたまその席におりませんでしたが,亡くなられてから追悼文掲載などの話があったときに前述の江副発言が編集委員会で話題にのぼったのです。たまたま,なにしろ急逝でしたので追悼文についても,もっと何人かの人にお願いしたらというような緊急提案もあったのですが,あまり何人もの追悼文を入れてもかえって変則になるし,時機を見て江副言行録などを含めたなんらかの座談会などをやった方が有益ではないかということになり,そこで江副先生の生前の前述の提案が再び浮かび上がってまいりました。さて,そのような段階で,江副案をストレートに企画するかどうかという論議になり,結局現在の時点で「精神病院のあり方」の座談会の企画をする前に,すでにいくつかの断片的には出ています,現在までの精神病院のたどってきた経過を戦争を中心にしてまとめてみる方が先ではないかということになり,そこで表題のような変わった座談会をすることになった次第なのです。すでに昭和33年に江副・臺両氏が,昭和20年前後の松沢病院の情況報告を精神経誌に発表しておりますが,今回は松沢病院のみならず,もっと広く,そしてもっと多角的に話題を出していただくことを期待しているわけです。前に述べた江副先生の追悼文掲載などについて私も発言したりした関係上,今回の座談会の司会を私がさせられることになってしまいました。なにぶんよろしくお願い申し上げます。ご出席願った先生方は,イ)昭和20年より大分前から太平洋戦争を通して戦後混乱期あるいはその後まで精神病院で活躍されていた先生,ロ)戦争頃からおられた先生,ハ)戦後精神病院に行かれた先生方というえらび方を一つの建前といたしました。
6 0 0 0 OA 大学生のためのスマートフォン行動嗜癖の自己評価尺度の開発
- 著者
- 風間 眞理 加藤 浩治 板山 稔 川内 健三 藤谷 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- pp.43046, (Released:2020-01-16)
- 参考文献数
- 35
本研究の目的は,スマートフォンの使い方を大学生が自ら評価できるスマートフォン行動嗜癖自己評価尺度を開発することである.首都圏の大学に在籍し,スマートフォンを使用している大学生を対象に,研究者で作成したスマートフォン行動嗜癖自己評価尺度の調査を実施した.探索的因子分析と共分散構造分析,使用時間等との相関を求めた.その結果,有効回答数は587.男子学生243名,女子学生344名であった.探索的因子分析後,5因子20項目となり,各因子名を「自己支配性」,「生活への侵食性」,「離脱症状」,「再燃性」,「非制御な通話」とした.共分散構造分析では,GFI=0.931,AGFI=0.909,CFI=0.932,RMSEA=0.052であった.また,スマートフォン行動嗜癖自己評価尺度総得点と利用時間で有意な相関がみられた.以上より,信頼性と妥当性が示された.
6 0 0 0 OA 日本の軍人は何故強いか 少年に与える訓話(上)
- 著者
- (海軍大将)加藤 寛治(閣下)
- 出版者
- ビクター
- 巻号頁・発行日
- 1936-02
6 0 0 0 OA 豆乳を用いたチーズ様食品の調製とその抗酸化性および特性
- 著者
- 西山 美樹 江崎 秀男 森 久美子 山本 晃司 加藤 丈雄 中村 好志
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.9, pp.480-489, 2013-09-15 (Released:2013-10-31)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
豆乳は栄養価に優れ,イソフラボン類などの機能性成分を含むが,その消費量は多くない.本研究では,豆乳の用途拡大および保健機能性の向上を目指して,豆乳から乳酸発酵豆乳,さらには豆乳チーズを試作するとともに,これらの抗酸化性の評価および主要成分の分析を行った.11菌株の乳酸菌で豆乳を発酵させたところ,9菌株において凝固が認められた.イソフラボン分析の結果,Lactobacillus plantarumおよびLactobacillus casei を用いた乳酸発酵豆乳では,豆乳中のグルコシル配糖体であるダイジンおよびゲニスチンは効率よく分解され,それぞれダイゼインおよびゲニステインを生成した.しかし,いずれの乳酸菌においてもマロニル配糖体は分解されなかった.Lb. casei MAFF 401404を用いた乳酸発酵豆乳は,滑らかなプレーンヨーグルト状に凝固し,官能評価においても高得点を収めた.この発酵豆乳よりカードを調製し,カマンベールチーズカビ(Penicillium camemberti NBRC 32215)およびロックフォールチーズカビ(Penicillium roqueforti NBRC 4622)を用いて豆乳チーズを調製した.いずれのチーズカビを用いた場合も,発酵·熟成にともない,ホルモール態窒素量および旨みを呈するグルタミン酸含量が顕著に増加した.また,官能評価においても高得点を得た.DPPH法による抗酸化試験の結果,豆乳チーズの抗酸化活性も発酵·熟成中に有意に(p<0.01)上昇し,カードの2~3倍に増大した.また,豆乳の乳酸発酵時には残存していたマロニル配糖体も,これらのチーズカビによって分解され,体内吸収性に優れたアグリコンに変換された.これらの結果より,この豆乳を用いたチーズ様食品は,将来,高付加価値をもつ新規食品として受け入れられる可能性が示唆される.
6 0 0 0 同性愛と同性婚の政治学 : ノーマルの虚像
- 著者
- アンドリュー・サリヴァン著 板津木綿子 加藤健太訳
- 出版者
- 明石書店
- 巻号頁・発行日
- 2015
6 0 0 0 関東大震災「朝鮮人虐殺」はなかった!
6 0 0 0 IR コミュニケーションノートの内容分析--ゲームセンターに集う若者像
- 著者
- 加藤 裕康
- 出版者
- 東京経済大学
- 雑誌
- コミュニケーション科学 (ISSN:1340587X)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.143-164, 2004-12-25
- 被引用文献数
- 2
6 0 0 0 OA ロボットアピアランスにおける"萌え"のデザイン検討
- 著者
- 加藤 健太 加納 政芳 山田 晃嗣 中村 剛士
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第30回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.1-4, 2014 (Released:2015-04-01)
解決すべきヒューマン・ロボット・インタラクションの問題の1 つに,ロボットの外観をどのようにデザインするのかという問題が挙げられる.ロボットの外観はインタラクションしているユーザの感情に影響を及ぼすことが先行研究によって示されており,その1 つが,森によって提唱された「不気味の谷」である.この「不気味の谷」に陥るのを回避しつつ好感の持てるロボットをデザインするため,本研究では"萌え"の要素を取り入れることを提案する.しかし"萌え"という概念が曖昧なため,対話型進化計算(Interactive Genetic Algorithm: IGA) を用いた3Dのデザインシステムを構築し,それを用いて"萌え"の概念を調査した.
6 0 0 0 OA 水田における空中散布農薬の大気汚染
- 著者
- 槌田 博 花井 義道 加藤 龍夫
- 雑誌
- 横浜国立大学環境科学研究センター紀要 = Bulletin of the Institute of Environmental Science and Technology, Yokohama National University (ISSN:0286584X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.29-48, 1988-12-27
The paddy field has a large area in Japan land and therefore the aerial splay of pesticides causes serious environmental problems. The authors carried out the experiments concerning mainly air pollution of pesticides. This paper displayed some examples of 12 points in various parts. Atmospheric pollution, Water contamination and falling to the ground were examined. As a result of these experiments, it was found that air pollution in the paddy caused by pesticide is evolved from three sources. i) In the operation of spray, the pesticide vaporizes from mist of spray. ii) Under sunshine, the pesticide sublimes from leaves of rice plants. iii) After the pesticide sublimed or flowed douwn, the Air-Water Henry's Law is effective. That is, the highest atmospheric concentration of pesticides from paddys is larger than that from the forests or fields. And the reduction of concentration on the former is faster than that on the latter. This tendency is explained on the above three reasons.
6 0 0 0 OA キノコバエ幼虫の発光(形態・細胞・遺傳)
6 0 0 0 自然排石された巨大な尿道結石
- 著者
- 友田 岳志 中橋 満 加藤 佳央 宮本 一行
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床泌尿器科 (ISSN:03852393)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.521-523, 2003-06-20
症例は80歳,女性。55歳の頃に脳梗塞を発症し,71歳頃より寝たきりとなり自宅で介護されていたが,肺炎のため入院し,尿道異物を指摘された。骨盤部単純X線写真で尿道に一致して大きな結石陰影が認められ,経尿道的結石破砕術を予定していたが,突然66×47×43mm,重量119gの巨大結石が自然排出された。結石分析はリン酸カルシウム,リン酸マグネシウム・アンモニウム,炭酸カルシウムの混合結石であった。
- 著者
- 加藤 隆之
- 出版者
- 亜細亜大学
- 雑誌
- 亜細亜法學 (ISSN:03886611)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.19-127, 2011-07
6 0 0 0 ターベルコース・イン・マジック
- 著者
- ハーラン・ターベル著 加藤英夫訳
- 出版者
- テンヨー
- 巻号頁・発行日
- 1975
6 0 0 0 レンズ光学の基礎4:光学系の瞳
- 著者
- 加藤 欣也
- 出版者
- 日本眼光学学会
- 雑誌
- 視覚の科学 (ISSN:09168273)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.89-93, 2015
レンズの瞳は開口絞りの像である。レンズおよびレンズ系の入射瞳は物体空間から見た開口絞りの像, 射出瞳は像空間から見た開口絞りの像である。別の言い方をすれば入射瞳, 開口絞り, 射出瞳はそれぞれ共役面である。 顕微鏡対物とリレーレンズを繋ぐ際, 顕微鏡対物の開口絞りとリレーレンズのそれとは共役面でなければならない。顕微鏡対物の射出瞳とリレーレンズの入射瞳が共役面であることが重要である。そうでないと視野周辺の像強度が急激に低下する。解決策は対物とリレーレンズの間にフィールドレンズを挿入することである。同様の理由で撮像素子の瞳とレンズ系の射出瞳を一致させることが望ましい。 瞳の球面収差によって視野周辺に影が生ずる。眼の移動に伴って, 影は視野内を動き回る。瞳の軸上色収差によって視野中心と周辺における色調差が生ずる。眼の移動に伴って, 視野のある部分の色調が変化する。
6 0 0 0 OA 若年者(小児)に発生する甲状腺癌の生物学的特性と遺伝子背景
20歳以下の若年甲状腺乳頭癌 (P-PTC) 81例と21歳以上の成人甲状腺乳頭癌 (A-PTC) 83例について、臨床病理学的に比較検討するとともに、BRAFV600E突然変異とTERT promoter突然変異を解析した。その結果、P-PTCはA-PTCよりも、腫瘍径が大きく、リンパ節転移率が高いことがわかった。一方、BRAFV600E突然変異率は、P-PTCは37%で、A-PTCの82%よりも低く、TERT promoter突然変異はA-PTCでは13%が陽性を示したが、P-PTCでは全例陰性となった。以上より、若年甲状腺癌はその臨床像とともに遺伝子背景も成人とは異なることが示唆された。
6 0 0 0 OA 大規模テキストデータを活用した投資家心理と株価変動の定量的解明
本研究では、ニュースデータ、ブログデータ、SNSなどのソーシャルデータを大規模に収集し、それらがどの銘柄について語っているものなのかを自然言語処理の諸技術を用いてデータベース化した。この結果、全上場企業約3600社それぞれについて、ニュースおよびソーシャルメディアの情報を紐付けていることになる。次に、市場に流れるコメントやニュースについて、ポジティブな文脈で語られているのか、あるいはネガティブなのかについて、評価表現辞書を作成することでスコアリングした。こうして作成した指標をセンチメント指数として時系列で捉え、金融市場における様々なアノマリー現象と、センチメント指数との関連性を明らかにした。