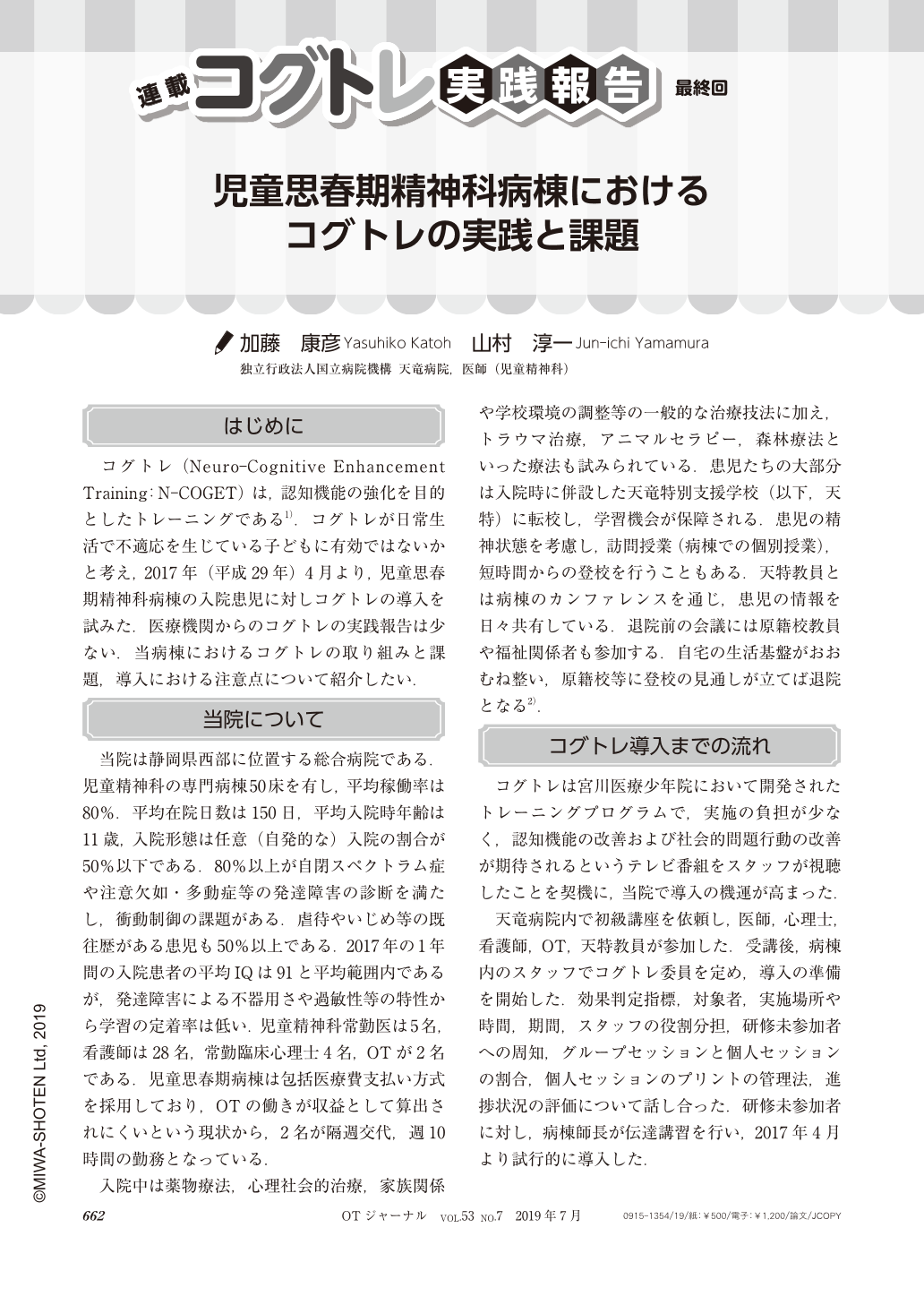5 0 0 0 OA [第30回日本嚥下医学会]軽症嚥下障害例に対する訓練法の検討
- 著者
- 岩田 義弘 長島 圭士郎 服部 忠夫 寺嶋 万成 清水 雅子 木原 彩子 三村 英也 堀部 晴司 岡田 達佳 加藤 久幸 櫻井 一生 内藤 健晴 大山 俊廣 戸田 均
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6Supplement2, pp.S128-S135, 2007-11-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 9
誤嚥はみられないが、嚥下時に咽頭-喉頭に異常感を訴える4名の高齢者に、症状の改善を目的に、訓練を行った。咽頭食道透視にて訓練を行った前後の比較を行った。訓練は対象者に下顎を胸の方向に強く持続牽引してもらい、施術者が頤部に手を固定し用手的に、下顎を短時間伸展するように牽引した。この操作により、2名において造影剤の通過時間の短縮がみられた。またこの訓練により、4例とも安静時の甲状軟骨の位置が高くなった。また軟口蓋の咽頭閉鎖も改善がみられた。簡易な訓練ではあるが、低くなった喉頭の位置の改善とそれによる誤嚥抑制の効果が期待された。
5 0 0 0 OA タイムカプセルに保存した9年前の「思い出」の記憶と変容
- 著者
- 新垣 紀子 北端 美紀 松岡 裕人 高田 敏弘 折戸 朗子 加藤 ゆうこ 都築 幸恵 大和田 龍夫
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.15-28, 2014-03-01 (Released:2015-02-02)
- 参考文献数
- 26
How should we save our personal memories? Many people keep diaries and take pictures for that purpose. In this study, we kept things of personal significance in a time capsule for 9 years and examined whether personal memories could be saved in a time capsule and how they might possibly change over time. We held a workshop in 2003 when participants put something that they had possessed which had personal significance at that time of their life. They were interviewed to explain what kinds of significance these possessions had for them, and these interview sessions were recorded. Nine years after the initial workshop, the participants came together again. Before the time capsule was opened, they were asked to recall what they had put in the time capsule and to describe in what ways their possession in the time capsule had been significant to them. By comparing the contents of the participants’ responses between 2003 and 2012, it was found that a great deal of the contents have been changed from 2003 to 2012. Implications were discussed as regards to the significance of objects themselves and the narratives that go with the objects in preserving personal memories.
5 0 0 0 OA 90年前の超高層RC造
- 著者
- 加藤 博人
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.595, 2015 (Released:2016-07-01)
5 0 0 0 IR 帝国日本の形成と日清・日露戦争における感染症問題
- 著者
- 加藤 淳 後藤 真孝
- 雑誌
- 研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:21888752)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-MUS-138, no.7, pp.1-21, 2023-08-20
音楽に合わせてタイミングよく歌詞が動くリリックビデオは楽曲のプロモーション手段として一般化したが,いつ再生されても同じ内容を提示するため,視聴者は受動的に楽しむしかない.そこで我々は,ユーザとのインタラクションにより歌詞のテキストを再生のたびに異なる方法で提示でき,静的メディアの制約を取り払える歌詞駆動型のインタラクティブな視覚表現を「リリックアプリ」と定義する.そして,この表現形式をプログラマやミュージシャンに開放するため,リリックアプリを開発・配信できる Web ベースのフレームワーク「Lyric App Framework」を提案する.当該フレームワークは,我々が研究・開発・運営してきたリリックビデオ制作支援サービス「TextAlive」の Web インタフェースと,歌詞駆動の表現を開発できる機能をプログラマ向けに開放する「TextAlive App API」で構成される.当 API は,既存の,プログラマが使い慣れたクリエイティブコーディングのためのライブラリと相補的な役割を果たし,インタラクティブなリリックアプリをすぐに開発可能である.我々は,2020 年に当 API を一般公開し,新たな表現形式の可能性を探ってきた.とくに,創作文化に関するイベント「マジカルミライ」ではプログラミング・コンテストが毎年開催され,最初の 2 回で 52 作品が集まった.これらの作品を分析して得られたリリックアプリのカテゴリ 8 種類と,音楽とプログラミングの未来に関する示唆を報告する.
- 著者
- 加藤淳 中野倫靖 後藤真孝
- 雑誌
- 研究報告音楽情報科学(MUS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014-MUS-104, no.15, pp.1-7, 2014-08-18
本稿では、歌詞を歌声と同期してアニメーションさせる Kinetic Typography と呼ばれる動画表現の制作環境 TextAlive を提案する。既存の制作ツールでは、歌詞と歌声の同期を手作業で取り、文字や単語、複数単語から成るフレーズに対して個別に望みの動きを設計する必要があった。その際は、動きを規定するアルゴリズムのパラメタを、スライダーなどの汎用 GUI で調整して試行錯誤を重ねていた。一方、本制作環境では、歌詞と音楽の時間的対応付けを自動で推定し、動きのアルゴリズムに対する初期パラメタを自動生成する。さらに、動きのアルゴリズムを編集できるコードエディタを備え、プログラマがパラメタ調整に適した専用 GUI を容易に提供できるフレームワークを提供する。これにより、TextAlive のユーザは Kinetic Typography を一から作る必要がなくなり、初めに時間合わせなどを行う手間をかけずに済む。また、歌詞の動きをインタラクティブかつグラフィカルに設計できるようになる。
5 0 0 0 OA 催眠薬
- 著者
- 加藤 信
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.339-345, 1977-09-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 12
5 0 0 0 OA 電気刺激を利用した痛み定量計測法の開発と実験的痛みによる評価
- 著者
- 嶋津 秀昭 瀬野 晋一郎 加藤 幸子 小林 博子 秋元 恵実
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.117-123, 2005 (Released:2007-01-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4
We have developed a method and a system to quantitatively evaluate human pain without relying on subjective criteria. The concept of pain quantification is to compare the magnitude of the subject's pain to the magnitude of a painless electric stimulus that is comparable to actual pain. We quantified degree of pain as the pain ratio, based on the ratio between pain equivalent current and minimum perceived current. In the system developed as the objective of this study, a gradually increasing pulsed current (frequency was 50 Hz, and the pulse width was 0.3 ms) was applied to the subject's medial forearms, and the subjects compared the magnitude of this sensation to electrical stimulation produced by an electrical current. Using test equipment, we conducted basic evaluations of measurement principles. We induced two types of experimental pain, by applying weight load to the upper arm and the lower leg, and by pinching the skin using clips. We examined whether changes in the degree of sensation with respect to electrical stimulation used in this method could be accurately observed, and whether or not it was possible to accurately and with high reproducibility measure minimum perceived current and pain equivalent current. As a result, we were able to make a clear comparison between pain and the degree of stimulation by electrical current, which was a sensation differing from pain. Although there were individual differences in the measured values, the reproducibility of the pain equivalent current as measured was favorable, and the measured values for pain ratio were also reproducible. We confirmed in the present study that the degree of experimental pain can be expressed as quantitative numerical values using an index defined as pain ratio.
5 0 0 0 児童思春期精神科病棟におけるコグトレの実践と課題
5 0 0 0 OA 北海道におけるヘリコプターと固定翼の連携
- 著者
- 浅井 康文 佐藤 昌太 坂脇 英志 相坂 和貴子 加藤 航平 水野 浩利 前川 邦彦 丹野 克俊 森 和久 奈良 理 高橋 功 目黒 順一
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.21-27, 2011 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 6
北海道では、ドクターヘリ(3機体制)と北海道防災ヘリなどとの共存体制や、さらなる航空機医療の充実を目的に、2010年5月北海道航空医療ネットワーク研究会が設立された。本研究会では、試験事業として民間企業からの寄付によって小型ジェット機を1ヶ月間チャーターし、患者搬送、医師搬送、臓器搬送を実施したので、その結果と運航の可能性や課題等について報告する。結果は、総出動件数16件で、患者搬送9件(要請11件)、臓器搬送4件、医師搬送3件であり、事故なく安全に運航できた。また、着陸可能な北海道内の8空港で見学会を開催し、普及活動も同時に実施した。1ヶ月間の固定翼機運航の成果を踏まえて、北海道地域再生医療計画に基づき、2011年度より3年間に渡り、固定翼機(メディカルウイング)の運航が実地される。
5 0 0 0 OA 身体を拡張する筋電義手:"障害"を再定義するテクノロジーの実現を目指して
- 著者
- 粕谷 昌宏 加藤 龍 高木 岳彦 伊藤 寿美夫 高山 真一郎 横井 浩史
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.887-899, 2016-03-01 (Released:2016-03-01)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 2
本稿では,身体機能を補完する義手と,身体を拡張する義手について述べる。まず,身体機能を補完する義手として,これまでに用いられてきた義手の種類や構成要素,動作原理を解説する。特に,義手の中でも近年注目されている,筋電義手について詳しく記述する。筋電義手の歴史は半世紀以上前までさかのぼるが,その制御方法は長らく革新されてこなかった。そのため,近年登場してきた多自由度の筋電義手においては,制御が複雑で使用者の負担となっていた。これに対し,多自由度の筋電義手でも,直感的で簡便な制御を可能とする,新たな制御方法が実用化されつつある。その研究動向について解説し,そのうえで,この新たな制御方法が実用化されることにより,身体を拡張する義手として,今後社会がどのように変化していくかを述べる。本稿では,最新の筋電義手の動向を,研究段階のものから実用段階のものまで広く解説する。
- 著者
- 加藤 伸弥 藤森 和美
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.70-79, 2021-09-06 (Released:2021-09-06)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,特性としてのシャーデンフロイデの感じやすさを測定するためのTrait Schadenfreude Scaleの日本語版(J-TSS)を作成し,その信頼性と妥当性を検討することであった。研究1では,原版を作成する際に用いられた54個の予備項目を邦訳したものを日本人の大学生に実施し,301名の回答を分析した。その結果,J-TSSは良性シャーデンフロイデと悪性シャーデンフロイデの2種の因子を持つことが明らかとなり,おおむね充分な信頼性が示された。研究2では,2つのサンプル(183名,184名)の大学生を対象に,J-TSSと他の尺度を用いた調査を実施した。その結果,先行研究とおおむね一致する結果が得られたが,本邦において的確な項目表現を吟味した手続き上の影響により,厳密な妥当性までをも立証することはできなかった。以上により,J-TSSの将来的な可能性が論じられた。
5 0 0 0 OA 太平洋のレアアース泥鉱床の発見と開発可能性
- 著者
- 加藤 泰浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.74-75, 2013 (Released:2019-10-31)
5 0 0 0 OA 日本の家庭米、自家米、市販米および韓国、タイ、フィリピン米の細菌汚染状況調査
- 著者
- 加藤 和子 駒込 乃莉子 峯木 眞知子 森田 幸雄
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成29年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.23, 2017 (Released:2017-08-31)
【目的】米は、世界の二大食糧作物で、日本のみならずアジア諸国でも食べられている。近年、米の入手方法も多様化し、家庭における保存状況も様々である。米を安心で安全に喫食するための一助として、日本およびアジアの米の細菌汚染状況を調査した。【方法】日本の家庭米35(精白米29、無洗米6)、自家米14、市販米11の計60検体、および韓国6、タイ7、フィリピン8検体の市販米、計21検体について一般生菌、大腸菌群、大腸菌、食中毒菌(ウェルシュ菌、バチルス属菌)を定量検査した。大腸菌群、大腸菌、食中毒菌の同定は食品衛生検査指針に準じた。【結果および考察】生米の一般生菌の検出状況は、平均菌数(対数値/g)はタイ米が2.45±0.09と低く、日本の市販米は3.88±0.11と高かった。タイ米、フィリピン米は日本の家庭米である精白米・無洗米・自家米・市販米および韓国米の検体に比べて、一般生菌数は有意に低かった。大腸菌は韓国米1検体のみ検出された。大腸菌群は日本の無洗米1検体が3.82と高く、タイ米・フィリピン米からは検出されなかった。ウェルシュ菌は、いずれの検体からも検出されなかった。バチルス属菌の検出では、日本の無洗米6検体中2検体から検出され、陽性検体の平均菌数(対数値/g)は4.06±0.16と高く、タイ米(7検体中3検体が陽性)は2.54±0.14と低かった。日本の家庭米の精白米1検体、タイ米2検体、フィリピン米1検体の加熱検体から平均菌数(対数値/g)約2のバチルス属菌が検出された。陽性検体数は少ないものの加熱して喫食する米飯ではバチルス属菌による危害を防止することが必要であると思われた。
- 著者
- 飯沼 宏之 山下 武志 傅 隆泰 加藤 和三
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.340-349, 2001-04-15 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 17
冠閉塞時の虚血性心筋ではATP産生が減少し細胞内ATPレベルが低下する結果,IK・ATPチャネルが開口し,K+は細胞外へ流出,〔K+〕oは上昇する.〔H+〕iの上昇に伴うK+のcotransportも〔K+〕oを高める.さらにNa+/K+ポンプ非活性化や灌流途絶によるwashout停止も〔K+〕o上昇に結びつく.このような〔K+〕o依存性の要因の他に,〔K+〕o非依存性の要因も加わって,虚血心筋では静止膜電位の減少(分極不全)が生じる.一方,静止電位の減少は,〔H+〕iの上昇と組み合わさってNaチャネルの不活性化を招き,これはCaチャネル不活性化とともに脱分極不全を生じさせる.このような分極不全/脱分極不全はそれぞれの拡張期/収縮期傷害電流を生じさせ,その結果,見かけの/真のST上昇が生じる.一方,冠狭窄時にはこのようなST上昇は心内膜側のみに限局し,健常な心外膜側で記録する心電図ではST上昇のミラー像としてのST下降が生じる.さらに冠閉塞解除後の心筋虚血からの回復期には,IKrチャネル発現減少に基づくAPD延長が生じ,これに虚血時の両親媒性脂質中間代謝体(LPCなど)上昇によるK+透過性減少やNaチャネル不活性化遅延などの変化が加わって,APDはますます延長する.このようなAPD延長は健常部の正常なAPDとの較差から著明な陰性T(冠性T)を生じさせる.
5 0 0 0 OA グローバル化時代の大学 : 違いを認め合う共生社会を目指して
- 著者
- サコ ウスビ 結城 幸司 加藤 博文
- 出版者
- 北海道大学ダイバーシティ・インクルージョン推進本部
- 巻号頁・発行日
- pp.5-20, 2022-05
(2022). 北海道大学ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言制定記念講演会記録集 北海道大学ダイバーシティ・インクルージョン推進本部
5 0 0 0 OA バナナの追熟および加熱調理による糖組成の変化
- 著者
- 伊藤 聖子 葛西 麻紀子 加藤 陽治
- 出版者
- 弘前大学教育学部
- 雑誌
- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
- 巻号頁・発行日
- no.110, pp.93-100, 2013-10-18
フィリピン産の高地栽培種(スウィーティオバナナ)および従来の低地栽培バナナ(レギュラーバナナ)を用い追熟過程および加熱(焼く、蒸す)調理過程それぞれでの糖度および糖組成の変化を調べた。高地栽培種、低地栽培種の可溶性糖質含有量は高地栽培種の方が多いことが確認された。また、両者ともその主成分はスクロース、グルコース、フルクトースであるが、追熟とともにスクロースが減少し、グルコースとフルクトースが増加することがわかった。また、微量に含まれるソルビトールは減少し、オリゴ糖は増加する傾向にあった。加熱調理(焼く:180℃のオーブンで20分、30分、40分処理、および蒸す:蒸し器で10分、20分、30分処理)では、いずれも、焼き調理より蒸し調理後の糖度が高くなる傾向がみられた。焼きは30分で最も高く40分では減少していた。また、蒸し調理では10~20分で最も高く、それ以上になると、かなり減少することがわかった。
- 著者
- 加藤 知子 Kato Tomoko
- 雑誌
- 研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.13-28, 2015-03-27
Women’s Active Museum on War and Peace (wam) is a Christian-affiliated institute, which is situated on the second floor of the AVACO (Audio Visual Activities Commission) Building in Tokyo. On the 6th of July, 2014, AVACO Building was targeted by conservative, nationalistic Japanese demonstrators, who most likely confused Women’s Active Museum on War and Peace with the AVACO Building. Such a demonstration has served as an opportunity for people, however, to think anew of what kind of institution wam is, what activities they are actually doing, and what sort of idea is behind them and their daily activities. The Asahi Shimbun, in its issues of the fifth and sixth of August, 2014, finally admitted that they had spread some misinformation about so-called Comfort Women who had allegedly been taken by force to offer sexual pleasure to Japanese Imperial Military officers and soldiers. Even after these articles were published, however, certain Christian-affiliated organizations, including wam, instead of rethinking their unique historical perspective on the Modern History of Japan, continued criticizing the country for her treatment of the so-called Comfort Women during the first half of the 20th century. The historical perspective on Modern Japan, like the one adopted by wam, has dominated the Japanese Christian circles since the end of the Second World War. In this paper, I will argue that such a historical perspective may drive Japan into havoc by showing that the wam’s endeavors (largely determined by their unique historical perspective) and the Chinese Communist Party’s military strategic zones somehow overlap. Finally, in Chapter Ⅴ of this paper, I will ask Japanese Christian priests and pastors to work on ways to interpret the passages in the Bible that include not only pacifist messages but also apparently militaristic ones. I will close this paper with a humble request that Christians in Japan should first seek for the Holy Spirit (ruach ha-kodesh, in Hebrew), who believers hold will guide them to the true knowledge including secular interpretations of the historical facts as well as religious understanding of Bible passages themselves.
5 0 0 0 高専における少人数影響を利用したヒヤリハット活動教育とその評価
- 著者
- 松岡 武史 佐々木 大輔 藤岡 潤 泉野 浩嗣 加藤 亨
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.4_45-4_51, 2018 (Released:2018-07-27)
- 参考文献数
- 19
Recently, the industrial accidents rate of young unskilled workers is increasing in our country. Therefore, in national institute of technology which produces young engineers, an effective safety and health education for these workers is also desired strongly. Action to collect near-miss incident information is important position in such education. However, the near-miss reporting is not functioning effectively at the majority of national institute of technology because of negative consciousness and lack of understandings about this activity. In this research, we proposed the teaching method about the near-miss reporting using minority influence in order to solve these issues and carried out this method for three years from 2015 at our school. In this paper, we showed that injury accidents and tool breakages decrease as student near-miss reports increase, and safety culture maturity level in the mechanical workshop rises.