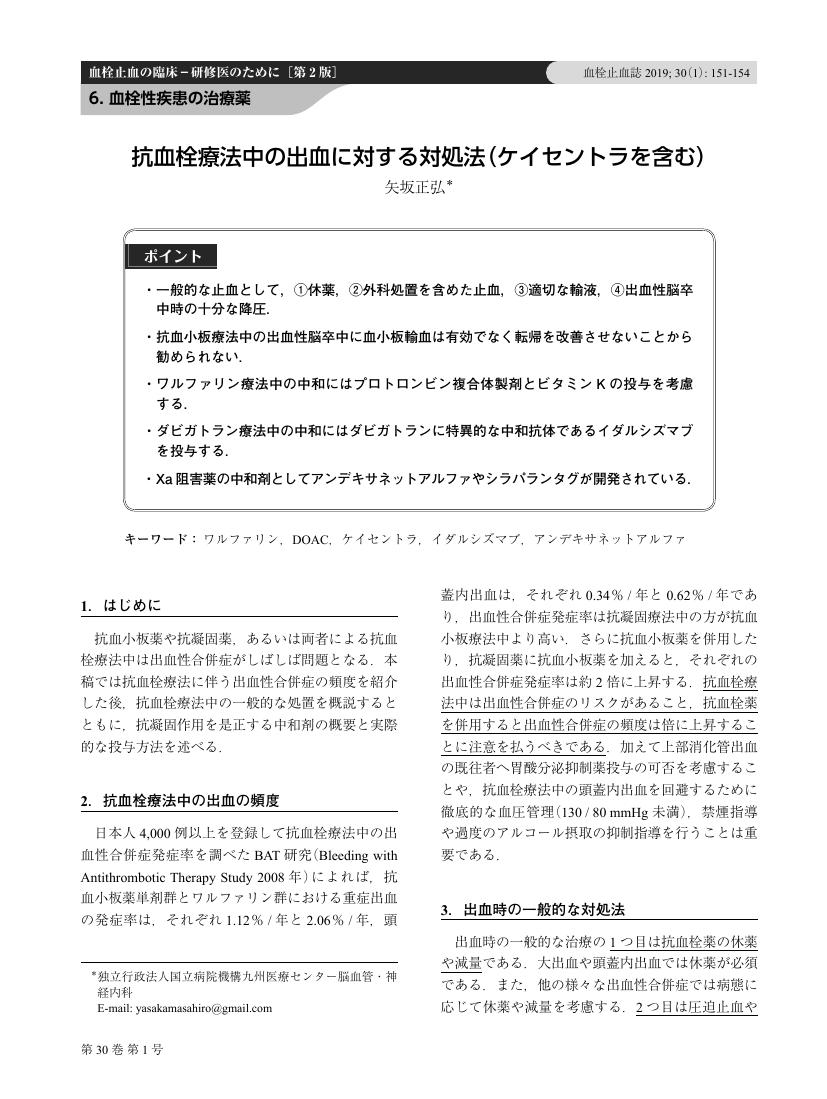- 著者
- 峰松 一夫 矢坂 正弘 米原 敏郎 西野 晶子 鈴木 明文 岡田 久 鴨打 正浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.331-339, 2004-06-25 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 7 10
【目的】若年者脳血管障害の頻度や臨床的特徴を明らかにする.【方法】統一形式の調査票を用い,1998年と1999年の2年間に入院した発症7日以内の51歳以上の脳卒中症例の概略と,1995年から1999年までに入院した発症1カ月以内の50歳未満の脳卒中症例の詳細を全国18施設で後ろ向きに調査した.【結果】合計7,245症例のデータが集積された.発症1週間以内入院の全脳卒中に占める若年者脳卒中の割合(調査期間補正後)は,50歳以下で8.9%,45歳以下で4.2%,40歳以下で2.2%であった.背景因子を51歳以上(非若年群)と50歳以下(若年群)で比較すると,高血圧(62.7%vs.48.5%),糖尿病(21.7%vs.13.6%),高コレステロール血症(16.5%vs.13.1%)及び非弁膜性心房細動の占める割合(21.2%vs.4.7%)は非若年群の方が高く(各p<0.01),男性(58.9%vs.62.8%),喫煙者(19.3%vs.27.3%)と卵円孔開存例(0.7vs.1.2%)は若年群で多かった(各々p<0.01,p<0.01,p=0.08).TIAの頻度に差は無かったが,脳梗塞(62.6%vs.36.7%)は非若年群で,脳出血(20.8%vs.32.1%)とくも膜下出血(7.3%vs.26.1%)は若年群で高かった(各p<0.01).若年群の原因疾患として動脈解離,Willis動脈輪閉塞症,脳動静脈奇形,抗リン脂質抗体症候群などが目立ったが,凝固系の検査や塞栓源の検索は必ずしも十分ではなかった.外科的治療は37.5%で,退院時の抗血栓療法は31.9%で施行された.退院時転帰は26.0%で要介助,死亡率は8.8%であった.【結論】全脳卒中に占める若年者脳卒中の割合は低く,その背景因子は非若年者のそれと大きく異なる.若年者脳卒中への対策の確立のためには,全国規模のデータバンクを構築し,適切な診断方法や治療方法を明らかにする必要がある.
1 0 0 0 OA 抗血栓療法中の出血に対する対処法(ケイセントラを含む)
- 著者
- 矢坂 正弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.151-154, 2019 (Released:2019-02-25)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 4.転倒や出血を考慮した抗血栓薬管理
- 著者
- 杉森 宏 森 興太 矢坂 正弘 岡田 靖
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.305-311, 2022-07-25 (Released:2022-09-07)
- 参考文献数
- 14
高齢者では転倒・転落による死亡者数は不慮の事故の中で最も多い.抗血栓療法は循環器疾患をそしてそれに伴う転倒も予防するが,同時に出血を宿命的に合併する.転倒は患者側の原因と環境原因が重なって起こることを認識してリスクを評価し,転倒リスクに関連する薬剤の処方などを抑制する.また適応があるなら新規経口抗凝固薬などより安全な薬剤を処方し,極端に虚弱な患者には抗血栓療法を控えることも考慮するなど総合的な対応が重要である.
- 著者
- 石川 英一 矢坂 正弘 岡田 靖
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.425-431, 2013-11-25 (Released:2013-11-25)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 4
要旨:【背景および目的】観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に関する研究(MARK study)において,処置時の抗血栓薬管理についてアンケート調査を行った.【方法】全国の国立病院機構の病院やセンターの診療科科長 を対象に郵送法で行った.【結果】抗血小板薬と比べ経口抗凝固薬は高率に中止・減量され,それぞれ全体の58%と66%であった.中止・減量時のヘパリン代替療法施行率は抗凝固薬で抗血小板薬より高い.抗血栓薬管理マニュアルがある診療科は35%に過ぎず,中止時に同意書を取得する診療科は12%であった.過去5 年間で,抗血栓薬を継続し大出血を経験した診療科は抗血小板薬,抗凝固薬いずれも8%台,抗血栓薬を中止し血栓・塞栓症を経験した診療科はいずれも約10%であった.【結論】抗血栓薬管理マニュアルの整備は約3 分の1,中止時の同意書取得率も約1 割と低く,周術期抗血栓薬管理法の確立は大きな課題である.
1 0 0 0 OA 脳動脈解離による急性期脳梗塞症例における発症30日以内の神経症候増悪因子の検討
- 著者
- 森 真由美 湧川 佳幸 矢坂 正弘 安森 弘太郎 詠田 眞治 岡田 靖
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.1-9, 2014-01-01 (Released:2014-01-15)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
脳動脈解離にともなう急性期脳梗塞における神経症候急性増悪例の特徴を検討した.急性期脳梗塞連続1,112例のうち,脳動脈解離にともなう脳梗塞は18例(1.6%)だった.平均年齢52歳,男性83%で,後方循環系解離が72%を占めた.発症30日以内の神経症候増悪例は4例(22%)で,すべて発症3日以内にみられ,入院時血圧が高値であり,優位側椎骨動脈や脳底動脈の解離をきたしていた.瘤形成症例を除いて積極的な抗凝固療法をおこなったが出血性合併症はみられなかった.増悪例の転帰は有意に不良であった.優位側椎骨動脈または脳底動脈解離による脳梗塞で,入院時血圧が高値である症例は,発症3日間はとくに注意深く観察する必要がある.
1 0 0 0 OA 就眠時頸部過伸展による内頸動脈解離の1 例
- 著者
- 溝口 忠孝 津本 智幸 鶴崎 雄一郎 徳永 聡 桑城 貴弘 矢坂 正弘 岡田 靖
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.81-85, 2018 (Released:2018-03-23)
- 参考文献数
- 18
特発性内頸動脈解離に対し,頸動脈ステント留置術を行い,良好な転帰を得た1 例を報告し,その原因を考察する.症例は30 歳男性.患者は睡眠時に頸をかしげた状態で寝てしまう習慣があった.起床後入浴中に頸部痛,運動性失語,右半身麻痺を呈した.頭部MRI では左基底核と左前頭葉深部に微小梗塞を認め,MRA では左内頸動脈の偽性閉塞を認めた.諸検査から頸動脈解離に伴う偽性閉塞と診断し,来院時には無症候性であることから内科治療を選択した.しかし,第4 病日目に行った血管撮影でも内頸動脈偽性閉塞所見は全く改善していないため頸動脈ステント留置術を施行し,脳血流の改善を認めた.後遺症なく15 病日目に自宅退院となった.本症例では発症機序としては入眠時の特徴的な姿位による頸部の過伸展が関与していると考えられた.内頸動脈解離の発症機序に関して,十分な病歴,生活習慣の聴取をすることも肝要であると考える.
1 0 0 0 OA 後頭部痛のみを呈し,積極的降圧療法で良好な転帰を得た椎骨動脈解離の2 例
- 著者
- 外山 祐一郎 矢坂 正弘 桑城 貴弘 湧川 佳幸 齊藤 正樹 下濱 俊 岡田 靖
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.428-433, 2015 (Released:2015-11-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
要旨:症例1 は63 歳男性.頸部回旋時より右後頭部痛を自覚した.右椎骨動脈に6 mm の拡張を認め,右椎骨動脈解離と診断した.出血や脳梗塞の所見なく,降圧療法を開始(150/90 から100/60 mmHg)した.後頭部痛は改善し第17 病日に消失し,第26 病日に退院した.症例2 は39 歳男性.起床時に正中後頭部痛を自覚した.第12 病日に当科受診.右椎骨動脈に9 mm の瘤形成を認め,降圧を行い(血圧120/60 から110/60 mmHg),後頭部痛は改善し第17 病日に消失し第23 病日に退院した.2~3 カ月後のMR 検査にて解離病変は症例1,2 ともに改善した.椎骨動脈解離急性期の降圧療法は頭痛や血行動態の改善に有効と考えられる.
1 0 0 0 OA 卵円孔開存
- 著者
- 矢坂 正弘 湧川 佳幸 岡田 靖
- 出版者
- 日本脳神経超音波学会
- 雑誌
- Neurosonology:神経超音波医学 (ISSN:0917074X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.79-80, 2013-01-31 (Released:2013-02-12)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- 木村 和美 矢坂 正弘 宮下 孟士 山口 武典
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.363-368, 1990-08-25 (Released:2009-09-03)
- 参考文献数
- 8
症例は68歳の心房細動を有する女性.上部脳底動脈の塞栓性閉塞に基づく特異な眼症候と無動性無言を呈した.両側性に垂直眼球運動障害があり, これに加えて, 左眼は外転位で内転障害が認められたが, 瞳孔異常はなかった.右眼はcorectopiaを呈し, 瞳孔は散大, 対光反射消失, 責任病巣として右Edinger-Westpha1核, 左動眼神経核, およびrostral interstitial nucleus of MLFが推測された.MRIで両側視床から中脳被蓋に連続した病巣を認め, 眼症候と無動性無言は, 傍正中視床動脈の閉塞に基づくものと考えられた.
1 0 0 0 OA 新規経口抗凝固薬に関する諸問題
- 著者
- 矢坂 正弘 岡田 靖
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.121-127, 2013-03-20 (Released:2013-03-25)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4 1
要旨:ワルファリンに替わって,2011から抗トロンビン薬や抗Xa薬などの新規経口抗凝固薬(novel oral anticoagulants; NOAC)が相次いで登場している.新規経口抗凝固薬はワルファリンと比較して,吸収が早く,半減期が短く,食物の影響を受けず,薬物の相互作用が少ない.頻回なモニタリングが不要で,脳卒中と全身塞栓症の予防効果はワルファリンと同等かそれ以上,大出血発現率はワルファリンと同等かそれ以下,頭蓋内出血発症率はワルファリンより大幅に少ない.このような観点から新規経口抗凝固薬はワルファリンと比較して一歩前進した抗凝固薬である.しかし,(1)出血性合併症の予防との緊急対処法,(2)脳梗塞急性期のrt-PA血栓溶解療法の可否,(3)適正使用の徹底,および(4)周術期の管理などの問題点が指摘されている.問題点に対して切な対処方法を開発していく必要がある.
- 著者
- 峰松 一夫 矢坂 正弘 米原 敏郎 西野 晶子 鈴木 明文 岡田 久 鴨打 正浩
- 出版者
- The Japan Stroke Society
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.331-339, 2004-06-25
- 被引用文献数
- 9 10
【目的】若年者脳血管障害の頻度や臨床的特徴を明らかにする.<BR>【方法】統一形式の調査票を用い,1998年と1999年の2年間に入院した発症7日以内の51歳以上の脳卒中症例の概略と,1995年から1999年までに入院した発症1カ月以内の50歳未満の脳卒中症例の詳細を全国18施設で後ろ向きに調査した.<BR>【結果】合計7,245症例のデータが集積された.発症1週間以内入院の全脳卒中に占める若年者脳卒中の割合(調査期間補正後)は,50歳以下で8.9%,45歳以下で4.2%,40歳以下で2.2%であった.背景因子を51歳以上(非若年群)と50歳以下(若年群)で比較すると,高血圧(62.7%vs.48.5%),糖尿病(21.7%vs.13.6%),高コレステロール血症(16.5%vs.13.1%)及び非弁膜性心房細動の占める割合(21.2%vs.4.7%)は非若年群の方が高く(各p<0.01),男性(58.9%vs.62.8%),喫煙者(19.3%vs.27.3%)と卵円孔開存例(0.7vs.1.2%)は若年群で多かった(各々p<0.01,p<0.01,p=0.08).TIAの頻度に差は無かったが,脳梗塞(62.6%vs.36.7%)は非若年群で,脳出血(20.8%vs.32.1%)とくも膜下出血(7.3%vs.26.1%)は若年群で高かった(各p<0.01).若年群の原因疾患として動脈解離,Willis動脈輪閉塞症,脳動静脈奇形,抗リン脂質抗体症候群などが目立ったが,凝固系の検査や塞栓源の検索は必ずしも十分ではなかった.外科的治療は37.5%で,退院時の抗血栓療法は31.9%で施行された.退院時転帰は26.0%で要介助,死亡率は8.8%であった.<BR>【結論】全脳卒中に占める若年者脳卒中の割合は低く,その背景因子は非若年者のそれと大きく異なる.若年者脳卒中への対策の確立のためには,全国規模のデータバンクを構築し,適切な診断方法や治療方法を明らかにする必要がある.
- 著者
- 外山 淳治 三浦 傅 竹越 襄 相澤 義房 古賀 義則 小川 聡 笠貫 宏 大江 透 井上 通敏 山口 武典 斉藤 崇 鬼平 聡 津川 博一 北川 泉 岡本 光弘 平井 真理 池主 雅臣 鷲塚 隆 中田 真詩 岩見 元照 中澤 博江 伊藤 公一 吉村 弘 松田 直樹 志賀 剛 草野 研吾 森田 宏 是恒 之宏 鎌倉 史郎 矢坂 正弘 長嶋 正實 安田 東始哲 杉 薫 児玉 逸雄 井上 博 矢野 捷介 奥村 謙 比江嶋 一昌
- 出版者
- 社団法人日本循環器学会
- 雑誌
- Japanese circulation journal (ISSN:00471828)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.931-978, 2001-11-25
- 参考文献数
- 122
- 被引用文献数
- 19