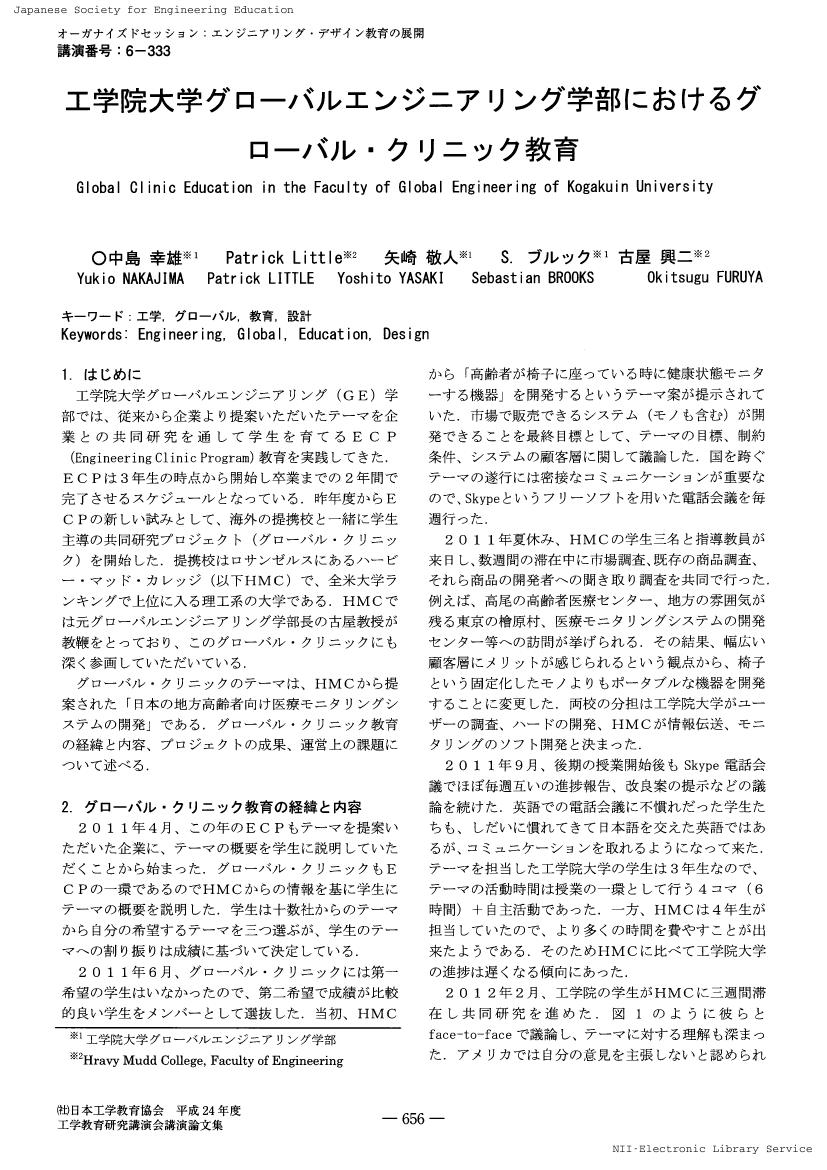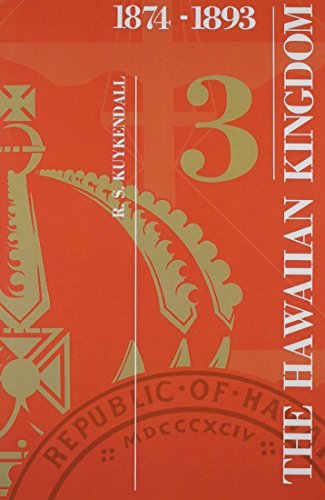- 著者
- Rina Ando Hirotaka Iwaki Tomoaki Tsujii Masahiro Nagai Noriko Nishikawa Hayato Yabe Ikuko Aiba Kazuko Hasegawa Yoshio Tsuboi Masashi Aoki Kenji Nakashima Masahiro Nomoto on behalf of the Parkinson's Disease Safe Driving Study Group of Japan
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.9653-17, (Released:2018-02-28)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 4
Objective We conducted a study to obtain information that could be used to provide Parkinson's disease (PD) patients with appropriate advice on safe driving. Methods Consecutive PD patients who visited our office were studied. Among these patients, those who had experienced driving after being diagnosed with PD were interviewed by neurologists and a trained nurse to investigate their previous car accidents, motor function, cognitive function, sleepiness, levodopa equivalent dose (LED), and emotional dysregulation. The rates of major car accidents before and after the onset of PD were compared. Results Fifteen patients had experienced a major car accident resulting in human injury or serious property damage since the onset of PD. When the rates of major car accidents before and after the onset of PD were compared, the ratio was 4.3 (95% CI 1.9-9.7). The incidence of accidents after the onset of PD was correlated with age, disease duration, LED, the cognitive function (MMSE, MoCA-J), but not the motor symptom score (UPDRS part III at the time of the study). The Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson's Disease (QUIP) score was also higher in patients with major car accidents. Conclusion The severity of symptoms (Hoehn-Yahr classification), cognitive function, and disease duration were expected to be risk factors for car accidents. However, the motor symptom score (UPDRS part III) was not associated with the incidence of major car accidents. In addition to a low cognitive function and the severity of symptoms, the QUIP score might be an independent factor that can be referenced when advising PD patients to refrain from driving.
1 0 0 0 OA 合鯉類タウナギの空気呼吸器官の構造
- 著者
- Jyoti S. D. Munshi George M. Hughes Peter Gehr Ewald R. Weibel
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.453-465, 1989-03-15 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 30
タウナギの空気呼吸器官の構造を, 光顕, 走査ならびに透過電顕によって観察し, 本種における口腔咽頭呼吸に関する形態的基礎を明らかにした.気嚢 (上咽頭室) は吸・出水口の役を果す開口部をもち, その2/3に形と大きさの異なる呼吸島をそなえている.呼吸島は水呼吸に役割を果すが, 水呼吸だけではタウナギは生活できない.血管分布のないところは, 微小堤をそなえた上皮細胞で覆われている.呼吸器官へは細動脈が深く侵入し, 呼吸島に特有の血管乳頭を形成する.血管乳頭も, 特殊化した上皮で覆われている.第2鯉弓は, 多角状微小堤をもつ上皮で覆われた少数の指状弁をそなえている.立体法並びにタウナギ相応の新しい範例をとり, 空気呼吸器官の形態計測を行なった.そして, 体重200gの呼吸膜における呼吸面積, 毛細管負荷などを算出した。
- 著者
- JUNG H.-S.
- 雑誌
- J. Climate
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.2989-3004, 2001
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- W. D. Tigertt G. W. Hunter III Ritchie L. S. Ritchie
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee
- 雑誌
- Japanese Journal of Medical Science and Biology (ISSN:00215112)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.5, pp.357-385, 1952 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 2 2
1 0 0 0 米国における1995年の狂犬病調査 (その1)
- 著者
- Krebs John W. Strine Tara W. Smith Jean S. Noah Donald L. Rupprecht Charles E. Childs James E.
- 出版者
- Japan Veterinary Medical Association
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.365-367, 1997
1995年に, 49州, コロンビア特別区, および自治領プエルトリコから, 疾病予防センターに対し, 動物の狂犬病症例7, 877件, 人間の狂犬病症例4件の報告がなされた. 全症例のうち, 92%近く (7, 247件) が野生動物で, 8%(630件) が家畜の症例であった. 報告された症例の総数は, 1994年の8, 230件から4.2%減少した. この減少は大部分, 北東部地域のアライグマの狂犬病報告症例が17.1%減少したことによる. この地域での狂犬病は現在, 同種動物間流行というより地域的流行となっている. 報告症例が例外的に増大している地域は, 狂犬病ウイルスが最近になってアライグマに入り込んだ地域, あるいは同種動物間流行が持続している地域である. この狂犬病ウイルス変異株に関連した同種動物間流行が増大した州 (狂犬病症例総数) は, メイン州 (1993年の3件から1995年には101件), ノースカロライナ州 (1990年の9件から1995年には466件), ロードアイランド州 (1993年の1件から1995年には324件), ヴァーモント州 (1993年の45件から1995年には179件) である. 狂犬病ウイルスのアライグマ変異株が現在見られるのは, アラバマ州, ペンシルヴェニア州, ヴァーモント州, ウェストヴァージニア州およびフロリダ州からメイン州にわたる大西洋岸諸州である. オハイオ州ではアライグマ変異株が1992年に1症例で発見されて以来みられなかったが, 1996年に再び発見されている.テキサス州中西部におけるキツネの狂犬病とテキサス州南部における犬とコヨーテの狂犬病の同種動物間流行は犬変異株によるもので, なお持続している. テキサス州で1995年に報告されたのは, キツネの狂犬病137件, 犬の狂犬病55件およびコヨーテの狂犬病80件 (全国では83件) である. コウモリの狂犬病の件数 (787) は25%近く増加し, 陸続きの48州中47州で報告されている. 全国の狂犬病の報告件数は牛136件 (前年比22.5%増), 猫288件 (同7.9%増), 犬146件 (同4.6%減) である. 猫は家畜の中では引き続き狂犬病症例の報告が最も多い動物であった. 人間について報告された狂犬病の症例はすべてコウモリに関連したウイルス変異株によるものであった. 18州と自治領プエルトリコで1995年に動物の狂犬病の減少が報告された. 1994年に減少が報告されていたのは, 28州とコロンビア特別区であった. 1995年に狂犬病の症例報告がなかったのはハワイ州だけである.
1 0 0 0 OA 照射食品の栄養学的及び安全性の研究
- 著者
- U.K. Vakil M. Aravindakshan H. Strinivas P.S. Chauhan A. Sreenivasan
- 出版者
- 日本食品照射研究協議会
- 雑誌
- 食品照射 (ISSN:03871975)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.73-84, 1973-03-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- TOM S. CHEN BYRON H. ARISON LINDA S. WICKER EDWARD S. INAMINE RICHARD L. MONAGHAN
- 出版者
- JAPAN ANTIBIOTICS RESEARCH ASSOCIATION
- 雑誌
- The Journal of Antibiotics (ISSN:00218820)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.118-123, 1992-01-25 (Released:2006-04-19)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 15 17
The immimosuppressants FK506 and FR 900520 were desmethylated by Actinoplanes sp. ATCC 53771 to yield various O-desmethylated products. The products were isolated and purified by solvent extraction and HPLC chromatography, and identified by NMR and MS spectroscopy.
1 0 0 0 World companies
- 著者
- Harshal S Mandavdhare Vishal Sharma Harjeet Singh Usha Dutta
- 出版者
- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement
- 雑誌
- BioScience Trends (ISSN:18817815)
- 巻号頁・発行日
- pp.2018.01028, (Released:2018-07-15)
- 参考文献数
- 7
Chylous ascites is an uncommon entity and infectious etiology is the most common cause in developing countries. However, recently, whether there is any change in trend of etiologies in developing countries is not known. In this study, a retrospective analysis of the data of cases of atraumatic chylous ascites was conducted. Twelve patients of atraumatic chylous ascites with a mean age of 35 years were studied and 6 of them were males. The mean duration of symptoms was 9.6 months and the clinical presentation was abdominal distension (12 cases), pain abdomen (10 cases), loss of appetite and weight (9 cases), peripheral lymphadenopathy (4 cases) and fever (3 cases). Etiologies were tuberculosis (3 cases), malignancy (2 cases), radiotherapy related (2 cases), pancreatitis related (2 cases), lymphatic malformation (2 cases) and multifactorial (1 case). Eight improved with conservative measures, 2 were lost to follow up and 2 died. Our outcomes found infectious etiology still as the most common cause of atraumatic chylous ascites. Benign treatable causes could be managed successfully with conservative measures while malignant etiology had a poor prognosis. Underlying etiology determines the outcome in atraumatic chylous ascites.
- 著者
- Schram S.R. 三浦 清一郎
- 出版者
- 現代評論社
- 雑誌
- 現代の眼 (ISSN:0435219X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.9, pp.236-246, 1974-09
1 0 0 0 OA 混合法における信託の比較法制史的研究
- 著者
- 松本 英実 吉村 朋代 溜箭 将之 葛西 康徳 イベトソン D. ケアンズ J. ベネット T. オズボーン R. テイト J. アヴラモーヴィチ S. ニコリッチ D. ラショヴィチ Z. ジヴァノヴィチ S. ヴコヴィチ K.
- 出版者
- 青山学院大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2014-04-01
混合法(ミクスト・リーガル・システム、mixed legal system)の方法論に立脚して、信託及び信託類似の制度について、比較法制史的考察を行った。混合法における信託を考察するためには、ローマ法の考察が不可欠であることを基本として、一方では古代ローマ法、古代ギリシア法を、他方では狭義混合法(特に南アフリカ法)、広義混合法(バルカン法)を比較対象として、混合法としての日本法との比較を試みた。特に、信託の公的コントロールにの多様なあり方を抽出し、ローマ法と信託法の伝播diffusionという視点から長期にわたる法の展開の全体像と日本法の位置づけを得ることが出来た。
- 著者
- グース アラン・H カイザー デイビッド・I リンデ アンドレイ・D 野村 泰紀 ベネット チャールズ・L ボンド J・リチャード ブーシェ フランソワ キャロル ショーン エフスタシウー ジョージ ホーキング スティーブン カロッシュ レナータ 小松 英一郎 クラウス ローレンス・M リス デイビッド・H マルダセナ フアン マザー ジョン・C パイリス ヒラーニヤ ペリー マルコム ランドール リサ リース マーティン 佐々木 節 セナトーレ レオナルド シルバースタイン エバ スムート ジョージ・F スタロビンスキー アレクセイ サスキンド レオナルド ターナー マイケル・S ビレンキン アレキサンダー ワインバーグ スティーブン ワイス ライナー ウィルチェック フランク ウィッテン エドワード ザルダリアガ マティアス
- 出版者
- 日経サイエンス ; 1990-
- 雑誌
- 日経サイエンス (ISSN:0917009X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.9, pp.49-52, 2017-09
マルチバースはインフレーション理論の研究から導き出された仮説だ。インフレーションは宇宙の大部分で永遠に続いているとの見方があり(永久インフレーション),その中でたまたまインフレーションがいったん終わった部分の1つが私たちが存在する時空で,それを私たちは唯一無二の宇宙(ユニバース)として認識しているが,同様にして無数の宇宙が生み出さ
- 著者
- 川端 晶子 澤山 茂 Palomar Lutgarda S.
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.6, pp.289-299, 1985
フィリピンのメニュー・カレンダー (Your Regional Menu Guide) を資料とし, 要素技術連関解析の手法を用いて, 献立における調理素材と調理法の相互関係の解析を行い, 以下のような結果を得た。<br>1) メニュー・カレンダーに記載されている料理数は3,414件であった。食品の出現頻度の合計は7,732回であったが, 大別して, エネルギー食品群29.1%, 身体構成食品群24.1%, 機能調整食品群41.1%, その他5.7%であった。出現頻度の最も高い食品は玉ねぎで, っづいて, トマト, 植物油, 生鮮魚, にんにく, うるち米の順であった。<br>2) 調理素材の共出現頻度は, 玉ねぎとトマトが470回であり, 連関度は0.6752が求められた。つづいて, 玉ねぎとにんにく, 玉ねぎと植物油, にんにくと植物油, トマトと植物油, トマトとにんにく, 砂糖とココナッツ, 玉ねぎと生鮮魚の組み合わせの順であった。<br>3) 調理法の出現頻度では"煮る"が最も高く, つづいて"生","炒める","揚げる","焼く","蒸す"の順であった。"煮る"と連関度の最も高い食品はうるち米で, つづいて, 玉ねぎ, 生鮮魚, トマト, 砂糖, ココナッツの順であった。"生"ではバナナ,"炒める"では植物油,"揚げる"では生鮮魚,"焼く"でも生鮮魚, "蒸す"ではもち米が最も高い連関度を示した。<br>4) 総括してみるならば, 食料栄養研究所 (FNRI) は, フィリピンの食生活の背景となっている自然, 社会, 文化の諸条件もふまえ, 国民栄養調査の結果をきめ細かく分析したうえで, おすすめメニュー集をカレンダーにまとめ, 誰にでも解りやすく, すぐ役立つ栄養改善の効果をねらったものであるということができる。
1 0 0 0 OA 進化から見た鳥類の音声コミュニケーションの起源と機能
- 著者
- モートン ユージン.S
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.69-78,99, 2000-09-10 (Released:2007-09-28)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 16 27
コミュニケーションは資源を巡る競争において闘争の代わりをつとめる.コミュニケーションは直接鉢合わせになってしまう危険が無いように他の動物の行動を制御する.メスはつがいの相手になるオスの資質を見定めるためにコミュニケーションを用いる.このように,性選択はコミュニケーションに大きく影響を受けている.音声コミュニケーションの起源は,最初の陸上動物である両生類に今でも見られる.カエルは鳥類や哺乳類と違って,性成熟に達した後も体の成長が続く.大きな個体は小さな個体よりも低い鳴き声を発することができ,闘争すれば強い.両生類では低い鳴き声は他のオスに対しては威嚇的であり,メスにとっては魅力的である.重要なことは,発声のための身体的な構造と音声の持つ機能とが直接的に関連していることである.音声の機能と発声の機構との関連は,人間の言葉のように任意なものではない.鳥類での体の大きさと鳴き声の音程との関係は,どのようにして証明されるのだろうか.体の大きさと音程との関係はより象徴的であり,さえずりを行う鳥の動機を最も良く説明している.鳥は攻撃的なときには低く耳障りな発声を,争いを鎮めようとしたり,おそれているときには高く調子を持った発声を行う.この体の大きさと鳴き声の音程との関係は動機-構造規則モデルと言われる.このモデルは大きさの象徴的意味と動機とを関係づけるとともに,体の大きさと闘争能力という基本的な関係から導き出される.この動機-構造規則モデルは,発生機構の身体的形態と機能との関係を実験するための仮説を立てるのに便利である.ほとんどの鳥の歌のように,長距離のコミュニケーションに用いられる発声は別の問題である,この場合は通常,近くの相手に対する発声ほどには動機は重要ではない.私は,鳥たちが互いの距離をどのように測っているかを説明するために「伝達距離理論」を創り出した.音と音との間の非常に短い時間の間隔を分析する鳥の能力は,音の減衰を知覚するのに役立っている.この減衰とは,歌い手から歌が伝播して来ることによって起こる反響などの変化ではなく,音が球状に広がることによって起こる周波数や振幅の成分変化のことである.彼らは聞こえてきた歌と自分の記憶にある歌とを比較することによって,その音がどの位遠くから伝わってきたかを判断することができる.伝達距離理論は方言や歌のレパートリー,歌の複雑さと同様に,いくつかのグループで歌の学習がなぜ進化したのかを説明する助けになる.
- 著者
- SMITH C. S.
- 雑誌
- Proc. Int. Sym. on Practical Design in Shipbuilding
- 巻号頁・発行日
- pp.73-79, 1977
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 IR 現代における生活と衣服との関連について(第1報) : 女子大生の被服購入状況の調査
- 著者
- "荻野 千鶴子 古川 智恵子 豊田 幸子 飯島 則子 池田 恭子" オギノ フルカワ トヨダ イイジマ / C. "OGINO C. FURUKAWA S. TOYODA N. IIJIMA K." IKEDA
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要 = Journal of the Nagoya Women's College
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.9-18, 1978-03-15
"以上女子大生の被服購入状況の調査結果をまとめると下記のようである。 1.学生の所持する衣服では,洋服がそのほとんどを占め,その製作割合は,洋服は80%が既製服であり,和服は家庭,注文製作がその大半を占め対象的にみられた. 2.流行への関心度では,女子大生は高い関心を示し,無関心は0で既製服購人の選択順位についても,和洋服ともに,サイズ,品質表示,価格などの実質面よりむしろデザイン,色・柄などの流行面の視点を第1位に選択し,流行への関心の高さがみられた.又,過去4年間の服種別流行への関心度では,ジーンズが顕著に高くみられた. 3.ジーンズ所持数大・小グループの2群にわけて意識を比較した結果,大グループは服の所持数が多くても,死蔵枚数が多く,活用枚数は少ない.又,購入時の計画性についても,小グループに比較して,無計画の傾向がみられた.流行おくれの服の処理でも,大グループはそのまま保管することが多く,小グループでは,そのまま着用したり,他人に譲ったりと活用範囲も広く,大グループに比較して効果的な衣生活運営の傾向が認められた."
- 著者
- L. J. HANKA A. DIETZ S. A. GERPHEIDE S. L. KUENTZEL D. G. MARTIN
- 出版者
- JAPAN ANTIBIOTICS RESEARCH ASSOCIATION
- 雑誌
- The Journal of Antibiotics (ISSN:00218820)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.12, pp.1211-1217, 1978 (Released:2006-04-12)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 141 205
A new antitumor antibiotic is produced in fermentation liquors of Streptomyces zelensis sp.n. The antibiotic is biologically active at extremely low concentrations. At 40 pg/ml, it inhibited 90% of the growth of L1210 cells in culture in tube dilution assays. The minimal inhibitory concentrations against Gram-positive bacteria is between 1-10 ng/ml, while these values for Gram-negative bacteria and fungi are mostly under 1 μg/ml. A microbiological assay with Bacillus subtilis can detect concentrations of 1-2 ng/ml.
- 著者
- 中島 幸雄 Patrick LITTLE 矢崎 敬人 ブルック S. 古屋 興二
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育研究講演会講演論文集 第60回年次大会(平成24年度) (ISSN:21898928)
- 巻号頁・発行日
- pp.656-657, 2012-08-22 (Released:2016-12-28)
1 0 0 0 The Kalakaua dynasty
- 著者
- Ralph S. Kuykendall
- 出版者
- University Press of Hawaii
- 巻号頁・発行日
- 1967
1 0 0 0 OA 『高野聖』研究:泉鏡花作品の幻想性
- 著者
- 小原 彩 Aya Obara 宮城学院女子大学(卒業生) Miyagi Gakuin Women's University
- 雑誌
- 日本文学ノート (ISSN:03867528)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.15-36, 2013-07-20