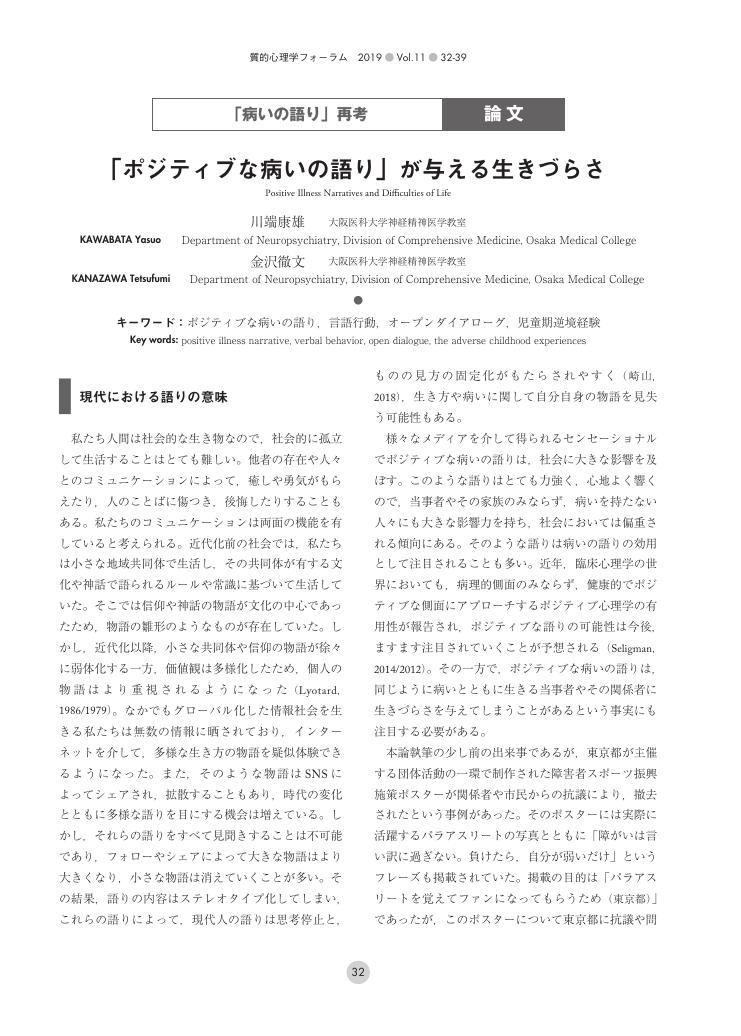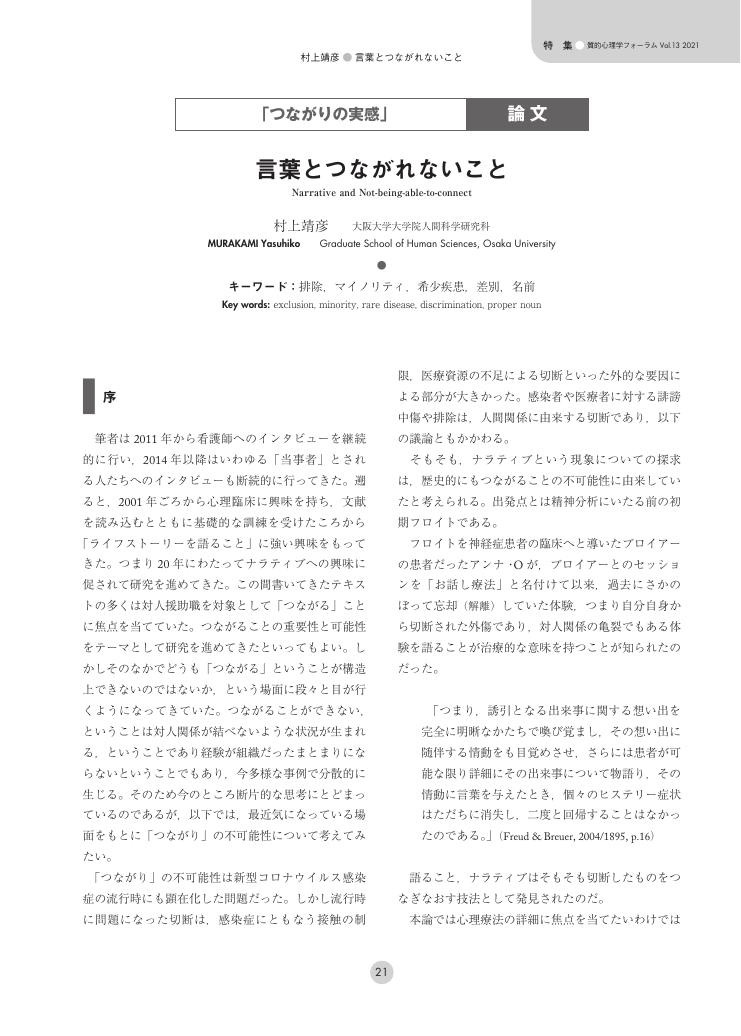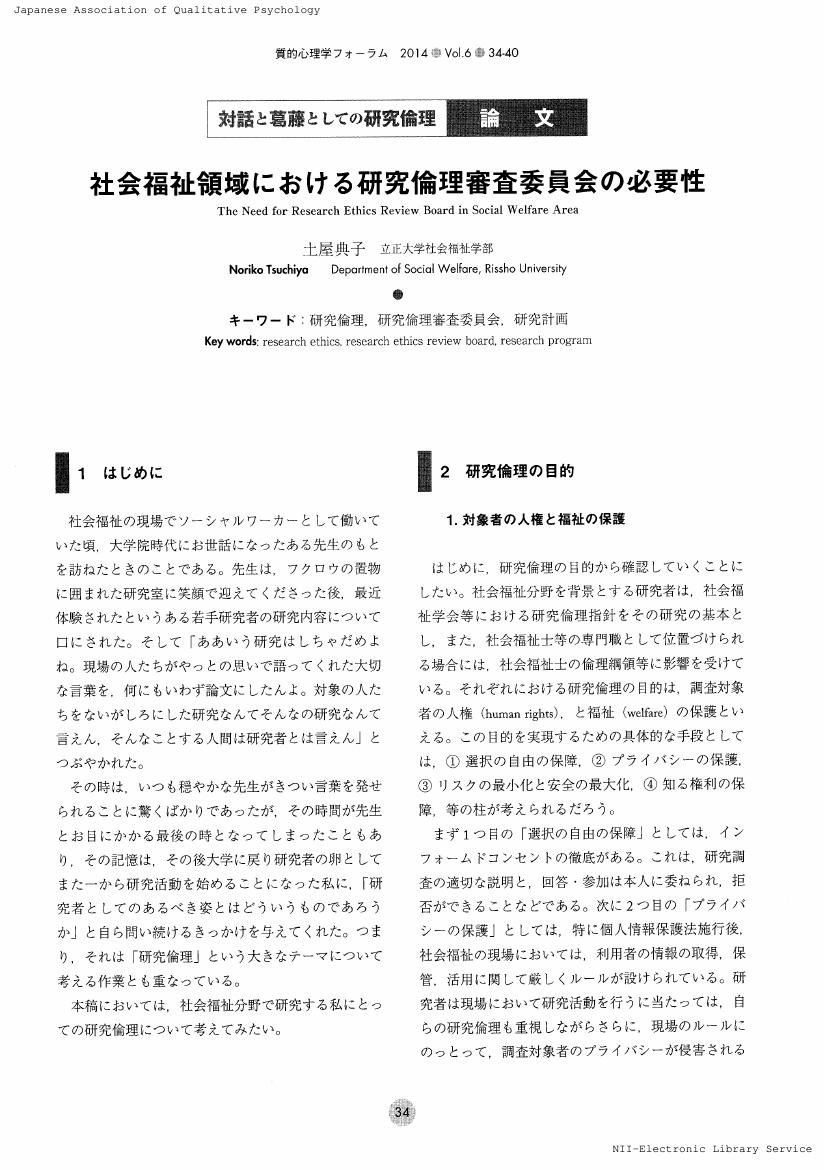3 0 0 0 OA 「ともに」「さまざまな」声をだす 対話的能動性と距離
- 著者
- 桑野 隆
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.6-20, 2008 (Released:2020-07-06)
- 被引用文献数
- 1
バフチンには,『ドストエフスキイの創作の諸問題』(1929)とその改訂増補版『ドストエフスキイの詩学の諸問題』(1963)という 2 つのドストエフスキイ論がある。本稿では,これらの著書およびその周辺の著作を比較検討することにより,主として〈ポリフォニー〉,〈対話〉,〈声〉に関する見解の変化を確認することにした。その結果,1920 年代後半から 30 年代半ばまでに目立つ「社会(学)的」視点が 1960 年前後の著作には見られないこと,また 1920-30 年代にはもっぱら「さまざまな声があること」を強調していたのに対して,1960 年前後には「ともに声をだすこと」をも重視しはじめていることが,明らかになった。さらには,『ドストエフスキイの詩学の諸問題』では,〈ポリフォニー〉や〈対話〉こそが他者に対する格別の「能動性」を必要とすることが繰り返し強調されていることも再確認できた。こうした点を考え合わせると,バフチンの対話原理の要点は,「距離」を確保した「対話的能動性」を身につけてはじめて「心に染み入る対話」も可能になるとの主張にあるといえよう。
- 著者
- 星 瑞希
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.83-101, 2023 (Released:2023-04-01)
本研究では,主権者育成を目標とする歴史授業を高校生がいかに意味づけたのかを,学習文脈と生徒の特性に着目して明らかにする。高校教師である筆者の授業を受けた高校生全員に対し質問紙調査と,そのうち18 名に半構造化面接を行い,M–GTA を用いて,意味づけのプロセスを明らかにした。暗記することに執着がある生徒以外は筆者の主権者育成を目標とする歴史授業を肯定的に意味づけていることが明らかになった。肯定的に意味づけている生徒は歴史事象と現代社会を関連づけたり,現代の歴史論争問題に関与したりすることを肯定的に意味づけ,歴史を学ぶ意味を実感していた。調査校では多大な歴史知識の暗記が求められる受験を意識しない学びが許容されている一方で,多くの歴史授業では生徒が多大な歴史知識を暗記することを評価している。そのため,暗記が苦手な生徒は多大な知識の暗記を要求しない筆者の歴史授業を肯定的に意味づけている。これに対し,暗記が得意でこれまでの試験で充分な試験の得点を取ってきた生徒は,筆者の試験でも充分な得点が取れる場合には,筆者の授業を否定的に意味づけることはなかったが,充分な得点が取れない場合は,筆者の授業を否定的に意味づけている。歴史マンガや家族との歴史談笑を好む生徒は,筆者の意図とは異なり歴史事象と現代を関連づけることをあまり肯定的には意味づけておらず,過去を学ぶこと自体を肯定的に意味づけていることが明らかになった。
3 0 0 0 社会科学における生活史研究,再考
- 著者
- 辻本 昌弘
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.63-81, 2021 (Released:2021-04-12)
本稿は社会科学における生活史研究の意義と方法を明らかにするものである。生活史とは,インタビューや文書 史料などをもとに,ひとりの人物の来歴をくわしく記録したものである。本稿では,生活史研究におけるインタ ビューと解釈の特徴について検討したうえで,以下の 2 点を指摘した。①生活史研究の意義は,既成の通念を揺 さぶり新たな解釈を生みだす手がかりを提供することにある。②生活史研究の意義を実現するためには,イン タビューにおいて出来事を具体的に描写する口述─出来事の写生─を語り手から引きだすことが必要となる。 以上を踏まえて,生活史研究における聞き手のインタビュー技術をめぐる諸問題,さらにインタビューで口述さ れた内容を編集して生活史を執筆するうえでの諸問題を論じた。最後に,生活史研究は,語り手・聞き手・読み 手の言語コミュニケーションをつうじて新たな解釈を豊かに生みだすものであることを指摘した。
3 0 0 0 OA 特集論文 「ポジティブな病いの語り」が与える生きづらさ
- 著者
- 川端 康雄 金沢 徹文
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.32-39, 2019 (Released:2020-04-28)
3 0 0 0 OA 特集論文 言葉とつながれないこと
- 著者
- 村上 靖彦
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.21-27, 2021 (Released:2022-04-20)
3 0 0 0 OA パイオニアにきく 第3回 面白い研究をどう評価するか : 認知科学と質的心理学
- 著者
- 佐伯 胖 荒川 歩
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.50-61, 2011-12-28 (Released:2020-03-11)
- 著者
- 山田 富秋
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.99-101, 2013
先行研究では,日本人キリスト教徒が「宗教」を語る際に,複数のポジション(ディスコース上の立ち位置)から「宗教」について矛盾した語りを行っていたことが見出されている。本研究では,この矛盾した語りに伴う葛藤に彼らがどのように対処しているのかを,ポジショニング理論によって検討することを目的とした。分析の結果,語りの時間的性質によってポジション間の矛盾を無化していることが見出された。また,個人的ポジショニングという「個人」を強調する発話行為によって,語り手が日本社会の「宗教」ディスコースのモラルオーダー(ポジションに付随するルール)に対処していることも見出された。個人的ポジショニングの検討から,この発話行為が語り手の固有性を指示することでモラルオーダーの効力の及ばない「聖域」を作り出すことが指摘された。現代社会において個人は,多様な文脈と単一の固有性とを同時に課せられている。それゆえ,多様なポジションが生じる語りの中で固有性を指示する発話行為として「個人」を捉えることは,現代社会の「個」の在り方を検討する上で有益と言えるだろう。
- 著者
- 渡邊 芳之
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.92-93, 2013
- 著者
- 五十嵐 素子
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム = Qualitative psychology forum (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.35-44, 2017
- 著者
- 松浦 李恵
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.14-23, 2015-09-20
2 0 0 0 OA X ジェンダーを生きる 男女のいずれかというわけではない性自認をもつ人々の語りから
- 著者
- 山田 苑幹
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.144-160, 2019 (Released:2021-04-12)
本研究は,性別違和を抱く人々が自身の性自認をどのように生きているのかについて質的に検討し,ジェンダー・アイデンティティ研究に新たな知見をもたらすことを目的に,男女のいずれかというわけではない性自認をもつX ジェンダー当事者2 名(S さん,K さん)にインタビュー調査を行った。得られた語りは,ナラティヴ分析の一つであるテーマ分析の観点から,語りの内容に注目して(1)性別違和の体験,(2)X ジェンダー概念に対する考え,について整理した。本研究の結果から,X ジェンダー当事者が,自身の性自認とどのように向き合いながらジェンダー・アイデンティティを形成し,X ジェンダー概念をどのように捉えて使用しているのかが浮かび上がった。考察では,S さんとK さんの語りの特徴を先行研究に照らし合わせて整理することで,性別違和を生きる上で重要と思われる点や,X ジェンダー概念がもつ特徴を検討し,X ジェンダーという概念の可能性と限界を浮かび上がらせた。
2 0 0 0 OA 展望論文 科学と非科学のあいだ 質的研究への期待
- 著者
- 外山 紀子
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.70-78, 2017-09-20 (Released:2020-04-28)
2 0 0 0 OA 特集論文 社会福祉領域における研究倫理審査委員会の必要性
- 著者
- 土屋 典子
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.34-40, 2014 (Released:2020-03-11)
2 0 0 0 OA 展望論文 質的研究の評価をどう考えるか 「APA スタンダード」を素材として
- 著者
- 能智 正博
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.45-55, 2019 (Released:2020-04-28)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA パイオニアにきく 第13回
- 著者
- 玉野 和志 石井 由香理 池口 佳子 堀田 裕子
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.49-58, 2021 (Released:2022-04-20)
- 著者
- 宮前 良平 置塩 ひかる 王 文潔 佐々木 美和 大門 大朗 稲場 圭信 渥美 公秀
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.73-90, 2022 (Released:2022-04-01)
エスノグラフィは長らく単独の調査者によって書かれてきた。本稿では,それに対して,地震の救急救援期にお けるチームエスノグラフィの事例をもとに,チームとしてエスノグラフィを行うことの方法論的可能性を論じる。 まず,チームエスノグラフィには,超克しなくてならない問題として羅生門問題と共同研究問題があることを確 認する。次に,既存のチームエスノグラフィにおけるチームには3 つの形態があることを整理し,本稿ではその 中でも同じタイミングで同じ対象を観察する,あるいは同じタイミングで異なる対象を観察した事例を扱うこと を述べる。具体的には,熊本地震の際にあらかじめチームを結成してから現地で活動を展開していった過程をエ スノグラフィとして記述していく。最後に,これらの事例をもとに,チームエスノグラフィには①新たな「語り」 を聞きに行く原動力となること②現場で自明となっている前提に気づくことで新たな問いを立てること③「調査 者-対象者」という非対称性を切り崩す可能性があること④現場に新たな規範を持ち込むことで現場の変革をも たらすことの4 点について議論した。
2 0 0 0 OA 質的研究における対話的モデル構成法 多重の現実,ナラティヴ・テクスト,対話的 省 察 性
- 著者
- やまだ ようこ
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.174-194, 2007 (Released:2020-07-06)
質的研究の新たな方法論として「質的研究の対話的モデル構成法(MDMC)」を提案し,その前提となる理論的枠組モデルを構成し,次の 3 つの観点から考察した。1)多重の現実世界と対話的モデル構成:現実世界は一つではなく,多重の複数世界からなり,研究目的によってどのような世界にアプローチするかが異なる。対話的モデル構成がアプローチする世界は,「可能的経験世界」と位置づけられる。他の「実在的経験世界」「可能的超越論世界」「現実的超越論世界」との対話的相互作用が必要である。2)多重のナラティヴのあいだを往還する対話:ナラティヴ研究者がアプローチする現 場 フィールドとナラティヴの質の差異も多重化すべきである。そこでナラティヴの現場を「実在レベル:当事者の人生の現場」「相互行為レベル:当事者と研究者の相互行為の現場」「テクスト・レベル:研究者によるテクスト行為の現場」「モデル・レベル:研究者によるモデル構成の現場」に分けて,それらを対話的に往還する図式モデルを構成した。3)「ナラティヴ・テクスト」と「対話的省察性」概念:対話的モデル構成において根幹となる二つの概念について,研究者がテクストと対話的に「語る」「読む」「書く」「省察する」行為と関連づけて考察した。テクストは,文脈のなかに埋め込まれていながら,相対的に文脈から「はなれる」(脱文脈化・距離化)ことによって,新しい「むすび」をつくり,物語の生成を可能にする。
2 0 0 0 OA 「意味の行為」とは何であったか? J. S. ブルーナーと精神の混乱と修復のダイナミズム
- 著者
- 横山 草介
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.205-225, 2018 (Released:2021-04-12)
本論の目的は,ブルーナーの「意味の行為」論本来の探求の射程を明らかにすることにある。ナラティヴ心理学 の展開におけるブルーナー受容においては,「意味の行為」は専ら物語を介して対象を「意味づける行為」とし て理解されてきた。だが,彼が本来の主張として訴えたのは,人間の意味生成の原理と,その機能の解明という主 題であった。これまでのブルーナー受容は,この論点を不問に処してきた傾向がある。これに対し我々は,ブルー ナーの「意味の行為」論本来の主題の解明に取り組んだ。我々の結論は次の通りである。ブルーナーの主張した 「意味の行為」とは,前提や常識,通例性の破綻として定義される混乱の発生に相対した精神が,その破綻を修復し, 平静を取り戻そうとする「混乱と修復のダイナミズム」の過程として理解することができる。この過程は,何ら かの混乱の発生に伴って生じた,今,この時点においては理解し難い出来事が,いずれ何らかの意味を獲得するこ とによって理解可能になるような「可能性の脈絡希求の行為」として定義することができる。最後に我々は,ブ ルーナーの「意味の行為」論は,心理学の探求による公共的な平和の達成という思想的展望を有することを指摘 した。この展望は特定の文化的脈絡の中で生きる我々が,他者と共に平穏な生活を営んでいくために精神が果た し得るその機能は何か,という問いと結びつくものであることが明らかとなった。
2 0 0 0 4人の震災被災者が語る現在:語り部活動の現場から
本研究は,4 人の震災被災者――庄野さん,浅井さん,長谷川さん,市原さん――が,阪神・淡路大震災の体験を語り継ぐための語り部活動(「語り部グループ117」)において,小中学生を対象に展開した語りを分析したものである。分析にあたっては,語りの「内容」よりも,むしろ,語りの「様式」に注目し,かつ,語り手個人の心理的特性よりも,むしろ,語りをめぐる集合性の動態に焦点をあてた。この際,個々の語りの「様式」を規定する存在として〈バイ・プレーヤー〉なる分析概念を提起した。その結果,4 人の語り手は同じ震災体験を語っているが,その様式がまったく異なっていることが見いだされた。具体的には,庄野さん,および,浅井さんの語りでは,語りの内部に登場する特定の人物が〈バイ・プレーヤー〉の役割を果たし,語り手本人と〈バイ・プレーヤー〉との間で生じる視点の〈互換〉が語りの基本構造を規定していた。他方で,長谷川さんの語りでは,聞き手が〈バイ・プレーヤー〉の役割を果たし,市原さんの語りでは,「神戸の街」という集合体全体が〈バイ・プレーヤー〉となっていた。同時に,4 つの語りとも,仮定法の話法によって視点の〈互換〉が聞き手へと展開していた。さらに,〈バイ・プレーヤー〉のあり方にあらわれた語りの「様式」のちがいが,各人のライフストーリーの構成様式のちがい,ひいては,生活世界の再構造化に見られるちがいを反映していること,および,語り手のみならず,聞き手や語りの対象となる人物,事物などをも包含する語りをめぐる集合性の動態分析を通じて,語りの固有性へのアプローチが可能となることを示唆した。