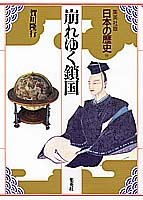1 0 0 0 OA Ernst MayrとWilli Hennig : 生物体系学論争をふたたび鳥瞰する
- 著者
- 三中 信宏
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.95-101, 2005-08-20 (Released:2018-03-30)
1 0 0 0 OA 街路形態及び街路樹が歩道に及ぼす熱的影響に関する実測研究
- 著者
- 高 偉俊 杉山 寛克 尾島 俊雄
- 出版者
- Architectural Institute of Japan
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.469, pp.53-64, 1995-03-30 (Released:2017-01-27)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 10 8
1. 概要 多くの都市における高密度な土地利用は路上の歩行者にとって不快な環境を作り出している。沿道に建てられた高い建物は冬には日射を遮断し、逆に夏の広い街路では、必要以上に日射を取得している。加えて、都市ではコンクリートやアスファルトヘの土地被覆の変化や人工排熱の増加により気温が高くなる。これらの都市の熱環境を改善するために様々な手法が用いられているが、街路樹を導入することが最も一般的に試みられている。特に冬の日射取得を妨げずに夏の日射遮蔽をもたらす街路樹の影響を街路の形態との関係を踏まえて把握することは歩行者の快適性を向上させるために重要である。そこで異なる季節において街路の形態と街路樹の有無による影響評価を行った結果、街路の形態が夏冬ともに大きな影響を及ぼしている一方で、街路樹は夏の熱環境緩和に効果的であることを示した。2. 実測方法 本研究では、街路の形態と街路樹が歩道上の熱環境にもたらす影響を夏と冬、24時間に渡って実測調査を行った。実測地点は図1に示す東京都新宿区の早稲田大学大久保キャンパス周辺の4地点。地点Aは南北街路で街路樹が約10m間隔にある。地点B、C、Eは東西街路上に位置し、地点Bは街路樹のない狭い街路、地点Cは緑化道路で両側の歩道沿いと道路中央に街路樹の樹冠が連続している。地点Dは道路の両側に街路樹の樹冠が連続している。実測地点Aは西側歩道、地点B、C、Dは北側歩道上に位置し、路面の素材はアスファルトであった。実測は1993年8月23日〜24日、1994年2月23日〜24日、各地点は共通して地上1.2mの高さにおいて移動計測によって気温、湿度、風速、歩道の表面温度、壁面温度をアスマン乾湿度計、熱線式風速計、赤外線放射温度計を用いて測定した。所要時間は24時間を通じて各々20〜25分であった。3. 実測結果 3-1. 冬の実測結果 図3に気温の日変化を示す。東西方向の広い街路にある地点Dが日中最も高く最高気温は12.5℃であった。一方で、狭い街路にある地点Bが一番低く、最高気温は10.5℃であった。しかしながら夜間は地点Bが地点Aを除いて高くなる傾向を示した。これは地点Bの天空率が低いことから夜間の放射冷却が抑えられているためと考えられる。また地点Cと地点Dの最高気温の差は天空率に起因している。図4では東西街路に位置する地点B、C、Dについて日射量を計算した。これより地点Dの日射量が最も多く、地点Bが最も少ない。つまり地点Bが他の地点と比べて気温が低くなるのは、取得する日射量が少ないからである。またほぼ同じ幅員の街路方位の異なる地点Aと地点Dを比較すると最高気温では地点Dの方が高いにもかかわらず、平均気温でみると地点Aの方が高い。これは日中を通じて南北街路の方が東西街路より日射を多く受けていることが日平均気温の上昇につながっていると思われる。図5は歩道の表面温度を示す。最高温度は地点Dで24℃、最低温度は地点Bで-1.5℃であった。日中は地点間の温度差が大きいが、夜間にはその差は縮小した。日中の最高温度は地点Cと地点Dでは13時付近でみられたが、地点Bとは1時間の時差があった。また地点Aでは直達日射を午前中にのみ受けていたために最高温度は12時付近でみられた。図6と図7には東西街路の壁面温度を示す。表面温度差は日中において顕著にみられ、直達日射をほとんど受けない南壁では温度差は小さく、天空率の最も高い地点Dが夜間において壁面温度が最も低くなった。しかしながら、北壁については地点BはH/W1.33で狭い街路であることから日射が遮断され最も低い壁面温度を示した。図8は湿度の日変化を示す。湿度は午後低くなり、夜間に上昇する傾向がみられたが、地点間の差は認められなかった。図9は風速の日変化を示す。地点Dのような広い街路では風速か弱くなるような傾向がみられた。一方では地点Bのような狭い街路では風速が強くなる傾向がみられた。3-2. 夏の実測結果 気温の日変化を図11に示す。夏には地点Bが日中を通じて気温が高く、地点Aと同様の変化を示す。これに対し、地点C、Dは平均気温で0.6-0.7℃、最高気温で1.7-2.0℃低くなり、街路樹の日射遮蔽により、気温を緩和する効果が認められる。図12は歩道上の表面温度の日変化を示す。街路樹によって覆われている地点Cは他の地点と比較して最高で約15℃低い。また、平均でみると街路樹がある地点の表面温度の方が街路樹のない地点と比較して約5℃低くなる。湿度の日変化を図13に示す。街路樹のある地点C、Dは街路樹のない地点Bと比較して僅かながら湿度が高くなる傾向がみられた。図14には風速の日変化を示す。冬と同様に地点Bは他の地点と比較して風速が最も強くなる傾向にあった。4. 考察 図15は気温と歩道の表面温度の関係を示す。夏と冬の結果は、街路空間の気温が歩道の表面温度と高い相関関係にある。気温と街路の形態との関係については冬のデータを用いて、地点Bと地点C、Dの間で検討した。その結果、図16に示すように日中は地点C、Dが地点Bに比べて気温が高くなるが、夜間にはむしろ地点C、Dが地点Bに比べて気温が低くなった。これは広い街路は日中では日射を多く取得するが、逆に夜間には狭い街路に比べて放射冷却しやすいことを示している。図17は街路樹の気温に対する影響を示す。地点C、Dは地点Bに比べて最高で1.7から2.0℃低く、街路樹は日射を遮蔽することにより、日中の熱環境を緩和する効果が明らかである。一方で夜間には地点Cは地点Bとほぼ同じもしくは僅かながら気温が高くなる。これは地点Cが低い天空率にも表れているように街路樹によって覆われ、夜間の放射冷却が抑えられていると考えられる。また地点Dは街路樹があるにもかかわらず、地点Bに比べて天空率が高いために気温が低く推移したとみられる。5. 結論 本研究は街路樹と歩道上の熱環境との関係を夏と冬の実測調査により次のような成果を得た。(1)街路形態の影響について冬の結果を解析すると街路の幅員が広いほど取得する日射量が多くなり、日中の気温が高くなる。(2)夜間の気温は主に天空率によって影響され、狭い街路ほど広い街路に比べて気温が僅かながら高くなる。(3)夏の結果からは街路樹により最高で気温が約2℃緩和されることがわかった。つまり、街路樹の量によって気温は低下し、街路樹か歩道の熱環境の緩和に非常に効果的であることが確かめられた。(4)気温は歩道の表面温度と高い相関関係にあり、歩道の表面温度が低くなると、気温も低くなる傾向にあった。一方で街路樹は歩道の表面温度に対して大きな影響を及ぼしている。つまり街路樹の緩和効果は主に歩道の表面温度の低下によって表れ、結果として気温の低下につながっているといえる。
1 0 0 0 OA 縫製機械分野におけるコンピュータ化
- 著者
- 村田 邦彦
- 出版者
- The Textile Machinery Society of Japan
- 雑誌
- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.P238-P248, 1996-04-25 (Released:2009-10-27)
- 著者
- 山東 愛美
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.39-51, 2019-11-30 (Released:2020-06-16)
- 参考文献数
- 43
本研究は,変容や多様化が指摘されている日本のソーシャルアクションをめぐる現状を整理するとともに,その背景要因を理論面から明らかにする.まず先行研究からソーシャルアクションのプロセスに関する記述を抜粋して類型化を行った.その結果,署名,陳情,裁判等の行動を伴うダイレクトアクションと,交渉や調整等を特徴とするインダイレクトアクションの二つの類型があることを確認した.また,ソーシャルアクションの概念が日本に導入された当初はダイレクトアクションとして理解されていたが,近年は,インダイレクトアクションが主流となり,両者が併存していることが明らかとなった.その理論的な背景要因として,ソーシャルワークの統合化とエンパワメントについての日本的な捉え方がある.今後は,ソーシャルアクションの2類型をふまえたさらなる研究の蓄積や,ソーシャルワーカーの役割分担を念頭においた実践モデルの構築が求められる.
1 0 0 0 OA ペニシリン製剤により著明な皮疹を来たした伝染性単核球症の一例
- 著者
- 伊藤 香子 松川 雅也 橋本 直明 高倉 裕一 関川 憲一郎 松浦 広 江藤 隆史 岸田 由起子 山崎 一人 薬丸 一洋
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.2, pp.207-210, 2005 (Released:2005-06-06)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 大東京區分圖三十五區之内赤坂區詳細圖
1 0 0 0 OA VR2.0の世界
- 著者
- 廣瀬 通孝
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.11, pp.785-793, 2018 (Released:2022-01-12)
1 0 0 0 OA 法政大学での50年
- 著者
- 田中 優子
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.9-24, 2021-03
1 0 0 0 OA VE酔い評価手法の開発に向けての基礎的検討
- 著者
- 中川 千鶴 大須賀 美恵子 竹田 仰
- 出版者
- Japan Human Factors and Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.131-138, 2000-06-15 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 6 5
近年, 仮想環境 (Virtual Environment: VE) の技術は著しく進歩しており, 多くの分野で普及しつつあるが, 一方で, VEシステムの利用時・利用後に生じる「酔い」の問題が顕在化し, その低減や防止策が強く望まれている. そこで, 我々は, VEシステム利用時の嘔吐に至らない程度の軽度の「酔い」を簡便かつ客観的に評価する手法を検討した. 13名の健常成人を被験者に用い, 黒い3次元空間に白いドットがランダムに分布している仮想空間内を移動する映像を刺激として用い, 暗室内の70inchの画面に提示して最大15分暴露した. この間の心電図, 呼吸などの生理反応を収集し, これらから得られる指標値と「酔い」の程度の主観評価との関係性を調べた. その結果, 軽度の酔いが発症した場合に, 呼吸周波数と心拍変動の0.1Hz近辺の成分が低下するという特徴的な現象がみられた. これらは, 他のストレス事態における生理反応パターンと異なるものであり, VEによる軽度の「酔い」の評価指標として用いられる可能性が示された.
1 0 0 0 OA 國語史研究資料としての聲明
- 著者
- 橋本 進吉
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教研究 (ISSN:18843441)
- 巻号頁・発行日
- vol.1929, no.32, pp.140-150, 1929-03-01 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 古戦場 : 秋田の合戦史
- 著者
- 秋田魁新報社地方部 編
- 出版者
- 秋田魁新報社
- 巻号頁・発行日
- 1981
1 0 0 0 情動や運動の記憶保持機能を基盤とした次世代語彙学習システムの設計
- 著者
- 福嶋 政期
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 さきがけ
- 巻号頁・発行日
- 2016
記憶に関する神経生理学や心理学の最新の研究成果により、人が新たな出来事や言語を記憶する際に、「情動(感情を含む)」や「運動」がその事象の五感覚情報を長期記憶として保持させることが明らかになりつつあります。本研究は、この情動や運動の記憶保持効果とVR・AR技術を統合し、人の記憶に効果的に介入する新たな語彙学習の潮流を創ることを目指します。