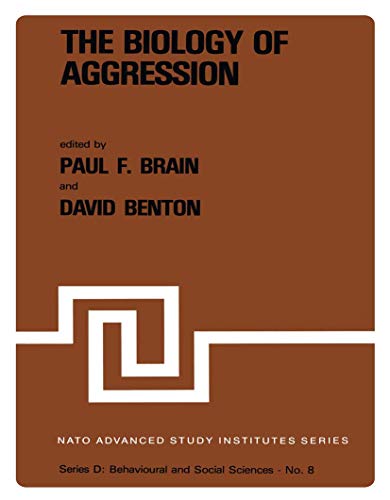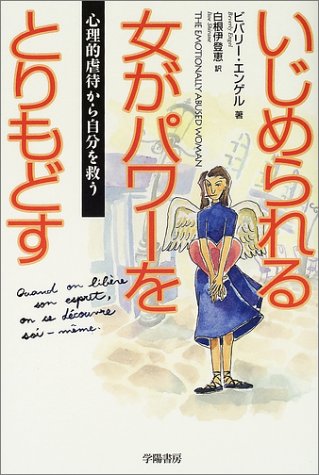- 著者
- 大島 優香
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.7, pp.257-262, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
化学構造検索による特許検索において,索引系データベースはその化学物質索引の信頼性と検索機能の利便性から必須である。一方,全文系特許データベースでは,索引系データベースでは索引されなかった化学物質の検索ができること,タイムラグ無く検索できることが実証できた。特に出願前先行技術調査や無効化資料調査の場面での活用が期待できる。全文系特許データベースの化学物質切出しは,システムにより異なる。そして,正確性の観点で,現時点で,どのシステムにおいても不十分と言える。今後の化学物質辞書の充実やAI技術の進展等により,正確な化学物質切出しに期待する。
1 0 0 0 進化するWIPOのPATENTSCOPE
- 著者
- 坪内 優佳
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.7, pp.251-256, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
PATENTSCOPE特許検索サービスは,世界知的所有権機関(WIPO, World Intellectual Property Organization)が無料で提供する特許文献検索サービスで,1億200万件以上(2022年3月末時点で)におよぶ特許文献を検索・閲覧することができる。2021年3月からは一部の非特許文献の検索も可能となり,同年9月からは化学化合物検索に関し,マーカッシュ構造の検索機能も追加されるなど,PATENTSCOPEは進化を続けている。本稿では,進化を続けるPATENTSCOPEについて,その特徴や最新機能も含めた全体像を紹介する。
1 0 0 0 特許調査におけるAI検索と概念検索の有効活用
- 著者
- 安藤 俊幸
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.7, pp.245-250, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
最近では知財情報業務への人工知能(AI: Artificial Intelligence)の適用も身近な存在になってきている。商用のAIを利用した特許調査ツールも複数登場している。ただ,これら商用のAI調査ツールをユーザーが使いこなす上で押さえておくべき基本事項や限界・課題も多いのも現実である。本報では,特許調査でのAI活用について,過去の概念検索の導入過程を振り返り,概念検索とAI検索との比較を,特許調査と機械学習の観点から特許調査システムのユーザーの立場として述べる。また,現在の深層学習(第3世代AI)の限界も指摘され,第4世代AIと言うべき提案もなされている。商用のAI利用特許調査システムにおいても,第4世代AIを目指すツールが出現しており注目している。
1 0 0 0 深層ニューラルネットによる自動翻訳の革命
- 著者
- 隅田 英一郎
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.7, pp.232-237, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
深層ニューラルネットの登場によって人工知能の実用化が様々な分野で進んでいる。自動翻訳はその典型的な成功事例である。2016年以降の深層ニューラルネットによる自動翻訳の高精度化は革命的である。汎用だけでなく分野特化型もあり,多くのサービスが上市され,加速度的に普及し始めている。高精度化の背景にある自動翻訳の固有の事柄を説明し,自動翻訳を一層高精度にするために研究者以外が大きく貢献できることを述べる。また,自動翻訳が音声技術と連携することによって可能となる,逐次通訳と同時通訳の自動化についても現状と展望を述べる。
1 0 0 0 特集:「特許調査を取り巻く技術の進展」の編集にあたって
- 著者
- パテントドキュメンテーション委員会
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.7, pp.231, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
「AIを用いた特許検索」を掲げて「KIBIT」が登場して大きな話題を呼んだのが2015年のことでした。それ以降,様々な検索システムがAIを前面に打ち出した拡張機能を搭載しており,今日ではAIを使った特許検索や特許分析,IPランドスケープ作成等を日常の調査業務に取り入れておられる方も少なくないことと推察いたします。重ねてAI技術の発展は自動翻訳や自動分類などの技術にも波及し,これらの技術が特許調査の領域でも使われ始めていることはご承知の通りです。化合物調査の分野でも,従来のように人の手により化合物構造式を索引してデータベース化するのではなく,AIが自動的に特許全文から化合物名称や構造式を取り込んで索引を作成する手法が提案され,実装が進んでおります。これらAI技術を核とした様々な機能の追加により,特許調査実務はまさに今,転換点を迎えていると言っても過言ではないと思います。本特集号は,これらの新しい手法に関する基本的知識や使用に際して留意すべきことをまとめて,特許調査に関わる皆様のお役に立てればという思いで企画しました。また,新しい調査・解析手法を日々研究しているエンドユーザー協議会様の研究成果の一端を紹介することで,最新の検索技術に対する知見を深めていただくことも企図しております。最初にAI自動翻訳の第一人者でおられる国立研究開発法人情報通信研究機構フェローの隅田英一郎氏に,自動翻訳の基本と同時通訳への適用を見据えた今後の展開について,初心者にもわかりやすく解説していただきました。第二稿は一般財団法人日本特許情報機構の長部喜幸氏に,中国特許のAI翻訳と自動分類についてSDGs特許を分類した実例を挙げてご紹介いただきました。第三稿は,アジア特許情報研究会の安藤俊幸氏に,AIを用いる特許調査と概念検索の利用に際する留意点をご提案いただきました。第四稿はデータベース提供の立場から世界知的所有権機関(WIPO)の坪内優佳氏に,WIPOが公開している「PATENTSCOPE」について解説いただいております。第五稿は日本アグケム情報協議会の大島優香氏に,第六稿は日本FARMDOC協議会の小島史照氏に,それぞれの協議会がユーザー視点で取り組まれた化合物検索システムの研究成果をご紹介いただきました。なお,化合物検索については各稿で取り上げた以外にも各種システムがありますが,今回は事例紹介の位置づけですので,全ての検索システムに言及してはおりませんことをご承知おきください。最終稿は日本EPI協議会の田中厚子氏に,IPランドスケープの事例として協議会での研究事例をご紹介いただいております。いずれの論文も読み応えがあり示唆に富んだものとなっております。皆様の日々の調査実務のご参考になれば幸甚です。INFOSTAパテントドキュメンテーション委員会
1 0 0 0 OA ターゲット反応を誘起する錯体化学的スマートデザイン
- 著者
- 松本 崇弘
- 出版者
- 公益社団法人 石油学会
- 雑誌
- Journal of the Japan Petroleum Institute (ISSN:13468804)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.134-139, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
- 参考文献数
- 42
錯体化学は,長い歴史の中で,経験則 · 物理化学 · 量子化学に基づく金属錯体のデザイン合理性「錯体化学的スマートデザイン」を確立してきた。これまでに報告されてきた数多くの金属錯体は,論理的に説明可能な設計原理に基づいて,その機能や性質の発現機構を理解することができる。本論文では,ターゲット反応を誘起するデザイン合理性により達成したいくつかの代表的な研究,特に酸素 · 水素 · メタンの変換反応について解説する。酸素を酸化剤とする芳香族環の水酸化 · スチレンのエポキシ化 · C–H結合の酸化は,二核銅酸素錯体を合理的にデザインすることで誘起させることができる。水素の酸化と酸素の還元は,二核ニッケル · 鉄錯体のバタフライ構造によって促され,水素燃料電池の電極触媒への展開も可能とした。酸素を用いるメタンの変換は,有機ルテニウム錯体に光エネルギーをインプットすることで発現する高い酸化力によって達成している。
- 著者
- 大澤 英昭 広瀬 幸雄 大友 章司 大沼 進
- 出版者
- 一般社団法人 日本リスク学会
- 雑誌
- リスク学研究 (ISSN:24358428)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.235-247, 2022-03-25 (Released:2022-04-22)
- 参考文献数
- 39
This study examined effects of a management strategy and of site selection process for high-level radioactive waste disposal on acceptance of siting repository in a German case. Data from 1,000 German residents, assigned by population composition ratio of 16 states, were collected in 2018 by internet survey. We considered evaluation of two policies: management strategy and site selection process. We also hypothesized own and national evaluations of the policies were relevant factors on the acceptance of siting repository. Results indicated that own evaluation of management strategy and site selection process directly had an effect on acceptance of siting repository, while own and national evaluation of management strategy had effects on own and national evaluation of site selection process, respectively. In addition, latent variables affected by the policies were different depending on which policy and/or which evaluation. National evaluations of both policies had effects on personal benefit, while own evaluations of both policies had effects on social benefit. Own evaluation of management policy had an effect on intergenerational subjective norms, while national evaluation of site selection process has an effect on stigma.
1 0 0 0 OA マイクロ水力発電の事務所ビル等への適用
- 著者
- 酒井 孝寿
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.266-270, 2012-04-10 (Released:2014-09-01)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 近世実録全書
- 著者
- 早稲田大学編輯部 編
- 出版者
- 早稲田大学出版部
- 巻号頁・発行日
- vol.第3巻, 1918
1 0 0 0 OA 簡単に分子模型や結晶模型を製作する研究 : 1. 紙で折り出す安価な方法
- 著者
- 田村 通和 M. Tamura
- 雑誌
- 中京大学教養論叢 = Chukyo University bulletin of the Faculty of Liberal Arts (ISSN:02867982)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.231-250, 1977-08-30
1 0 0 0 The biology of aggression
- 著者
- edited by Paul F. Brain and David Benton
- 出版者
- Sijthoff & Noordhoff, 1981
- 巻号頁・発行日
- 1981
1 0 0 0 OA 正定値行列の実用的な判別法について
- 著者
- 李 磊
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.91-96, 1997-03-15 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
This paper presents some practical criteria for the positive definite matrices. They are applicable to wider situations and are easy to check than other criteria now in common use.
- 著者
- 木村 直弘
- 出版者
- 宮沢賢治学会イーハトーブセンター
- 雑誌
- 宮沢賢治研究annual (ISSN:0917334X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.93-105, 2014-03-31
- 著者
- 鉄谷 龍之 西山 忠良 高野 真矢 石井 信夫 安藤 元一
- 出版者
- 森林野生動物研究会
- 雑誌
- 森林野生動物研究会誌 (ISSN:09168265)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.19-25, 2018-03-30 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 23
静岡県伊東市に生息する特定外来生物アムールハリネズミErinaceus amurensisについて,2007年,2008年,および2012年の6月から11月までの期間に,手捕りによってゴルフ場3カ所と公園1カ所で捕獲された113個体の胃内容物を分析した.胃内容物は地表性の昆虫類が大部分を占め,1個体当たりの餌品目数(平均±SD)は3.2±1.3であった.出現頻度では,芝生の害虫としてよく見られるスジキリヨトウSpodoptera depravataの幼虫をはじめとするチョウ目Lepidoptera(81.4%)が最も多く,オサムシ科Carabidae(15.0%),シデムシ科Silphidae(11.5%),コガネムシ科Scarabaeidae(17.7%)などのコウチュウ目Coleoptera(74.3%),バッタ目Orthoptera(20.4%),ハチ目Hymenoptera(15.9%)がそれに次いだ.胃内容物中におけるコウチュウ目とチョウ目の幼虫の増減と発生の季節変動が同様であることから,アムールハリネズミに餌の選好性はないと考えられる.捕獲時間ごとの胃内容物の乾燥重量は夜間を通じて増加したことから,本種は夜間を通じて採食していると考えられる.
1 0 0 0 いじめられる女がパワーをとりもどす : 心理的虐待から自分を救う
- 著者
- ビバリー・エンゲル著 白根伊登恵訳
- 出版者
- 学陽書房
- 巻号頁・発行日
- 2002
1 0 0 0 OA 心理的虐待と非行 : 少年院での家族への働き掛け
- 著者
- 浅野 正
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 人間科学研究 = Bulletin of Human Science (ISSN:03882152)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.141-148, 2014-03-01
Previous research has indicated that emotionally abusive parenting, which includes neglect, rejection, hostility, anger, and psychological control, is associated with juvenile delinquency. Prevention programs are known to effectively reduce child abuse by enhancing the emotional relationship between parents and children and improving parents' ability to control their children. Since the Juvenile Training School Act was revised, new educational activities involving both juvenile delinquents and their parents have been conducted in juvenile training schools. This article explores how educational activities should be conducted to effectively reduce emotional abuse and prevent future reoffending. Programs to prevent child abuse are effective at reducing child abuse, so the skills they teach should be actively utilized in educational activities conducted by training school staff when dealing with abusive parents and abused juveniles.
1 0 0 0 恋をしてみて : 他二篇
- 著者
- アンドレ・ジイド 著
- 出版者
- 改造社
- 巻号頁・発行日
- 1937
- 著者
- 兼村 晋哉 BRAATHEN JOHANNES ALF
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2018-10-12
本研究では拡張ヒッグス模型で結合定数に対する2ループレベルの精密計算等を行う事により、将来実験を用いて電弱対称性破れの機構を解明するとともに標準理論を超えた新物理を探求する。ヒッグス粒子は発見されたが対称性の破れの根幹のヒッグスポテンシャルは未検証である。その構造と性質は新物理と密接に関連する。例えば電弱バリオン数生成シナリオでは強い一次的相転移が要求される為拡張ヒッグス模型が必要になるが、一次相転移が実現する場合には数10%の1ループ補正がヒッグス自己結合(3点結合)に現れるので、将来加速器で検証できると期待される。本研究は世界で初めて拡張ヒッグス模型の3点結合を2ループで計算する。重力波による1次相転移の検証可能性等も研究し、多角的にヒッグスポテンシャルに迫るタイムリーで重要な研究である。ニュートリノ質量や暗黒物質を同時説明する新模型を各種実験により絞り込む研究も行う。2020年度は、新しく古典的スケール不変性を持つ拡張スカラー模型(NスカラーCSI模型とヒッグス2重項が2個含まれるCSIモデル)を研究を修士課程2年生の下田誠氏との3人の共同研究として実施した。2015年に受け入れ研究者が研究したC S Iモデルに関する1ループ計算の研究を精査し、ついで2ループレベルの摂動計算に進んだ。古典的スケール不変性に基づく理論では、自己結合に対する1ループ補正は模型の詳細によらず66%程度の補正となることが知られていたが、我々の今回の研究によって、2ループレベルの補正によって模型の詳細によるユニバーサリティからのずれが発生し、そのずれが20-30%になることを示した。成果は論文として出版し、世界各地で開催された国際会議やセミナー等で多数の研究発表をおこなった。