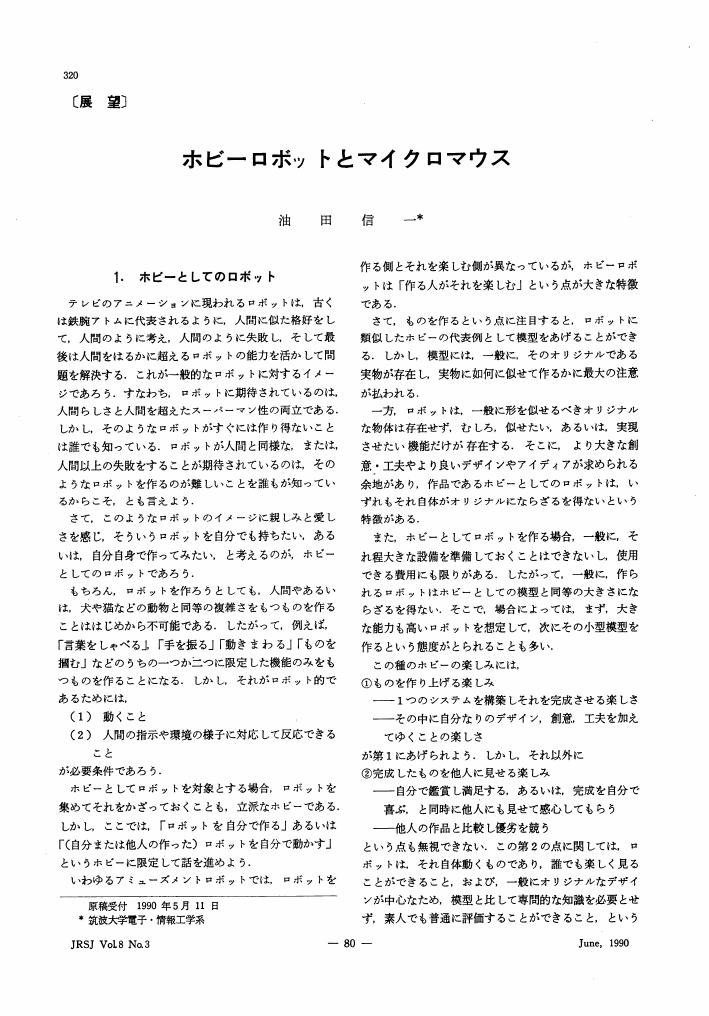1 0 0 0 第21回IUPAC化学熱力学国際会議(ICCT-2010)
- 出版者
- 一般社団法人 日本粘土学会
- 雑誌
- 粘土科学 (ISSN:04706455)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, 2009
1 0 0 0 OA ホビーロボットとマイクロマウス
- 著者
- 油田 信一
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.320-323, 1990-06-15 (Released:2010-08-25)
1 0 0 0 OA 伊那谷の地形面の編年と気候変動および地盤運動との関連
- 著者
- 松島 信幸 寺平 宏
- 出版者
- 飯田市美術博物館
- 雑誌
- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.171-198, 1999 (Released:2017-10-01)
1 0 0 0 OA 生態系改変者ヤンバルオオフトミミズによるササラダニの多様性維持機構
- 著者
- 金子 信博 榎木 勉 大久保 慎二 伊藤 雅道
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第52回日本生態学会大会 大阪大会
- 巻号頁・発行日
- pp.359, 2005 (Released:2005-03-17)
ヤンバルオオフトミミズによって作り出された地表面の微小生息場所に生息する小型節足動物群集,特にササラダニの群集構造を比較した.ヤンバルオオフトミミズは沖縄本島北部にのみ生息し,日本で初めて見つかった土壌穿孔表層採餌種(anecic)である.本種は地下約20cmに横走する坑道に住み,落葉を土壌表面の入口に集めた上で摂食し,土壌と混じった糞を出口に排泄する.糞塊は20cmほどの塔状になる.集められた落葉はmiddenと呼ばれている.照葉樹林は秋に一度に落葉が集中するのではなく,春と秋を中心に長い時間にわたって落葉が供給される.沖縄では気温が高いため,落葉の分解速度は高い.ミミズにとっては落葉を他の分解者に利用されないように自分の生息場所であるmiddenに集めていると考えられる.坑道やmiddenではミミズから供給される可溶性炭素や窒素が栄養源となって微生物の活性が高く,微生物バイオマスも多いと考えた. リターの堆積量は糞塊の周囲で最も多く,middenとミミズの影響のない土壌では差がなかった.ササラダニの個体数密度はリター層ではミミズの影響のない土壌できわめて少なく,middenと糞塊でほぼ同じ程度であった.一方,土壌層ではミミズの影響のない土壌で最も少なく,糞塊よりもmiddenでの密度が高かった.ササラダニの種数はミミズの影響のない土壌と糞塊で差がなかったが,middenではこれらの倍近い値を示した.これらのことからヤンバルオオフトミミズは落葉資源を移動させ,土壌と混合することによって地表面の微小生息場所の多様性を高め,ササラダニの密度と多様性を大きく高めており,生態系改変者として土壌生物群集に大きな影響を与えていた.
1 0 0 0 OA 序 おもしろい研究とは何か
- 著者
- 土井 健司
- 出版者
- 日本基督教学会
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.1-3, 2016 (Released:2018-02-22)
1 0 0 0 ヘドロは本当に肥料になるのか
- 著者
- 儀満 光紀
- 雑誌
- サイエンスキャッスル2016
- 巻号頁・発行日
- 2016-12-01
- 著者
- 北野 秋男
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.1-9, 2015-09-12 (Released:2017-08-10)
- 被引用文献数
- 1
現代アメリカの学力向上政策は、1990年頃を境に「ハイステイクス・テスト」「タフ・テスト」と呼ばれる学力テストの結果に基づく教育アカウンタビリティ政策の具現化を特徴とする。M.フーコーは、「規律・訓練のすべての装置のなかでは試験が高度に儀式化される」(フーコー,1977: 188)として、試験が生徒を規格化し、資格付与し、分類し、処罰を可能とする監視装置となることを指摘したが、今や学力テストは児童・生徒を評価・監視するだけではない。学区・学校・教師をも評価・監視する装置へと変貌している。本論文で指摘する学力テストの「暴力性(violence)」とは、学力テストの実施と結果を利用した「抑圧」「統制」「管理」という「権力性(gewalt)」を意味するものであり、それは連邦政府や州政府によってもたらされた全ての児童・生徒、学区・学校・教員に対する脅威となるものである。
1 0 0 0 メンズ・ル-ム (現代建築批評の方法--身体/ジェンダ-/建築)
- 著者
- Edelman Lee 滝本 雅志
- 出版者
- INAX
- 雑誌
- 10+1
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.130-142, 1998-08
1 0 0 0 OA 日本コミュニティ心理学会 第17回大会 倫理委員会企画講演 職業倫理とコミュニティ心理学
- 著者
- 村本 詔司
- 出版者
- 日本コミュニティ心理学会
- 雑誌
- コミュニティ心理学研究 (ISSN:13428691)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.37-49, 2015-08-31 (Released:2019-04-23)
- 参考文献数
- 9
Helping professional ethics, traditionally functioning within the framework of individualism, needs to be reconsidered in terms of community psychology. Its basic concepts such as decision making, moral agent and profession, usually defined in rationalist outlook, must integrate irrational factors mostly associated with community life. Both professional ethics and community psychology are expected to be theoretically elaborated by communitarianism, and now invited to meet challenges of increasingly dominant intellectual trends in the world today: social contract theory and neoliberalism. Finally, community psychology may adequately contribute to the coping with problems, especially on the management of boundaries, facing professionals practicing in small communities.
1 0 0 0 日本列島の氷河・氷河地形研究史と展望
- 著者
- 青木 賢人
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.291, 2011
現成の氷河が存在せず(とされていた),氷河地形の分布範囲も広くなく,そのアプローチも悪い日本列島において,非常に多くの氷河地形研究が蓄積されてきた.その研究史については,岩田(2010)において既に,時系列,テーマ別に精緻に整理されており,1936~2010年の間に公表された400本を超える報文がリスト化されている(岩田編,2010).「1970年代に活動した研究者たちに育てられた新しい世代の大学院生」であった演者らには,これらの研究史を整理し,次の課題を見出す責務が課されたといえよう. 本発表では,これらの日本列島の氷河地形に関する研究を,その指向性から「地域研究としての氷河地形研究」と「基礎研究としての氷河地形研究」とに整理し,それぞれについて,今後の研究課題に関する展望を述べてみたい.
1 0 0 0 OA 七ケ宿ダム管理用発電所の計画・設計について
- 著者
- 渡辺 勝 今田 晃
- 出版者
- Japan Society of Dam Engineers
- 雑誌
- ダム工学 (ISSN:09173145)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.22, pp.57-68, 1996-06-15 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 5
七ヶ宿ダム管理用発電所は、ダム放流水と水道用水を利用し両掛水車により発電するもので、平成4年4月より運転を開始し、その発電出力は3,600kWで全国のダム管理用発電所の中でも最大の規模を誇っている。発生電力はダム管理用として使用し、余剰電力は一般電気事業者に供給することにより、ダム管理費用の節減につながっている。近年、ダムの取水設備は、その取水目的と水質問題等に対応するため専用の取水設備を設置していることから、別系統で取水された水力エネルギーの効率的発電方法として両掛水車は有効な方法である。
- 著者
- 吉崎 弘之 相場 キミイ 内海 聡
- 出版者
- 日本精神科看護技術協会
- 雑誌
- 日本精神科看護学会誌 (ISSN:09174087)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.396-400, 2003
1 0 0 0 OA ミカヅキゼニゴケ雌器床の形態と同種の有性生殖に関する研究
- 著者
- 赤司 一
- 出版者
- 日本蘚苔類学会
- 雑誌
- 蘚苔類研究 (ISSN:13430254)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.6, pp.163, 2021 (Released:2021-07-06)
1 0 0 0 OA 朝鮮鉱物誌
- 著者
- 朝鮮総督府地質調査所 編
- 出版者
- 三省堂
- 巻号頁・発行日
- 1941
1 0 0 0 OA 透析低血圧と生命予後 多施設前向き共同研究 第47回日本透析医学会ワークショップより
- 著者
- 勝二 達也 椿原 美治 藤井 正満 今井 圓裕 中之島Study group
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.1181-1182, 2003-06-28 (Released:2010-03-16)
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 中学校における抽象絵画の指導についての一考察 ―類型化の試み―
- 著者
- 山竹 弘己
- 出版者
- 大学美術教育学会
- 雑誌
- 美術教育学研究 (ISSN:24332038)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.337-344, 2019 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 6
本研究の目的は,抽象絵画の教育効果を検証し,授業への活用を促進することにある。抽象絵画の実践はこれまで難解なイメージから中学校現場では敬遠されることが多かった。そこで,中学校現場で指導の指標となることを期待した。本稿では抽象絵画を抽象形の形成方法によって3つに類型化し,形成方法別に学習支援することで,抽象絵画への理解を深めたかを検証している。また,主題と抽象形・色・構図を結びつけて視覚化したり,感情移入したりする様子を考察することで,「見立て」や「置換」がそれらへの意味づけ,価値づけにどのように関与しているかを明らかにし,「見立て」や「置換」の有効性も検証した。考察では,生徒感想から抽象形の形成方法による抽象絵画の類型化と「見立て」と「置換」の理解,さらに形成方法別の支援が生徒の抽象絵画の理解に深く寄与していることを明らかにしている。
- 著者
- 佐々木 康
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号
- 巻号頁・発行日
- vol.47, 1996
1 0 0 0 OA 報告 : 「少女漫画」と「イラスト」の関係についての予備的考察
- 著者
- 秦 美香子 Mikako HATA 花園大学文学部 Faculty of Letters Hanazono University
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.25-38,