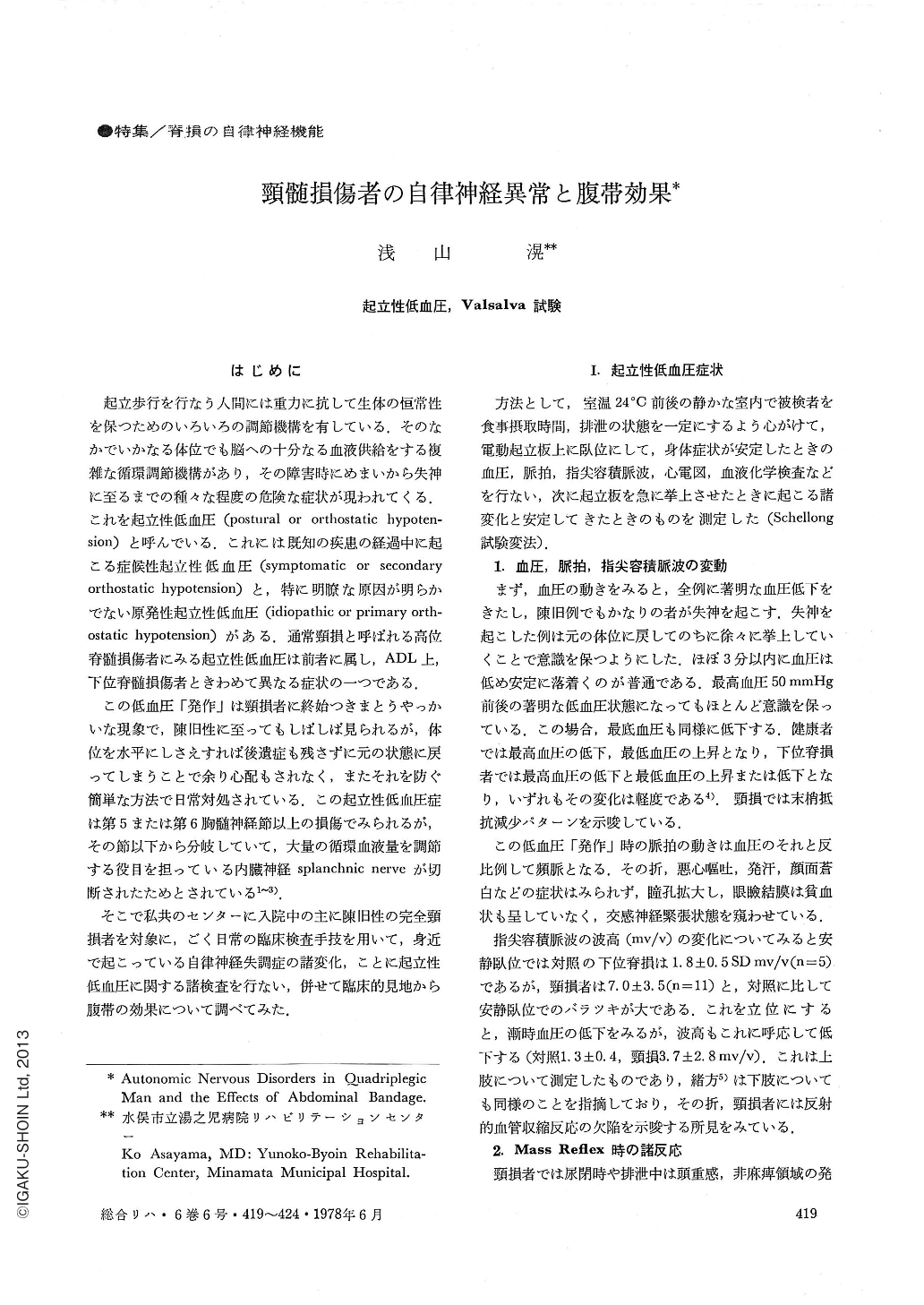1 0 0 0 大杉谷国有林の施業変遷史
1 0 0 0 OA 越谷市における廃棄物行政に関する一考察
- 著者
- 浅井 勇一郎
- 出版者
- 獨協大学環境共生研究所
- 雑誌
- 環境共生研究 = Studies on environmental symbiosis (ISSN:1882787X)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.87-99, 2020-03
- 著者
- 岡本 芳晴 山下 真路 大﨑 智弘 東 和生 伊藤 典彦 村端 悠 柄 武志 今川 智敬 菅波 晃子 田村 裕
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会
- 雑誌
- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.408-412, 2020-01-15 (Released:2020-01-16)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
2010年,我々はインドシアニングリーン(ICG)をリン脂質成分に結合させたICG修飾リポソーム(ICG-lipo)を開発した.今回,動物の自然発症腫瘍38症例に対して治療成績を評価した.治療はICG-lipo(抗がん剤等内包)を点滴投与後,半導体レーザー装置を用いて患部に10~20分間光照射した.照射間隔は毎日~週3日で実施した.Response Evaluation Criteria in Solid Tumors(RECIST)に基づく判定結果は,CR(Complete response):3例,PR(Partial response):13例,SD(Stable disease):18例,PD(Progressive disease):4例,だった.奏効率(CRおよびPRの割合)および有効率(CR,PR,SDの割合)は,42.1%および89.5%だった.特にリンパ腫の奏功率は85.7%と高値を示した.2症例以上ある腫瘍で,リンパ腫,血管肉腫以外は有効率が100.0%を示した.本治療を実施することにより,約半数の獣医師が一般状態の改善を認めた.このことは本治療法の有効性を示すものと思われる.
1 0 0 0 OA セルフ・モニタリング尺度に関する研究
- 著者
- 岩淵 千明 田中 国夫 中里 浩明
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.54-57, 1982-04-30 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 9 8
This study attempted to examine the internal structure of Snyder's Self-Monitoring (SM) scale. Factor analysis of SM scale yielded three factors: Extraversion, Other-Directedness, and Acting. In correlational analyses with other personality measures, Extraversion correlated positively with Maudsley Personality Inventory-E (MPI-E) scale and Self-Esteem scale and negatively with Social anxiety of Self-Consciousness (SC) scale. Other-Directedness correlated positively with Public Self-Consciousness of SC scale. Acting correlated positively with MPI-E scale. Extraversion factor was founded to discribe the behavior of extraverts. Other-Directedness factor was interpreted to be a concern for the appropriateness of social behavior. Acting factor was related to tactfulness and liking for speaking to and entertaining others. These three factors showed highly positive inter-correlations, and each factor had some degree of internal consistency. These findings suggested that the factorial structure of the SM scale was not unidimensional but multidimensional.
1 0 0 0 OA 3歳児における発達検査結果と診療に対する適応性との関連について
- 著者
- 中原 順子
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.458-468, 2007-09-25 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 39
著者は小児の診療に対する適応性を精神運動機能発達(以下,発達)という側面から調査してきた。今回は3歳児における精神運動機能の発達検査結果と診療に対する適応性との関連を調査する目的で,都内のA歯科医院へ来院した3歳児35名(男児18名,女児17名)を対象に,発達検査と歯科診療に対する適応性総合判定を行い,以下の結果を得た。1.歯科診療に対し適応性が高い小児ほど,発達指数100未満の発達検査領域をもつ割合は低かった。2.発達指数と歯科診療に対する適応性との相関がある領域は「基本的習慣」,「対人関係」,「発語」であった。3.治療に対する適応性総合判定結果から分類した「不適応群」「適応群」「高適応群」,各グループでの発達指数の平均値の差を検討した結果,「移動運動」で「高適応群」は「適応群」より有意に高い値を示し,「対人関係」で「高適応群」は「不適応群」より有意に高い値を示し,「発語」で「適応群」は「不適応群」より有意に高い値を示した。以上の結果から,発達検査をすることは,小児の診療に対する適応性を予測する上で有用な判断資料になると示唆された。
1 0 0 0 OA 魚類に嘔吐中樞は存在せざるか
- 著者
- 末廣 恭雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.6, pp.307-311, 1934-03-15 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
It is well known that fishes while jostling in the fishing net vomit their taken food during the manipulation of the fishing. Whether this vomiting is simply a mechanical disgorging due to the violent jostle of the fish in the net, or a real vomiting produced by the excitement of the nervous vomiting center as is observable in the case of higher vertebrates, is still unknown. Indeed, it has not yet been proved, whether the low class vertebrate, such as the fish, has the vomiting center, or not. The writer used apomorphine hydrochloride to test if fishes react to the emetic. 0.2-1.0 c.c. of its 0.5% solution was injected into the body cavity of various sea fishes, to which sufficient food had previously been given. The reaction was extremely remarkable; almost all the fishes thus treated vomited entirely their stomach contents soon after the injection of the emetic. The control experiment was also done by the injection of the distilled water. Negative reaction was, however, obtained. Since, thus, apomorphine hydrochloride is equally applicable as an emetic to the fish and it is the stimulant of the vomiting center in the higher vertebrates, the writer makes suggestion on the existence of the vomiting center in the fish.
1 0 0 0 頸髄損傷者の自律神経異常と腹帯効果
はじめに 起立歩行を行なう人間には重力に抗して生体の恒常性を保つためのいろいろの調節機構を有している.そのなかでいかなる体位でも脳への十分なる血液供給をする複雑な循環調節機構があり,その障害時にめまいから失神に至るまでの種々な程度の危険な症状が現われてくる.これを起立性低血圧(postural or orthostatic hypotension)と呼んでいる.これには既知の疾患の経過中に起こる症候性起立性低血圧(symptomatic or secondary orthostatic hypotension)と,特に明瞭な原因が明らかでない原発性起立性低血圧(idiopathic or primary orthosatic hypotension)がある.通常頸損と呼ばれる高位脊髄損傷者にみる起立性低血圧は前者に属し,ADL上,下位脊髄損傷者ときわめて異なる症状の一つである. この低血圧「発作」は頸損者に終始つきまとうやっかいな現象で,陳旧性に至ってもしばしば見られるが,体位を水平にしさえすれば後遺症も残さずに元の状態に戻ってしまうことで余り心配もされなく,またそれを防ぐ簡単な方法で日常対処されている.この起立性低血圧症は第5またば第6胸髄神経節以上の損傷でみられるが,その節以下から分岐していて,大量の循環血液量を調節する役目を担っている内臓神経splanchnic nerveが切断されたためとされている1~3). そこで私共のセソターに入院中の主に陳旧性の完全頸損者を対象に,ごく日常の臨床検査手技を用いて,身近で起こっている自律神経失調症の諸変化,ことに起立性低血圧に関する諸検査を行ない,併せて臨床的見地から腹帯の効果について調べてみた.
1 0 0 0 OA 研究資料 京都・神光院蔵 木造薬師如来立像
- 著者
- 皿井 舞
- 雑誌
- 美術研究 = The bijutsu kenkiu : the journal of art studies
- 巻号頁・発行日
- no.404, pp.69-81, 2011-08-30
The standing wooden image of Prince Shotoku (figure H. 76.3 cm), reveals workmanship superior to that seen in other examples of the subject. Nevertheless, the work has not been mentioned since the publication of photographs of the image in Ishida Mosaku, ed., Shotoku taishi sonzó shúsei [Photographs on Portraits of Prince Shotoku] (Kôdansha, 1976). The reason for this hiatus lies in the fact that by the time of the 1976 publication, the sculpture had changed hands, and the details of that transfer were long unknown. The author, however, obtained permission from the image'scurrent owner, Korinji, and was able to conduct a survey of the work. This article presents the detailed findings of that study with the aim of introducing this work as reference material for further research. It confirms that the image is in the style of the Araki-Azabu sect of the Shinran school of Pure Land Buddhism, and suggests that the work was created in the first half of the 14th century (late Kamakura period).
1 0 0 0 OA 那智発掘仏教遺物展観目録
- 出版者
- 東京帝室博物館
- 巻号頁・発行日
- 1928
1 0 0 0 IR インドにおけるサティー(寡婦殉死)の風習 : その宗教性と社会的背景
- 著者
- 西川 髙史
- 出版者
- 加計学園倉敷芸術科学大学
- 雑誌
- 倉敷芸術科学大学紀要 (ISSN:13443623)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.95-104, 2013
1 0 0 0 OA ドイツのギムナジウムにおける音楽教育 ―アビトゥーア試験問題を中心にして
- 著者
- 木戸 芳子
- 出版者
- 東京音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 = Bulletin of Tokyo College of Music (ISSN:02861518)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.21-37, 2018-02-28
1 0 0 0 OA 18) 3歳児をもつ父親の育児支援行動と母親の育児負担感との関連
- 著者
- 山口 咲奈枝
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.3_131, 2010-07-21 (Released:2019-07-12)
1 0 0 0 OA 印象形成過程の研究 (II)
- 著者
- 高橋 超
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 教育・社会心理学研究 (ISSN:0387852X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.61-69, 1970 (Released:2010-03-15)
- 参考文献数
- 15
本研究は, 印象形成過程における情報統合モデルとしての加算 (summation) -平均 (averaging) モデルの比較検討を行なったものである。被験者は, 市内の女子短期大学生68名で, 各Ssは, つぎの8 setの刺激情報を, 好意度の面から2つの20点評定尺度で判断した。(1) HH (2) LL (3) M+M+ (4) M-M- (5) HHM+M+ (6) LLM-M- (7) HHHH (8) LLLL得られた主な結果は, つぎのごとくである。1) HH-HHM+M+, LL-LLM-M-の各評定値の差を検討した結果, それぞれの差は有意でなかった。すなわち, 極性化した特性に, 中位に極性化した特性を加えても, 反応は増加せず, 平均モデルと一致した結果である。2) HH-HHHH, LL-LLLLの各評定値の差は, 後者についてのみ有意であった。すなわち, 刺激が増加すると, 反応も大となるset-size効果がみられる。3) 平均モデルの公式〔4〕に基づいて, HHHH, LLLLの予測値を求めて, 実測値と比較したが, ともに有意なずれはみられない。以上の結果は, いずれも平均モデルを支持するものであるが, 本研究では, 情報の質の差による統合化の差も伺がわれ, 今後, さらに綿密な分析が必要とされる。
1 0 0 0 抗RNP抗体
異常値の出るメカニズムと臨床的意義 いわゆる抗核抗体の抗原を検索する過程で,核成分抽出物の可溶性分画はENA(extractable nuclear antigen)と呼ばれた(→「抗ENA抗体」の項参照).そのうち,リボヌクレアーゼで処理すると患者血清との反応性が消失する抗原に反応する抗体(RNase感受性抗ENA抗体)のかなりの部分は,抗RNP抗体に相当する.RNP(ribonuclear protein)とは,mRNA,rRNA,tRNA以外に細胞内に大量に存在する低分子RNAと蛋白の複合体を指すが,そのうちのU1RNPという複合体を構成する蛋白(8サブユニット存在する)のうち3種類を抗原とする自己抗体が狭義の(一般的に用いる)抗RNP抗体に相当する.最近では定義を厳密にするために抗U1RNP抗体とも呼ばれる. 抗RNP抗体は混合性結合組織病(MCTD)の診断に必須とされているが,SLEをはじめとするその他の自己免疫疾患でも検出される.その存在はさほど特異的なものではないが,臨床像と照合するとある種の症候と相関していることを示唆する報告もいくつか存在し,興味深い点もある.
本研究の目的は、タイ北部で唯一の狩猟採集民と知られるムラブリを対象に、ムラブリの文化的特質を学際的なアプローチから明らかにすることで、今日の東南アジア山地研究(ゾミア論)の学問的空白を補うとともに、「森のゾミア」論を構築することである。この目的を達成するため、初年度は、2018年6月に富山国際大学にて共同研究者全員で本研究課題の内容と方向性を改めて相互に確認するとともに、それぞれの研究課題と研究調査スケジュールについて検討を行った。また、DropBoxを用いて本科研用のストレージを作成し、円滑な情報共有を行えるようにした。タイ北部ナーン県での現地調査は各研究者がそれぞれ実施し、自身の研究課題に沿った研究調査を行なった。人類学班は、遊動と社会性の関係について調査を行い、言語班はムラブリ語の方言差と語派内の特異性について調査を行なった。農学班はムラブリが利用する森の植物性資源について生態学的・栄養学的観点から調査を行うとともに、食用や医療用に用いられてきた有用資源の利用と効果の検証を行った。なお、これらの調査は、被調査者の同意を得て行われた。だが初年度は資料収集がメインだったこともあり、論文や学会発表を通じた成果の発表、そしてフィールドで得られた知見の理論化に十分な時間を割くことができなかったと考える。だが各自2回ほどの現地調査を行ったことで、予想もしていなかった新たな資料などを得ることが出来、調査の成果は十分にあったと考えている。なお、2019年3月には、フィールドにて共同研究者全員が集まり、初年度の成果を共有するとともに、2年目の予定について話し合った。
1 0 0 0 OA ブプレノルフィン持続皮下注入法による術後疼痛管理
- 著者
- 飯田 豊 鬼束 惇義 片桐 義文
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.36-39, 2010-01-15 (Released:2010-02-19)
- 参考文献数
- 10
当科では, 消化器外科手術後疼痛管理をブプレノルフィン持続皮下注入 (Bu皮下注) で施行している. 従来施行してきたモルヒネ持続硬膜外注入 (Mo硬膜外注) と比較検討したところ, 鎮痛効果, 補助鎮痛薬使用回数, ガス排泄までの日数には差を認めなかった. 膀胱内留置バルーン抜去までの日数はBu皮下注の方が短かった. 帰室時PaCO2はMo硬膜外注の方が高値であった. Bu皮下注でみられた副作用は投与中止により速やかに軽快した. Bu持続皮下注入は手技的にも簡便で安全であり, 呼吸抑制も少ないため有用な術後疼痛管理法である.
1 0 0 0 OA ムシ飼育のねらいとその飼育経験効果について : 幼稚園・保育園におけるムシの飼育の意味
- 著者
- 山下 久美 ヤマシタ クミ Kumi Yamashita
- 雑誌
- 人文・社会科学論集
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.79-98, 2006-03
Insects familiar to young children are very easy-to-handle educational material, being inexpensive and not being troublesome. Insects are being bred at many preschools. Thus, teachers were queried on the reason for breeding insects, and it was learned that breeding was for the purpose of "informing young children of the ecology of insects,""teaching them of the importance of life." and "nurturing in them the thoughtfulness for others." However, since a study has not been performed hitherto on whether or not insect breeding truly has an effectiveness on such matters, an interview survey was accomplished on 100 young children. In the replies of 30 children of a preschool which routinely bred insects, the effectiveness of insect breeding experience was clearly perceptible as a result of a comparison with the replies from 70 children of preschools which had never bred insects. Children of the preschool that bred insects had greater knowledge of insect ecology and were able to understand that once dead an insect could not be revived in comparison with children of preschools that did not breed insects. The sympathetic feelings of children towards insects that died were observed. Although a feeling of thoughtfulness toward children younger than themselves was also discernible, this matter requires additional research.
1 0 0 0 Spinopelvic harmony(PI-LL)
Spinopelvic harmonyとは,脊椎と骨盤において良好な矢状面アライメントの調和が得られている状態をいう.脊椎矢状面アライメント異常は腰痛や生活の質(QOL)の低下をきたす1).腰椎矢状面形態は骨盤形態によって規定されており,pelvic incidence(PI)は個人固有の骨盤形態を表す指標として重要である2).また代償の働いていない理想的アライメントは脊椎のみならず関節や軟部組織に対する最小負荷で立位姿勢を保持できると考えられ(cone of economy)3),脊柱変形に対する矯正手術においては理想的アライメントの獲得が目標とされる.Schwabら4)は無症候成人75例の検討で,PIによるlumbar lordosis(LL)の予測式としてPI=LL+9°を提唱,さらに成人脊柱変形術後患者125例の臨床成績を検討し5),sagittal vertical axis(SVA)>50mm,骨盤傾斜(pelvic tilt:PT)>20°とともにPI-LL>9°がoswestry disability index(ODI)約40以上となる指標となることを示し,“Harmony among spinopelvic parameters is of primary importance” と述べている.そして2012年,脊椎骨盤アライメントとhealth related quality of life(HRQOL)に基づく成人脊柱変形の指標として,Scoliosis Research Society(SRS)-Schwab分類が提唱された6).SRS-Schwab分類はSVA,PT,PI-LLをsagittal modefierとし,SVA>40mm,PT>20°,PI-LL>10°がsagittal deformityと定義され,これが現在の成人脊柱変形評価のスタンダードとなっている.しかし,腰椎前弯減少に対する体幹バランス不全の代償は骨盤後傾によってのみならず胸椎後弯減少や下肢関節屈曲によっても行われる.変形矯正手術により腰椎前弯を獲得してもreciprocal changeにより胸椎後弯が増強し矢状面体幹バランス不全が残存することもしばしば認められる.Roseら7)は矯正手術の指標として,胸椎カーブを含めたフォーミュラを提唱しており,Le Huecら8)はC7から膝屈曲による代償まで考慮したフォーミュラ[full balance integrated(FBI)technique]を提唱した.また,わが国においても,各年代のPTの予測式から理想的なPTを得るために必要なLLを算出する浜松フォーミュラ9)や,PI-LLの値がPIにより変化するという解析結果をもとに算出された獨協フォーミュラ10)など,さまざまな算出式が提唱され,いまだ議論されている.また,PTは頚椎矢状面アライメントにも相関があり,頚椎矢状面形態と姿勢異常の関連もあることから11),脊椎手術においては局所や隣接アライメントだけでなく,全脊椎アライメントあるいはバランスを考慮することの重要性が指摘されている.さらに近年は,立位のみならず,若年者や高齢者の坐位における脊椎アライメントの検討も行われ12,13),さまざまな生活動作や姿勢における脊椎アライメント変化も明らかになってきている.しかし,個々の脊椎アライメントは健常者においてもばらつきがあり,また高齢者のspinopelvic harmonyは若年者と同じなのかなど,明らかにすべき課題も多く,さらなる検討が必要である.