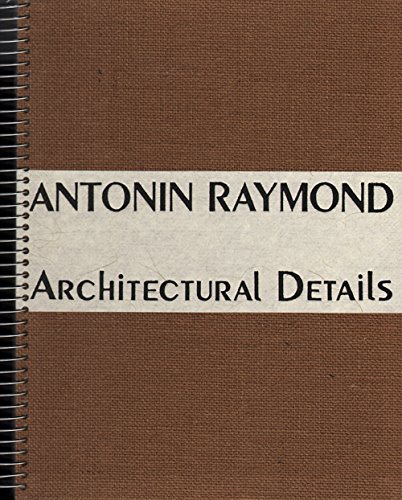2 0 0 0 OA Sudden Changes in the Tropical Stratospheric and Tropospheric Circulation during January 2009
- 著者
- Kunihiko KODERA Nawo EGUCHI Jae N. LEE Yuhji KURODA Seiji YUKIMOTO
- 出版者
- (公社)日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.283-290, 2011-06-25 (Released:2011-06-30)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 7 18
In mid-January 2009, sudden changes in circulation occurred in the tropical troposphere and stratosphere. Convective activity situated over the equatorial Maritime Continent showed an abrupt weakening, whereas that over the South American to African sectors became stronger. Changes also occurred in the latitudinal structure; convective activity in the Northern Hemisphere became weaker, whereas that in the Southern Hemisphere became stronger. The change in convective activity took place in association with a change in tropical circulation, from east–west to north–south type (i.e., from Walker- to Hadley-type circulation). Almost simultaneously with these events in the troposphere, a change in meridional circulation occurred in the stratosphere during a record-breaking stratospheric sudden warming event in January 2009. Stratospheric tropical temperature showed a decrease in response to a strengthening of the hemispherical meridional circulation. In the present study, we show how the stratospheric and tropospheric circulation changes are dynamically coupled.
2 0 0 0 258 インドール酢酸(IAA)による酵母細胞の増殖阻害について
- 著者
- 下坂 誠 野嶋 由美子 戸川 良一 岡崎 光雄
- 出版者
- 公益社団法人日本生物工学会
- 雑誌
- 日本醗酵工学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.62, 1987-11-02
2 0 0 0 OA 熟語産出課題における産出熟語数と辞書に記載された熟語数との関係
- 著者
- 川上 正浩
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学研究紀要 (ISSN:21860459)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.47-53, 2013-01-31
言語の認知過程研究においては、視覚呈示された単語のみならず、それと正書法的に類似した単語である類似語(Coltheart, Davelaar, Jonasson, and Besner, 1977)も同時に活性化することが示唆されている。この問題の検討に際しては実験者は何らかの語彙基準を参照し、類似語数を操作することになる。しかし、こうした操作そのものの妥当性を受け入れる前に、辞書などの外在基準に基づく類似語数が実験参加者の心的辞書における類似語数と対応していることを確認しておく必要がある。本研究では、川上(1997)が報告している資料に基づく漢字二字熟語の類似語数と、漢字一文字を手がかりとして、実験参加者が産出可能な漢字二字熟語の数とが対応しているのか否かが吟味された。229名の実験参加者を対象とした実験の結果、川上(1997)に基づく類似語数と実験参加者が産出した漢字二字熟語の数との間に対応が認められた。この対応は、川上(1997)が参照した辞書である岩波広辞苑第四版と実験参加者が有する心的辞書との間に対応があることを示していると解釈された。
- 著者
- SHIMIZU Masako
- 出版者
- 川崎医療福祉大学
- 雑誌
- Kawasaki journal of medical welfare (ISSN:13415077)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.35-42, 1995
D.H.Lawrence's The Rocking-Horse Winner(RHW) is a parapsychological story focusing on the relationship between a mother who has always had a grinding sense of a shortage of money, and her son who made 80,000 pounds by betting on horse races, but who, in the end, died insane. Young Paul becomes crazy about betting to stop repeated unspoken voices, saying "There must be more money", echoing in the house. This phrase may be regarded as an effective stylistic index 'repetition', because it describes the mother's inner desire for money.In this thesis, we discuss the unspoken phrases which are a clue to Paul's psychological state as a stylistic feature. As the first part of the story implies, the mother's grudge was caused by a loveless relationship with her husband that turned to an endless lust for money. We conclude that the striking stylistic feature of repetition represents an obsessional effect on Paul by his mother's inner vacancy to produce in him a kind of 'auditory hallucinations'. We also indicate that RHW is worthy of being called a modern parable since Lawrence generalizes the pathological nature of the mammonism of this modern world beyond 1926 when this story was written.
2 0 0 0 OA <研究論文>フラクタルサウンド
- 著者
- 吉田 浩
- 出版者
- 宝塚造形芸術大学
- 雑誌
- Artes : bulletin of Takarazuka University of Art and Design : 宝塚造形芸術大学紀要 (ISSN:09147543)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.169-180, 1997-03-31
自然のなかにあるものには必ず「ゆらぎ」が存在する。そのゆらぎのなかで自然の風のゆらぎは「1/fゆらぎ」とよばれ,「フラクタル」構造の特徴である自己相似性を持つ。このゆらぎの数値的シミュレーションをゆれる風鈴を仮想3次元空間で映像化することで実現させると同時にMIDIによる音の制作もゆらぎの数値を用いて行った。この音は映像ともよく合致し,快いものである。この音が風の音すなわち風のフラクタルサウンドである。
2 0 0 0 台湾産ブンチョウの羽色の表現型とその活用法
- 著者
- 山本 るみ子 齋藤 勉 宮川 博充
- 出版者
- 愛知県農業総合試験場
- 雑誌
- 愛知県農業総合試験場研究報告 (ISSN:03887995)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.331-334, 2001-12
台湾産白ブンチョウの羽色の表現型を調査し、国内における白ブンチョウの生産性向上のために利用できるか検討した。 1.台湾産白ブンチョウは桜(有色)に対し劣性である白の遺伝子をホモ型で保有していると推定された。 2.台湾産白ブンチョウ羽色の特徴としては、弥富産白文鳥雛にある黒い刺し毛が全くなく、純白であった。 3.台湾産白ブンチョウと弥富産桜ブンチョウの交配から発生した子はすべて桜ブンチョウの羽色で多量の白い刺し毛が存在していた。したがって、台湾産白ブンチョウは弥富産白ブンチョウが持つ桜(有色)に対し優性で、致死作用のある遺伝子(Wh)を保有していないと推定された。 そのため、台湾産白文鳥同士を交配することにより、白ブンチョウの生産性と品質を向上させることが期待された。
2 0 0 0 OA 仮名一文字で表される音韻から想起される漢字データベース
- 著者
- 川上 正浩 小野 菜摘 佐々木 美香 西尾 麻佑
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学研究紀要 (ISSN:21860459)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.95-103, 2012-01-31
本研究では、読み(音韻)から漢字(形態)への対応について、人間の反応に基づいたデータベースを構築することを目的とした。具体的には、仮名一文字で表記される特定の音韻(読み)から想起される漢字のバリエーションについて明らかにすることを目指した。実験参加者169 名を4 つの群に振り分け、それぞれの群に、仮名一文字で表される15 個の音韻を呈示した。30 秒の制限時間内に当該音韻から想起される漢字一文字のデータベースを作成した。集計の結果、本研究で対象とした仮名一文字のうち、もっとも多くの漢字が想起されたのは「か」(4.98)であり、もっとも少ない漢字が想起されたのは「ぬ」(0.80)であった。これは各実験参加者の想起漢字数であるが、想起された漢字のバリエーションについては、「か」(46)がもっとも多く、「せ」(3)がもっとも少なかった。
- 著者
- 磯前 順一
- 出版者
- 人間社
- 雑誌
- アリーナ = Arena (ISSN:13490435)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.258-292, 2016
- 著者
- 鳥養 雅夫
- 出版者
- アイ・エル・エス出版
- 雑誌
- The Lawyers
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.44-49, 2015-01
2 0 0 0 OA 遺伝子診断による文鳥の性判別技術
- 著者
- 市川 あゆみ 市村 卓也 中村 明弘
- 出版者
- 愛知県農業総合試験場
- 雑誌
- 愛知県農業総合試験場研究報告 = Research bulletin of the Aichi-ken Agricultural Research Center (ISSN:03887995)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.175-180, 2006-12 (Released:2011-01-18)
遺伝子診断による性判別法の文鳥への利用を目的として、鶏及び他の鳥類において性判別の報告があるプライマー、鶏W染色体特異的繰返し配列Xho領域を標的とする2種類と、鳥類の性染色体上に存在するCHD(chrcmo-helicase-DNA binding proein)遺伝子を標的とする5種類について検討した。その結果、文鳥ではXhoに関してはDNAが増幅されず判別不可能であったが、CHDに関しては、複数のプライマーでDNAの増幅が認められた。そのうち3本のプライマーを用いた方法(Ellegren 1996)で性特異的なバンドが検出され、性判別が可能であった。この方法はスズメ目のシロエリヒタキ(collared flycacher)のCHD-Wの配列を基に設計されたプライマーを用いたものである。また、材料とするDNAの安全で簡便な採取方法を検討したところ、爪から採取した少量の血液から判別に必要なDNAを抽出することができ、4週齢以降の個体での性判別が可能となった。
- 著者
- 山本 龍一 酒向 慎司 北村 正
- 雑誌
- 研究報告音楽情報科学(MUS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012-MUS-96, no.13, pp.1-6, 2012-08-02
本稿では,楽譜に基づく音楽音響信号から,演奏位置とテンポを推定する問題について論じる.隠れセミマルコフモデル (HSMM) に基づく演奏位置推定と,線形動的システム (LDS) に基づくテンポ推定を組み合わせることで,入力信号の未来の情報が使えない制約の元で効果を発揮する実時間拍予測アルゴリズムを提案する.具体的には,遅延を許容して信頼性のある演奏位置を推定し,テンポを用いて現在位置を予測する.クラシック音楽およびジャズ音楽データベースを用いてオンセット検出に関する評価実験を行った結果,提案する実時間拍予測アルゴリズムを用いることで,許容誤差 300ms において約 15% 精度が向上することが確認された.
- 著者
- 林 千渝 宇野 彰
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.37-42, 2015
- 被引用文献数
- 1
本研究では台湾の小学三年生103名を対象とし,これまで報告されてきた文字習得にかかわるとされる音韻認識能力,視覚認知能力,自動化能力,語彙力のなかで,台湾の中国語話者児童においてどの認知能力が中国語漢字の音読力に関与するのかを明らかにすることを目的とした.さらに,台湾で用いられている注音の構造から,音節と音素の2種類に分けた音韻認識能力の検査を用い,音読発達にかかわる影響を検討した.その結果,視覚認知課題と自動化課題の成績が漢字一文字音読成績を予測していた.中国語漢字は形態的変化によって意味や読み方が異なる文字であるため,視覚認知能力の貢献度が高かったのではないかと考えられた.また,台湾児童は,音読の際,音素や音節の単位よりも,sub-syllabic unitであるonsetやrimeを認識し,操作している可能性が考えられた.
2 0 0 0 アントニン・レーモンド建築詳細図譜
- 著者
- アントニン・レーモンド著
- 出版者
- 鹿島出版会
- 巻号頁・発行日
- 2014
2 0 0 0 OA 東武鉄道線路案内記 : 図入
2 0 0 0 OA 獣皮の禁忌
- 著者
- 井本 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.1-17, 1988 (Released:2010-03-12)
The dying person is wrapped up in the animal skin as the dead person is in Iran. The animal skin is of goat or sheep. It would seem that they get spirited wearing the skin of a sacrificed animal.It was the custom of neolithic Egypt to be buried with the animal skin on the body. In the ancient world even the deity needed the animal skin when he was to be full of life. The animal skin revitalized the dead, the deity, and the living as well.The animal sacrifice was not to offer up an animal to the deity but to kill the deity itself. The skin of the animal was full of life. Therefore the dying deity clad in the skin of the sacrificed animal came to life again.
2 0 0 0 OA 日英同盟終了後の帝国海軍練習艦隊ニュージーランド訪問記 : 遠来の友を迎えて
- 著者
- ケン マクニール
- 出版者
- 日本ニュージーランド学会
- 雑誌
- 日本ニュージーランド学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.2-11, 2002-06-22
第二次大戦以前、日本とニュージーランドの交流は極めて少なかった。その中で、1880年代から1930年代にかけて行なわれた大日本帝国海軍練習艦隊のニュージーランド訪問は、13回にのぼり、両国間の少ない交流の中で大きな役割を果たしたと言える。これらの訪問は、西洋社会の政治的対日認識の移り変わりという観点から、3つの時期に分けることができる。第一期、第二期については既に述べたので、本稿では、第三期の訪問について論じる。練習艦隊の訪問第三期は1920〜1930年代で、それは日本が、太平洋の白人諸国との利害の衝突や大陸での軍事行動などで、以前にも増して非難を浴びた時代であった。そのため、南太平洋の白人主義の地に寄港した練習艦の軍人は当然冷淡に扱われるはずであったが、実はそうではなかった。ニュージーランドは、日本とは利害の衝突が直接にはなく、また、第一次世界大戦中に日本海軍が海路防衛の役割を果たしたことをまだ高く評価していた。そのため、日本海軍の防衛に依存していた時代ほどではなかったが、ニュージーランド人は依然として諸手を挙げて艦隊を歓迎したのである。当時日本の近代化がかなり進んでいていたことを、ニュージーランド人はある程度知っていたはずだが、やはり「エキゾチックな日本」というイメージがまだ根強かったようである。そのため、異国情緒を求める好奇心が以前と同じように練習艦への関心を高めていたと思われる。艦隊の将校が現地のニュージーランド人のために開いた催しも、その好奇心に応えて、艦隊訪問の成功の大きな要因となった。直接にふれて確かめてからでないと物事を判断しない、と言われるニュージーランド人は、「利口」で「こざっぱりした」「礼儀正しい」日本軍人の行動や好意の表現を、自分の目で観察して、日本人は信頼できると判断したようである。勿論、艦隊の軍人を観察するニュージーランド人の中には、日本人が与えた好印象にもかかわらず、日本に対して疑いを抱いている者もいたのだが、日本を貶す意見は1935年までの練習艦隊の訪問についてのメディア報道には見られない。本稿では、練習艦隊の訪問に対する現地人の反応だけではなく、艦隊側が現地人に対して抱いた印象にもふれる。日本側はまず、遠洋航海の最果ての地ニュージーランドで盛んに受けた歓迎を喜んだようである。しかし、それと同時に、ニュージーランド人が盛んに示す好意や好奇心に比べて、真の日本についての知識に欠けていることが気になったようである。以前から、半官半民的な文化宣伝は練習艦隊の役割の大きなものの一つだったのだが、ニュージーランドのメディアに引用された日本側の発言にもあるように、西洋諸国で対日反感が募る一方の1920〜1930年代には、文化宣伝活動の重要性がさらに自覚されたようである。遠洋航海の記録にも、エキゾチックな日本に対する好奇心にアピールした催しの大成功が記されると共に、真の日本を紹介する活動の必要性も強調されている。艦隊の将校の中には、日本と英米との間の軋轢に対して軍事的解決を求める反英米派も存在していた。しかし、ニュージーランド側の場合と同様に、英米を貶す声は1935年までは日本側の記録に見られなかった。つまり、日本と英米の関係が悪化しつつある中で、1920〜1930年代の練習艦隊のニュージーランド訪問は相互的好意をその特徴としていたのである。それほど日本に対する関心が高くないニュージーランドの場合、あらかじめあった対日イメージに反応したというよりも、艦隊の訪問がそのイメージ造りに大きな役目を果たしたと言えるのだ。その意味で、練習艦隊の寄港は、好意的な対日認識形成に大いに有効であった。
2 0 0 0 IR 日本のファミコン論争(スペイン文)
- 著者
- 加藤 隆浩
- 出版者
- 三重大学
- 雑誌
- 人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要 (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.117-123, 1995
2 0 0 0 IR 『おもろさうし』にみる神話、伝承、他界観 : 王の行幸と「創世オモロ」をめぐって
- 著者
- 小山 和行
- 出版者
- 法政大学沖縄文化研究所
- 雑誌
- 沖縄文化研究 (ISSN:13494015)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.123-148, 2015-03-31