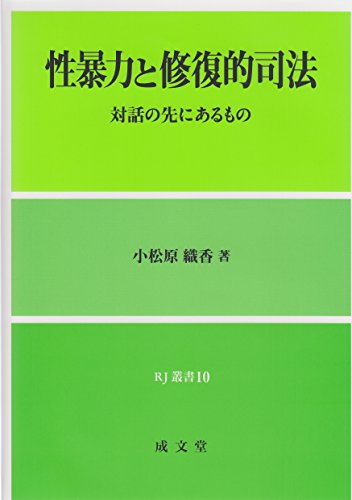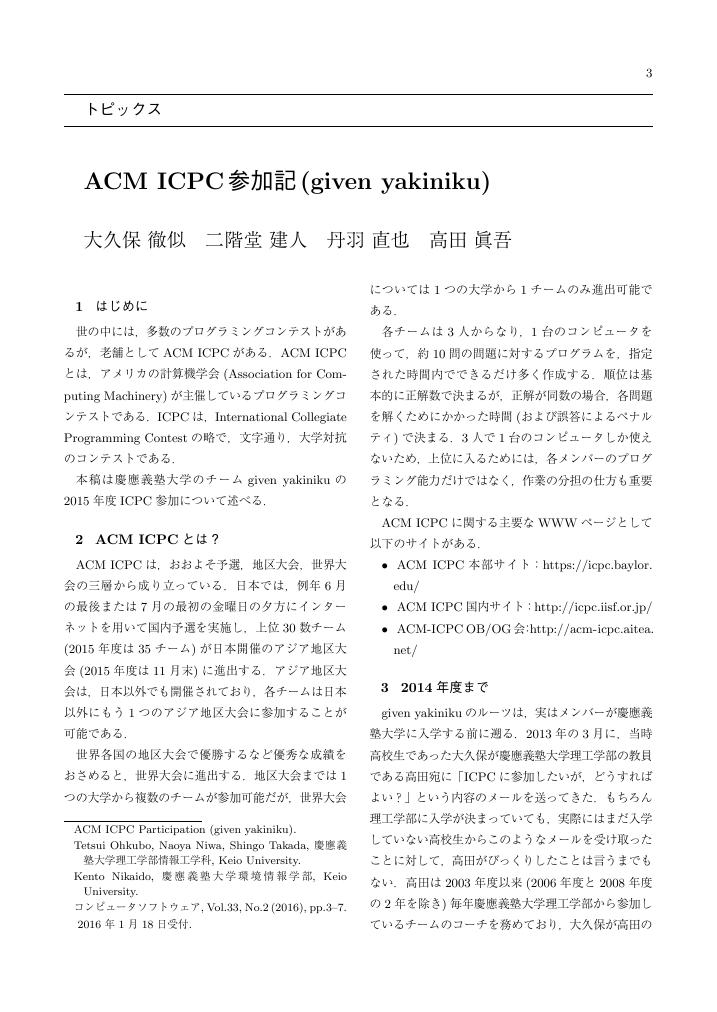13 0 0 0 OA 原子力発電所の立地と原発交付金による地域振興事業
- 著者
- 川久保 篤志
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.40, 2013 (Released:2013-09-04)
1.はじめに 2011年3月の東日本大震災に端を発する福島第一原発の未曾有の大事故は、現在でも事故原因の究明が完全には進んでおらず、避難を余儀なくされている原発周辺住民の帰還の目途も立っていない。にもかかわらず、政府は将来における原発廃止を決定できずにいる。この背景には、国家レベルでのエネルギーの安定供給の問題に加えて、原発の立地に伴う電源三法交付金による地域振興効果に期待する立地自治体等の思惑がある。 では、原発の立地地域では交付金をもとにどのような地域振興が図られてきたのか。本発表では、これまでの研究蓄積に乏しい島根原子力発電所(以下、島根原発)を事例に検討する。島根原発が地元にもたらしてきた交付金は1980年代に入って急増し、2010年までに累計720億円に達しており、その使途について検証する意義は大きいと思われる。 なお、島根原発が立地する松江市鹿島町は、松江市と合併する2005年までは八束郡鹿島町であったため、合併前に建設された1号機・2号機に関する地域振興効果の分析は旧鹿島町域で行い、現在建設中の3号機に関する分析は新松江市域で行うことにする。2.1号機・2号機の建設に伴う旧鹿島町の交付金事業の実態 旧鹿島町は、島根県東部の日本海に面した人口約9000人、面積約29km2の小さな町で、県東部有数の漁業の町として発展してきた。島根原発計画は1966年に持ち上がり、当時は原子力の危険性より用地買収や漁業補償に焦点が当たりながら、1974年には1号機、1989年には2号機が稼働した。 これにより多額の交付金や固定資産税が入ってきたため、特に1980年代と2000年代に積極的に地域振興事業が行われた。旧鹿島町役場と住民へのヒアリングによると、その主な使途は1980年代半ばまでは学校や運動公園、保健・福祉関係等の箱モノ建設が中心だったが、次第に、歴史民俗資料館(1987年)、プレジャー鹿島(1991年)、野外音楽堂(1998年)、鹿島マリーナ(2002年)、温泉施設(2003年)、海・山・里のふれあい広場(2005年)など、娯楽・観光的要素の強い事業が増加してきたという。これらの事業の中で住民から評価が高いのは、小・中学校校舎の新増設や公民館・町民会館の建設で、次代を担う世代の教育と地域住民のコミュニティ活動を活発化させる上で大きな役割を果たしたという。また、1992年の下水道施設の整備も高齢者の多い地元では高く評価されている。 一方、産業振興という観点では農業と漁業の振興が重要だが、農業については水田の圃場整備事業やカントリーエレベーターの新設を行い、生産の効率化・省力化を進めた。また、プレジャー鹿島や海・山・里のふれあい広場では地元の農水産物等の直売が行われた。漁業についても、町内4漁港の整備改修が進められ、恵曇地区に水産加工団地が整備されたた。しかし、これらの事業は一定期間、農業・漁業の維持に貢献したものの、1990年代後半以降には担い手不足から衰退傾向が著しくなった。 また、都市住民との交流促進の観点からは、総合体育館(1998年)・鹿島マリーナ・温泉施設が一定の成果をあげている。例えば、総合体育館は1999年以降毎年、バレーボールVリーグの招待試合を開催しており、2010年以降には松江市に本拠を置くバスケットボールbjリーグの公式戦や練習場として利用されている。鹿島マリーナは贅沢施設に思えるが、町中央部を貫流する佐陀川に無造作に係留していた船舶がなくなることで浄化が進み、かつ、山陽地方の釣りを趣味とする船主が係留料を支払うことで多額の黒字経営を続けているという。また、温泉施設は年間20万人の利用者がおり、夕方以降は常に満員という状況にある。3.3号機の建設に伴う松江市の交付金事業の展開と問題点 2005年に建設着工した島根原発3号機は、出力が137万kwと1号機・2号機を大きく上回っており、その交付金事業は桁違いの規模になった。図1は、これをハード事業(施設の建設が中心)とソフト事業(施設の運営が中心)とに分けて、示したものである。これによると、交付金は着工後に急増して2007年にピークの75億円に達した後、稼働年(2012年予定)に向けて減額されていることがわかる。また、交付金の使途は減額が進む中でソフト事業を中心としたものに変化していることがわかる。なお、発表当日はこの資料をもとに、交付金事業の内容を批判的に検討する。
13 0 0 0 IR 美術館アーカイブズが守るべき記録とは何か : カナダ国立美術館の事例を中心に
- 著者
- 川口 雅子
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要. アーカイブズ研究篇 (ISSN:18802249)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.83-104, 2012-03
近年、世界の主要美術館では来歴研究がさかんに推進されている。背景には、略奪美術品問題など社会からの要請があるが、そのような社会的使命を視野に入れつつ、今日の美術館アーカイブズはどのような記録の保存に取り組んでいるのか、カナダ国立美術館を事例として探るのが本稿の目的である。美術館において重要視されている記録は、作品に関する記録や展覧会に関する記録であるが、カナダ国立美術館では前者はコレクション・マネジメント室に、後者はアーカイブズ室において保管されているという具合に、必ずしも館内の全ての重要な記録がアーカイブズ室に引き渡されているわけではない。しかしアーキビストは館内における記録の作成部局や保管部局の把握に努め、全体を監視して、記録を守る役割を果たしていた。アーカイブズ室では展覧会記録のアクセシビリテイ向上に力点を置いているが、その特徴は検索手段として図書館目録を使っている点にある。それにより、組織の活動に関する重要な資料は、図書館所蔵かアーカイブズ所蔵かにかかわらず、共通のプラットフォームにおける総合的な検索が可能となっているのである。Over the last decade, several major art museums around the world have made substantial headway in conducting research on provenance, or the history of ownership of a work of art. Behind this phenomenon there is increasing public interest at the international level in looted and confiscated art from the World War II era. Taking this issue into account, this paper examines on the basis of the example of the National Gallery of Canada what types of records shall be kept in art museums. The author first provides an overview of records and archival materials that are maintained in the Gallery. Whereas the records relating to the Gallery exhibitions are maintained in the Library and Archives, there cords relevant to the artworks of the Gallery are housed in the Collections Management Department. The author gives attention to the fact that the archivist is fully aware of what records are kept in which department and plays an important role in preserving there cords under such circumstances. Finally, the author describes the project of the Archives of the Gallery to make the exhibition related records more accessible to the public.
13 0 0 0 OA 共感と共同体 -「共感の共同体」批判をめぐって-
- 著者
- 山崎 広光
- 雑誌
- 朝日大学一般教育紀要 = Journal of liberal arts and science Asahi University (ISSN:13413589)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.17-31, 2010-01-31
- 著者
- 河野 勝
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 日本政治学会年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- no.1999, pp.181-203, 1999
13 0 0 0 ローマ(古代,ヨーロッパ,二〇〇七年の歴史学界-回顧と展望-)
- 著者
- 本村 凌二
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.5, pp.950-954, 2008
13 0 0 0 IR 誰が兵士になったのか(2) : 学歴・職業による兵役の不平等
- 著者
- 渡邊 勉 Tsutomu Watanabe
- 雑誌
- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)
- 巻号頁・発行日
- no.119, pp.19-36, 2014-10-31
13 0 0 0 OA 「青い目茶色い目」の実践から考える道徳の教育方法―松下良平の道徳教育論を導きとして―
- 著者
- 木下 慎
- 雑誌
- 東京電機大学総合文化研究 = Bulletin of Tokyo Denki University, Arts and Sciences (ISSN:1348799X)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.211-215, 2017-11-15
13 0 0 0 OA 霊長類の行動研究におけるロボットの利用可能性
- 著者
- 上野 将敬
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- pp.34.002, (Released:2018-06-27)
- 参考文献数
- 75
Group-living primates often perform complex social behaviors. Traditionally, observational and experimental studies have provided important insights into the social behaviors of primates; however, these studies have limitations regarding unambiguous causality. The use of artificial stimuli can aid in understanding the mechanisms of animal behavior. A robot, which can perform some behavior sequences automatically or by remote control, serves as a new method to study the response of an animal to the stimulus of the same or other species. One of the advantages of using a robot is that researchers can change the appearance and behavior in line with their purpose. In addition, using a robot can help investigate the influence of more than one individual on another individual's behaviors. Although it is advantageous to use robots in the study of animal behaviors, it entails various challenges. This paper reviews the studies on animal behavior that used robots as stimuli and discusses the contribution of using robots in primate behavior study in the future.
13 0 0 0 第7回森林施業シンポジウム 報告脱ダム宣言と森林整備
- 著者
- 塚原 雅美 中田 理恵
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 森林科学 (ISSN:09171908)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.57-59, 2003
13 0 0 0 df-pnアルゴリズムの詰将棋を解くプログラムへの応用
- 著者
- 長井 歩 今井 浩
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.6, pp.1769-1777, 2002-06-15
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 9
詰将棋を解くプログラムの研究はこの10年の間に大きく進歩した.その原動力となったのは,証明数や反証数という概念の導入である.詰将棋に適用すると,直感的にいうと,証明数は玉の逃げ方の総数を,反証数は攻め方の王手の総数を表す.前者は攻め方にとって,後者は玉方にとって非常に重要な値である.証明数・反証数を対等に扱った,最もナイーブなアルゴリズムは,Allisによるpn-searchという最良優先探索法である.我々は近年,df-pnアルゴリズムという,pn-searchと同等の振舞いをする深さ優先探索法を提案している.この論文では,df-pnアルゴリズムを用いて詰将棋を解く強力なプログラムを作成し,その過程で導入した様々な技法を提案する.これらの技法をdf-pnの上に実装することにより,我々のプログラムでは300手以上の詰将棋のすべてを解くことに初めて成功した.しかもそれは,シングルプロセッサのワークステーションで解くなど,解答能力と解答時間の両面で優れた結果を出すことができた.During this decade, a study of programs to solve Tsume-Shogi problemshas greatly advanced. This is due to the development ofthe concept of a proof number and a disproof number.Allis' pn-search is the most naive best-first algorithm that usesboth proof numbers and disproof numbers on equal terms.We already developed a df-pn algorithm which is a depth-firstalgorithm that behaves the same as pn-search.In this paper, we applied df-pn algorithm to a program solvingTsume-Shogi problems. Moreover, we propose some techniqueswhich we imported during implementing the program.As a result, by these techniques implemented on df-pn,our program solved all the Tsume-Shogi problems,for the first time, that require over 300 plies to reach to the checkmate.
13 0 0 0 OA EOS Kiss X50 電子先幕専用シャッター
- 著者
- 豊田 靖宏
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.3, pp.280-284, 2012 (Released:2013-06-25)
デジタル一眼レフCanon EOS Kiss X50は,『誰もが簡単に使いこなし,思い通りのきれいな写真が撮れるカメラ』を目指した.このカメラには,デジタル時代の発想で実用化した技術として,電子先幕専用のフォーカルプレーンシャッターが初めて搭載されている.シャッター幕は,メカニカルな先幕が無く,後幕のみとなっている.その特徴的な機構と動作を解説する.
13 0 0 0 OA 被災者生活支援に関する制度の現状と課題 : 東日本大震災における対応と課題
- 著者
- 中川秀空
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13492098)
- 巻号頁・発行日
- no.712, 2011-06-02
13 0 0 0 OA 09-27-西体-19 世界一流テニス選手のファーストサービスに着目したゲーム分析 : ロジャー・フェデラー対ラファエル・ナダル戦を対象として(09.体育方法,一般研究発表抄録,ひろしま発 ひとを育む体育・スポーツ)
- 著者
- 岩月 猛泰 高橋 正則 吉本 俊明
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- no.60, 2009-08-26
13 0 0 0 OA HPVワクチンによる子宮頸癌予防
- 著者
- 井上 正樹
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.155-164, 2008-12-24 (Released:2009-08-13)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 3 4
20世紀後半からの腫瘍ウイルス学研究はHPVが子宮頚癌の原因ウイルスであることを明白にした.HPVは性行為にて感染することが疫学的にも明らかとなり,HPV感染を予防することで子宮頸癌を撲滅する戦略が見えてきた.その基軸をなすものはHPVワクチンの開発である.現在実用化されているワクチンはHPVの外郭蛋白をつくるL1遺伝子を酵母菌や昆虫細胞で発現させる遺伝子組換え型ワクチンである.HPV-DNA 16/18型に対する2価ワクチンとHPV16 /18型に尖圭コンジローマの原因ウイルスである6/11型を加えた4価ワクチンの2種類が実用化されている.ワクチンには重篤な副作用は無く「前癌病変」や「コンジローマ」をほぼ100%防御する.既に世界の多くの国で承認され,若年女性を中心に接種が開始されている.
13 0 0 0 OA Effects of Nordic walking on physical functions and depression in frail people aged 70 years and above
- 著者
- Han Suk Lee Jeung Hun Park
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.8, pp.2453-2456, 2015 (Released:2015-08-21)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 3 25
[Purpose] This study investigated the effects of Nordic walking on physical functions and depression in frail people aged 70 years and above. [Subjects] Twenty frail elderly individuals ≥70 years old were assigned to either a Nordic walking group (n=8) or general exercise group (n=10). [Methods] The duration of intervention was equal in both groups (3 sessions/week for 12 weeks, 60 min/session). Physical function (balance, upper extremity strength, lower extremity strength, weakness) and depression were examined before and after the interventions. [Results] With the exception of upper extremity muscle strength, lower extremity strength, weakness, balance, and depression after Nordic walking demonstrated statistically significant improvement. However, in the general exercise group, only balance demonstrated a statistically significant improvement after the intervention. There were significant differences in the changes in lower extremity muscle strength, weakness and depression between the groups. [Conclusion] In conclusion, Nordic walking was more effective than general exercise. Therefore, we suggest that Nordic walking may be an attractive option for significant functional improvement in frail people over 70 years old.
13 0 0 0 OA 二人のピーター : 20世紀初頭のイギリス児童文学における「他者」としての子ども
- 著者
- 菱田 信彦
- 出版者
- 川村学園女子大学
- 雑誌
- 川村学園女子大学研究紀要 (ISSN:09186050)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.159-175, 2006-03-15
イギリス人の子ども観は,ピューリタン主義の影響を受け,子どもをなるべく大人の世界に触れさせないことをよしとするものだった。17世紀ごろまでには,子どもは社会規範を身につけるまでは世の中に出さず,家庭や学校で教育するのがよいとする考え方が一般的になり,その一方で,子どもの世界を実社会の規範や価値観に束縛されない「別世界」としてイメージ化する傾向が生じた。このような子ども観はイギリス児童文学の発展に大きく影響し,とくに19世紀後半から20世紀初頭にかけての児童文学作品においては,子どものイメージをどのように扱うかについて作者がさまざまに模索した様子が見てとれる。ある作品では子どもは社会秩序を混乱させかねない要素として危険視され,また他の作品では,子どもの世界が理想化され,日常を離れてその世界に遊ぶことへのあこがれが描かれた。イギリスにおいてこれほど豊かな児童文学の伝統が花開いたのは,イギリス社会におけるこの大人と子どもの間の独特の緊張関係によるところが大きいだろう。
13 0 0 0 性暴力と修復的司法 : 対話の先にあるもの
13 0 0 0 OA 「町人のきもの2 江戸後期~明治初期のきもの」
- 著者
- 水上 嘉代子
- 出版者
- 社団法人 繊維学会
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.8, pp.P_268-P_271, 2008 (Released:2008-09-30)
13 0 0 0 OA ACM ICPC参加記(given yakiniku)
- 著者
- 大久保 徹似 二階堂 建人 丹羽 直也 高田 眞吾
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.2_3-2_7, 2016-04-22 (Released:2016-06-22)