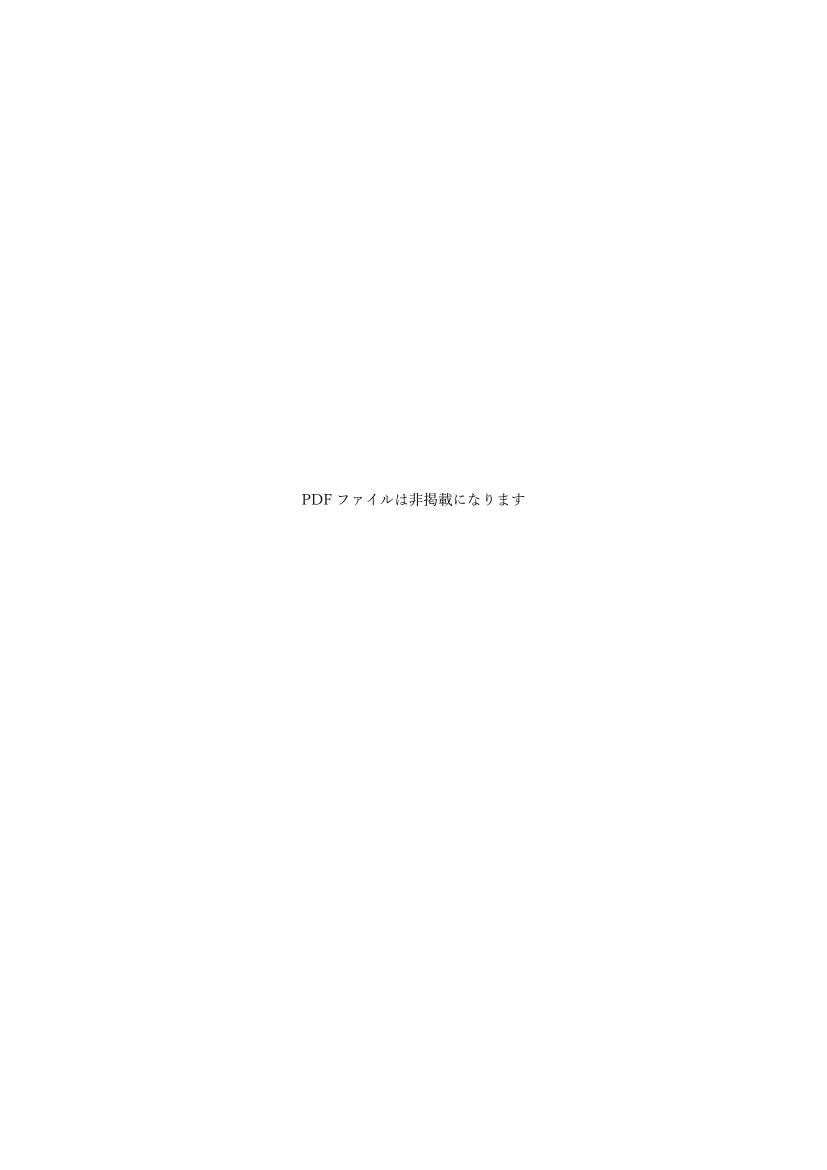1 0 0 0 OA 公的年金給付増大が個人住民税の課税ベースにもたらす影響について
- 著者
- 八塩 裕之
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.283-301, 2013 (Released:2021-10-26)
- 参考文献数
- 10
近年,人口の高齢化により勤労所得から公的年金給付への所得の代替が進んでいる。年金給付の増加は大きく,勤労所得の減少のかなりの部分を賄うが,公的年金等控除の影響などで年金の多くは課税ベースから除かれるため,やはり課税ベースは縮小してしまう。しかし,こうした税制を維持したままでは,今後個人住民税の課税ベース縮小がとどまることなく進む可能性がある。その結果,さらなる税収ロスとともに,地方自治体間の税収調達力格差の拡大が懸念される。こうした問題意識をもとに,本稿では経済低迷による勤労所得減少や税制改革の効果をコントロールしつつ,高齢化が個人住民税の課税ベースに及ぼす影響について計量分析を行う。そのうえで,日本の税制の問題点を検討する。
1 0 0 0 OA 韓国のEITC(勤労奨励税制)改革による所得再分配効果
- 著者
- 朴 寶美
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.211-226, 2013 (Released:2021-10-26)
- 参考文献数
- 24
勤労貧困層の所得支援と勤労意欲の向上のため2006年度に導入された韓国の勤労奨励税制は,12年現在,支給開始から4年が経過した。12年度改革は,特に所得基準額と最大受給額の拡大はもちろん,扶養子どもの人数などによる最大受給額が異なるようになるなど,最も大きな改革である。勤労奨励税制はその構造設計によって受給対象者と彼らの行動パターンが変化すると思われる。本稿は,このような勤労奨励税制の改革がどの程度の所得再分配効果をもたらすのかを,受給による労働時間の変化を考慮した検証を行っている。その結果,Phase-out区間で労働時間が減少する世帯が多かったものの全体的に労働供給が増え,労働供給を内生化すると更なる格差縮小効果が見られた。しかし,その幅は小さく,また給与所得額や扶養子どもの人数により労働供給の動きが異なるため,所得階級と子ども数ごとの格差縮小効果は全体的に見たときと異なる結果が得られる可能性も考えられる。
1 0 0 0 OA 過疎地域からみた公的医療の問題と課題 ―岩手県旧沢内村「生命行財政」の歴史的考察を中心に
- 著者
- 桒田 但馬
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.268-289, 2012 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 24
本稿の目的は岩手県旧沢内村における「生命行財政」を主な対象にし,その歴史的な考察を通して過疎地域からみた公的医療の問題を明らかにし,その政策課題を提起することである。その意義は総務省「公立病院改革ガイドライン」が重視していない側面に光を当てる点にある。 本稿では,①1980年代なかば以前の「生命行政」に対象を限定し,積極的な評価だけを与えてきた先行研究の不十分さをカバーした。②農村地域医療研究で不十分な自治体財政,公立病院経営の側面に焦点を当て,構造的な問題を明らかにした。③農村地域医療の理論構築および議論展開の出発点として,公的医療・病院経営理念,保健行財政などを問い直した。 この旧沢内村の理念と実践は,公的医療の成果として住民参加・自治にもとづく「生命行財政」のモデルとされ,全国の過疎地医療に大きな影響を与えた。しかし,1980年代なかば以降は沢内方式が変質していく。それは国の(地方)行財政構造改革や医療制度改革などが主な要因になっている。公的医療の中・長期的な課題としては,沢内方式の現代的な再構築があげられる。
- 著者
- Takei Yutaka Sakaguchi Eiji Sasaki Koichi Tomoyasu Yoko Yamamoto Kouji Yasuda Yasuharu
- 出版者
- Public Library of Science
- 雑誌
- PLOS ONE
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.9, pp.e0274604, 2022-09-14
Transporting patients down stairs by carrying is associated with a particularly high fall risk for patients and the occurrence of back pain among emergency medical technicians. The present study aimed to verify the effectiveness of the Airstretcher device, which was developed to reduce rescuers’ physical burden when transporting patients by dragging along the floor and down stairs. Forty-one paramedical students used three devices to transport a 65-kg manikin down stairs from the 3rd to the 1st floor. To verify the physical burden while carrying the stretchers, ratings of perceived exertion were measured using the Borg CR10 scale immediately after the task. Mean Borg CR10 scores (standard deviation) were 3.6 (1.7), 4.1 (1.8), 5.6 (2.4), and 4.2 (1.8) for the Airstretcher with dragging, Airstretcher with lifting, backboard with lifting, and tarpaulin with lifting conditions, respectively (p < 0.01). Multiple comparisons revealed that the Airstretcher with dragging condition was associated with significantly lower Borg CR10 scores compared with the backboard with lifting condition (p < 0.01). When the analysis was divided by handling position, estimated Borg CR10 values (standard error) for head position were 4.4 (1.3), 2.9 (0.9), 3.2 (0.8), and 4.0 (1.1) for the Airstretcher with dragging, Airstretcher with lifting, backboard with lifting, and tarpaulin with lifting conditions, respectively, after adjusting for participant and duration time (F = 1.4, p < 0.25). The estimated Borg CR10 value (standard error) for toe position in the Airstretcher with dragging condition was 2.0 (0.8), and the scores for the side position were 4.9 (0.4), 6.1 (0.3), and 4.7 (0.4) for the Airstretcher with lifting, backboard with lifting, and tarpaulin with lifting conditions, respectively, after adjusting for participant and duration time (F = 3.6, p = 0.02). Transferring a patient down stairs inside a house by dragging using the Airstretcher may reduce the physical burden for rescuers.
1 0 0 0 OA 都道府県立美術館の効率性 ―確率的フロンティア分析法を用いた実証分析
- 著者
- 須原 三樹
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.191-208, 2011 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 26
地方公共団体の財政悪化に伴い運営予算の縮減が続き,指定管理者制度等の市場原理が導入される中で,公立美術館にも効率的な運営が求められている。本稿では,全国の都道府県立美術館に焦点を当て,計量経済学モデルを用いて施設運営の効率性を実証分析する。そして,美術館外部の要因(環境・行政要因)と,内部の要因(運営・事業要因)の両視点から技術的効率性の要因分析を行う。 確率的フロンティア生産関数の推定の結果,都道府県立美術館の運営には非効率性が存在することが統計的に有意に認められ,技術的効率値の平均値は0.64となった。技術的効率性の要因分析の結果,市街地から当該美術館までのアクセスの良さや,特別展や教育普及プログラムの充実,展覧会における共催展の割合が技術的効率性に有意に正の影響を与えることが示された。
- 著者
- 田中 宏樹
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.234-250, 2012 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 26
本稿は,2000年代に進んだ公教育の分権化が,教育行政をめぐる自律性を志向した首長の政治的支持の上昇に結びついているかを,理論モデルから導かれる回帰式を推定することで実証的に解明する。より具体的には,都道府県別プール・データを用いて,2000年代中盤に進んだ義務教育費国庫負担金の総額裁量制への移行が,知事選での業績投票的な意味合いを強める方向に作用し,都道府県レベルでのElectoral Accountabilityの上昇に寄与したか否かを,実証的に解明することに力点を置く。実証分析の結果,公教育サービスの水準やその提供に要した財政措置は,有権者による知事の業績判断の材料となって,その政治的支持・不支持の決定に結びついているという理論の帰結が支持された。
1 0 0 0 OA カナダの消費課税システムにおけるケベック売上税(QST) ―QST導入過程の分析を中心に
- 著者
- 篠田 剛
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.176-198, 2012 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 35
現在,カナダの消費課税システムは,1991年に連邦付加価値税である財・サービス税(GST)が導入されて以来,小売売上税である州売上税(PST),付加価値税であるケベック売上税(QST),協調売上税(HST)が併存しているが,このような複雑な制度がなぜ生じたのかについては十分に明らかにされてこなかった。本稿では,州レベルの付加価値税でありながら高い課税自主権を保持するQSTの導入がいかにして可能であったのかを,各主体の利害関係を中心に政治過程・経済過程両面の分析を通じて明らかにする。本稿の分析によって,QSTは,対米輸出促進というケベック州と連邦政府の利害の一致と,連邦政府による戦略的妥協の産物であったことが示され,地方消費課税における税制調和と課税自主権のトレードオフの1つの解決形態としてのQSTの性格が示唆される。
1 0 0 0 OA ドイツにおけるエコロジー税制改革の発展と限界
- 著者
- 佐藤 一光
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.155-175, 2012 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 25
本稿はドイツの「エコロジー税制改革の更なる発展に関する法律」の特徴を明らかにし,その成立過程を分析することで環境税と二重の配当を租税論的に再検討するものである。第2次シュレーダー政権のもと成立した同法の特徴は,①環境政策上有害な租税支出を縮小し,②エネルギー源別の税率を調整し,③租税負担のキャップにエネルギー利用削減のインセンティブを付与するという,エコ税のグリーン化ともいうべきものであった。その一方で,④二重の配当による失業の減少を目指さずに財政健全化の財源として位置づけられた。このことは,第1次シュレーダー政権の雇用政策と租税政策が景気後退期において失敗し,失業と財政赤字が拡大するという文脈の中で理解されうる。租税論的知見として,①費用効率性ではなく原因者原則と充分性による環境税の理解,②雇用政策に租税政策を活用することの困難性が示唆された。
1 0 0 0 OA 環境税の導入過程と二重の配当論の再検討 ―ドイツ・エコロジー税制改革を中心に
- 著者
- 佐藤 一光
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.230-249, 2011 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
環境問題の深刻化と環境意識の高まりによって,欧州諸国で次々に環境税が導入されてきた。そこでの重要な概念は,環境税による環境改善と環境税収によって既存の歪みをもたらしている税率を引き下げることによって社会厚生をさらに高めるという二重の配当論であった。二重の配当の可能性について,理論的・実証的研究がなされてきたが,必ずしも十分に財政学的考察がなされてきたわけではなかった。本稿ではドイツのエコロジー税制改革を題材とし,政治過程分析と制度分析を組み合わせることで,環境税と二重の配当論の財政学的な考察を試みた。本稿の分析によって,ドイツにおける公的年金制度の構造によって受益の不均衡が生じ,軽減税率の導入によってその是正を図ったことが明らかになった。このような軽減税率の導入は租税原則上も,環境税と二重の配当の理論上も,望ましいものではなかったが,軽減税率の導入を肯定的に評価する可能性も示された。
1 0 0 0 OA アジア4ヵ国と日本の法人実効税率の比較
- 著者
- 鈴木 将覚
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.209-229, 2011 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 13
アジア諸国への資本逃避の懸念が広く共有されている一方で,アジア諸国の法人実効税率の比較が行われることは少ない。本稿では,シンガポール,タイ,中国,韓国という法人税制の特徴が異なるアジア4ヵ国を対象に,EATRとEMTRの時系列的な変化を計算し,日本との比較を行った。その結果,①シンガポールとタイは,日本よりもEATR,EMTRともにはるかに低く,②日本と韓国のEATRの差は12%,中国と日本の差は7%であり,③日本と中国のEMTRがほぼ同じ水準にあることがわかった(機械設備の標準ケース)。こうした分析は,日本の法人税改革の当面の目的がEATRを5~10%引き下げて立地インセンティブを与えることであることを示唆する。また,タックスホリデーを用いた分析では,中国を除く国では免税期間が短い場合に実効税率が逆に上昇するとの興味深い結果が得られた。
1 0 0 0 OA 中国年金制度の問題点 ―年金数理における年金財政の持続性の分析
- 著者
- 李 森
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.199-215, 2012 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 27
年金制度の財政危機をどう乗り越えるか。これは年金制度を安定的に維持していくうえで欠かせない研究課題である。急速に進展する人口高齢化社会のもとで,将来の年金財政を維持するためには,年金制度の再検討と改革が必要となる。 本稿では,中国の各地域(省)別の年金財政の現状分析にあたって,年金制度のカバー率と省レベルの社会プール化の限界点および年金財政の持続可能性などの視点から,中国の現行年金制度の問題点を取り上げ,さらに現行制度の改革の必要性について議論する。
1 0 0 0 OA ブレア政権の医療改革によるNHSの財政構造の変化 ―健全性・公平性の観点による考察
- 著者
- 柏木 恵
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.250-271, 2011 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 36
本稿の目的は,英国ブレア労働党政権の医療改革がNHS財政にどのような影響を与えたかについて,健全性・公平性の観点から検証することにある。先進諸国は福祉国家として財政を維持するのが難しくなってきており,医療政策は重要課題であることと,橋本・小泉政権は英国保守党政権を参考にした部分が多く,ブレア政権をみることで,これからの日本がみえるのではないかと考えるからである。英国は2003年度に医療費を拡大したが,2004年度から赤字に転落し,2006年度にV字回復した。その原因は人件費の増大と予算配分の変更である。政権公約のうち職員増については目標以上に達成しており,これが財政赤字の原因でもあった。しかし一方で,医療費拡大で1人当たりの医療水準が上がり,低所得者が受けられる医療範囲が増え,公平性を高めていた。保守党政権は現金給付に力を入れていたが,ブレア政権は医療を含めた現物給付に力を入れていたことも明らかとなった。
1 0 0 0 OA 地方債充当率の実証分析 ―市町村データからの検証
- 著者
- 大野 太郎 小林 航
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.176-190, 2011 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 14
本稿では地方債充当率に着目し,市町村データ(推定期間:1998~2008年度)を用いて充当率(実績値)の決定要因を探るとともに,地方公共団体が地方債充当率の上限規制から影響を受けているのか否かについて実証分析を行った。検証の結果,当期の経常歳入が充当率(実績値)に対して負に寄与していること,また足下の充当率(実績値)が高い市町村は上限規制が起債の制約になっていることも示された。
1 0 0 0 OA 地方債充当率の経済分析 ―理論分析と都道府県データからの検証
- 著者
- 大野 太郎 小林 航
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.170-189, 2010 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
本稿では地方債充当率に着目し,その決定要因に関する理論分析と,都道府県データを用いた実証分析を行う。考察と検証の結果,実証的に最も支持される点として,当期の経常歳入が充当率に対して負に寄与しており,財政力の高い地域ほど充当率が低いことが示される。また,地方債充当率には上限規制が存在するが,実証分析の結果,少なくとも本稿の推定期間内においては,それが大きな制約にはなっていないことも示唆される。
1 0 0 0 OA 最適線形所得税の推計 ―MCFからの接近
- 著者
- 別所 俊一郎
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.149-169, 2010 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 25
本稿では,日本の労働所得税を対象に,就業構造基本調査の個票データを用いて最適な線形所得税(flat tax)の形状を独身世帯に対して推計する。また,同様の手法を負の所得税(NIT: negative income tax)にも応用する。働き盛りの単身世帯を対象として推計したところ,現行税制と比べて高所得者層に減税となるようなものも,増税となるようなものも,社会的な不平等回避度如何によって正当化されうる。ただし,いずれの結果においても最も所得の低い階層には減税することが望ましい。また,社会厚生の評価は,最適な線形所得税が現行の累進所得税よりも高いとの結果も得た。
1 0 0 0 OA 法人所得税の限界実効税率 ―日本の個別企業の実証分析
- 著者
- 林田 吉恵 上村 敏之
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.131-148, 2010 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 15
本稿では,投資家である家計の税制と法人所得税が企業の設備投資に与える影響を分析する。そのため,設備投資の資金調達手段の違いを考慮した個別企業ごとの租税調整済み資本コストと限界実効税率を計測して投資関数を推計し,投資率に対する法人実効税率の弾力性を求めた。本稿は,これらの分析結果の分布の推移に注目する。 限界実効税率の平均は1970年代から90年代にかけて高く推移し,その後に低下する。その分布は,1970年代から90年代にかけて広がりを見せるが,2000年代になれば小さくなる。投資関数の資本コストの係数は,1970年代から90年代まではさほど変わらないが,2000年代は小さくなる。1970年代と80年代の限界実効税率の投資率に対する弾力性の値は大きいが,90年代から2000年代に入ると低下する。 本稿の分析により,過去の法人所得税の限界実効税率は設備投資に対して影響力を持っていたが,2000年代に入り,影響力は小さくなったことが指摘できた。
1 0 0 0 OA フランスにおける単一総合累進所得税制の形成 ―1959年税制改革の考察
- 著者
- 小西 杏奈
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.208-231, 2010 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 56
フランスでは,第2次世界大戦後も総合累進所得税と分類所得税から成る二重の所得税制が継続し,1959年の税制改革でようやく二重の所得税制が統一され,単一の総合累進所得税制が導入されることとなった。本稿では,この所得税制改革の分析を通じて,フランスで単一の総合累進所得税制が導入される過程と本改革の特質を明らかにする。1959年改革時に,内外の経済政治状況の変化に直面していたフランスでは,労働所得への軽課という伝統的な租税原則の根拠が希薄化し,この原則を担保していた分類所得税制の見直しが要求された。そして,財政担当大臣のイニシアティブにより,分類所得税制は廃止され,単一総合累進所得税制の創設が決定されたのだが,従来の租税原則が当時の政権のディスインフレ政策と結びついて影響力を持ったため,改革のインパクトは限定され,労働所得への軽課という特質は残存した。
1 0 0 0 OA 財政を通じた地域間再分配と生産要素の移動
- 著者
- 川崎 一泰
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.107-122, 2011 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 12
わが国の地域間の人口移動は,地域間所得格差の縮小に伴い収束に向かいつつある。こうした現象に対して,Barro and Sala-i-Martin(1992)をはじめとした実証研究がすすめられ,人口移動の収束が限界生産性の均等化によるものかが論点となっている。この論争の中で,持田(2004)では,人口などの生産要素の移動は,限界生産性に加え,財政余剰も影響を及ぼしていることを指摘している。本稿では,生産要素の流動化を通じた労働力及び資本の最適配分を推計し,近年の人口移動の収束が地域間格差縮小によるものか否かを判定するとともに,その際に財政を通じてなされた地域間再分配の影響を明らかにする。 実証分析を進めた結果,わが国の人口移動の収束は,地域間所得格差の縮小によるものではなく,限界生産性の地域間格差を相殺するように財政余剰の格差が生じているためであることが明らかになった。財政を通じた再分配は,地域間所得格差を縮小することはできたが,生産性の差を縮小することはできなかった。つまり本稿は,財政の再分配には所得格差を縮小する代わりに,地域の自立的発展を阻害する側面があることを明らかにした。
1 0 0 0 OA 公的支出の地域経済への効果
- 著者
- 近藤 春生
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.123-139, 2011 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 23
本稿の目的は,わが国における国ないしは地方政府の公的支出が地域経済(生産量,雇用,民間需要)にどのような影響を与えているかを,地域レベルのデータを用いた実証分析により明らかにしようとするものである。財政政策の効果について,ベクトル自己回帰(VAR)モデルを用いて分析した結果,以下の3点が明らかにされた。①公共投資が生産量や雇用を高める効果は認められるものの,政府消費の効果は低いこと,②1990年代以降,公的支出の民間需要,生産量に与える効果は大幅に低下していること,③公的支出の経済効果を地域別に見ると,都市圏において高く,非都市圏において低いことである。この結果から判断する限り,公共投資政策をはじめとする,公的支出が地域経済に及ぼす効果は限定的であり,地域経済の活性化を意図して,裁量的な財政政策を行うことには限界があるといえる。
1 0 0 0 OA 韓国における付加価値税増税の公平と効率の問題
- 著者
- 朴 寶美
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.190-207, 2010 (Released:2022-07-15)