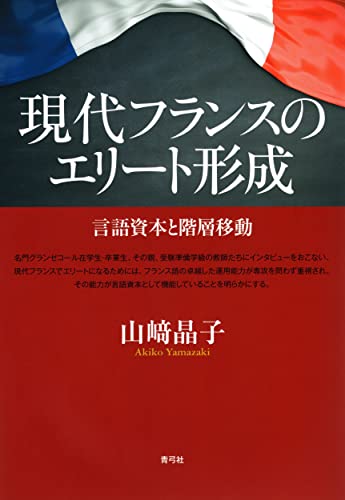1 0 0 0 OA 市町村合併の歳出削減効果 ―合併トレンド変数による検出
- 著者
- 宮﨑 毅
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.145-160, 2006 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3
市町村合併には規模の経済による歳出削減効果があると指摘されてきたが,日本では合併による1人当たり歳出削減効果の実証分析は少ない。本稿では,1990年代の市町村合併が1人当たり歳出の削減をもたらしたかを,全国市町村パネルデータを用いて分析した。次のような結果が得られた。第1に,合併後1人当たり歳出は増加するが,その後徐々に減少する。第2に,合併により1人当たり人件費は減少する。合併後平均給与は上昇するが,規模の経済により公務員数を削減できるためと考えられる。第3に,合併後1人当たり普通建設事業費は上昇するが,徐々に減少する。合併後に大型事業が始められるが,その後算定替期間の終了や財政の逼迫により縮小されるためと思われる。
1 0 0 0 OA 地方自治体の行政改革に関する要因分析
- 著者
- 加藤 美穂子
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.264-279, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 24
本研究は,地方自治体の政策決定要因として,首長や議会など地方内部の政治的特性に注目し,計量的にその影響を明らかにしようとするものである。とくにここでは,地方自治体の意思が比較的表れやすい行政改革への取組みに注目する。今後,地方分権の進展にともない,地方財政や地方行政における自治体内部の政治的意思決定は,その重要性がより高まっていく。その過程を考察するための第一歩としても,今回,このような検証を試みている。 本稿の検証結果からは,今日の各自治体の行政改革への取組み具合は,財政状況や都市規模などの社会的・経済的環境のみならず,首長の党派性や選挙競争の程度,議会との関係といった政治的環境によってもやはり影響を受ける可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 金利機能の正常化と財政危機
- 著者
- 井手 英策
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.245-263, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 26
本稿では,量的緩和政策への転換が財政運営や日銀の政策選択に与えた影響について考察する。量的緩和は,バランスシートの毀損,為替介入の積極化と政府債務の増大,借換政策への日銀の動員など予期しえぬ政策の連鎖をもたらした。その結果,量的緩和からの転換という金融政策の「正常化」が,かえって財政の抱え込んだリスクを顕在化させかねない状況を作り出すこととなった点を論証する。
1 0 0 0 OA 地方債の元利補給の実証分析
- 著者
- 土居 丈朗 別所 俊一郎
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.311-328, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 4
地方債は,地方税,地方交付税交付金や国庫支出金とともに,国と地方の財政関係の一環として運営されている。地方債の元利償還金は地方交付税交付金額算出の基礎となる基準財政需要額の算定に影響を与え,地方交付税を通じた異時点間・地域間の所得再分配が明示的に行われている。本稿では,とくに地方交付税交付金を通じた元利償還金の補塡による財政移転に着目する。本稿の目的は,元利償還への補給の規模を明らかにするとともに,このような措置が地方政府の行動に与えた効果について計量的に分析することにある。そのために,これまで利用されることの少なかった基準財政需要の内訳のデータを用いた分析を行った。地方交付税交付金を通じた明示的な地方債の元利補給については,その規模が近年では交付税交付金の30%,公債費支出の40%をこえる規模に達していることが示された。また,このような元利補給が地方債発行を誘導していることが示唆された。
1 0 0 0 OA 地方環境税の税率制限
- 著者
- 羽田 亨
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.294-310, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 7
地域を越えて汚染物質あるいは汚染源が移動して環境汚染による負の外部性が地域間で相互に及ぶ状況を想定する。このとき,各地域の地方政府に地方環境税の税率の自主決定権を与える完全な分権的環境税システムにおいて,汚染物質が越境移動するケースでは,最適な水準に比べて過小な水準に,汚染源が越境移動するケースでは,過大な水準に税率が設定されることにより非効率が発生する。また,全地域一律に均一税率を適用する中央集権的環境税システムも効率的ではない。各地域の地方政府が設定できる地方環境税の税率に上限および下限を設けて,その範囲内で自由な税率の選択を認める部分的な分権的環境税システムが,一定の条件のもとで中央集権的環境税システムおよび完全な分権的環境税システムに対して優位な制度であることを示す。
1 0 0 0 OA 地方政府の政策決定における政治的要因 ―制度的観点からの分析
- 著者
- 砂原 庸介
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.161-178, 2006 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3
本稿では,都道府県を対象として,地方政府における知事-議会関係と中央政府と地方政府の制度的な関係に注目しながら,地方政府が政策をどのような政治的要因によって決定しているかについて,その影響を計量的な手法で分析することを試みた。具体的な政策として開発政策(インフラ整備・農林水産)と再分配政策(教育・福祉)に焦点を当て,その支出水準に対して議会における保守・革新といった党派性,知事の支持基盤・経歴,知事の再選動機という3つの政治的要因がどのような効果をもたらしているかを検証する。本稿の分析から得られた主要な結論として,特に冷戦期を中心に政党の党派性が地方政府の政策決定に一定の影響を与えており,地方政府が自らの議会の選好に応じてある程度自律的な意思決定を行うことが可能であったこと,知事のような人的ルートを通じて中央政府の意向が地方政府の政策に反映される経路がありうることが示された。
1 0 0 0 OA 環境税制改革の所得再分配効果と二重配当仮説
- 著者
- 小林 航
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.213-226, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
本稿では,消費者部門に特化した簡易モデルを用いて,炭素税導入とともに他の税目を減税する税収中立的な環境税制改革の帰結を分析する。特に,社会保険料や労働所得税を減税対象とするケースにおいて2つ目の配当が正になること,および炭素税の逆進性と労働所得税の累進性からこのような環境税制改革は公平性を大きく損なうものの,正の不平等回避度のもとでも非環境的厚生が増加する可能性があること,などが示される。
1 0 0 0 OA 日本型消費税政策の新政治経済学
- 著者
- 赤石 孝次
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.195-212, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 35
本稿は,福祉国家財政の一般消費税(general consumption tax)への依存が国際的に進む中で,日本の同税への依存が低位にとどまっている理由と帰結を,歴史的新制度論アプローチと社会契約論アプローチを結合することで明らかにしている。第1に,総税負担の増大と逆進的課税への依存が,政治制度構造とそれによって醸成された社会契約によって規定されたということである。日本では,単記非委譲式中選挙区制度(single non-transferable vote,以下,SNTVと記す)のもとで,雑多な利益集団の支持を得るために,自由民主党(自民党)はそれらの集団との間に一連の社会契約を取り決めてきた。しかし,このことによって政治エリートが短期的なコストを課すことが妨げられ,そのことが寛大な福祉国家建設と引替えに逆進的な税負担の増大を受容するという西欧的な租税政策の展開を不可能にした。第2に,日本的な制度的枠組みの中で重視された生産者重視の政策は,政府の再分配機能に対する国民の理解を矮小化させ,政府の役割に対する彼らの不信を定着させた。このことは,グローバル化と高齢化が進む中で,政府が福祉国家の財源として消費税の負担を引き上げることを困難にしている。
1 0 0 0 OA 公共事業をめぐる政策展開 ―1990年代末以降の公共事業縮減の諸契機と意義
- 著者
- 碇山 洋
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.163-176, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 6
高度経済成長期から形成されてきた公共事業依存型経済,公共投資偏重型財政も1990年代末から大きな転機を迎えている。公共事業縮減への転換のもっとも重要な契機は多くの論者が指摘するように財政危機であるが,本稿は,財政危機を実際の政策転換に媒介する他の諸契機を,資本蓄積,なかでも公共事業と最も直接的に関係する建設業の資本蓄積との関連で検討する。公共事業によって独特の蓄積パターンをたどってきた建設業の過剰蓄積がバブル崩壊後,膨大な不良資産・不良債権を生み出し,財政危機下での公共事業縮減の足かせとなる。そうした状況での公共事業縮減への転換を,日本企業の海外進出と分化,それらを反映した財界内部での公共事業政策をめぐる対立と決着をふまえて論じ,公共事業縮減の意義をしめす。
1 0 0 0 OA 税制と事業形態選択 ―日本のケース
- 著者
- 田近 栄治 八塩 裕之
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.177-194, 2005 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
アメリカでは税が個人事業者の事業形態選択に影響を及ぼしてきた。そこでは所得税と法人税の限界税率差が重要とされ,とくに1986年の所得税減税の効果は注目された。 一方,日本でも税と事業形態選択の問題は重要であったが,その原因はアメリカとは異なるものであったと考えられる。日本では個人形態と法人形態で適用される控除,具体的には給与所得控除の適用可否が異なることが重要であった。とくに1974年の控除引き上げは大きく,これが事業の法人化による節税を引き起こしたと考えられる。本稿では個人事業者のこうした節税行動を分析し,それを通じて日本の所得税の問題点を考察する。
1 0 0 0 OA 最新トレンド 東京駅
- 著者
- 平野 邦彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本不動産学会
- 雑誌
- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.106-107, 2013-03-25 (Released:2016-11-24)
1 0 0 0 OA フランス高等教育における学位・免状制度
- 著者
- ティエリ マラン 夏目 達也
- 出版者
- 独立行政法人 大学評価・学位授与機構
- 雑誌
- 大学評価・学位研究 = RESEARCH ON ACADEMIC DEGREES AND UNIVERSITY EVALUATION (ISSN:18800343)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.27-43, 2014-11
1 0 0 0 OA フランスの高等教育における職業教育と学位
- 著者
- 夏目 達也 大場 淳
- 出版者
- 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
- 雑誌
- 学位と大学
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.63-82, 2016-08
1 0 0 0 現代フランスのエリート形成 : 言語資本と階層移動
1 0 0 0 IR 私的交通の意味
- 著者
- 生田 保夫
- 出版者
- 流通経済大学
- 雑誌
- 流通経済大学論集 (ISSN:03850854)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.p48-72, 1979-07
1 0 0 0 国家プロジェクトにおける価値伝達を重視した技術マネジメントの研究
- 著者
- 岡田 匡史 Okada Masashi
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 巻号頁・発行日
- 2010-09
学位授与大学: 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 2010年度 博士(システムエンジニアリング学) 甲第3377号 学位授与年月日: 2010年9月21日
1 0 0 0 OA 日本語格助詞の文法論的位置づけ : 井上和子の「変形文法と日本語」における「格」
- 著者
- 井東 廉介
- 出版者
- 石川県公立大学法人 石川県立大学
- 雑誌
- 石川県農業短期大学研究報告 (ISSN:03899977)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.56-66, 1991 (Released:2018-04-02)
日本語の統語構造の分析は格助詞の機能意味の解明を中心に行われてきた。規範文法的視点でも記述文法的方法でも変形生成文法的方法でも,この分析方法については変わっていない。日本語の統語理論で変化してきたのは,統語要素の設定に関わる部分である。明治期以来,日本語文法は英文法を始めとする英欧語文法の枠組みを手本とし,統語要素の同定は英文法の統語要素に日本語格助詞の機能意味を対応させることによって行われてきたと言われている。しかし,「-ハ-ガ-」構文のように英欧諸語の文構造の中には見られないものが日本語構造の中に含まれていることが頻繁に論議されるようになるにつれて,日本語文法には英欧諸語の文法の枠組みでは解決できない独自の言語現象が含まれていることが指摘されるようになった。その結果,日本語の格助詞「ハ」,「ガ」,「ニ」,「ヲ」を英語の主語,目的語などの統語機能と単純に対応させ,文構造のモデルを「主語+目的語+述語」のような枠の中だけで片付けようとする分析は日本語の分析に十分対処できない事が明らかになってきた。主語,目的語などの統語要素は,本来,動詞に対して定まった関係意味を持つものではない。主語になる名詞句は,動詞の意味との関連で,その行為者,経験者,対象,道具などを表す。目的語になる名詞句は,対象として作用,影響を受けるもの,結果として生じるもの,利益(害)を受けるものなど多様な意味関係のものを含んでいる。C.Fillmoreの格文法理論は,動詞と述語項とのこのような意味関係を「格」として統語構造派生の説明の中に取り込んだ。彼は,格概念の中心を従来の屈折語尾と統語構造内の位置関係から動詞と述語項との意味論的関係へと移したのである。英欧諸語の格概念を日本語に移植する時には,西欧諸語の語順や格屈折語尾などの格表現形式を類似の日本語表現と対比させた上で,それらの更に奥にある名詞句と述語との関係から割り出された文法的意味をそれに相当する日本語の語彙形態に当てはめることになるであろう。ここにFi11more的な格把握と共通するものがある。日本語の助詞の意味を主語,目的語などの英語の統語要素に対応させた「機能意味」だけではなく,動詞の意味に対する述語項の意味論的役割関係の中で捉えた「機能意味」の観点から再類型化すると,日本語の統語構造を英語の統語構造に依存する事なく分析する手がかりを与えてくれる。本論では,変形生成文法の言語分析成果を基盤とし,意味論的に日本語の統語構造生成を扱った井上和子の「変形文法と日本語」に於ける「格」の取扱方を検討する。
1 0 0 0 OA レーザー光を用いた水の吸光度の測定 : 水の青色を考える実験教材
- 著者
- 田中 謙介
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.240-247, 2005-09-10 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
The mechanisms of how materials are colored are not mentioned in high school science programs, even though colors or changes of colors are very useful in science as indicators of chemical reactions or the presence of chemical substances, for example, litmus papers and starch-iodine titrations. The primary question, 'Why is water blue?', has never been answered in science textbooks for high school. The color of a transparent material is shown as the complementary color of absorbed light in the material. Therefore water absorbs red colored light more than green and blue ones. I developed a new device which can measure optical absorbance of pure water by using red and green laser pointers as light sources and a solar battery as a sensor. The performance of this device shows the following : 1. Red colored light is clearly more absorbed in pure water than green colored light. 2. An absorbance coefficient of red colored light could be calculated as 3.5×10-3, which is almost the same as the previously known figure (E.O. Hulburt, 1945). Laser pointers have become inexpensive and several other colors are being developed. This device which uses these light sources, is expected to be utilized for school experiments.