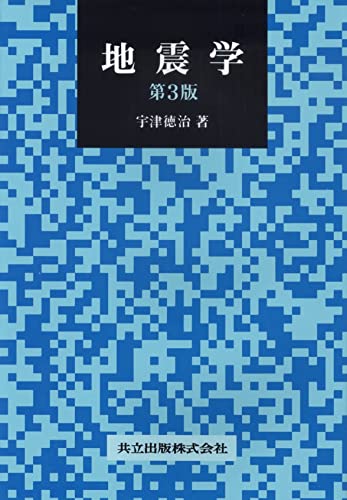1 0 0 0 OA 三重県鈴鹿山麓北部のマンボ灌漑の研究
- 著者
- 服部 義男
- 出版者
- 愛知教育大学地理学会
- 雑誌
- 地理学報告 (ISSN:05293642)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.95-101, 1971-05-31
1 0 0 0 なぜ日本企業は中国市場で消費者の心をつかめないのか
- 著者
- 莫 邦富
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- D&M日経メカニカル (ISSN:13486314)
- 巻号頁・発行日
- no.593, pp.63-68, 2004-02
- 被引用文献数
- 1
2003年12月上旬に,その事件は起きた。事の起こりは,同じ年の 11月下旬に,中国の19の雑誌と11の新聞に掲載された広告である。トヨタ自動車の4輪駆動車「覇道」(日本名「プラド」)と「陸地巡洋艦」(同「ランドクルーザー」)の中国での発売を知らせるその広告の内容は,次のようなものだった。 プラドの走る風景の中に,中華街の獅子舞でおなじみの,獅子が描かれている。
1 0 0 0 OA 東海地震説から東海地震対策へ-40年前の防災対策事始め-
- 著者
- 川端 信正
- 出版者
- NPO法人 地下からのサイン測ろうかい
- 雑誌
- コラボ : 地下からのサイン測ろうかい会報 : カーダス会報 (ISSN:24361534)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-4, 2016 (Released:2021-10-25)
1 0 0 0 OA 研究と実践のはざま ─東海地震予知をめぐって─
- 著者
- 松村 正三 科学技術動向研究センター
- 出版者
- 科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター
- 雑誌
- 科学技術動向2009年11月号 = Science & Technology Trends (ISSN:13493663)
- 巻号頁・発行日
- 2009
1 0 0 0 東海地震と防災 (東海地震と防災<特集>)
- 著者
- 宇佐美 竜夫
- 出版者
- 古今書院
- 雑誌
- 地理 (ISSN:05779308)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.9, pp.p13-47, 1977-09
- 著者
- 川端 信正
- 出版者
- 日本消防設備安全センター
- 雑誌
- 月刊フェスク (ISSN:13435116)
- 巻号頁・発行日
- no.276, pp.4-11, 2004-10
1 0 0 0 特集 どうなる 東海大地震
- 出版者
- 日経サイエンス
- 雑誌
- 日経サイエンス (ISSN:0917009X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.10, pp.26-43, 2002-10
1 0 0 0 地震予知連絡会情報-37-東海地震説について
- 著者
- 佐藤 裕
- 出版者
- 建設広報協議会
- 雑誌
- 建設月報 (ISSN:09171304)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.p77-80, 1978-03
1 0 0 0 東海地震を予告するデ-タ
- 著者
- 石橋 克彦
- 出版者
- 朝日新聞社
- 雑誌
- 科学朝日 (ISSN:03684741)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.p59-67, 1977-01
1 0 0 0 東海地震説から東海地震対策へ-40年前の防災対策事始め-
- 著者
- 川端 信正
- 出版者
- NPO法人 地下からのサイン測ろうかい
- 雑誌
- コラボ : 地下からのサイン測ろうかい会報 : カーダス会報
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-4, 2016
1 0 0 0 IR 研究と実践のはざま--東海地震予知をめぐって
- 著者
- 松村 正三 科学技術動向研究センター
- 出版者
- 科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター
- 雑誌
- 科学技術動向 (ISSN:13493663)
- 巻号頁・発行日
- no.104, pp.9-21, 2009-11
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 東海大地震に備えて : その予知と防災
- 著者
- 大竹 政和
- 出版者
- 独立行政法人防災科学技術研究所
- 雑誌
- 防災科学技術 (ISSN:04541871)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.10-14, 1979-09-25
「大規模地震対策特別措置法」の適用第1号として,静岡県を中心とする6県の合計170市町村が「地震防災対策強化地域」に指定された.中央防災会議,各県,各市町村,.国鉄・NHKなどの指定公共機関,石油化学コンビナートなどの民間の重要施設では,それぞれのレベルで地震防災計画を策定して,大地震の来襲に備えることになる.大地震がいよいよ発生すると判断された場合には,「警戒宣言」が発せられ,それぞれの計画に従って地震防災応急対策が実行に移される.警戒宣言は,気象庁長官から報告される専門的な地震予知情報にもとづいて,総理大臣の判断と責任において発せられることになっている.予知を前提とする地震対策という,世界にも前例を見ない野心的な試みがその第一歩をふみ出したわけである.今回の地域指定の標的は,言うまでもなく駿河湾から御前崎沖を震源地とする「東海大地震」である.それでは,予測される東海大地震とはどのような地震なのだろうか,これを予知するためにどのような努力が行なわれているのだろうか.本稿では,東海大地震の予知に関する現状を概観してみる.
1 0 0 0 OA 日本の地震の予知問題
- 著者
- 茂木 清夫
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.Appendix, pp.40, 1997-03-28 (Released:2011-07-19)
日本は世界有数の地震国であり, これまでたびたび大震災を経験してきた. 先進国の中で国全体が活発な地震帯の中にある国は日本だけである. 従って, いかにして地震災害を軽減するかという問題は, とりわけ我が国において重要な問題であり, その対策の一つとして, 地震予知計画が30年前にナショナルプロジェクトとしてスタートし, 今日に至っている.その間, 国内・国外において地震予知の可能性について, ある時には極端な楽観論が台頭し, ある時には悲観論が主張され, 今日なお地震予知の可能性についての対立した議論が続いている. 極端な悲観論も楽観論も適当でない.一昨年の阪神大震災はここ50年の間では際立って大きい災害をもたらした. この地震は, 予知されずに突発的に起こったが, 地震発生後収集された前兆現象をまとめて見ても, 微弱であり, 予知が困難なケースであった.最後に, 1978年に制定された大規模地震対策特別措置法 (大震法) によって, 予知できることを前提とした東海地震対策が進められているが, その重大な問題点を指摘し, その早急な再検討が必要である.
1 0 0 0 IR 地震音波データ同化システムの開発 ―双子実験による検証―
- 著者
- 長尾 大道 樋口 知之
- 出版者
- 統計数理研究所
- 雑誌
- 統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics (ISSN:09126112)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.257-270, 2013-12
要旨あり環境リスクと統計解析 -データ基盤構築と解析-原著論文
1 0 0 0 短周期微動に含まれるレイリー波の特性と地盤構造の関係
- 著者
- 時松 孝次 宮寺 泰生
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会構造系論文報告集 (ISSN:09108025)
- 巻号頁・発行日
- vol.439, pp.81-87, 1992
- 被引用文献数
- 18 17
Short-period microtremors are observed at two sites using arrays. It is found that their variation with frequency of amplitude ratio between horizontal and vertical motions is stable during a 24-hour period and is similar to that of Rayleigh waves, and that the frequencies at which the amplitude ratio becomes the maximum correspond to the natural periods of the sites. The frequency wavenumber spectrum analysis of microtremor vertical motions yields Rayleigh wave dispersion curves which reflect the shear structures of the sites. These findings suggest that site effects can be reliably estimated by extracting Rayleigh wave characteristics from microtremors.
1 0 0 0 1977年8月インドネシア・スンバワ島の地震による地球の自由振動
- 著者
- Kashiwabara Shizuo Hamada Nobuo Yamamoto Masahiro
- 出版者
- Japan Meteorological Agency
- 雑誌
- 気象研究所研究報告 (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.153-165, 1979
地球の自由振動については,1960年のチリ地震以来,数多くの観測および解析結果が報告されている。しかし観測の歴史はまだ浅く今後さらに観測資料の蓄積が大切であろう。<BR>現在気象庁で用いている測器で地球の自由振動のような長周期地震波の解析に利用できるものとしては,松代の石英管式ひずみ計・WWSS地震計・ASRO地震計および地震課で東海・南関東地域に展開中の埋込式ひずみ計がある。これらの器械は観測期間がまだ短かいこともあって,今日までに,自由振動の観測および解析はあまり行なわれていない。このため今回,松代の石英管式ひずみ計および伊良湖・三ケ日の埋込式ひずみ計の資料を用いて1977年8月にインドネシア・スンバワ島付近に発生した地震の解析を行なった。主な結果は次のとおりである。<BR>(1)石英管式ひずみ計から<SUB>0</SUB>S<SUB>n</SUB>について29個,<SUB>1</SUB>S<SUB>n</SUB>について10個,<SUB>2</SUB>S<SUB>n</SUB>について8個,<SUB>l</SUB>T<SUB>n</SUB>について23個のモード,また埋込式ひずみ計から<SUB>0</SUB>S<SUB>n</SUB>について29個のモードの地球の自由振動周期が得られた。これらの値と今日までに求められている観測値の平均値〔Anderson・Hart(1976)による〕との差はほとんどのモードで約0.5%以内である。<BR>(2)観測から得られた地球の自由振動周期を用いて表面波の位相速度を求めた。求めたレイリ波の位相速度は,Anderson・Hartの値から求めた速度よりやや大きくなる傾向が見られた。この相違は解析した地震の波の伝播径路中に位相速度の大きい海洋的地域および盾状地的地域(Canadian・Brazilian shields)の占める比率が大きいために生じたものであろう。<BR>(3)自由振動の解に含まれる関数d<SUP>2</SUP>P<SUB>n</SUB><SUP>m</SUP>(cosθ)/dθ<SUP>2</SUP>から求めた位数の零点列と地震記録の周期解析から求めたスペクトルピークの極小を与える位数の列を比較して自由振動のデグリーを決めた。松代の石英管式ひずみ計による伸び縮み振動に対応するスペクトルを用いた場合,デグリーは0または2となる。
1 0 0 0 IR 皮肉らしさに関わる要素についての一考察 : 皮肉表現以外の要素に着目して
- 著者
- 太田 いずみ Ota Izumi オオタ イズミ
- 出版者
- 大阪大学大学院言語文化研究科日本語・日本文化専攻
- 雑誌
- 日本語・日本文化研究 = Studies in Japanese language and culture (ISSN:09182233)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.216-225, 2017-12
1 0 0 0 日本におけるキャンプ場の森林利用の動向
- 著者
- 平野 悠一郎
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース
- 巻号頁・発行日
- vol.132, 2021
<p>日本では1960~90年代にかけて、アウトドア・レジャー活動としてのキャンプへの関心が高まり、各地の国有林・民有林内にも多くのキャンプ場が設立された。しかし、1990年代後半以降は、経済不況と利用者の減少による施設過剰状態となり、大多数のキャンプ場の経営が悪化した。これを受けて、2000年代以降は、民間の経営主体を中心に、キャンプ場の再生の動きが顕著となる。その一環として、ウェブを通じた情報集約・予約システムの構築や、宿泊・体験の「質」を重視する動きが見られてきた。近年では、そうしたキャンプ場再生の動きが、幾つかの方向性を伴って加速しつつある。例えば、グランピングやワーケーションの場としての施設整備に加えて、自然教育の機会としてのプログラムを充実させ、また、地域資源活用による地域活性化の基点として位置づける等の傾向が、事例調査を通じて確認できた。</p>