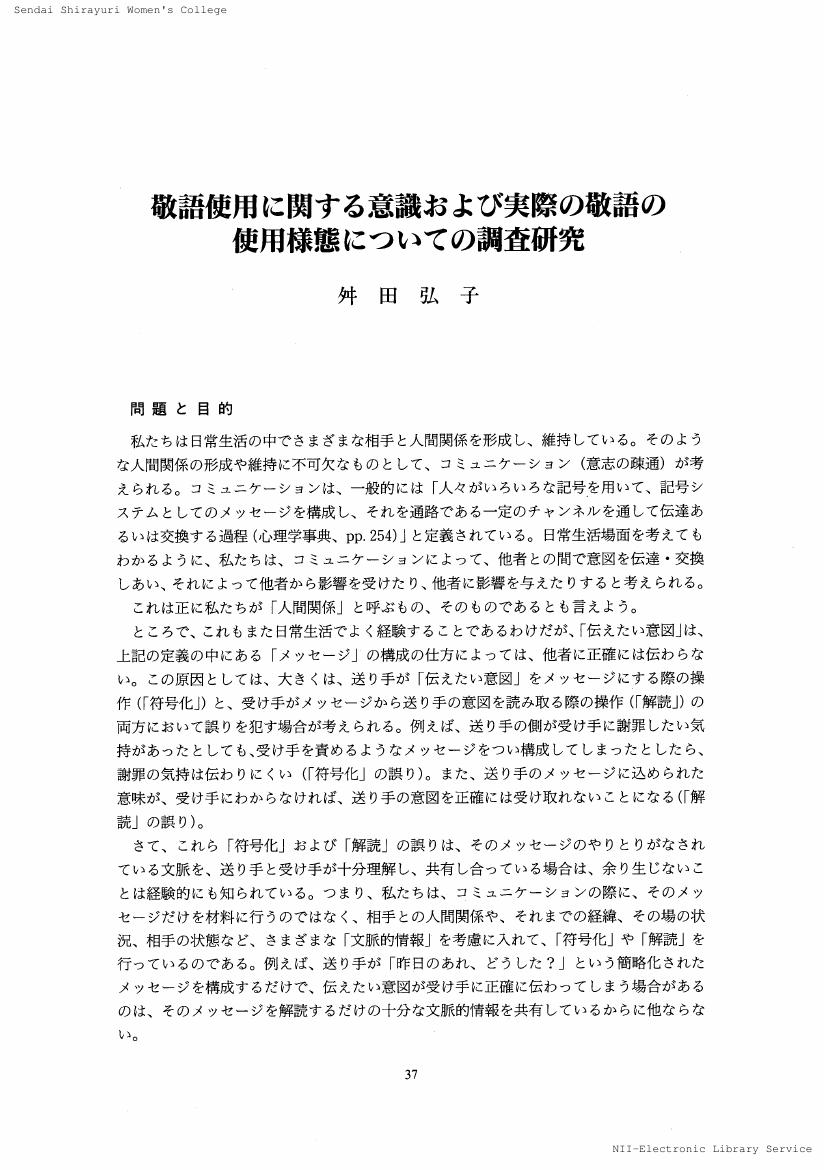1 0 0 0 林冠閉鎖前の若いオオハ゛ヒルキ゛人工林の落葉量推定
1 0 0 0 OA バルザック『十三人組物語』における数をめぐって
- 著者
- 西川 和泉
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会関西支部
- 雑誌
- 関西フランス語フランス文学 (ISSN:24331864)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.14-23, 2004-03-31 (Released:2017-07-14)
La societe secrete <<Les Treize>> ne joue qu'un role secondaire dans les trois recits de l'Histoire des Treize. Pourtant, le nombre sinistre <<treize>> n'est pas pose au hasard par Balzac, interesse par la mystique et l'ecole pythagoricienne qui considere le nombre comme un symbole des idees. Les variantes de La Duchesse de Langeais nous donnent un indice sur la reflexion du romancier sur l'utilisation des nombres, en particulier du nombre <<treize>>. Par ailleurs, l'analyse des indications temporelles dans Ferragus et La File aux yeux d'or nous permettra de constater que la mort des heroines est egalement donnee treize jours apres un evenement crucial pour elles. Cette utilisation strategique des nombres, commune surtout entre ces deux recits, nous offre la possibilite de lire ces recits - apparemment independants - comme une trilogie dont le titre porte le nombre <<Treize>>.
1 0 0 0 NFTと法律関係(第1回)NFTの仕組みと私法上の整理
- 著者
- 熊澤 拓也
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.63-80, 2015
本稿の目的は、1933年から1937年までの日本におけるアメリカンフットボール(以下「フットボール」)を事例に、その中心的な活動主体だったアメリカからの日系二世留学生に焦点を当て、日本スポーツ外交史の一端を読み解くことである。<br> 日本においてフットボールは1902年に初めて行われたが、競技の危険性などから、その後30年間は定着することがなかった。しかし、1933年に日系二世留学生によって始められた活動は、1934年の統括団体の結成と公式戦の開催、1935年の全米学生選抜の来日、1936年から1937年にかけての全日本選抜のアメリカ遠征など、数年の内に急速に展開し、現在の日本フットボール界の起源となった。<br> この背景には、1931年の満洲事変、1932年の上海事変と満洲国の建国、1933年の国際連盟脱退通告などを背景に、国際社会の中で進む日本の孤立化という時代状況があった。当時、日本の政府関係者や指導者層は、日本の正当性を国際社会に向けて喧伝する目的で、2つの手段に着目した。 第1は国際交流やスポーツ外交であり、第2は日系二世留学生である。スポーツに関しては1932年のロサンゼルスオリンピックの成功を受け、その外交的有用性が認知されていた。また、1931年の満洲事変を機に急増した日系二世留学生に対しては、日米の懸け橋というまなざしが向けられていた。これは、留学生が本国に帰った後、日本の立場を擁護する代弁者としての役割を果たすよう期待する考えである。<br> 以上より、1933年から1937年までの日本において、フットボールの活動が急速に展開した要因は次の2点が考えられる。第1は、日米の懸け橋というまなざしを向けられていた日系二世留学生が中心的な活動主体であったこと、第2は日米親善を目的としたスポーツ外交が求められていたことである。このことは、1937年の日中戦争勃発を機に、日系二世留学生の数が減り始め、国際交流やスポーツ外交が沈静化すると同時に、フットボールの活動も停滞し始めることと無関係ではないだろう。
1 0 0 0 IR 2020年シンガポール総選挙 : 与党停滞と野党伸張、議会政治の転換点と将来への希望
- 著者
- 久末 亮一
- 出版者
- 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- IDE スクエア -- 論考
- 巻号頁・発行日
- pp.1-15, 2020-08
1 0 0 0 OA デンマークとオランダにおける医療健康データの二次利用について
- 著者
- 伊藤 伸介
- 出版者
- 一般社団法人 日本統計学会
- 雑誌
- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.109-138, 2020-09-30 (Released:2020-12-10)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
ヨーロッパ諸国の中で,北欧諸国を中心に行政記録情報に基づく「レジスターベース」の統計作成システムが確立されてきた.デンマークのような北欧諸国やオランダのような国々では,学術研究のための行政記録情報の利用サービスも展開されている.それに伴い,行政記録情報の1つである医療健康データへのアクセスを可能にするための仕組みも整備されてきた.本稿では,デンマークとオランダの事例をもとに,行政記録情報としての医療健康データの二次利用の展開方向を洞察する.デンマークやオランダにおける医療健康データの二次利用の特徴は,IDによって各種のレジスターデータをリンケージした上で仮名化された医療・健康に関するデータの利用が可能になっていることである.これらの事例は,わが国における行政記録情報の利活用のあり方を検討する上でも参考になる点が少なくないと思われる.
1 0 0 0 OA フィンランドにおける医療分野レジスタとデータ提供の状況
- 著者
- 木村 映善 大寺 祥佑 佐々木 香織 黒田 知宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本統計学会
- 雑誌
- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.47-80, 2020-09-30 (Released:2020-12-10)
- 参考文献数
- 80
- 被引用文献数
- 1
我が国は超高齢化社会に伴う医療費の拡大を控え,政策に資するエビデンスを導出するために,外的妥当性が高いと期待されるReal World Dataを用いた研究に注目しつつある.次世代医療基盤法の認定事業者は2019年末に第1号が認定されたばかりであり,管理,匿名加工,データ提供の方法論を模索中である.一方包括的かつ悉皆的な医療情報の収集体制を制度的に実現したフィンランドは,オプトアウト方式で全国の医療機関から個人番号つきで患者情報を収集し,様々なデータソースから個人番号を用いた個人単位のデータ連結を行い,二次利用用途に匿名化したデータを提供している.まさに認定事業者が担わんとしている役割を先行的に実現しているところであり,同国の現状を知ることは 我が国における今後の医療情報に関する政策の方向性を検討する上で,有意義であると推察される.渡航及び文献調査にもとづいて,フィンランドの健康医療情報に関するレジスタ,制度環境,匿名加工に関するガイドラインならびに最近の動向を紹介する.
- 著者
- 佐々木 香織 大寺 祥佑 木村 映善
- 出版者
- 一般社団法人 日本統計学会
- 雑誌
- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.81-108, 2020-09-30 (Released:2020-12-10)
- 参考文献数
- 40
わが国では診療情報の二次利用を促進する「次世代医療基盤法」が2018年5月11日より施行された.この法律により「認定事業者」なる機関が,日本全国の施設から診療記録を収集・保管し,更に膨大なデータから医療統計を用いた研究を行う専門家に対して「認定事業者」が匿名加工を施したデータを供与することが可能となった.イギリスのEnglandでは我が国に先んじて,Care dot Data(2013–6)という医療データの二次利用を促進させる政策を実行したが,市民からの信頼を得られず逆に不信感をつのらせ,2015年に一時中断し2016年には正式に廃止する結果となった.ところが2015–6年よりNHS Digitalを中心として,新たな制度と基盤を構築し始めたところ,その政策は成功を収める結果となった.そこで本稿はEnglandにおいて政策的失敗後に,如何にしてより包括的でより正確な医療統計を可能とするような医療情報の二次利用の基盤や社会システムを整備し,政策的成功へと導いたかを議論する.その目的はEnglandの経験や知恵が日本にどのように活かすことができるかを考察し,我が国により良い制度が構築できるよう提言することである.なお本稿における論考は専門家と専門知が如何に現代社会を支えているかを論じたルーマン(1990),ギデンズ(1993),ベック(1998)に依拠し,医療統計をはじめとした様々な統計の社会的な役割を含め,専門家と専門知に支えられた今日の社会秩序の構築と,それらに対する市民からの「信頼」に関する課題を視野に入れて進められる.
1 0 0 0 OA 「恋愛社会学」序説 恋愛の社会学的分析の可能性
- 著者
- 山田 昌弘
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.1989, no.2, pp.95-106, 1989-06-17 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 25
There have been few articles on the sociological analysis of love. In this paper, it is tried to make framework of sociological analysis of love in with reference to ‘Sociology of Emotions’, and to understand the character of the love institution in modern society by using the fruits of Social History. It is understood that love is constructed subjectively by feeling rules regulating the relation between situations, desires to act, emotional words. And love is institutionalized by the several types of norms. In modern society, the love institutions are characterized by the enclosure in marriage.
1 0 0 0 「牛白血病に関する衛生対策ガイドライン」の概要
- 著者
- 井川 真一
- 出版者
- 獣医疫学会
- 雑誌
- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.114-118, 2015
- 被引用文献数
- 2
牛白血病は大きく2つの型に分類され,一つは地方病性牛白血病(Enzootic bovine leukosis。以下「本病」という。)と呼ばれる型で,牛白血病ウイルス(bovine leukemia virus。以下「BLV」という。)が関与する家畜の伝染性疾病である。大部分のBLV感染牛(以下「感染牛」という。)は無症状のままで過ごし,経済動物としての役割を全うできるが,一部の感染牛が体表リンパの腫脹,削痩,元気消失,眼球突出,乳量減少,下痢など様々な症状を呈する。もう一つは,散発性牛白血病(Sporadic bovine leukosis)と呼ばれる原因が不明の型がある。牛白血病が平成10年に届出伝染病に指定されて以降,届出件数は増加傾向にあり,我が国における更なる感染拡大が危惧されている。このような中,農林水産省では,平成22~24年度に実施したレギュラトリーサイエンス新技術開発事業で,飼養管理の変更による感染拡大リスクの低減効果の検証等を行い,ここで得られた本病の伝播リスクやまん延防止措置に係る研究結果を基に検討を進め,都道府県,関係団体等の意見も踏まえて,平成27年4月,本病対策の基本的な考え方,農場内での感染拡大を防止するための対策,農場への侵入防止対策等を定めた「牛白血病に関する衛生対策ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を取りまとめた。本稿では,このガイドラインの構成に沿って概要を紹介する。
1 0 0 0 OA 『一刀斎先生剣法書』訳注及びスポーツ教育的視点からの考察 (1)
- 著者
- 竹田 隆一 長尾 直茂
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 山形大学紀要. 教育科学 = Bulletin of Yamagata University. Educational Science
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.51(145)-68(162), 2003-02-17
剣道の技術に関する名辞は, 非常に難解であり, 円滑な技術指導の障害となることも考えられる。しかし, それは, 剣道のもつ身体観や技術観などの文化的特性のあらわれととらえることができる。そこで, 剣道技術指導書の先行形態である近世の武芸伝書を取り上げ, 技術に関する名辞を考察することによって, 剣道の文化的特性を明らかにすることを目的とした。 本稿では, 一刀流の伝書である『一刀斎先生剣法書』取り上げたが, それは, 一刀流が現代剣道の源流の一つに数えられるためである。ただ, 流祖伊藤一刀斎みずからが書いた伝書というものは現在伝わらず, 一刀流を理解するためには, その門人達の伝書によるしかないのである。そこで, 一刀斎の門人古藤田俊直を祖とする唯心一刀流の伝書『一刀斎先生剣法書』を現代語訳し, 技術に関する名辞をスポーツ教育の視点から考察することにした。その結果, 従来から使用されている「事理」, 「水月」,「残心」,「威勢」の意味内容が明らかになった。なお, 今回の考察は, 全16章のうち5章までである。
1 0 0 0 OA 『一刀斎先生剣法書』訳注及びスポーツ教育的視点からの考察(3)
- 著者
- 竹田 隆一 長尾 直茂
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 山形大学紀要. 教育科学 = Bulletin of Yamagata University. Educational Science
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.1(251)-12(262), 2005-02-15
承前 : 研究の目的・意図等については前稿である(1)(2)(『山形大学紀要(教育科学)』第13巻・第2, 3号所収。2003年2月及び2004年2月刊)の冒頭に記したので,ここに贅言を重ねることはしない。ただし,凡例のみは便宜上,今一度載せることとした。今回は第11章から最後の第16章までの5章を取り扱う。 凡例 : ◎訳注の底本には,今村嘉雄『日本武道大系』第二巻・剣術(2)(同朋舎,1982)に収録された,京都鈴鹿家所蔵本『一刀斎先生剣法書』を用いた。但し,句読点は適宜に改めた箇所がある。また,参考資料として杉浦正森『唯心一刀流太刀之巻』を用いたが,これも『日本武道大系』第二巻所収のテキストに拠る。ちなみに『一刀斎先生剣法書』は寛文四年(1664)に,『唯心一刀流太刀之巻』は天明三年(1783)に稿成ったものである。 ◎本書は16章から成るが,これを適宜に段落に分かち,そこに語注,現代語訳,そして必要に応じて補説を加えた。 ◎語注は長尾が担当し,補説は竹田が担当した。現代語訳は両者で検討,吟味した上,ここに掲出した。なお,抄訳ではあるが,本書の現代語訳を試みたものに,吉田豊『武道秘伝書』(徳間書店,1968)があり,適宜に参照した。
1 0 0 0 OA 『一刀斎先生剣法書』訳注及びスポーツ教育的視点からの考察 (2)
- 著者
- 竹田 隆一 長尾 直茂
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 山形大学紀要. 教育科学 = Bulletin of Yamagata University. Educational Science
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.45(237)-58(250), 2004-02-16
承前 : 研究の目的・意図等については前稿(『山形大学紀要(教育科学)』第13巻・第2号所収。pp145-162。2003年2月刊)の冒頭に記したので, ここに贅言を重ねることはしない。ただし, 凡例のみは便宜上, 今一度載せることとした。今回の考察は第6章から10章までの5章である。 凡例 ◎訳注の底本には, 今村嘉雄『日本武道大系』第二巻・剣術(2)(同朋舎, 1982)に収録された, 京都鈴鹿家所蔵本『一刀斎先生剣法書』を用いた。但し, 句読点は適宜に改めた箇所がある。また, 参考資料として杉浦正森『唯心一刀流太刀之巻』を用いたが, これも『日本武道大系』第二巻所収のテキストに拠る。ちなみに『一刀斎先生剣法書』は寛文四年(1664)に, 『唯心一刀流太刀之巻』は天明三年(1783)に稿成ったものである。 ◎本書は16章から成るが,これを適宜に段落に分かち,そこに語注,現代語訳,そして必要に応じて補説を加えた。 ◎語注は長尾が担当し, 補説は竹田が担当した。現代語訳は両者で検討, 吟味した上, ここに掲出した。なお, 抄訳ではあるが, 本書の現代語訳を試みたものに, 吉田豊『武道秘伝書』(徳間書店, 1968)があり,適宜に参照した。
1 0 0 0 日本における豚コレラの撲滅達成と今後
- 著者
- 青木 博史
- 出版者
- 獣医疫学会
- 雑誌
- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.120-124, 2008
- 被引用文献数
- 1
平成19年4月1日に,我が国は国際獣疫事務局(OIE)の規約により豚コレラ清浄国となった。すなわち,明治21年の初発生から約120年を経て,養豚分野に大きな被害をもたらした豚コレラが完全に排除されたわけである。この「豚コレラ撲滅達成」という日本の家畜衛生史に残る偉業は,他国に類をみない優れた予防・診断技術の開発や改良,それらを取り入れた撲滅計画が個々に優れているのはもちろん,過程における,生産者,各民間団体,行政機関,研究・検査機関及びワクチン製造所など関係者が一体となって取り組んできた結果によるものであり,世界的にも高く評価される。そして,豚コレラの撲滅を達成した後も「豚コレラ防疫史」をさらに築き綴らねばならない。「清浄化」は免疫のない高感受性の豚集団の再汚染・拡散のリスクを有していることと表裏一体であり,従って,豚コレラウイルスの侵入と拡散を防止するための迅速かつ円滑な豚コレラ発生予防及びまん延防止措置を継続し,清浄化を維持することが重要となる。豚コレラ清浄化から間もなく2年を迎える現在,関係者の不断の努力により野外ウイルスの侵入を許していない。この監視体制をもって豚コレラ清浄化を継続・維持しなければならない。
1 0 0 0 OA シャンプー・トリートメントによる毛髪の修復機構
- 著者
- 杉山 保行 太田 雅壽
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子論文集 (ISSN:03862186)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.94-98, 2018-01-25 (Released:2018-01-25)
- 参考文献数
- 7
Because of shampooing, drying, brushing etc., hair twists, breaks or acquires split ends; furthermore the cuticle may come off. We tried developing a shampoo agent and conductive treatment agent which repairs hair damaged by washing, drying, brushing, coloring, or perming. The effect of both agents on repair of damaged hair was examined by transmission electron microscopy and electrical conductivity. We compared previous data of optical microscopy with transmission electron microscopy images. As a result, it is clear that a scale-forming material, like a cuticle, is deposited in the keratinization region, and the frizzled hair became straight, because of using shampoo agent and conductive treatment agent containing hematin. These facts suggest that components of shampoo, treatment and/or hair cortex are preferentially adsorbed to the asperities of fragments which are cut off from the cuticle and then these components produce the scale-forming material, like a cuticle, due to epitaxial growth.
1 0 0 0 OA <論文>敬語使用に関する意識および実際の敬語の使用様態についての調査研究
- 著者
- 舛田 弘子
- 出版者
- 学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学
- 雑誌
- 仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.37-47, 2001 (Released:2018-07-20)
1 0 0 0 OA 子育て期世帯の都心居住 関西三都市の比較研究
- 著者
- 高田 光雄 巽 和夫 毛谷村 英治 大森 敏江
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.775-780, 1991-10-25 (Released:2020-05-01)
THIS STUDY IS THE ANALYSIS ABOUT URBAN LIVING OF FAMILIES WITH CHILDREN IN CENTRAL AREA OF 3 BIG CITIES, KYOTO, OSAKA AND KOBE, IN THE KANSAI REGION, BASED ON THE QUESTIONNAIRE TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR MOTHERS. THE RESULTS ARE AS FOLLOWS; 1)THE CHARACTERISTIC OF FAMILIES WITH CHILDREN IN CENTRAL AREA IS THAT NUMBERS OF 3 GENERATOIN FAMILIES AND DUAL-INCOME FAMILIES ARE MANY. 2) MOST PEOPLE APPRECIATE CONVENIENCE OF COMMUTING AND SHOPPING, BUT SHORTAGE OF PLAYGROUND, NOISE AND AIR POLLUTION MAKE THE LIVING ENVIRONMENT FOR CHILDREN WORSE. 3)MOST OF CHILDREN PLAY INDOOR, THOUGH THEY PREFER TO PLAY IN PARKS.
- 著者
- 相良 友哉
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究 (ISSN:21871930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.30, pp.852-859, 2020-01-01 (Released:2020-10-15)
- 参考文献数
- 18
社会構造の変化により,「社会的な居場所づくり」への関心が高まっている.とりわけ,家庭,職場・学校に次ぐ第三の場,いわゆるサードプレイスを持つことが重要視されているが,コロナ禍の外出自粛に代表されるように,様々な事情で,人々が直接集うことが出来ない場合がある.このような問題に対処するひとつの方策として,サイバー空間にサードプレイスを形成し,オンラインで交流する方法がある.そこで,本研究は,動画の生配信を行うコミュニティスタジオに注目し,サードプレイスとしての要件を持っているか検討した. 首都圏にあるスタジオCのFacebookページの内容分析および,スタジオでの参与観察により,スタジオCが,サードプレイスとしての8つの特徴を備えていること,スタジオにおけるオフラインの直接的なコミュニケーションと生配信を通じたオンラインのコミュニケーションとが重層的に機能しており,配信者にとっても,視聴者にとっても心地よい居場所になっていることが示唆された.