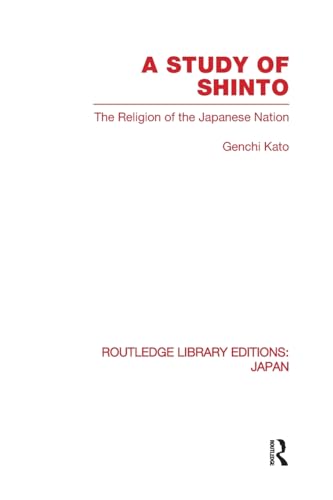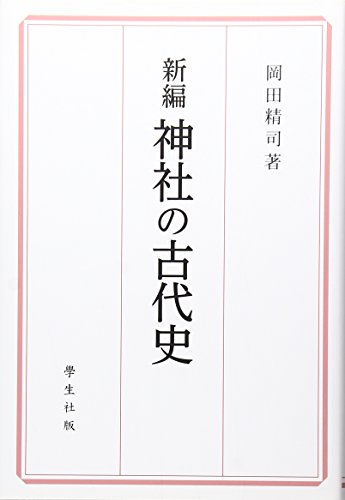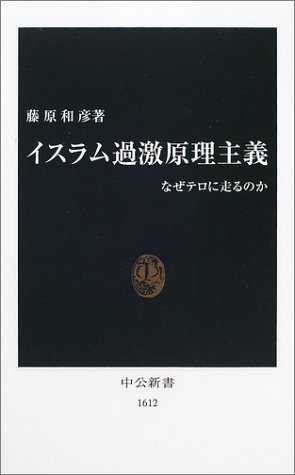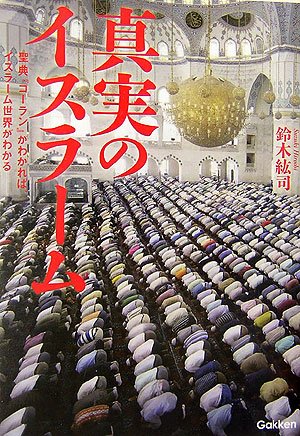1 0 0 0 IR 「妣国根之堅州国」をめぐって--「黄泉国」との関係
- 著者
- 小村 宏史
- 出版者
- 早稲田大学国文学会
- 雑誌
- 国文学研究 (ISSN:03898636)
- 巻号頁・発行日
- vol.145, pp.51-62, 2005-03
1 0 0 0 IR 文献資料から見る石上神宮の鎮魂と鎮魂祭 : 古代から近現代の資料を中心とした考察
- 著者
- 田村 明子
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 常民文化 (ISSN:03888908)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.150-127, 2011-03
1 0 0 0 IR 土俵まつり考
- 著者
- 山田 知子
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.p14-27, 1989-12
1 0 0 0 IR 古代日本の神仏信仰 (共同研究 神仏信仰に関する通史的研究)
- 著者
- 北條 勝貴
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.148, pp.7-39, 2008-12
古代日本における神社の源流は、古墳後期頃より列島の多くの地域で確認される。天空や地下、奥山や海の彼方に設定された他界との境界付近に、後の神社に直結するような祭祀遺構が見出され始めるのである。とくに、耕地を潤す水源で行われた湧水点祭祀は、地域の鎮守や産土社に姿を変えてゆく。五世紀後半~六世紀初においてこれらに生じる祭祀具の一般化は、ヤマト王権内部に何らかの神祭り関係機関が成立したことを示していよう。文献史学でいう欽明朝の祭官制成立だが、〈官制〉として完成していたかどうかはともかく、中臣氏や忌部氏といった祭祀氏族が編成され、中央と地方を繋ぐ一元的な祭祀のあり方、神話的世界観が構想されていったことは確かだろう。この際、中国や朝鮮の神観念、卜占・祭祀の方法が将来され、列島的神祇信仰の構築に大きな影響を与えたことは注意される。律令国家形成の画期である天武・持統朝には、飛鳥浄御原令の編纂に伴って、祈年祭班幣を典型とする律令制祭祀や、それらを管理・運営する神祇官が整備されてゆく。社殿を備えるいわゆる〈神社〉は、このとき、各地の祭祀スポットから王権と関係の深いものを中心に選び出し、官の幣帛を受けるための荘厳された空間―〈官社〉として構築したものである。したがって各神社は、必然的に、王権/在地の二重の祭祀構造を持つことになった。前者の青写真である大宝神祇令は、列島の伝統的祭祀を唐の祠令、新羅の祭祀制と対比させつつ作成されたが、その〈清浄化イデオロギー〉は後者の実態と少なからず乖離していた。平安期における律令制祭祀の変質、一部官社の衰滅、そして令制以前から存在したと考えられる多様な宗教スポットの展開は、かかる二重構造のジレンマに由来するところが大きい。奈良中期より本格化する神階制、名神大社などの社格の賜与は、両面の矛盾を解消する役割を期待されたものの、その溝を充分に埋めることはできなかった。なお、聖武朝の国家的仏教喧伝は新たな奉祀方法としての仏教を浮かび上がらせ、仏の力で神祇を活性化させる初期神仏習合が流行する。本地垂迹説によってその傾向はさらに強まるが、社殿の普及や神像の創出など、この仏教との相関性が神祇信仰の明確化を生じた点は無視できない。平安期に入ると、律令制祭祀の本質を示す祈年祭班幣は次第に途絶し、各社奉祀の統括は神祇官から国司の手に移行してゆく。国幣の開始を端緒とするこの傾向は、王朝国家の成立に伴う国司権力の肥大化のなかで加速、やがて総社や一宮の成立へと結びつく。一方、令制前より主な奉幣の対象であった畿内の諸社、平安京域やその周辺に位置する神社のなかには、十六社や二十二社と数えられて祈雨/止雨・祈年穀の対象となるもの、個別の奉幣祭祀(公祭)を成立させるものが出現する。式外社を含むこれらの枠組みは、平安期における国家と王権の関係、天皇家及び有力貴族の信仰のあり方を明確に反映しており、従来の官社制を半ば超越するものであった。以降、神社祭祀は内廷的なものと各国個別のものへ二極分化し、中世的神祇信仰へと繋がってゆくことになるのである。
- 著者
- Genchi Katu
- 出版者
- Routledge, Taylor & Francis Group
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 祟り神の変身--祟る神から罰する神へ
- 著者
- 佐藤 弘夫
- 出版者
- 日本思想史学会
- 雑誌
- 日本思想史学 (ISSN:03865770)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.45-63, 1999
1 0 0 0 日本神話に見る生と死 (生と死の思想<特集>)
- 著者
- 上田 賢治
- 出版者
- 東洋哲学研究所
- 雑誌
- 東洋学術研究 (ISSN:02876086)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.p48-62, 1988-08
1 0 0 0 本居宣長の神の定義について
- 著者
- 大久保 紀子
- 出版者
- 日本思想史学会
- 雑誌
- 日本思想史学 (ISSN:03865770)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.129-146, 1996
1 0 0 0 IR 8・9世紀の神社行政 : 官社制度と神階を中心として
- 著者
- 巳波 利江子
- 出版者
- 奈良女子大学史学会
- 雑誌
- 寧楽史苑 (ISSN:02878364)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.22-57, 1985-02-15
1 0 0 0 IR 中国におけるイスラム教教派
- 著者
- 丸山 鋼二
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文教大学国際学部紀要 = Journal of the Faculty of International Studies, Bunkyo University (ISSN:09173072)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.129-155, 2001-02
Islam sects in Modern China are generally called "Three-big Sects and Four-big menhuan". The first Islam sect "Sufism brotherhood(menhuan)" was shaped 300 years ago, though Islam was introduced into China in 7th century. In opposition to the appearance of menhuan(jahariyah、Khufiyyah、Kubrawiyyah、Cadriyah), muslims who had maintained the traditional ceremony and system from old times called themselves "Qadim". Its characteristics is tolerance. In early 20th century the two sects were differentiated. One is a new sect "Ikhwani", which criticized both Qadim and menhuan strictly as unfaithful to the Koran. The other is Xidaotang, called "Chinese classics Sect". The doctrinal difference is not great among Islam sects in China. There are distinguished differences in the unessential problems of the religious ceremony and customs. Those differences frequently gave rise to a quarrel of bloodshed between Ikhawani and other sects in Modem China.
1 0 0 0 イスラム過激原理主義 : なぜテロに走るのか
1 0 0 0 OA 学級通信の教育的効果とその意義 : 生活ノート連動型学級通信の実践事例
- 著者
- 岸田 幸弘 吉岡 典彦
- 出版者
- 学校法人松商学園松本大学
- 雑誌
- 教育総合研究 = Research and Studies in Education (ISSN:24336114)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.191-206, 2021-11-30
本事例は、生徒の生活ノートと連動した学級通信を発行し続けている中学校教師の実践を詳細に分析し、一つの事例として検討することを通して、改めて学級通信の役割と作成の視点を明らかにした。生徒・保護者・同僚職員のアンケート調査から、生徒の文章表現力を高め、担任教師と生徒との信頼関係を築き、生徒同士の仲間意識を醸成することをねらいとした生活ノート連動型学級通信は、先行研究で指摘されている「保護者との連携」「子どもとの信頼関係」「教師としての資質向上」「子ども同士の信頼関係」を構築するツールとして機能していたことが示唆された。
- 著者
- 李 瑾 周 霏
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.896-901, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)
- 参考文献数
- 18
多くの水害ハザードマップでは、紙面での表現が限定されているため、浸水想定区域内のみを示すケースが多い。しかし、浅い浸水想定区域でも、最大流速が速い場合は、避難が困難になる。住民が正確に避難判断を行うためには、最大浸水深、最大流速、浸水到達時間などの複数の情報を掲載することがよいが、すべての住民に高度な情報解釈能力が備わっているとは限らない。ハザードマップを判読する際に、正しい情報を読み取れにくいことから、誤解を招く可能性がある。本研究では、いすみ市ため池(名熊ダム)ハザードマップ作成を事例として、最大浸水深、最大流速、浸水到達時間を掲載しつつ、数値情報への理解が困難な場合でも、より現地に適した災害リスク情報を反映するバッファゾーンの設定を試みる。バッファーゾーンの設定は、簡易氾濫解析データをもとに、国土地理院で公開されている基盤地図情報を用いて、現地調査を行い、浸水想定区域が広がると思われるケース、浸水想定区域が広がらないと思われるケース、標高の観点から簡易氾濫解析データの精度の確認、浸水想定区域の浸水深を消去したケース、既往豪雨時の浸水実績の反映の5つの視点から、現地調査の結果から浸水想定区域の妥当性を判断した。
- 著者
- 向井 理 柳本 操
- 出版者
- 日経BP社 ; 2002-
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.24-27, 2015-01
明治大学の農学部で遺伝子工学を学び、実験三昧だった日々から、バーテンダーへ、さらに俳優へと転身。20代の10年間で軽々と活躍するステージを飛び越えてきた、俳優・向井理さん。「大きな目標に固執し続けるのはかえってマイナスになることも。
- 著者
- 植田 健男
- 出版者
- 部落問題研究所
- 雑誌
- 人権と部落問題 (ISSN:13474014)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.32-37, 2022-01
1 0 0 0 OA 1984年日向灘津波と周辺の津波活動
- 著者
- 羽鳥 徳太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.1-6, 1987-03-25 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
Based on tide-gauge records, the Hyuganada tsunami of Aug. 7, 1984 is investigated. Adding the present data, the pattern of tsunami activity off the east coast of Kyushu since 1899 is discussed on a space-time diagram. The magnitude (Imamura-Iida scale) of the 1984 tsunami is estimated to be m=-1. This grade is small for an earthquake having magnitude of M=7.1. The source area of tsunami estimated by means of an inverse refraction diagram agrees with the aftershock area, and the source length is 25km in the N-S direction. The initial motion of the tsunami was in an upward direction at Hyuga-Shirahama, but at Tosa-Shimizu and Muroto, the initial disturbance began with a down motion. It suggests the west side of the sea-bottom uplifted and the east side subsided.According to the geographic distribution of the source area of the Hyuganada tsunamis generated during the last 86 years (1899-1984), the tsunami sources are parallel to the bathymetric line and their region is divided by three groups: A) is located near the Kyushu coast, B) about 50km east from the Kyushu coast and C) off the Shikoku coast. A tsunami of each group was generated on extension of the major axis of the former source. Tsunami magnitudes (Imamura-Iida scale, m=0-1.5) of the A and C groups are larger than that of the B group. From the pattern of generating cycle, the northern part of the A group is considered a region of relatively high tsunami risk as a type of the 1941 earthquake.
1 0 0 0 OA 奄美語の現況から
- 著者
- 松本 泰丈 田畑 千秋
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, pp.143-154, 2012 (Released:2021-09-15)
- 参考文献数
- 8
2009年にユネスコによって「危機言語」として指定された奄美語の現況を,本土出身の研究者(松本)と島出身のnative speaker(田畑)という異なった立場を持つ二名が,それぞれの立場から粗描した。粗描の方法は「1960年代までの奄美語」,「1970~80年代の奄美語」,「1990~現代の奄美語」に分け,それぞれの時代における奄美語の状況を,両名の直接見聞をふまえて述べる。(結論的にいえば)両名は,1960年代まではシマユムタ(伝統的方言)が生きて使われていた時代,1970~80年代はトンフツゴ(奄美共通語)が急速に広まった時代,1990年~現代はシマユムタが急速に消滅している時代ととらえている。 また,論文末には,明治以降に奄美大島旧笠利村赤木名集落の人々によって再開拓されたトカラ列島諏訪之瀬島の言語事情についても現況を簡単に報告した。
- 著者
- 笹倉 いる美
- 出版者
- 北海道立北方民族博物館
- 雑誌
- 北海道立北方民族博物館研究紀要 (ISSN:09183159)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.105-026, 2005 (Released:2020-07-31)
This paper will present Dr. Hattori's records which show the situation of the Nivkh (Gilyak) language research in 1937-1943. Dr. Hattori Takeshi (1909-1991), a Nivkh(Gilyak) language linguist, traveled in Karafuto (Sakhalin) in Showa 12 (1937). Those days, the southern part of Sakhalin island from north latitude 50 degrees was the Japanese territory. The indigenous peoples as Nivkh, Uilta and others, except Ainu, mostly lived in Otasu of Shisuka (now Poronaisk) suburbs. Dr. Hattori went to Otasu and made a field work. Based on the data gathered in the travel, Dr. Hattori pursue the exact research on Nivkh (Gilyak) language with the support of the Nihon Gakujyutsu Shinko-kai in 1940-1943 In 1994, Dr. Hattori's collection of books, notebooks, voice tapes, microfilms, and photos was filed and stored in the Hokkaido Museum of Northern Peoples. The account of a travel had been filed to a Karafuto-related binder (reference number N-175). The reference numbers of draft of the Nivkh (Gilyak) language research are T544-l and T545-l.