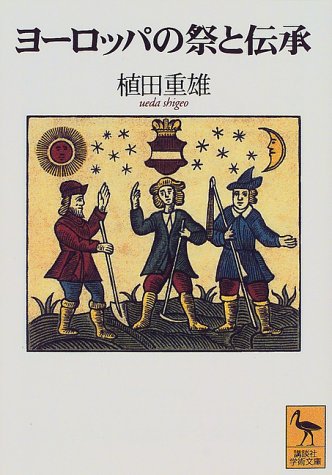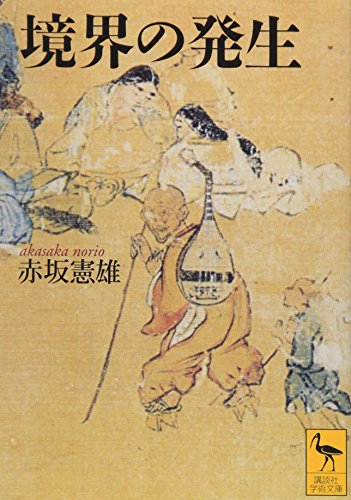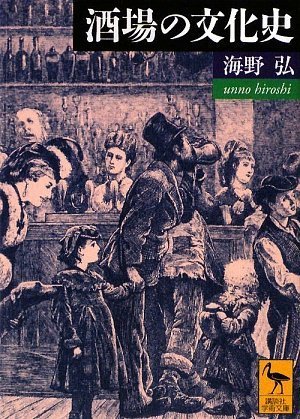1 0 0 0 IR 沖縄県におけるさとうきび作と製糖業の現状と課題
- 著者
- 井上 荘太朗
- 出版者
- 農林水産省農林水産政策研究所
- 雑誌
- 農林水産政策研究 (ISSN:1346700X)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.65-84, 2006-09
さとうきび作は、沖縄県の経済振興のために必須の作目と政策的に位置づけられてきた。この背景には、沖縄県、特に離島部の経済がさとうきび作と製糖業に対して大きく依存しており、かつ代替的な作目が見出しがたいとする認識がある。しかし農家の高齢化に伴い、沖縄県のさとうきび作は縮小してきている。また、島ごとにみると、他の経済部門が小さい上に輸送条件が不利な遠隔離島地域にある平坦部の広い島(南北大東島や宮古島等)では、依存度は確かに高いが、こうした島を除くと、依存度はあまり高くない場合もあることが指摘される。このように各島での事情は異なるが、製糖工場の操業度が低下していることもあり、いずれの島でも、さとうきび生産の拡大を強く支援するために多様な施策がとられており、高い成果をあげている場合もある。しかし、国内の砂糖市場が縮小し、国内糖業の支持のための財政負担の効率性も厳しく問われている状況下においては、こうしたモノカルチャー的なさとうきび作の拡大に偏った政策を再検討することも必要かもしれない。さらには、今後、離島社会の振興をより持続的な基盤の上で進めるためには、各島の事情に応じて、農業と他の経済部門との連携を含んだ柔軟な施策を採用していくことが求められると考察される。
1 0 0 0 OA 沖縄県におけるさとうきび作と製糖業の現状と課題
- 著者
- 井上 荘太朗
- 出版者
- 農林水産省農林水産政策研究所
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.65-84, 2006 (Released:2011-03-05)
さとうきび作は、沖縄県の経済振興のために必須の作目と政策的に位置づけられてきた。この背景には、沖縄県、特に離島部の経済がさとうきび作と製糖業に対して大きく依存しており、かつ代替的な作目が見出しがたいとする認識がある。しかし農家の高齢化に伴い、沖縄県のさとうきび作は縮小してきている。また、島ごとにみると、他の経済部門が小さい上に輸送条件が不利な遠隔離島地域にある平坦部の広い島(南北大東島や宮古島等)では、依存度は確かに高いが、こうした島を除くと、依存度はあまり高くない場合もあることが指摘される。このように各島での事情は異なるが、製糖工場の操業度が低下していることもあり、いずれの島でも、さとうきび生産の拡大を強く支援するために多様な施策がとられており、高い成果をあげている場合もある。しかし、国内の砂糖市場が縮小し、国内糖業の支持のための財政負担の効率性も厳しく問われている状況下においては、こうしたモノカルチャー的なさとうきび作の拡大に偏った政策を再検討することも必要かもしれない。さらには、今後、離島社会の振興をより持続的な基盤の上で進めるためには、各島の事情に応じて、農業と他の経済部門との連携を含んだ柔軟な施策を採用していくことが求められると考察される。
- 著者
- 前田 真吾 原 雄介 秋元 琢磨 橋本 周司
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.65, 2010
- 著者
- 渡邉 泰彦
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.1752-1764, 2006
資料
1 0 0 0 29pZC-10 カップルした格子における樹枝状形態
- 著者
- 大瀧 昌子 本庄 春雄 坂口 英継
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.56, 2001
- 著者
- 先崎 理之
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.91-94, 2019
- 著者
- 竹内 秀一
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集 第67回(2016) (ISSN:24241946)
- 巻号頁・発行日
- pp.105_2, 2016 (Released:2017-02-24)
運動部活動などを舞台に物語が紡がれるスポーツ漫画は、我々とスポーツとの関わりを映し出すひとつの鏡といえる。例えば、1990~96年に井上雄彦氏によって連載された『スラムダンク』は、多くの若者をバスケットボールへと駆り立てた。このような現象を松田(2009)は、「マンガに描かれたスポーツ世界のリアリティが、逆に現実世界のスポーツのリアリティ感覚の受皿となる」と述べる。すなわち、スポーツ漫画は単なる表象文化ではなく、他方スポーツに新たな現実を生起させる循環装置にもなっているのである。ところで、漫画が世代ごとの「アイデンティティ」を確認する役割を担うという報告(諏訪、1989)もある。ここより、スポーツ参与者の同一性(=プレイヤー・アイデンティティ)を基底している言説、あるいは揺らぎのダイナミクスをスポーツ漫画から捉えることができるのではないか。そこで本研究では、スポーツ漫画におけるキャラクターの表象について、「アイデンティティ」という補助線を用いて考察していく。そして、そこから透けてみえる運動部活動における現代的な力学の様相を明らかにすることを目的とする。
1 0 0 0 OA 全国飲食料業界大鑑
- 著者
- 帝国飲食料新聞社 編纂
- 出版者
- 帝国飲食料新聞社
- 巻号頁・発行日
- vol.満鮮の部, 1933
1 0 0 0 OA 乱用薬物の代謝とその機構
- 著者
- 山田 英之 小栗 一太
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.9, pp.895-899, 1998-09-01 (Released:2018-08-26)
- 参考文献数
- 24
1 0 0 0 三味線組歌古譜資料の比較研究
- 著者
- 井口 はる菜
- 出版者
- 日本歌謡学会
- 雑誌
- 日本歌謡研究 (ISSN:03873218)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.69-88, 2019
1 0 0 0 OA 帝国飲食料同業名鑑
- 著者
- 帝国飲食料新聞社 編
- 出版者
- 帝国飲食料新聞社
- 巻号頁・発行日
- vol.近畿の部, 1926
1 0 0 0 IR 『古今集』六義の原拠について : 中国詩論の六義説を通して
- 著者
- 田中 和夫
- 出版者
- 立正女子大学短期大学部文芸科
- 雑誌
- 文藝論叢 = Literary Arts Selection Of Treatises (ISSN:02887193)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.38-43,
1 0 0 0 OA 機関車空気ブレーキ : 鉄道省教授要目準拠 附・客貨車
1 0 0 0 ヨーロッパの祭と伝承
1 0 0 0 OA 結晶学とドラッグデザインの関わり
- 著者
- 平山 令明 松浦 良樹
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.25-27, 1990-04-30 (Released:2010-09-30)
- 著者
- 佐藤 和艮
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.356-357, 1996
最近,科学教育が学校の中だけにとどまらず,広く社会活動としても実施されるようになってきた。代表的なものとして「青少年のための科学の祭典」の全国ツアー,物理教員サークルの地域における「親と子の科学広場」の開催,大学の子供向け公開講座「科学実験教室」の開催,博物館での「実験教室」,さらに自宅を実験室に改造して子供達を集め実験広場にしている活動などがある。様々な形態をとりながらも,いずれも意義深い貴重な活動として賞賛される。筆者も小規模ながら,名古屋の「でんきの科学館」において「中学生のための第2土曜でんき実験くらぶ」という実験教室を1993年2月から実施しているので,その内容を報告し読者からの助言を期待したい。
- 著者
- 谷本 潤 萩島 理 田中 尉貴
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.640, pp.753-757, 2009-06-30 (Released:2010-01-18)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
An improved cellular automaton model based on Yanagisawa & Tomoeda , Nishinari (2007) was established, where both Static Floor Field and collision effect were considered. Several model parameters were carefully determined by going through a turning process based on experimental data provided by other previous studies. Both results by simulation based on the model and analytical approach derived from the so-called Mean-Field Approximation proved that the outflow rate from an evacuation exit, usually estimated by the so-called flow coefficient, can be improved by putting appropriate obstacles in front of the exit. This is because the appropriate allocation of obstacles can deflate collision probability at the exit by increasing collisions around the obstacles before the exit.
1 0 0 0 青山地球社会共生論集
- 著者
- 青山学院大学地球社会共生学会 [編]
- 出版者
- 青山学院大学地球社会共生学会
- 巻号頁・発行日
- 2016