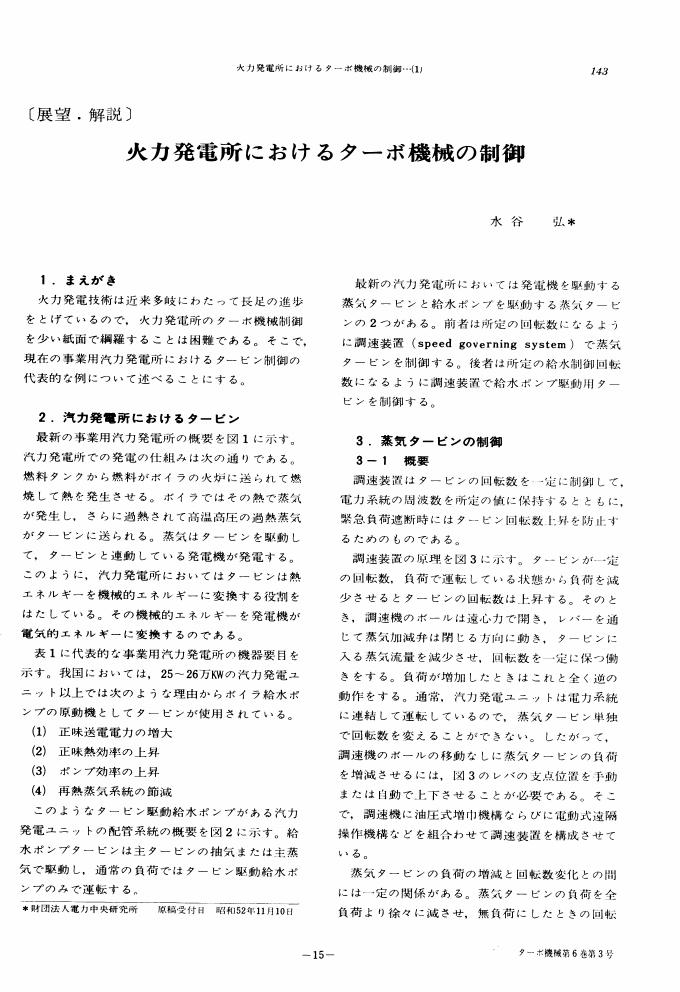1 0 0 0 IR 穀物女神の継承者としての聖母マリア--神秘の釜の図像をめぐって
- 著者
- 久木田 直江
- 出版者
- 日本基督教学会北海道支部/北海道基督学会
- 雑誌
- 基督教學 (ISSN:02871580)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.p19-24, 1995-07
1 0 0 0 IR 黒猫はどこからきたか-2-精神分析批評から神話・元型批評へ
- 著者
- 福田 立明
- 出版者
- 岐阜大学
- 雑誌
- 岐阜大学教養部研究報告 (ISSN:02863251)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.p135-150, 1982
1 0 0 0 IR ミュケナイ時代の宗教(2)王宮の聖所を中心に
- 著者
- 山川 廣司
- 出版者
- 愛媛大学法文学部
- 雑誌
- 愛媛大学法文学部論集 人文学科編 (ISSN:13419617)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.1-22, 2009
1 0 0 0 IR 悲嘆の女神
- 著者
- 安村 典子
- 出版者
- 京都大学西洋古典研究会
- 雑誌
- 西洋古典論集 (ISSN:02897113)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.24-47, 1994-03-30
この論文は国立情報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化されました。
1 0 0 0 IR 卒業論文 エレウシスの秘儀
- 著者
- 西郷 田美子
- 出版者
- 学習院大学
- 雑誌
- 哲学会誌 (ISSN:03886247)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.51-62, 2003-07
1 0 0 0 「三春滝桜」の樹勢回復工事による樹勢変化
- 著者
- 手代木 徳弘
- 出版者
- 樹木医学会
- 雑誌
- 樹木医学研究 (ISSN:13440268)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, 2000
1 0 0 0 『大原集』の証心
- 著者
- 鈴木 佐内
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.263-275, 1998
『代集』の「大原集 証心撰、おおはらの歌。」の一行の記録をたよりにして、長明『伊勢記』の旅の同伴者証心法師の考察をした。『大原集』の証心は『朗詠要抄』の藤氏朗詠相承系譜にみえる中原有安の弟子証心と同一人物であるとし、証心像を拡大した。『大原集』の証心の存在は、長明と洛北大原とのかかわりを明かし、長明の履歴解明、『方丈記』解釈にも資することになるわけで、「大原集 證心撰、おおはらの歌。」という一行の記録は貴重であると言わねばならない。
1 0 0 0 第3回 ジョン・スノウとコレラ
- 著者
- 酒井 弘憲
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.558-559, 2014
爽やかな春も終わり,梅雨が近づいてきた.6月と言えば,ジューンブライドで結婚式の季節というイメージがあるのではないだろうか? 2012年のぐるなびウエディングのアンケート調査結果を見てみよう.まず既婚者(男性700名,女性432名)に「どの時期に結婚したか」という質問に対して,春~初夏(4~6月)が1番多く28.7%,続いて秋(10~11月)が23.9%と続く.結婚の意思のある未婚者(男性161名,女性178名)に「どの時期に結婚したいか」を尋ねると,秋が1番多く,53.1%,続いて春~初夏の41.0%となる.親族や友人など式への出席者側(男性1029名,女性703名)の意識では,「いつ出席したいか」という質問に対して,こちらも秋が41.0%で,続いて春~初夏の27.0%という回答であった.つまり,6月に結婚式が1番多いというわけではないのである.<br>もっと詳細に示せば,未婚者の結婚希望時期は10月が1位で6月は4位なのである.既婚者の結婚時期でも1位は11月で,6月は6~7位なのである.例外的に6月に挙式が増えた年があったが,それは,1990年と1993年である.それぞれ6月に秋篠宮,皇太子のご成婚があり,それにあやかっての挙式増加であった.現実的な話をすれば,梅雨時期で稼働率の下がるホテルや式場が欧米のロマンチックな言い伝えを利用し,ジューンブライドとぶち上げて6月の集客を回復しようと画策したのが始まりらしい.ヴァレンタイン・デーを利用してチョコレートの売り上げを伸ばそうとした製菓業界とまったく同じ構図なのである.こういうキャンペーンはそのまま鵜呑みにせず,数字の裏付けを確認することが大事である.<br>ところで,この時期になると決まって懐かしくなるのがロンドンの清々しさである.この時期のロンドンは夜も21時過ぎまで明るく,空気もカラッとしていて実に過ごしやすい.著者がロンドンを訪問する際に必ず立ち寄る場所がある.根っからのシャーロキアン(英国ではホーメジアンと呼ばれるらしい)としては,チャリングクロスのパブ・シャーロック・ホームズと言いたいところだが,同じパブでもそれはジョン・スノウ・パブなのである.と言っても読者のなかでそれを知っている人がいれば奇跡に近い話であろう.有名なエロス像のあるピカデリーサーカスからリージェント・ストリートを北に進み,ブルックス・ブラザーズの店舗の角を右手に曲がって5分ほど進み,さらに左に折れて進んだ先のブロードウィック・ストリートの左角に目指すパブは佇んでいる.別に危険な場所ではないが,普通の観光客は絶対にこんな路地裏までには入ってこないだろう.ここが生物統計学の源流の一つである疫学の"聖地"なのである.
1 0 0 0 OA 雑誌『明星』における男性アイドル観の形成 ― スポーツと恋愛を中心に ―
- 著者
- 田中 卓也
- 雑誌
- 環境と経営 : 静岡産業大学論集 = Environment and management : Journal of Shizuoka Sangyo University
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.47-54, 2019-12-01
本研究では、芸能雑誌『明星』(集英社)を取り上げ、多くの女性ファンの心をつかむことに成功した男性アイドルについてとりあげ、男性アイドル観がどのように形成されたのかについて考察・検討を試みるものである。また男性アイドルが、「スポーツ」と「恋愛」について、どのように結びついていくことになったのかについて見出すものである。 1960年代初頭にジャニー喜多川が手掛けた4人組グループの「ジャニーズ」が「野球」を通じて交流した若い青年が最初のジャニーズタレントになって以降、現在に至るまで、多くのタレントを排出した。彼らは「野球」をはじめ、様々なスポーツと関わるなかで、若い女性から人気を博すことになった。女性にとっての男性アイドル観は、「新御三家」に始まり、「たのきんトリオ」の登場で形成されはじめ、「SMAP」に至るまで以後多くの女性から愛される(恋愛対象としての)存在になっていった。『明星』誌は、スポーツと恋愛が女性ファンと結びつける装置としての機能を有した。
- 著者
- 鈴木 常彦
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-CE-145, no.9, pp.1-5, 2018-06-02
FreeBSD の OS パーティショニング機能である Jail とネットワーク仮想化機能 VIMAGE を操作し,自由に仮想ネットワークをプログラミングできる Ruby ライブラリ VITOCHA を作成した.VITOCHA による仮想ネットワークは DNS キャッシュポイズニングの解明に大いに役立ったほか,ネットワーク技術者を集めた DNS 勉強会 「DNS 温泉」 においても VITOCHA による DNS シミュレーション環境は重要な役割を担っている.また本学においては遅延やパケットロスを変化させ TCP のスループットを測定する工学実験の授業に役立てている.これらの実践について VITOCHA の解説を交えて報告する.
- 著者
- 吉川 徹 田制 弘 Pascal NDAYONGEJE Jean-Bosco NUWARUGIRA Marie BUKURU Chantal KABAREBZI 三室 直樹 水流 晶子 阿部 一博
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 日本人間工学会大会講演集
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.286-287, 2010
1 0 0 0 OA 非高温下でのオクラ種子出芽を促進する培養土プライミング
- 著者
- 髙畑 健 三浦 周行
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1-6, 2017 (Released:2017-03-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
オクラ種子の非高温下における出芽を生産者が容易に促進できるように,培養土を水分調節資材に用いたプライミングを開発しようとした.‘東京五角’ 種子と35~55%水分含量の培養土を瓶に入れて15~30°C下で1~4日間プライミングした後,コンテナに播種して20°C下に置いた.30°C/1日/45%区の出芽促進が著しく,播種後8日の出芽率が,無処理区の53%に対して,94%と優れた.30°C/1日/45%区の種子を5月に圃場播種したところ,無処理区より出芽が早く開始し,地上部新鮮重が均一であった.30°C/1日/45%区の種子を数日間室温下で保管後5月に圃場播種した結果,処理終了後直ちに播種した区と出芽特性に差がなかった.本実験のプライミングは出芽を促進させ,その効果は播種期の延期を想定した処理種子保管後も維持された.
1 0 0 0 OA 火力発電所におけるターボ機械の制御
- 著者
- 水谷 弘
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.143-151, 1978-03-10 (Released:2011-07-11)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA イオン液体を用いたGLP-1受容体作動薬の腸管吸収性検討
【目的】イオン液体(ILs)は有機アニオンと有機カチオンからなる常温で液体の塩で、様々な分野での応用が期待されている。我々は以前に、イオン液体を用いてタンパク質などの高分子、中分子核酸、ペプチドなどを経皮吸収させる技術を開発した。ところで、2型糖尿病治療薬でペプチド製剤であるグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)受容体作動薬はほとんどが皮下注射製剤であり、低い服薬コンプライアンスが課題である。それに比べ、経口投与製剤は投与の簡便さ、非侵襲的なことが利点で、高い服薬コンプライアンスを実現できる。そこで、ILsを基剤として用いることで腸管での吸収性向上を期待し、GLP-1受容体作動薬の一つであるLixisenatide(Lix.)をILsと混合した時の腸管での吸収性を評価した。【方法】Lix.をILsに溶解させ(Lix.-ILs)、Lix.の胃での分解を避けるため経腸投与、あるいはLix.をSalineに溶解させ(Lix.-Saline)皮下投与し、Lix.血中濃度をEIAキットを用いて評価した。また、それぞれ投与した後に糖負荷試験をすることで、血糖値の上昇抑制効果を評価した。【結果・考察】Lix.をILsと混合して顕微鏡で確認したところ、加温することでLix.の結晶が消失したことから溶解したと判断した。Lix.-ILsの経腸投与により、Lix.血中濃度が顕著に上昇したことから、ILsはLix.の腸管吸収を促進することを新たに見出した。この時、Lix.-ILsは投与後1時間でピークとなり、投与後6時間まで高いLix.血中濃度が維持された。糖負荷試験において、Lix.-ILsの経腸投与で血糖値の上昇抑制が認められ、同程度のLix.血中濃度を示すLix.-Salineの皮下投与と同等の薬理効果が確認された。以上の結果より、Lix.をILsに溶解させることでGLP-1受容体作動薬の腸管吸収性が上昇することを示した。
- 著者
- 川村 晃生
- 出版者
- 慶應義塾大学藝文学会
- 雑誌
- 藝文研究 (ISSN:04351630)
- 巻号頁・発行日
- no.102, pp.106-88, 2012
2011年度慶應義塾大学藝文学会シンポジウム : 文学は危機を迎えているか
1 0 0 0 OA なぎなた専門分科会企画
- 著者
- 鍋山 隆弘 碓氷 典諒 奥村 基生
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.55-71, 2021-03-31 (Released:2021-04-28)
- 参考文献数
- 17
This study investigates how spatiotemporal conditions of interpersonal distance and timing in movement initiations influenced decision-making and actions for offence and defense in kendo. We also intend to present verifiable data on the problem of how two players separate from tsubazeriai in matches. Participants were top level players in Japanese university kendo clubs. In the experiment, participants were either given the role of “the first player”, who initiates movements, or “the second player”, who initiates movements after the first. The participants performed each trial as if in a real match from distances of 150, 175, 200, 225, 250, and 275 cm. We analyzed two trends in their decision-making and actions, one of which was the “ease of active striking,” meaning that they were able to initiate movements from a strike rather than defense in each trial. The other trend was the “ease of striking”, meaning participants could strike in each trial and were not only confined to defense. The results showed that it was easier for the first players than the second players with regards to “ease of active striking” and “ease of striking”. In both results, the differences between the first and the second players were extremely clear at a distance of 150 cm and were very clear at 175 to 250 cm distances and almost disappeared at 275 cm. In total, the first players also had a greater frequency of striking success (ippon) than the second players. These results indicated that movement initiation distance and timing changed reaction and movement times in both offence and defense, and also changed the degree to which the first and the second players’ decision-making and actions gave them an advantage. This is because the reaction and movement times required for offence and defense became shorter if the two players were closer to each other. In addition, the first players’ active movements caused the second players to react passively making it easier for the first players to initiate an attack.. Therefore, at close distances, offence became easier while defense became more difficult, and the first players gained a advantage while the second players were placed at a disadvantage. It can be concluded that the first players gain an advantage and the second players become disadvantaged in terms of offence when they are at close distances of 150 to 250 cm. These findings should be useful in combat sports such as kendo for the coaching of decision-making and actions, as well as for making the rules fairer on offense and defense.
1 0 0 0 鉄安定同位体を用いた海洋生物の鉄代謝評価法の開発
- 著者
- 山方 優子 田中 佑樹 平田 岳史
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.61, 2014
海洋環境において海水に含まれる鉄は非常に微量であるため、本研究では、鉄濃度情報に代えて鉄の同位体比情報(56-Fe/54-Fe, 57-Fe/54-Fe)を用いることで海洋生物の鉄代謝効率および海洋環境中の生物学的鉄循環に関する知見を引き出す。陸上動植物中では、栄養段階に応じて鉄同位体比が系統的に変化する(Walczyk and Blanckenburg,2002,2005)のに対し、海洋生物では、陸上生物と比較して大きく変化しないことが報告されている(Jong et al., 2007; Bergquist and Boyle, 2006; Walczyk and Blanckenburg, 2002)。そこで本研究では、これまでに測定されてこなかった高栄養段階に位置し、かつ鉄の局所的な酸化・還元の影響を受けない遠洋性の生物から鉄安定同位体比を分析した。分析対象とした試料は、カズハゴンドウ、マカジキ、ビンナガ、メバチの血液、筋肉、肝臓である。本発表では、分析結果を発表する。