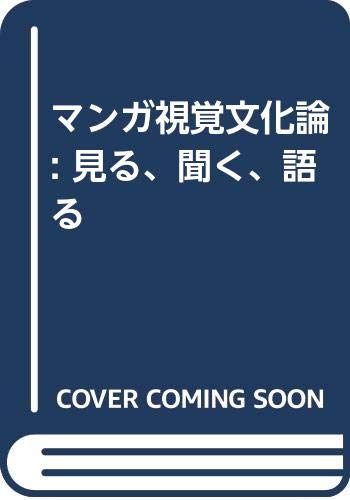5 0 0 0 OA 配給食品の栄養とその調理
- 出版者
- 国立栄養研究所
- 巻号頁・発行日
- 1948
5 0 0 0 IR 発光する背びれと戦後日本 : 核兵器とゴジラ映画史
- 著者
- 猪俣 賢司 Inomata Kenji
- 出版者
- 新潟大学人文学部
- 雑誌
- 人文科学研究 (ISSN:04477332)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, pp.1-29, 2012-03
5 0 0 0 OA 「美学」概念はいかにして形成されたか?
- 著者
- 石川 伊織
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.5, pp.1-33, 2021 (Released:2021-03-31)
5 0 0 0 IR 言語の違いが音楽の感得に与える影響
- 著者
- 井戸 和秀 矢内 淑子
- 出版者
- 岡山大学教育学部
- 雑誌
- 岡山大学教育学部研究集録 (ISSN:04714008)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.1, pp.93-99, 2006
我が国では,正式に音楽教育を受けるということは,西洋音楽を学ぶということと等しい。それは,伝統音楽が一部導入されるようになった現在でも真実である。特に,音楽大学や教員養成大学において,歌の学習といえば,イタリア語やドイツ語,英語等で歌うことが当然のこととなっている。それでは,多くの日本人は,歌われる外国語の意味や歌のイメージをどのように感得しているのだろうか。そこで,本研究では,歌を歌う際の言語の違い -ドイツ語と日本語-が聴取者に与える感得を調査した。その結果,シューベルト作曲「野ばら」をドイツ語で歌った場合には,言語の意味は不明ながら,概ね軽やかでリズミックに,日本語で歌った場合には,言語の意味は漠然としながら,概ね柔らかで流れるように感得された。
5 0 0 0 OA 松葉蘭譜
- 著者
- 長生舎主人 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1836
マツバランはもっとも原始的なシダ類で、生きた化石。茎が繰り返し二股に分かれながら伸びてホウキ状を示す。胞子は上部に着き、熟すれば黄色になる。文政~天保期(1818-43)に流行し、全体の容姿や胞子の着き方の変異を競った。熱帯・亜熱帯に広く分布するが、この奇妙な植物を園芸品としたのは日本だけである。本書は122品の花銘を記し、うち60品を色刷として示す。著者長生舎主人は幕臣(奥御右筆)で故実家の栗原信充(のぶみつ、1794~1870)である。信充は万年青(オモト)なども好み、「金生樹譜シリーズ」7点を刊行する予定だったが、第1冊の『金生樹譜別録』(特1-1549、文政13年=文化元年、1804刊)、第2冊の『万年青譜』(特1-1769、天保4序刊)、第3冊の本書と、3点だけに終わった。玉清堂編『松蘭譜』(しょうらんふ、特1-934、天保8年[1837]刊 )は最高のマツバラン図譜だが、当館資料は上巻を欠く。(磯野直秀)
5 0 0 0 OA 近接する糖尿病性乳腺症のために広がり診断に苦慮した乳癌の1例
- 著者
- 日下部 恵梨菜 村上 朱里 西山 加那子 山下 美智子 福島 万奈 亀井 義明
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.11, pp.2186-2191, 2020 (Released:2021-05-31)
- 参考文献数
- 18
症例は70歳,女性.2型糖尿病に対し,2年前からインスリン治療中であった.数日前より左乳房腫瘤を自覚し前医を受診.針生検にて浸潤性乳管癌と診断され,加療目的に当院を受診した.左乳頭外側に2cmの腫瘤を触知,MMGで乳頭直下から外側にFADを認めた.超音波検査では約2cmの境界不明瞭な低エコー域を認めた.左乳癌cT2N0M0 Stage II Aと診断し,左乳房全切除術+センチネルリンパ節生検を施行した.割面のマクロ像では,術前画像と一致して乳頭直下から外側かつ胸壁側まで広がる約2.5cmの病変を認めたが,組織学的には乳頭直下の約1cm程度の部分のみに癌が存在し,その胸壁側の領域は糖尿病性乳腺症で悪性所見は認めなかった.病理学的ステージはpT1bN0M0 Stage Iであった.今回われわれは,近接する糖尿病性乳腺症のために広がり診断に苦慮した乳癌の1例を経験したので,文献的考察を加え報告する.
5 0 0 0 マンガ視覚文化論 : 見る、聞く、語る
- 著者
- 鈴木雅雄 中田健太郎編 夏目房之介 [ほか] 執筆
- 出版者
- 水声社
- 巻号頁・発行日
- 2017
5 0 0 0 OA 自然流下式水道管網において地震時に水圧が低下する現象の解析的検討
- 著者
- 鈴木 崇伸
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震工学会
- 雑誌
- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.4_25-4_37, 2018 (Released:2018-08-31)
- 参考文献数
- 11
本文は地震時に水道管内の水圧が異常に低下する現象を解析的に分析した結果を報告している.東北地方太平洋沖地震時に川越市内で起きた水圧低下に関し,貯水槽のスロッシングによる水圧変化と管路内の水の振動外力による運動に分けて応答計算を行った.水圧低下量を説明できるのは水の圧縮性を考えた管路内の水の解析結果であり,外乱によって蓄えられたエネルギーが消散していく過程で水圧低下が起きることを説明している.
5 0 0 0 淺間丸龍田丸機關部計畫及び成績に就て
The completion of the M.S. Tatsuta Maru, the sister ship of the Asama Maru and the biggest motor liner of almost wholly a Japanese production, is an important event for Japanese Shipping and Shipbuilding. On this remarkable occasion, it does not appear to be wholly nonsense to make some reference about these ships. In this paper, a short review is made about the vast designs and long efforts to arrive at the final elaborate design of the Pacific Liners. Some results are also picked up from those of the exhaustive trials, and finally, an attempt is made to lay out 2,000 B.H.P. geared Diesel installation for a high speed Trans Pacific Liner which might come into question in future.
- 著者
- 白峰 旬
- 出版者
- 別府大学アジア歴史文化研究所
- 雑誌
- 別府大学アジア歴史文化研究所報 (ISSN:0288108X)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.1-22, 2022-02
研究ノート
- 著者
- 山田 耕作
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.6, pp.460-461, 1984-06-05 (Released:2020-05-26)
5 0 0 0 IR 室町時代の内侍所御神楽における綾小路家と四辻家
- 著者
- 中本 真人
- 出版者
- 新潟大学人文学部
- 雑誌
- 人文科学研究 (ISSN:04477332)
- 巻号頁・発行日
- no.149, pp.T1-T19, 2021-12
5 0 0 0 OA 『加沢記』からみた真田氏の自立 : 外交政策・家臣統制を中心に
- 著者
- 富澤 一弘 佐藤 雄太 Kazuhiro Tomizawa Yuta Sato 高崎経済大学経済学部 高崎経済大学経済・経営研究科博士後期課程
- 雑誌
- 高崎経済大学論集 = The Economic Journal of Takasaki City University of Economics (ISSN:04967534)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3「高橋章教授退職記念号」, pp.31-47, 2012-02-01
5 0 0 0 OA 小学校段階における討論学習の必要性の再検討――認知面と心理面への影響の分析を通して――
- 著者
- 北川 雅浩
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, pp.15-23, 2018-03-30 (Released:2018-04-27)
- 参考文献数
- 18
本研究では,小学校段階における討論学習の必要性と指導すべき要点を再検討することを目的とした。そのため,他者からの異論を聞くのみの学習と討論学習とを認知面及び心理面から比較してその差異を分析した。その結果,討論学習の必要性として以下の3点を導出した。①議論された意見を取り入れながら自分の考えを発展させられること,②思考をどのように進めるかを学ぶ場となること,③互いの意見や立場を尊重することや協同的な態度の大切さを学べること,である。また,指導の要点としては,討論における質問・賛同・創出の大切を学ばせること,思考に柔軟性をもたせること,ふり返る場面を設定すること,協同探究の態度を育成すること,が挙げられる。
5 0 0 0 IR 文学篇 熊本地震後の復興スローガン
- 著者
- 茂木 俊伸
- 出版者
- 熊本大学
- 雑誌
- 文学部論叢 = Kumamoto journal of culture and humanities (ISSN:03887073)
- 巻号頁・発行日
- no.110, pp.45-56, 2019-03
This paper reports the results of a survey and analysis of reconstruction slogans such as "Ganbarou! Kumamoto" (Let's not give up! Kumamoto) seen in the linguistic landscape following the Kumamoto Earthquake of April 2016. In this survey, 118 notices exhibiting reconstruction slogans were gathered from June 2016 to April 2018 from shopping districts in the center of Kumamoto city. An analysis of these notices led to the following conclusions: (1) over the year after the earthquake, the number of notices with reconstruction slogans decreased significantly, then slightly increased after a year, and again decreased gradually; (2) case studies of reconstruction slogans following the Great East Japan Earthquake exhibited similarities with the results of this survey, including the basic structure of the slogans as "verb+sentence-final expression+place name."
5 0 0 0 OA 実証的研究の事前登録の現状と実践 ──OSF事前登録チュートリアル──
- 著者
- 長谷川 龍樹 多田 奏恵 米満 文哉 池田 鮎美 山田 祐樹 高橋 康介 近藤 洋史
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.188-196, 2021 (Released:2021-08-25)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 4
In the midst of the current reproducibility crisis in psychology, pre-registration is considered a remedy to increase the reliability of psychological research. However, because pre-registration is an unconventional practice for most psychological researchers, they find it difficult to introduce pre-registration into their studies. To promote pre-registration, this article provides a detailed and practical step-by-step tutorial for beginners on pre-registration with Open Science Framework. Furthermore, a typical example what beginners might experience and ways to resolve such issues are provided as supplementary material. Finally, we discuss various issues related to pre-registration, such as transparent research, registered reports, preprints, and open science education. We hope that this article will contribute to the improvement of reproducible psychological science in Japan.