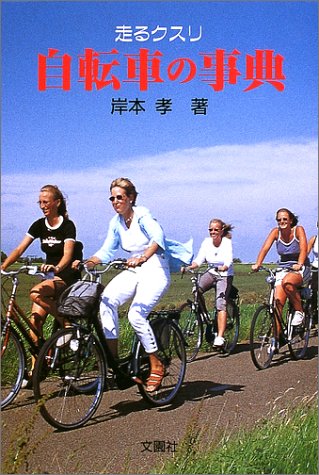1 0 0 0 結帯動作の改善に対するストレッチ回数の検討
- 著者
- 鈴木 静香 田中 暢一 村田 雄二 永井 智貴 高 重治 正木 信也
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48102087-48102087, 2013
【はじめに、目的】 我々は、第47回日本理学療法学術大会において、結帯動作の制限と考えられる筋に対してストレッチを施行し、結帯動作の即時効果の変化を捉えた。そして、結帯動作の制限因子は、烏口腕筋、棘下筋であることを報告した。その後、「烏口腕筋・棘下筋は介入回数が増えることでより効果が増大し結帯動作は改善するのではないか?」また、「小円筋は介入回数が増えることで効果が出現し結帯動作は改善するのではないか?」という疑問が出てきた。そこで今回は、前回介入した筋に対して、介入する回数を増やし結帯動作の変化を捉えることを目的に研究を行なった。【方法】 対象は左上肢に整形外科疾患の既往のない健常者10名(男性7名、女性3名、年齢22~36歳)とした。結帯動作の制限因子と考えられる烏口腕筋、棘下筋、小円筋を対象とし、これらの筋に対してストレッチを週2回を2週間、計4回実施した。結帯動作の評価方法は、前回同様、立位にて左上肢を体幹背面へと回し、第7頸椎棘突起から中指MP関節間の距離(以下C7-MP)を介入前後で測定し比較を行った。各筋に2分間ストレッチを実施する群(烏口腕筋群、棘下筋群、小円筋群)とストレッチを加えず2分間安静臥位とする群(未実施群)の計4群に分類し、複数回の介入による結帯動作の経時的変化を検討した。よって、1回目介入前の値を基準値とし、C7-MPの変化は、基準値に対し各介入後にどれだけ変化したかを変化率として統計処理を行った。また、それぞれの筋に対する介入効果が影響しないよう対象者には1週間以上の間隔を設けた。統計処理では、各群について、複数回の介入による結帯動作の変化を検討するために対応のある一元配置分散分析を用い、多重比較にはTukey法を用いた。【倫理的配慮、説明と同意】 全ての被験者に対して事前に研究参加への趣旨を十分に説明し、同意を得た。【結果】 棘下筋群の変化率の平均は、1回目10.8%、2回目11.4%、3回目15.7%、4回目19.5%であった。一元配置分散分析の結果、棘下筋群のみに有意差を認めた(p=0.0003)。しかし、多重比較では各回数間の有意差は認めなかった。また、烏口腕筋群や小円筋群や未実施群は、有意差は認めなかった。【考察】 結果では棘下筋群のみに有意差を認め、前回の介入でも棘下筋に効果を認めた。高濱らは、結帯動作の制限因子は棘下筋であると述べている。以上より、棘下筋に介入することで結帯動作を改善することができるとわかった。しかし、多重比較において、有意差を認めなかったため、どの回数間で効果が得られているのかを追究することができず介入回数についての考察に至ることができなかった。その原因としては、症例数が少ないことが考えられる。今後は症例数を増やし、複数回の介入による結帯動作の変化について取り組み、介入回数についても考察したいと考える。烏口腕筋では、前回、介入において即時効果を認めていたが、複数回の介入による結帯動作の変化は認めなかった。烏口腕筋は肩の屈筋であり、上腕骨の内面に付いているために伸展および内旋で緊張するという報告もあり、結帯動作における制限因子の可能性は高いと考えられる。しかし、今回有意差を認めなかった原因は、症例数が少ないことや、他にストレッチの強さや場所など方法になんらかの問題があったとも考えられる。今後、方法を確立した上で、症例数を増やし、複数回の介入による結帯動作の変化について取り組んでいきたいと考える。小円筋では、小円筋は介入回数が増えることで効果は出現し結帯動作は改善するのではないかと考えていた。しかし、即時効果・複数回の介入による効果はともに結帯動作の変化に有意差を認めなかった。高濱らは、結帯動作は肩の外転・伸展・内旋の複合運動であり、小円筋は内転位であるために下垂位では緩んでいると述べている。以上より、即時効果・複数回の介入による効果はともに結帯動作の変化に有意差を認めず、結帯動作における改善には小円筋は関係がないと考える。【理学療法学研究としての意義】 今回の結果より棘下筋に複数回介入することで、結帯動作の変化率はより増大することがわかった。臨床において結帯動作が困難な症例に対しての介入の一つとして有効である可能性がある。具体的な介入回数について追究できなかったため、今後の課題として取り組んでいきたい。
1 0 0 0 OA アメリカ合衆国での人文学の復興と日本の戦後高等教育改革(教育哲学)
- 著者
- 立川 明
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. I-A, 教育研究 (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.1-15, 2002-03
本論ではまず戦後の日本での高等教育改革の一つの前提となる,当時のアメリカ合衆国での教養教育の特色の一端を論じたい.その要点は,20世紀前半のアメリカの教養教育は,主として人文学の立場から構成されていた,という点である.この論点を,できるだけ戦後の教育改革に実際に携った人物の意見を中心として,再構成してみたい.その上で,教養教育についてのアメリカ側からの提起を,日本側がどう受け止めたのかについて,多少とも触れたい.最後に,戦後教育改革において,ウォールター・イールズの果たし(得)た役割について,ジュニア・カレジと教養教育との関係に焦点をあて,論じたいと考える.
- 著者
- 山田 英明
- 出版者
- 歴史人類学会 ; 1980-
- 雑誌
- 史境 (ISSN:02850826)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.20-35, 2013-03
本研究はニッケル触媒を用い、従来は報告例の少なかった遷移金属触媒による含硫黄複素環化合物の簡便な合成法を確立することを目的として行ってきた。最終年度である今年度は、これまでの2年間で得られた知見を基にして、これまでに報告例のなかった、硫黄を含むヘテロ芳香環の直接的な切断を伴った環化付加反応を2つ見いだした。一つ目は炭素2位にトリフルオロメチル基を有するベンゾチアゾールとアルキンの環化付加反応である。本反応の直接的な生成物は7員環のベンゾチアゼピンであるが、反応系を加熱することで硫黄の脱離が促進され、6員環であるキノリン環を得ることができる。本反応は形式的に硫黄原子とアルキンの置換反応と見なすことができ、非常に興味深い反応である。また、反応機構解明のために当量実験を行った結果、鍵中間体である酸化的付加体を得ることに成功し、その構造を単結晶X線構造解析によって同定することができた。これによって本反応が芳香環の直接的な切断を伴って進行していることを実験的に確認した。さらに。この反応で得られた知見を基にして、ベンゾチオフェンを基質として用いた場合にも同形式の反応が進行することを見いだした。ベンゾチオフェンを基質として用いた場合、7員環生成物であるベンゾチエピンを良好な収率で得ることができた。本反応では、2位の置換基として、一般的に電子供与性の置換基と見なされるメトキシ基や、電子求引性基として見なされるフルオロ基のどちらも用いることができることを明らかとした。これら二つの反応は、これまで全く報告例のなかった芳香環の直接的な切断を経る環化付加反応であり、得られる生成物が重要な構造を有しているだけでなく、学術的にも非常に興味深い反応である。
1 0 0 0 吉野大峰山と本山派当山派
- 著者
- 吉井 敏幸
- 出版者
- 仏教史学会
- 雑誌
- 仏教史学研究 (ISSN:02886472)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.p105-118, 1984-10
- 出版者
- 日経ホーム出版社
- 雑誌
- 日経マネー (ISSN:09119361)
- 巻号頁・発行日
- no.307, pp.46-53, 2008-06
プロが国内で取り扱いのあるETFの中から有望なものをピックアップ。具体的に紹介する。予算などをチェックし、投資に役立ててほしい。
1 0 0 0 OA 中国語話者のための日本語教育文法を構築するための基礎研究
1 0 0 0 OA 省エネルギー性と品質を考慮した水産物流通工程の最適化手法の検討
水産物の冷凍流通は、未凍結での冷蔵流通に比べて可食期間が遥かに長いため、船舶輸送による輸送エネルギーの低減や、食品廃棄の抑制など、環境面では優位性が期待できる。しかし、多くの消費者が冷凍品は美味しくないというイメージを持っており、冷凍流通品の地位は低い。本研究では、マグロとサンマを用いた官能評価を行い、環境負荷と美味しさを統合的に評価することを試みた。この結果、冷凍品は環境負荷が大幅に小さく、美味しさにはそれほど顕著な違いが無いことが示された。すなわち持続可能な社会を実現するためには、冷凍流通を上手に利用することが有効であると言える。
今年度は主に2つに分類される研究を平行して進めてきた。一つ目は昨年に引き続き、D.LewisとP.Griceの言語観を考察するという研究である。2人の言語観を考察するうえでかかせないのは、哲学で「命題的態度」と呼ばれる問題についての考察である。命題的態度は従来、例えば「私はクラーク・ケントは空か飛べないと信じている」のような信念文を分析するうえで、命題的態度の発話者Sが「クラーク・ケントは空か飛べない」という命題pとの間に、信じる(B)という関係に立っている、つまりSBpという構造を命題的態度が持っていると考えられて来た。この命題的態度についてS.Schifferの著書The Things We Meanを手がかりに研究を続けて来た。命題について問われるのはその存在論的身分である。一般的な物と違い、命題は目に見えるわけでも触れるわけでもない。しかしSchifferはPleonastic Propositionという命題を導入する事により、この命題が従来の存在論の中に組み込まれても従来の存在者の数を保存拡大(変化させない)ことにより、命題が存在する事によって生じる問題を排除したうえで、命題が存在するという立場をとる。このSchifferの立場が擁護可能かということを考察するのが今後の課題である。二つ目はD.Lewisが著書Conventionにおいて、conventionという概念を合理的再構成することによってconventionという概念の正当化を行ったことの意味を研究することである。論理実証主義者が算術命題の必然性を説明するために「規約主義(conventionalism)」という考え方をとり、その規約主義への批判がV.O.Quineらによって積極的になされ、その結果言語にconventionが存在するという考え方自体が否定されることを通して、conventionという概念自体が曖昧な概念だとみなされたことに対して、D.Lewisはconventionの概念(特に言語の中に存在する事)を全うな概念であると擁護し、それらの見解に対してアンチテーゼを提出したということができよう。問題はLewisがたとえconventionという概念を合理的再構成することによって正当化できていたとしても、その正当化はあくまで規約主義批判への応答という文脈に立ってなされていることである。これはどのようなことかと言うと、Lewisがconventionの概念を正当化するうえで、合理的再構成という手段をとったのは規約主義批判への応答の手段としてではないかということを明らかにする必要がおるからである。つまりLewisは現実にconvention(規約、慣習)のあり方を見て、実際に人々がどのように慣習にのっとって振る舞っているかを見て、そこから現実に成立しているconventionのメカニズムを探すことによってconventionの概念を正当化するという手段をとらなかった。Lewisはこのように現実的にconventionが成立している地点から出発することも可能だったはずである。しかしLewisはそういった地点からconvention概念の正当化をしようとはしなかった。この点についてもっと研究を進める必要がある。
1 0 0 0 OA 現代日本において家庭の経済状況は子どもの食生活と栄養状態に影響するか?
本研究は、現代日本において家庭の経済状況は、子どもの食生活と栄養状態に影響するかについて明らかにすることを目的とした。母子生活支援施設と連携し生活保護受給世帯、NPOフードバンクと連携し生活困窮世帯の子ともの食生活について3つの調査をおこなった。その結果、家庭の経済状態は、子ども食生活に影響することが明らかになった。特に低所得(生活困窮)世帯の子どもの食事について、欠食が多く、主食に偏り、たんぱく質やビタミン、ミネラル等の栄養素摂取量が少ないという課題があることが示された。
1 0 0 0 OA 有島武の經濟策論
- 著者
- 堀江 保藏
- 出版者
- 京都帝國大學經濟學會
- 雑誌
- 經濟論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.587-596, 1942-11
1 0 0 0 OA 生活改善 : 随筆評論集
- 著者
- 牛山 崇 東条 英明 小野 智之 小関 英邦 石井 靖彦 内田 安信
- 出版者
- 一般社団法人日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.2-9, 1983-09-30
- 被引用文献数
- 2
だれでもが歯科治療に不安を抱いている。しかし中には,その不安が強度のために,歯科治療を拒否したり,回避したりというような不適応行動をとる患者が認められる。我々は彼ら患者を"歯科治療恐怖症"と呼称し,本症の病態解明に努めている。我々は行動論的立場より取り組むのが最も妥当と考え,その見地より歯科治療恐怖症は歯科治療を通して獲得された不安反応であり,オペラント学習にのっとって治療からの逃避ないし回避を発現している神経症的な不適応行動であると考えている。したがってその治療方法も学習理論に基づく心理療法である行動療法により可能であると捉えている。現在までのところ,我々は行動療法の一技法である系統的脱感作法を用いて,87%の者に有効性を見い出し,この方法が"歯科治療恐怖症"治療に大変有用であると考えている。最近ではバイオフィードバック,モデリソグ,フラッディング法,向精神薬の投与などの併用を行い,その有効性に関して検討している。
1 0 0 0 OA 透析患者のQOL向上を実現するアクティブライフスタイル教育プログラムの開発と運用
包括的な栄養アセスメントにより、血液透析患者の栄養状態・ QOLの維持向上の方策として、透析日の生活活動と亜鉛摂取量の増加が重要であることを見出し、透析中に行う低強度運動プログラム(ストレッチ・マッサージ)を開発した。このプログラムは、患者の身体能力や意欲に応じて選択可能な段階的コースを用意するとともに、患者が自己の最適ペースで実施できるよう、教育メディア(DVD)を制作した。また、亜鉛強化菓子を考案し、透析後に提供して栄養指導の動機づけとするダイエットプログラムを開発した。これらのプログラムの介入効果として、患者の貧血改善や下肢の筋肉量の増加、身体機能の向上が示唆された。
1 0 0 0 自転車の一世紀 : 日本自転車産業史
- 著者
- 自転車産業振興協会編
- 出版者
- 自転車産業振興協会
- 巻号頁・発行日
- 1973