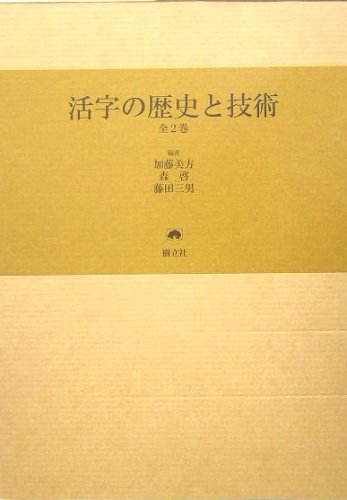5 0 0 0 OA 大正三年櫻島噴火記事
- 著者
- 九州鐵道管理局 編纂
- 出版者
- 九州鐵道管理局
- 巻号頁・発行日
- 1914
5 0 0 0 OA 不足する病院薬剤師の確保 ──北海道の薬剤師配備の現状から見た課題と解決方法の共有──
- 著者
- 徳田 禎久
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.6, pp.705, 2020 (Released:2020-05-17)
- 著者
- 中山 大成 長谷川 和範
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- Venus (Journal of the Malacological Society of Japan) (ISSN:13482955)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1-2, pp.19-26, 2016-04-13 (Released:2016-04-15)
- 参考文献数
- 12
沖縄県恩納村瀬良垣から金城浩之氏によって採集された日本産イトカケガイ科の1種をイボヤギヤドリイトカケ属(新称)Epidendrium A. & E. Gittenberger, 2005の新種として記載する。また,本種の属位を決定するにあたり,従来北西太平洋でAlora属に含められていた近似種と比較するとともに,それらの属位についても見直しを行った。Epidendrium parvitrochoides Nakayama n. sp. エンスイイトカケ(新種・新称)(Figs 8–10)殻長は3~5 mmの小型で薄く,円錐形。茶褐色。各層に胎殻は平滑で円筒形,体層,次体層とも下方に角張るが底盤を形成しない。次体層は6層内外で,殻表は縦肋と螺肋が交差し格子状の彫刻をなす。殻口は四角く外唇薄く著しい張り出しにはならない。臍孔は大きく開く。タイプ標本:ホロタイプ,殻長 5.8 mm; 殻径4.0 mm,NSMT-Mo 77925;パラタイプ1,殻長4.8 mm; 殻径 3.1 mm, NSMT-Mo 77924;パラタイプ2,殻長4.3 mm; 殻径 2.8 mm,NSMT-Mo 77923。タイプ産地:沖縄県恩納村瀬良垣,水深20~25 m。分布:タイプ産地のみからしか知られていない。付記:Epidendriumイボヤギヤドリイトカケ属(新称)はE. sordidum A. & E. Gittenberger, 2005ヒロベソイボヤギヤドリイトカケ(新称)をタイプ種としてGittenberger & Gittenberger(2005)によって創設され,従来Alora属とされていた種の幾つかがここに移された。後にGittenberger & Gittenberger(2012)はAlora属とEpidondrium属の違いについて改めて議論し,遺伝子配列の比較から系統的に隔たったものであることを示した。殻の形態では両者の区別はやや困難であるが,貝殻の全般的な形状や殻質などの違いによって区別が可能であると考えられる。これらの形質に基づいて,日本産の従来Alora属に含められていた種を再検討した結果,まず土田(2000)や Nakayama(2003)によってAlora billeeana(DuShane & Bratcher, 1965)イボヤギヤドリイトカケとして図示された種はE. aureum A. & E. Gittenbereger, 2005(Figs 1–2)に訂正される。この種と同時に記載されたヒロベソイボヤギヤドリイトカケも今回初めて沖縄から産出が確認された。E. reticulatum(Habe, 1962)センナリスナギンチャクイトカケは,貝殻の形態から本属に含めたが,本属の知られているすべての種がイボヤギ類に着生する(Gittenberger & Gittenberger, 2005)のに対して,本種はヒドロ虫類のセンナリスナギンチャクに付着する(Habe, 1962)ことから,今後の詳しい検討が必要である。Alora annulata (Kuroda & Ito, 1961)テラマチイトカケは寄主などの情報が不明であるが,原殻の形態的特徴と近年の他の文献等に倣い暫定的にAlora属に残す。Alora kiiensis Nakayama, 2000キイテラマチイトカケは明らかに異旋する大型の原殻をもつことなどから,タクミニナ科のTuba属に移される。本新種はE. billeeanumやイボヤギヤドリイトカケよりも小型で,螺層が角張りを持ち,殻口が方形であることで明瞭に異なる。ヒロベソイボヤギヤドリイトカケとは縫合が浅く,彫刻が弱いことで区別される。センナリスナギンチャクイトカケは殻形が最も近似するが,周縁が丸く,螺肋がより強くて数が少なく,格子状の彫刻を示すことで区別される。
5 0 0 0 ピル : 私たちは選ばない
- 著者
- 女のためのクリニック準備会編
- 出版者
- 女のためのクリニック準備会
- 巻号頁・発行日
- 1987
5 0 0 0 OA 正座 : 「日本人」を作る
- 著者
- 橋本 満
- 出版者
- 甲南女子大学
- 雑誌
- 甲南女子大学研究紀要. 人間科学編 (ISSN:13471228)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.89-100, 2014-03-18
- 著者
- Akiho Sugita Ling Ling Taishi Tsuji Katsunori Kondo Ichiro Kawachi
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20190337, (Released:2020-09-19)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 10
Background: Active engagement in intellectually enriching activities reportedly lowers the risk of cognitive decline; however, few studies have examined this association, including engagement in traditional cultural activities. This study aimed to elucidate the types of cultural engagement associated with lower risk of cognitive impairment.Methods: We examined the association between cultural engagement and cognitive impairment using Cox proportional hazards models in a cohort of 44,985 participants (20,772 males and 24,213 females) aged 65 years or older of the Japan Gerontological Evaluation Study from 2010 to 2016. Intellectual activities (e.g., reading books, magazines, and/or newspapers), creative activities (e.g., crafts and painting), and traditional cultural activities (e.g., poetry composition [haiku], calligraphy, and tea ceremony/flower arrangement) were included among cultural engagement activities.Results: Over a follow-up period of six years, incident cognitive disability was observed in 4,198 respondents (9.3%). After adjusting for potential confounders such as depression and social support, intellectual activities were protectively associated with the risk of cognitive impairment (hazard ratio, HR for those who read and stated that reading was their hobby: 0.75 [95% confidence interval, CI 0.66–0.85] and those who read but did not consider reading a hobby: 0.72 [95% CI, 0.65–0.80]). Engagement in creative activities was also significantly correlated with lower risk of cognitive impairment (crafts: 0.71 [95% CI, 0.62–0.81] and painting: 0.80 [95% CI, 0.66–0.96]). The association between traditional cultural activities and the risk of cognitive impairment was not statistically significant.Conclusions: Engagement in intellectual and creative activities may be associated with reduced risk of dementia.
5 0 0 0 OA 内面化と社会的前意識 社会過程としての社会化
- 著者
- 加藤 隆雄
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.136-147, 1988-10-03 (Released:2011-03-18)
- 被引用文献数
- 1
5 0 0 0 野木宮の合戦再考 : 内乱における「合力」
- 著者
- 菱沼 一憲
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1-20, 2016-02
5 0 0 0 OA 主な業績と回顧
- 著者
- 河野 康子
- 出版者
- 法学志林協会
- 雑誌
- 法学志林 = Review of law and political sciences (ISSN:03872874)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.1・2, pp.5-15, 2018-03-13
5 0 0 0 OA 出版年鑑
- 著者
- 「読書人」編輯部 編
- 出版者
- 国際思潮研究会
- 巻号頁・発行日
- vol.1926年, 1926
5 0 0 0 OA 逆問題の解析手法
- 著者
- 久保 司郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.470, pp.1595-1604, 1992-11-15 (Released:2009-06-03)
- 参考文献数
- 72
- 被引用文献数
- 4
5 0 0 0 活字の歴史と技術
- 著者
- 加藤美方 森啓 藤田三男編
- 出版者
- 樹立社
- 巻号頁・発行日
- 2005
- 著者
- 大谷 道輝 川端 志津 假家 悟 内野 克喜 伊藤 敬 小瀧 一 籾山 邦男 森川 亜紀 瀬尾 巖 西田 紀子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.5, pp.323-329, 2002-05-01 (Released:2003-02-18)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 11 13
The effect of the intake of 200g of grapefruit pulp (corresponding to one grapefruit) on the pharmacokinetics of the calcium antagonists nifedipine (NF) and nisoldipine (NS) were investigated in 8 healthy Japanese male volunteers. A crossover design was used for the study: group I did not ingest any grapefruit (control group); group II ingested grapefruit 1 h after drug administration; and group III ingested grapefruit 1 h before drug administration. The intake of grapefruit pulp increased the plasma concentrations of both NF and NS, an effect that has previously been reported with grapefruit juice. The increase was most marked when grapefruit was eaten before drug administration. For both NF and NS, subjects who ingested grapefruit 1 h before drug administration exhibited a greater Cmax and AUC0—24 than did subjects in the control group. For NF, the Cmax was 1.4 times higher and the AUC0—24 1.3 times larger in group III than in group I. For NS, the Cmax was 1.5 times higher and the AUC0—24 1.3 times larger in group III than in group I. The increase in the AUC0-24 was significant for both drugs (p<0.05). The finding that the ratios of Cmax and AUC0—24 for unchanged drug and metabolites did not vary greatly among the three groups for either drug suggests that the increase in serum concentration produced by grapefruit intake may be due to other factors than an inhibitory effect on drug metabolism. Also, the increases in Cmax and AUC0—24 of NS produced by grapefruit intake were smaller than those produced by grapefruit juice intake, indicating that grapefruit pulp and juice have different effects on the pharmacokinetics.
- 著者
- 田中 優子
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.63-70, 2009
- 被引用文献数
- 3
本研究では,批判的思考に影響を及ぼす要因について検討することを目的とし,大学生138名を対象に,複数の論理的に正しいとは言えない論法のタイプを含む文章を3題提示した.参加者は,自由に感想を書いてよいフェーズ,任意で批判を要求されるフェーズ,強制的に批判を要求されるフェーズにおいて文章に対する記述を求められた.その際,参加者の半数には専門家が,残りの半数には匿名の大学生が書いたと説明することによって情報ソースの信憑性を操作した.論理的に正しいとは言えない論法を指摘できているかといった観点から批判的思考得点を算出した結果,論法のタイプが批判的思考の抑制に影響を及ぼすこと,批判の要求が明示的になるに従い批判的思考は促進されることが明らかになった.また,情報ソースの信憑性の高さが批判的思考を抑制する傾向があるものの,その影響は外的要求の程度や論法のタイプによって異なることが示された.
5 0 0 0 直面化が奏効した心因性対麻痺の1例
- 著者
- 岩橋 成寿 國井 啓子
- 出版者
- 一般社団法人日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.143-149, 2005-02-01
対麻痺を繰り返し神経内科で多発性硬化症が疑われた症例に二次的疾病利得を認め, 直面化技法を行い, これが奏効したので報告する. 患者は38歳, 大学工学部卒の男性. 突然の両下肢の知覚消失と麻痺が生じ, 多発性硬化症を疑われて神経内科に入院, ステロイド療法を施行された. 過去に2度, 7年前と8年前に対麻痩のため, それぞれ前脊髄動脈症候群, 横断性脊髄炎の診断で6カ付き間の神経内科入院歴があった. 脳と脊髄のMRI所見に異常を認めず, 症状と神経学的所見の解離を認められて第18病日に心療内科に紹介された. 家族面接により, 患者は職場での使い込みと借金を繰り返し, その度に親が責任を問わずに返済していたこと, 今回の発症も使い込みの露見直後である事実が判明し, 使い込みの責任を疾病によって回避するという二次的疾病利得の存在が明らかになった. 診断は転換性障害と詐病の判別が極めて困難であった. 生育歴上, 両親に溺愛され, 父性原理が欠如した養育を受けており, 超自我が未発達と思われた. 父親から「借金の後始末は今回が最後で, 次回は刑事責任も自分でとれ」と通告された後に対麻痺は消失し, 3日後に退院した.
5 0 0 0 アレルギー性鼻炎における昆虫アレルギーの全国調査
- 著者
- 奥田 稔 宇佐神 篤 伊藤 博隆 荻野 敏
- 出版者
- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科學會會報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.12, pp.1181-1188, 2002-12-20
- 被引用文献数
- 4 7
アレルギー性鼻炎患者(AR)における昆虫アレルゲンの症状への関与を調べるため,560例のARを対象にしてガ,ユスリカ,ゴキブリを含む13アレルゲンに対するIgE抗体を測定した.また,65例の患者でこれら3種の昆虫の鼻誘発試験を実施した.<br>ガ,ユスリカおよびゴキブリに対するIgE抗体保有率はそれぞれ32.5%,16.1%,13.4%であった.これらIgE抗体保有率には,地域,年齢,治療および合併症による差は認められなかった.<br>鼻誘発試験で陽性と判定される割合は,RASTクラスが高いほど多くなる傾向があった.とくにゴキブリ,ガにおいて,RASTクラス3以上では,各々55.6%および61.5%が鼻誘発試験に陽性を示した.<br>昆虫間のIgE抗体価の相関を検討したところ,ガ,ユスリカ間には強い相関が認められ共通抗原性を示唆したが,ゴキブリ,ガ間およびゴキブリ,ユスリカ間では強い相関は認められなかった.また,いずれの昆虫もヤケヒョウヒダニおよび室内塵に対するIgE抗体価との相関は認めなかった.<br>以上の結果,日本においてガ,ユスリカ,ゴキブリは,アレルギー性鼻炎を起こす原因となっていることが示された.
5 0 0 0 実母からの出産体験の伝承に対する妊婦の意味づけ
- 著者
- 実積 麻美 大谷 愛佳 山崎 愛沙 山下 恵 和田 亜弓 谷脇 文子
- 出版者
- 日本母性衛生学会
- 雑誌
- 母性衛生 (ISSN:03881512)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.542-550, 2008-01
本研究は実母からの出産体験の伝承(実母が経験した妊娠・出産・育児の体験や,その体験によって感じた思いを実母自身の言葉で表現し,娘に語り伝えること)に対する妊婦の意味づけを明らかにすることを目的とした。妊娠中期・後期の初産婦6名に半構成的面接法によりデータを収集し,質的帰納的に分析を行った。その結果,実母からの出産体験の伝承に対する妊婦の意味づけとして,次の5つの特徴,『母への親密性を強める』『親になる偉大さを感じる』『親準備性に向かう』『次世代への伝承の必要性を感じる』『自己成長のきっかけとなる』が見出された。そして,実母の出産体験の伝承が妊婦の自律性の育成を培い,母性意識の発達を促し,主体的な親になる準備性を支えていることが明らかとなった。本研究における看護への示唆として,伝承により意味づけられた妊婦の主体性をより促進する援助の重要性が見出された。伝承を看護の中に位置づけることで,妊婦の主体性を促進し,妊婦が目指す出産体験を尊重するような援助につなげていく必要がある。
5 0 0 0 IR 『承久記絵巻』について--新資料紹介
- 著者
- 松本 寧至
- 出版者
- 二松學舎大学
- 雑誌
- 二松学舎大学東洋学研究所集刊 (ISSN:02867192)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.53-82, 1997