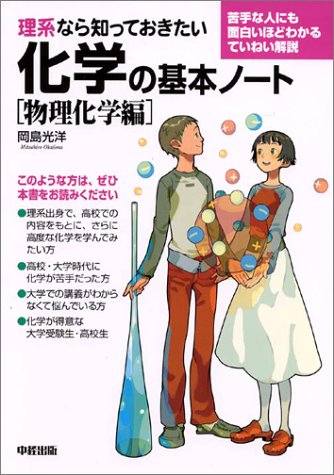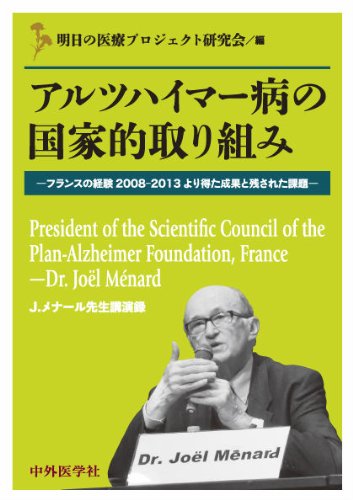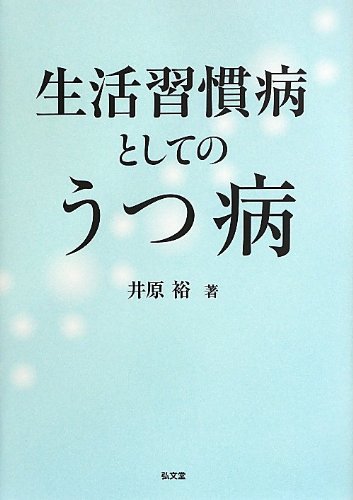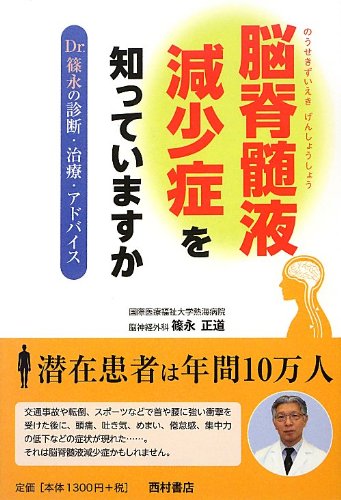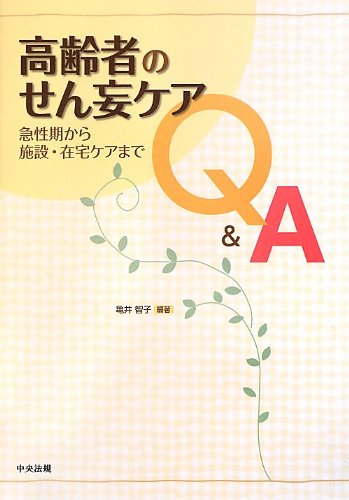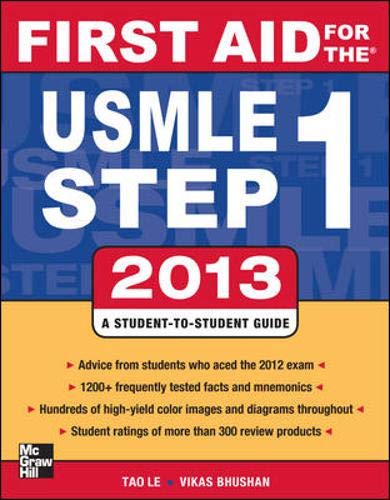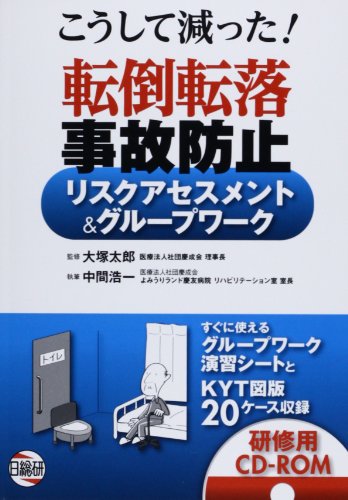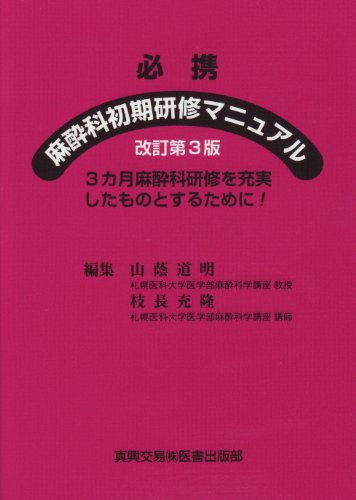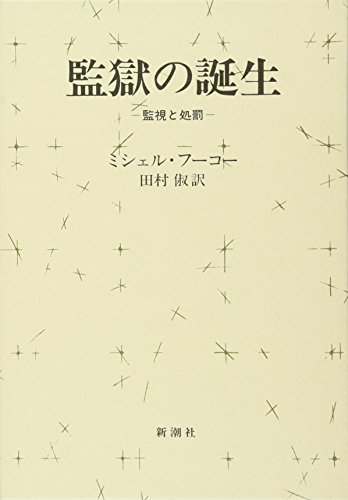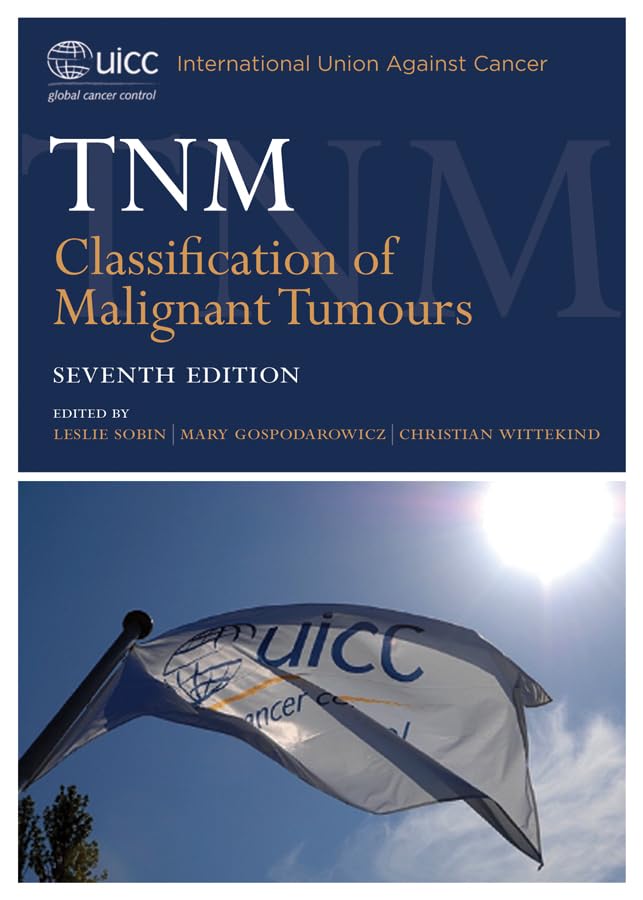1 0 0 0 OA 若い小惑星族小惑星の自転状態と表面状態の解明
- 著者
- 高橋 健太郎
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経network (ISSN:1345482X)
- 巻号頁・発行日
- no.72, pp.67-87, 2006-04
- 被引用文献数
- 1
「インターネット」という言葉が新聞やテレビに出ない日はないだろう。そのくらいインターネットは私たちの暮らしに身近な存在となっている。 インターネットを一言で表すと,世界規模のコンピュータ・ネットワークとなる。技術的に見れば,次の二つの特徴を持つ。一つは,「IP」(internet protocol)というプロトコル(通信手順)によってしくみが決められていること。
1 0 0 0 女子体育
- 著者
- 日本女子体育連盟編集
- 出版者
- 日本女子体育連盟
- 巻号頁・発行日
- 1962
1 0 0 0 OA G蛋白共役型受容体のホモダイマー形成によるリガンド親和性・細胞シグナルの変化に関する研究
- 著者
- 堀江 武 中川 博視
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.687-695, 1990-12-05
- 被引用文献数
- 24 21
イネの幼穂分化, 出穂および成熟などの発育ステージを環境要因の経過から予測するモデルの基本構造とパラメータの推定法を提案し, その考え方のもとに出穂期の気象的予測モデルを導き, 水稲品種日本晴に適用した。本モデルでは, de Witらの発育速度の慨念を適用して, 出芽後n日目の発育指数 (Developmental Index, DVI) はその間の発育速度 (Developmental Rate, DVR) を積算したものとして与える。さらに出芽時のDVIを0, そして出穂時のそれを1と定めることによって, 出芽から出穂に到る発育過程をDVI=0〜1の間の連続的な数値として表すことができる。このようなDVIの制約条件下で, DVRと気温および日長との関係を与える数式を導き, かつそのパラメータを, 筑波と京都での日本晴の作期移動試験および人工気象室実験から得られた出穂日のデータを用いて, シンプレックス法によって決定した。得られたパラメータの値から, 日本晴の出芽から出穂までの最小日数 (基本栄養生長性) は51.4日, 限界日長は15.6時間, 発育の最低温度は12〜13℃, 同最適温度は30〜32℃, そして日長に感応し始める時期はDVI=0.20と推定された。本モデルによる出穂データの推定精度は標準誤差で3.6日であったが, 従来の有効積算温度法によるそれは6.5日であった。したがって, 本報のモデルは従来の方法に比較して高い予測精度を得ることが可能と考えられる。
- 著者
- Tomonori ANDO Yoshiyuki KABASHIMA Hisanao TAKAHASHI Osamu WATANABE Masaki YAMAMOTO
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (ISSN:09168508)
- 巻号頁・発行日
- vol.E94-A, no.6, pp.1247-1256, 2011-06-01
We study nn random symmetric matrices whose entries above the diagonal are iid random variables each of which takes 1 with probability p and 0 with probability 1-p, for a given density parameter p=α/n for sufficiently large α. For a given such matrix A, we consider a matrix A ' that is obtained by removing some rows and corresponding columns with too many value 1 entries. Then for this A', we show that the largest eigenvalue is asymptotically close to α+1 and its eigenvector is almost parallel to all one vector (1,...,1).
- 著者
- 大川 なつか
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院 教育学研究科紀要 別冊 (ISSN:13402218)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.71-80, 2007-09-30
1 0 0 0 OA ジョン・コレットとヒューマニズム
- 著者
- 大川 なつか
- 出版者
- 早稲田大学ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所
- 雑誌
- エクフラシス : ヨーロッパ文化研究 (ISSN:2186005X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.95-107, 2012-03-20
1 0 0 0 樹木の耐凍性獲得機構の解明
常緑樹の葉は、冬季であれば低温障害を受けることのない低温や降霜によって秋や春には甚大な被害を受けることが知られている。これは常緑樹が周囲の温度環境の変化に応じて樹体の低温耐性を変化させていることを示している。本研究では、暖温帯を主な生育地域とするスギを材料として、周囲の温度環境をどのように感知し、葉の低温耐性を高めたり低めたりしているのかを明らかにすることを目的に、実験的に地下部と地上部の温度環境を別々に制御して葉の水分特性がどのように変わるのかを調べた。葉の膨圧を失うときの水ポテンシャルは、秋から冬にかけて低下し、特に気温が5℃以下で急激に低下する季節変化を示す。この水分特性値の変化は、凍結温度の低下や細胞外凍結時の細胞内水の減少に対する耐性を高めるものである。このような季節変化が、地温を下げることによって早まり、暖めることによって遅れること、水分特性の変化には1週間程度の時間がかかることを明らかにした。この時、飽水時の浸透ポテンシャルの低下は明瞭でなかった。また、地温が5℃以下の時に葉を暖めても葉が低温耐性を失なわず、苗木全体を暖めることによって低温耐性を失う(可逆的な変化)ことを明らかにした。地温の低下に伴う葉の水分特性値や糖濃度の変化を検討し、膨圧を失うときの水ポテンシャルの低下に寄与しているのは、細胞内溶質の増加よりも、体積細胞弾性率(細胞壁の堅さ)の増大の方が大きいことを示した。以上の結果から、秋から冬にかけての地温の低下に応答して、スギの葉が低温に対する耐性を獲得することを明らかにした。季節はずれ降霜(晩霜、早霜)の害は、気温に比べて地温の季節変化が穏やかであり、急激な気温の低下に樹木が応答できないために発生すると考察した。
- 著者
- 長尾和夫 トーマス・マーティン著
- 出版者
- 三修社
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 理系なら知っておきたい化学の基本ノート
- 著者
- 明日の医療プロジェクト研究会編
- 出版者
- 中外医学社
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 生活習慣病としてのうつ病
1 0 0 0 高齢者のせん妄ケアQ&A : 急性期から施設・在宅ケアまで
- 著者
- Tao Le ...
- 出版者
- McGraw-Hill Medical
- 巻号頁・発行日
- 2013
- 著者
- 山蔭道明 枝長充隆編集
- 出版者
- 真興交易医書出版部
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 監獄の誕生 : 監視と処罰
- 著者
- ミシェル・フーコー [著] 田村俶訳
- 出版者
- 新潮社
- 巻号頁・発行日
- 1977
- 著者
- edited by L.H. Sobin M.K. Gospodarowicz and Ch. Wittekind
- 出版者
- Wiley-Blackwell
- 巻号頁・発行日
- 2010