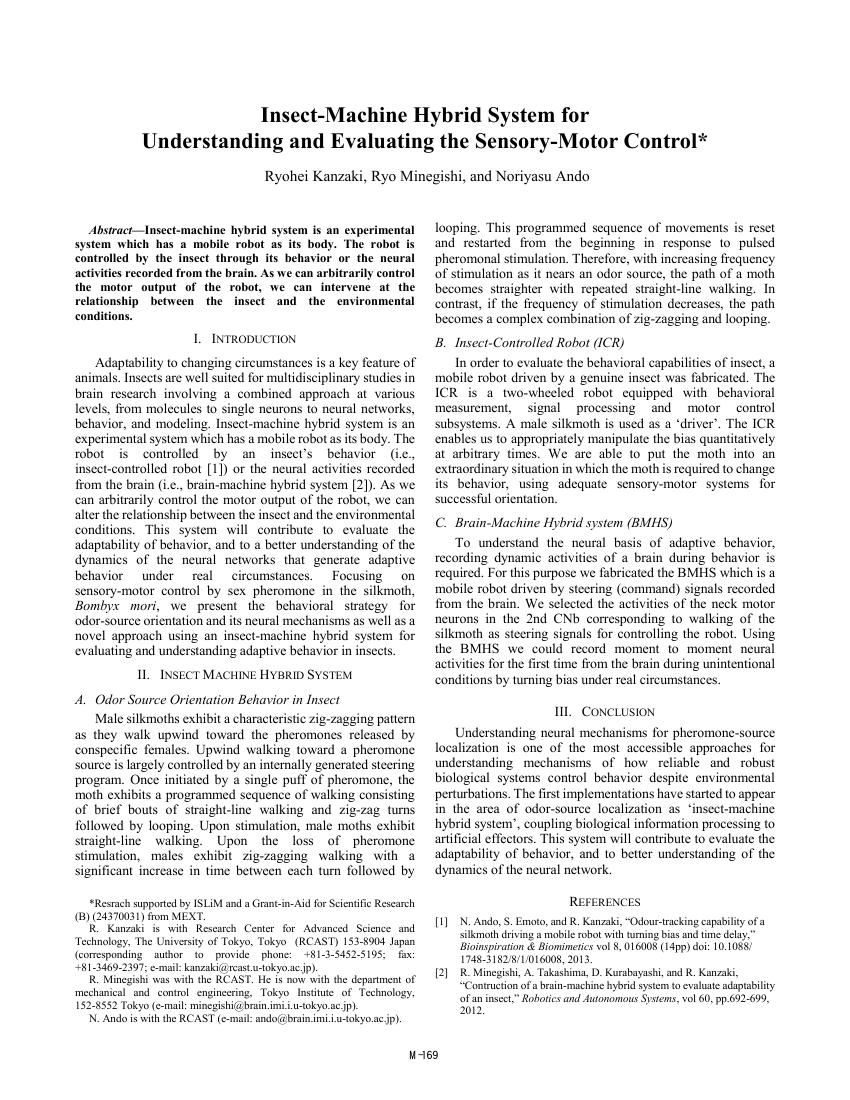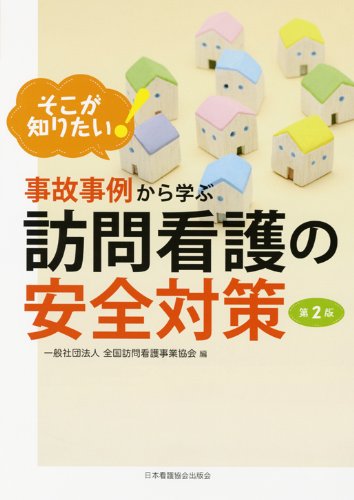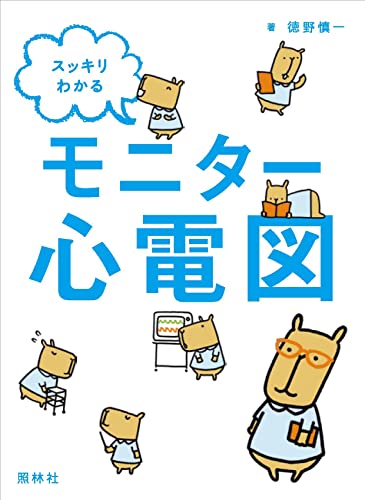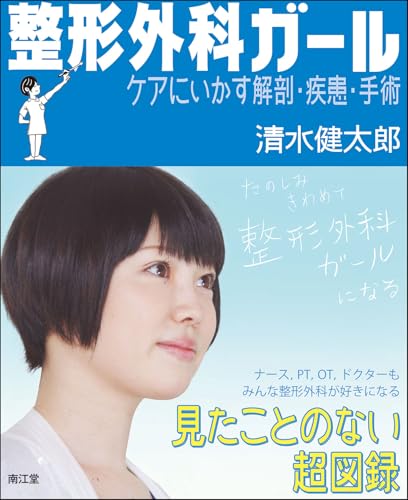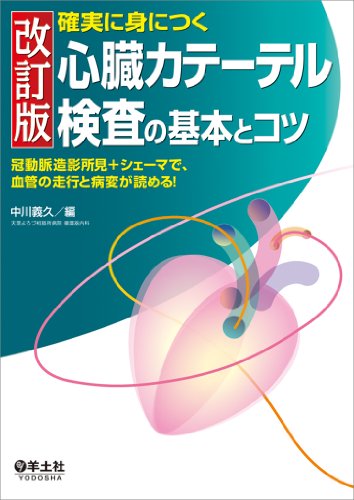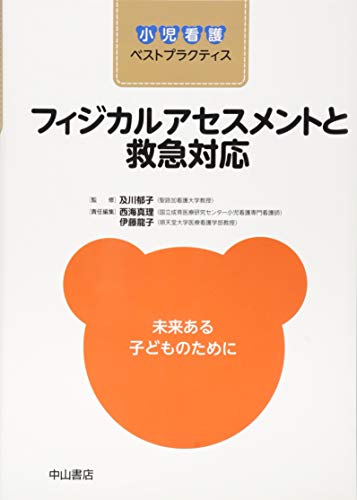1 0 0 0 手書き建築間取り図面理解システム : Sketch Plan
- 著者
- 塩 昭夫 青木 康浩
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-情報処理 (ISSN:09151923)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.431-439, 1999-03-25
- 被引用文献数
- 5 2
定規などを用いずに手書きされた建築間取り図面を, スキャナから読み取って認識し, 建具, 収納, 階段などの建築要素に自動変換するシステム(Sketch Plan)を開発した. 本論文では, このシステムの入力条件, 図面認識/理解処理アルゴリズム, 及びシステム評価の結果について述べる. 筆記変動を含む手書き図面を自動認識するため, 図面上の線分情報と領域情報を独立に処理し, それらの結果を統合する独自の図面認識処理アルゴリズムを考案した. このアルゴリズムを実際の手書き間取り図面を用いて評価した結果, 認識率93%を得た. また, 認識結果の確認・修正も含めた図面入力時間を実測した結果, マウスを用いたマニュアル入力の約1/9になることがわかった.
1 0 0 0 OA 魚類における配偶システム・雌雄同体性の系統進化と脳内ホルモン遺伝子に関する研究
単系統群を形成するハゼ科ベニハゼ属・イレズミハゼ属を用いて, 一夫一妻,一夫多妻を示す種について,繁殖行動への関与が知られるアルギニンバソトシン(VT)およびイソトシン (IT) の上流域を種間で比較し, 配偶システムとの関連を探索した. 配偶システムは5種で一夫一妻, 7種で一夫多妻であった.一夫一妻3種, 一夫多妻2種について, VT遺伝子及びIT遺伝子上流域の塩基配列を決定した.配偶システムと関連は見られなかったが,雌雄異体のカスリモヨウベニハゼと雌雄同体の他種の間に塩基配列の変異が認められた.これはVTが性転換に関係した転写調節機構を有している可能性を示唆している.
1 0 0 0 OA 日本語で書かれた専門用語は生き残れるか
- 著者
- 太田 泰弘
- 出版者
- 日本フードシステム学会
- 雑誌
- フードシステム研究 (ISSN:13410296)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.1-1, 2008-06-30 (Released:2010-12-16)
- 著者
- 小西 英則 Hidenori Konishi
- 雑誌
- 共立女子大学文芸学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.59-81, 2014-01
- 著者
- Ryohei Kanzaki Ando Noriyasu Minigishi Ryo
- 出版者
- 一般社団法人日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Supplement, pp.M-169-M-169, 2013 (Released:2013-09-06)
- 著者
- Alper Bozkurt
- 出版者
- 一般社団法人日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Supplement, pp.M-166-M-166, 2013 (Released:2013-09-06)
- 著者
- Chun Kit Alex Chan Hiroyuki Hamada KOHEI HIGUCHI Kazusuke Maenaka
- 出版者
- Japanese Society for Medical and Biological Engineering
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Supplement, pp.M-158, 2013 (Released:2013-09-06)
- 著者
- Abhijit Suprem
- 出版者
- Japanese Society for Medical and Biological Engineering
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Supplement, pp.R-12, 2013 (Released:2013-09-06)
1 0 0 0 OA Accurate Detection of T Wave with an Improved Electrode Structure in a Capacitive Sheet-Type Sensor
- 著者
- Shinsuke Yamagishi Yoshihiro Masuda Yutaka Fukuoka Akinori Ueno
- 出版者
- 一般社団法人日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Supplement, pp.R-15-R-15, 2013 (Released:2013-09-06)
1 0 0 0 IR 連続ステレオ画像からの3次元情報の抽出
- 著者
- 山本 正信 Yamamoto Masanobu
- 出版者
- 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子通信学会論文誌 D (ISSN:0374468X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.11, pp.p1631-1638, 1986-11
- 被引用文献数
- 42
両眼ステレオ視は,3次元情報の手軽な獲得法ではあるが,左右画像間の対応付けの際に,(1)多重対応,(2)隠れ,(3)順序の逆転,(4)水平エッジ,などがある場合に於て,対応点探索が困難になる.本論文では,視点を移動させつつ得られた連続ステレオ画像から,シーンの3次元情報を推定する手法を提案する.まず,連続ステレオ画像から,見かけの運動軌跡が線分として画像化されるような2次元画像を合成する.その時,対応付け問題は,合成画像上の線分検出問題として簡略化される.検出された線分の相互関係を調べることにより,隠れの検出や,見かけの逆転が起きた場合の対応付けも容易になる.更に,視点を一方向だけではなく,それと直交する方向にも移動させることにより,エッジの向きに依存しない一意な対応付けが可能となる.大量の連続ステレオ画像が高速に入力可能な装置を構成し,実際に,複雑なシーンの3次元構造を復元する.
1 0 0 0 地域住民のライフスタイルと精神的健康度との関連
1 0 0 0 OA 黒潮再循環変動特性の解明と大気大循環場への影響理解
1 0 0 0 OA 配糖體に關する二三の實驗説
- 著者
- 山下 泰藏
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- 藥學雜誌 (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- no.385, pp.227-234, 1914-03-26
其一,アミグダリン酸の酸誘導體につきて著者はアミグダリン酸バリウムに無水醋酸と醋酸曹達とを作用せしめて得たるアセチール誘導體がアルカリに不溶解なることと其分析數C_<32>H_<38>O_<18>なることより六アセチールアミグダリン酸のラクトン體なることを唱へ又アミグダリン酸バリウムに冷時にベンツオイルクロリドを作用せしめて五ベンツオイール化合物を得たるも亦アルカリに不溶なるを以て四ツのベンツオイール基のみが水酸基と交換し一つはアミグダリン酸の炭酸基と混合無水酸の状態にあることを論ぜり又無水安息香酸の作用によりては八アセチール化合物に相當する物質を得たるも元來アミグダリン酸には七箇の水酸基あるのみなるを以て他の一つは亦無水酸の状態に附加せることを述べたり 其二、芳野櫻花蕾の配精體櫻葉及櫻花のクマリン香氣は生時に之を發せずして或る醗酵を受けて初めて生ずるものなればクマリンはもと他の化合物恐くは配糖體の状況にて植物體中に存在するもの、如し著者は此見地より芳野櫻の蕾を取扱ひしに珈琲酸の配糖體を得たるのみなりき
1 0 0 0 OA 18世紀後半の知の形成と伝達における言語とイメージの相互作用
1 0 0 0 OA 民俗学的実践と市民社会―大学・文化行政・市民活動の社会的布置に関する日独比較
- 著者
- 岩本 通弥 森 明子 重信 幸彦 法橋 量 山 泰幸 田村 和彦 門田 岳久 島村 恭則 松田 睦彦 及川 祥平 フェルトカンプ エルメル
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-01
本研究は、日独の民俗学的実践のあり方の相違を、市民社会との関連から把捉することを目指し、大学・文化行政・市民活動の3者の社会的布置に関して、比較研究を行った。観光資源化や国家ブランド化に供しやすい日本の民俗学的実践に対し、市民本位のガバナビリティが構築されたドイツにおける地域住民運動には、その基盤に〈社会-文化〉という観念が根深く息づいており、住民主体の文化運動を推進している実態が明確となった。
1 0 0 0 事故事例から学ぶ訪問看護の安全対策 : そこが知りたい!
- 著者
- 全国訪問看護事業協会編
- 出版者
- 日本看護協会出版会
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 スッキリわかるモニター心電図
1 0 0 0 整形外科ガール : ケアにいかす解剖・疾患・手術
1 0 0 0 フィジカルアセスメントと救急対応
- 著者
- 西海真理 伊藤龍子責任編集
- 出版者
- 中山書店
- 巻号頁・発行日
- 2014