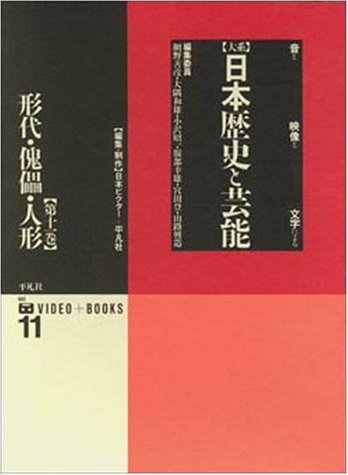1 0 0 0 OA 知的障害生徒における選択行動アセスメントマニュアルの作成と社会的妥当性の検討
- 著者
- 裴 虹 園山 繁樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.505-516, 2012 (Released:2013-09-14)
- 参考文献数
- 16
本研究では、選択行動を一連の行動連鎖ととらえた「選択行動アセスメントマニュアル」を作成し、中国の知的障害特別支援学校1校で実際に適用し、その社会的妥当性を検討した。教師22名に本アセスメントマニュアルを、学校の多くの日常場面において、担当する知的障害生徒22名に適用してもらい、適用後に、教師に対して、「記録表の内容」「記録表の記入」「アセスメントの実施」「アセスメントの効果」「アセスメントマニュアルの合理性」の5項目に関する社会的妥当性評価のアンケート調査を実施した。その結果、選択行動アセスメントマニュアルはおおむね妥当であったと評価されたが、記録表の記入が難しかった教師も少数あり、記録の仕方やアセスメントの実施により、時間がかからないような工夫が求められた。今後は、本アセスメントマニュアルを適用した指導事例の検討を行い、その具体的な有用性と使用方法を検討する必要がある。
1 0 0 0 福祉教育・ボランティア学習の実際に関する考察
- 著者
- 外崎 紅馬
- 出版者
- 会津大学短期大学部
- 雑誌
- 会津大学短期大学部研究年報
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.169-179, 2010-03-25
- 被引用文献数
- 1
学校教育における福祉教育は、1977(昭和52)年度にスタートした「学童生徒のボランティア活動普及事業」(福祉教育協力校制度)によって全国的に展開された。現在、「総合的な学習の時間」の創設により、学習課題としての社会福祉への取り組みを行う学校も多くみられるようになった。しかし、そこで取り組まれている学習活動は、募金活動や清掃・美化活動、車いすやアイマスクなどを使っての疑似体験や、高齢者・障害者施設への訪問、交流活動などが中心となっており、学習内容としては、体験から得られる児童生徒の感想まかせで、必ずしも合理性のある意図的な教育活動とはいえない状況である。一方、小・中・高の現職教員そのものの社会福祉についての理解の不足から、福祉教育についての必要性は感じながらも、教育実践について戸惑いがあり、その教育内容にも確信をもてずにいることも事実である。そこで本研究では、現在の小中高等学校の福祉教育の実際について検討を行った。
1 0 0 0 IR アイマスクによる体験学習の効果 ―臨床実習への応用―
- 著者
- 中西 代志子 池田 敏子 徳永 順子
- 出版者
- 岡山大学医療技術短期大学部
- 雑誌
- 岡山大学医療技術短期大学部紀要 (ISSN:09174494)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.63-66, 1993-01-31
We introduced the method of the experiential learning of eyesight-screening into the area of a sense organ practice in order to research on how it could influence the students' understanding of psychology of the patients suffering from eyesight trouble and the ways of their helping the patients. As a result, we came to the conclusion that the introduction of the experiential learning by using eyemasks was quite effective in understanding patient psychology and in helping the patients psychologically. We could find out the remarkable effects in understanding the necessity of helping the patients as well as the ways to help the patients.
1 0 0 0 OA 物体の持ち上げ時に知覚される重さに関する基礎的研究-慣性力情報の処理機構-
持ち上げ時に知覚される物体の重さへの慣性力の影響を検討した。慣性力は指先の物体接触面から物体までの距離(作用点-重心)および軸周りの質量分布に影響される。故に同じ質量で大きさ(3水準)および距離(3水準)が異なる9種類の竿付立方体を用い、これら刺激から知覚される重さの変化から、距離(実験1)および大きさと距離(実験2)の影響を調べた。実験1からは距離の増大は重さの増大を生じた(p <.05)。実験2からは距離の増大+大きさの減少は重さの増大(あるいはその逆)を生じたが、両要因の拮抗関係が崩れると重さは複雑に変化した。そこで複雑な両要因の影響を量的・組織的に説明できるモデルを提案した。
1 0 0 0 OA 大主教ニコライ師襄事録
- 著者
- 大主教ニコライ師葬儀委員会 編
- 出版者
- ハリストス正教会本会
- 巻号頁・発行日
- 1912
1 0 0 0 OA 省庁別財務書類 : 総務省
1 0 0 0 OA 見る者の眼 : シェイクスピア喜劇の異性装とジェンダー(序論)
- 著者
- 小野 良子
- 出版者
- 桃山学院大学
- 雑誌
- 英米評論 (ISSN:09170200)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.57-71, 2000-12-20
The female figures in Shakespeare's comedies, such as Rosalind in As You Like It and Viola in Twelfth Night, are traditionally portrayed as healthily asexual heroines by women actors on the modern stage or screen. The disguised heroine as witty, eloquent, and beautiful boy who is erotically alluring to another female figure in the play reveals in the final act the female body in the female clothes to celebrate her own marriage to a male superior. The cross-dressing of the female figure is simply taken for granted as a theatrical convention and never raises sociopolitical issues concerning sexuality and gender among the modern audience. However, for the critical reader of Shakespeare's plays transvestism and 'the body beneath' of the female figures are of much consequence in speculating on the representation and its reinterpretation of the Elizabethan stage. Every Shakespeare student knows that there were no professional women actors on the English stage before 1660, and that the female roles had been played by young male actors. The taking of female parts by boy actors should not be dismissed as the convention. Indeed, this fact has raised crucial issues of postmodern cultural criticism among Shakespearean readers. From the recent critical point of view, identity, either gendered or sexed, has been seen as a historical production. The human subject is considered the ideological product of the relations of power in the Elizabethan patriarchal society. The theatre then becomes an agent of the absolutist state, reproducing the state's strategies and celebrating and confirming its power. The purpose for my essay is to examine the process by which power is produced and legitimated on the Shakespearean stage and to lead to the argument which explores possibilities of reinterpretation and its cultural production of Shakespeare's comedies on the modern Japanese stage. This paper traces the contemporary anti-theatrical campaign and its discourse which condemned the closs-dressing of the boy actor as the threat to the male identity and hierarchical society itself; and then speculates upon the relation between the boy actor and the woman he plays-the imaginedbody of a woman, a staged body of a boy actor-and how clothes embodied and determined a particular sexual identity and contradictory fantasies of the body beneath.
1 0 0 0 OA カナダへの香港人移民
- 著者
- 谷垣 真理子
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)
- 巻号頁・発行日
- vol.157, pp.156-190, 2010-03-26
1997年问题出现以后,香港有不少人移民海外。加拿大就是其中之一个移民目的地。为了调查香港移民情况,笔者访问过多伦多(1998年,1999年)和温可(1998年,1999年,2009年)。2009年笔者参加了关元昌家族宗亲会活动。本搞首先整理从香港移民至北美的历史,以考察二战后香港移民如何巩固移民加拿大后的生活。本稿亦整理了笔者在加拿大的采访调查。笔者还讨论了1980年代以前移民加国的‘老香港’与1980年代以后移民加国的‘新香港’,特别是1997年以后加拿大香港移民的化情况。既往的研究往往关注因香港回归问题所引发的香港移民的特殊性。但本文也将揭示,在加拿大香港移民中,恰恰是1960年代以移民的‘老香港’所建构的文化社会安全网而令‘新香港’的安顿创造了条件。‘香港人’一词是二战后新出现的用语,其本身也是冷战的产物,因为冷战结构延续至中国,香港中断了与中国内地的交流,与香港工业化过程同时出现的,是香港社会的统合进程。
1 0 0 0 OA 高知県軍事援護誌
- 出版者
- 軍人援護会高知県支部
- 巻号頁・発行日
- 1941
1 0 0 0 IR 佐藤春夫『西班牙犬の家』論 : 幻想文学の手法を中心として
- 著者
- 及川 早紀
- 出版者
- 青山学院大学
- 雑誌
- 青山語文 (ISSN:03898393)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.75-84, 2010-03
- 著者
- 星野 次汪 伊藤 誠治 谷口 義則 佐藤 暁子
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.21-25, 1994-03-05
- 被引用文献数
- 5
粒大と品質との関係を明らかにするため, 1989/1990年, 1990/1991年に栽培したコユキコムギを用いて, 原粒を縦目篩を用いて大きさ別に分け, 原粒及び粒大別に製粉された60%粉の粗タンパク含有率, 灰分含有率及びコムギ粉生地の物性などについて試験を行った. 粒大が大きいほど千粒重は大きく, 3.0mmの粒は1.8mmの粒の約3倍の重さであった. 粗タンパク含有率は1989/1990では粒大が大きいほで高くなったが, 1990/1991ではいずれの粒大でもほぼ一定の値であった. 灰分含有率は1989/1990では2.4mm, 1990/1991では2.6mmの粒が最も低く, それより粒大が大きくなるかあるいは小さくなるにしたがって高くなった. 製粉歩留は, 粒大が大きいほど高くなり, 粒大間に1%水準の有意差が認められた. 粉の比表面積(cm^2/g)は粒大が大きいほど小さかった. 粉の白さ(R455), 明るさ(R554)は粒大が大きいほどその値は大きかったが, 胚乳の色づき(logR 554/R 455)は逆に小さかった. ファリノグラムの特性値(Ab, DT, Stab., V. V, Wk)及びアミログラム最高粘度は粒大間で有意差が認められなかったが, エキステンソグラムの各特性値のうち, 面積は1.8mmの粒を除けば粒大が小さいほど大きく, 伸長抵抗は粒大の大きいもの及び小さいものが小さかった. これらのことから, 大粒は, 灰分含有率が低く, 製粉歩留が高く, 粉色相が優れているが, ブラベンダー特性はやや小粒の方が優れていた.
1 0 0 0 OA 西南夢物語 : 狂言の世界ハ報知新聞脚色の大意ハ戦地直報
- 出版者
- 高雄州
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和12年度, 1938
- 著者
- 平岡 辰士
- 出版者
- 日本知的障害者福祉協会 ; 2002-
- 雑誌
- さぽーと : 知的障害福祉研究 (ISSN:13476521)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.8, pp.14-16, 2013-08
1 0 0 0 OA 改正まちづくり三法と歩いて暮らせるまちづくりの経済地理学
東日本大震災と原子力災害の発生により,研究目的及び研究実施計画を一部変更して,被災商店街や商業者を対象とする調査を行った。調査結果からは「歩いて暮らせるまちづくり」の重要性がより強く認識されることとなった。商店街は地域社会の経済活動だけでなく,地域社会における諸活動の要の役割を果たしてきている。それは震災・原災という非常時においても,地域住民に商品やサービスを可能な限り早く提供するという業務的役割のほかに,瓦礫の片づけ,除染活動,食糧援助,募金活動など地域社会への貢献活動を積極的に行った。それは大型店とは違った顔の見える地域社会への貢献である。併せて,商店街が復旧に立ち上がるためにも,水・電気・ガソリンなどのライフラインの確保が前提となることが再認識された。
- 著者
- 石田 雅樹
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 筑波法政 (ISSN:03886220)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.103-123, 1998-12