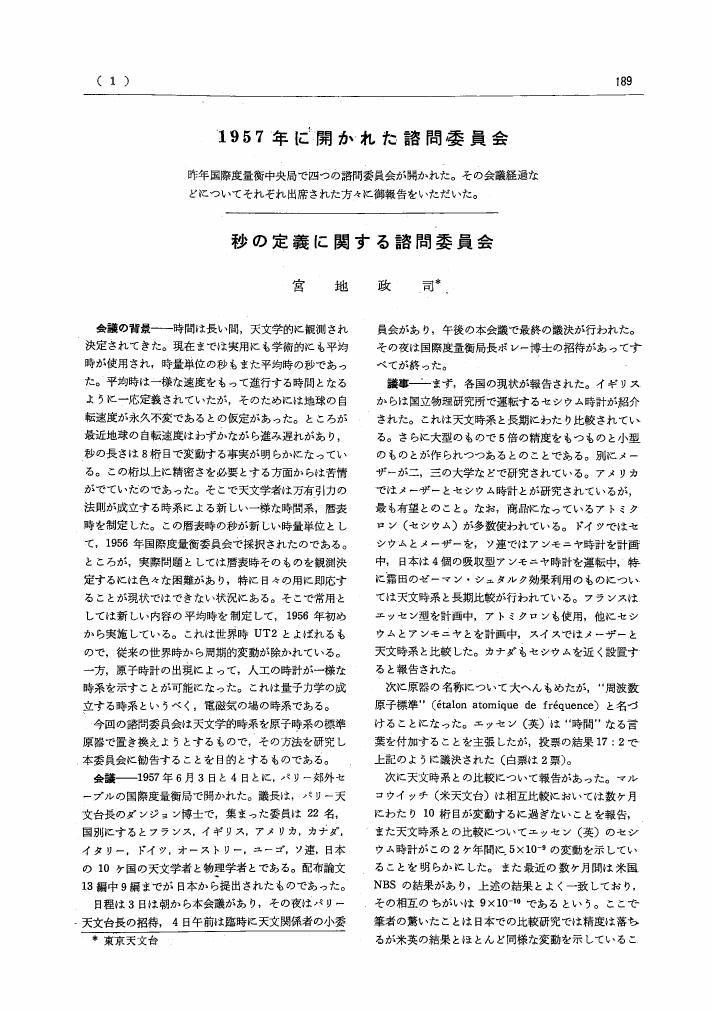1 0 0 0 OA 高解像度蛍光カルシウム画像の定量的評価法の確立
近年、2光子顕微鏡などのイメージング装置の急激な発展により、細胞内のカルシウム動態を時空間的に高解像度で計測可能となった。我々は、高解像度カルシウムイメージングデータの解析手法を開発した。研究I:カルシウムイオン濃度と観測可能な蛍光シグナルの間にある物理過程を状態空間モデルで記述し、細胞内カルシウム濃度を推定するベイズ統計手法を開発した。研究II: 樹状突起内のカルシウム波を定量的に解析する手法を開発した。研究III: 高解像度多細胞イメージングデータに非負値行列因子分解を適用し、細胞体や樹状突起などの機能単位の蛍光信号を自動的に分離するアルゴリズムを開発した。
本研究の第一年目の計画は資料収集と研究準備の段階を設定しております。今年度は一連の図書館、博物館、史料館で19世紀後半における長崎、浦塩、上海と海底電信に関する史料収集を行った。具体的に長崎市では海底線史料館、長崎歴史文化博物館、長崎県立図書館で、上海市では上海市図書館、上海市档案館、上海市電信博物館でウラジオストク市立ゴーリキー図書館、国立遠東大学図書館、国立アルセーニエフ総合博物館、アムール地区研究会図書館で文献資料収集した。集めたロシア語の史料の一部を英語に翻訳してもらいました。又はデンーマクの学者の協力を得て、大北電信会社の営業報告書の一部を入手した。極東アジア都市史と通信史の先行研究も購入した。さらに資料収集と共に、中国ロシアの研究者と都市史、通信史について有意義な交流が出来ました。これらの研究活動によって、19世紀後半から20世紀に初期にかけて長崎、浦塩、上海における「通信事情」と研究状況を解明することが出来ました。言うまでもなく、これらの研究活動は本研究の基盤である、こらから、史料の補足と分析する必要がある,これに基づいて、技術史、都市史等の諸分野の最新研究に照準し極東アジア地域通信史への新視角を構築することが出来ると信じている。
- 著者
- 船曳 建夫
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, 1983-11
Recent studies on social changes in Melanesia initiated by contact with the West could be divided into two: 1) those on the consequential changes among inhabitants after their closed society was opened up by westerners'visits ; 2) those on socio-political changes at a stage when a small community as a whole after its initial changes is going through social and institutional re-formation. The former are mostly concerned with the process of traditional culture being influenced by Western civilization and the latter with that of traditional society being re-structuralized into a much wider framework, for example, a nation. In the south-western part of Malekula Island, the New Hebrides, however, we can find the two kinds or stages of change referred to occurring in two adjacent areas. In the interior region, the inhabitants called Mbotgote are undergoing initial influence from the West on their culture, though they still keep their own way of life. On the coast, more west-ernized villagers who were converted to Christianity in their own or preceding generations now see a new situation arising from the imminent political schedule of the nation's independence. The author first describes the historical and cultural background of the New Hebrides archipelago and also that of the South-West of Malekula Island. In the description of the setting and the later discussion, a pair of notions, kastom and skul, is used as the analytical framework. Kastom in a narrow sense means ritual objects and, more broadly, anything proper to traditional life. Skul means a church as well as a school, but it has also a broader meaning: anything introduced from the Western world. The history of the archipelago has so far been the one-directional process of the skul side encroaching on the kastom side. But the following microso-ciological examination of the materials from Malekula reveals much oscillating movement of the people in the two areas concerned, which are presented in three aspects : 1) ritual and cosmology, 2) politics and administration, and 3) material life and economy. The interpretation of the data demonstrates that social change at a given time could differ in these three aspects in its extent and direction, and that, however limited their conditions are, these people positively manipulate the new elements of skul as a means to achieve their political and economic ends and even to defend their ritual (kastom) activities. In the last section the author suggests a working hypothesis that the most crucial point in a society's changing phenomena is whether the people's notion of ‘change’ itself is changing or not. The Mbotgote still basically conceive ‘change’ as var-iation within a fixed structure, while the coastal Christian people are realizing that ‘change’ is always there to push them to re-form their life and society under the name of progress or development.
1 0 0 0 マサ土を用いた盛土斜面の室内崩壊実験
- 著者
- 内田 一郎 鬼塚 克忠 平田 登基男
- 出版者
- 公益社団法人地盤工学会
- 雑誌
- 土質工学会論文報告集 (ISSN:03851621)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, 1977-03-15
マサ土地帯は山くずれ, 盛土ノリ面の侵食, 崩壊などが数多く発生し, 宅地造成や切土, 盛土斜面の形成工事において人身事故につながる危険性が大きく防災上からこの方面に関する研究の必要が高まっている。本文は, マサ土による盛土斜面の破壊機構を明らかにする目的でマサ土の物理的特性と共に, 圧縮沈下特性, 圧縮強度特性, セン断特性(間ゲキ圧・ダイレイタンシー・強度定数c, φ)を調べる基礎的実験と関連させて, 盛土斜面の模型実験から上部載荷, 繰返し荷重, 水の浸水による盛土斜面の崩壊機構について検討している。その結果, マサ土においても, 締固め密度が小さく含水比が大きくなると荷重による沈下量, 間ゲキ圧が増大し, 強度, 強度定数c, φダイレイタンシー指数が減少することを示し, さらに, ノリ肩近傍に載荷した場合の支持力算定式については, スベリ線の発生順序を考慮に入れるべきことを指摘し, マイヤーホッフの提案した支持力式の適用限界について論述している。
1 0 0 0 OA 伊勢湾台風災害と地球環境問題 : 流木被害と環境社会システム
- 著者
- 中須正
- 出版者
- 防災科学技術研究所
- 雑誌
- 防災科学技術研究所研究報告 (ISSN:13477471)
- 巻号頁・発行日
- no.75, 2009-09
1 0 0 0 IR 光増感反応を応用した内耳微小循環障害により誘発される平衡障害の新規ラットモデル
1 0 0 0 OA 形式言語の効率的学習アルゴリズムの開発及びその応用システムの構築
決定性プッシュダウン変換器のスタック記号を1種類に限定した決定性限定1カウンタ変換器について,それが最終状態受理式の場合,より一般的なε-推移を持つ場合についてもその等価性判定及び包含性判定が多項式時間で行えることを明らかにした.また,実時間最終状態受理式決定性限定1カウンタ変換器に対して,所属性質問及び等価性質問を用いた多項式時間の学習アルゴリズムを開発した.更に,正則言語の部分クラスに対する正例からの極限同定を組み込んだジュウシマツの歌構造解析ツールEUREKAを利用することによって,コンピュータ上でトランプゲームの大貧民の対戦を行うプログラムの挙動の規則性が抽出可能なことを示した.
- 著者
- 吉田 志緒美 富田 元久 露口 一成 鈴木 克洋
- 出版者
- Japanese Society for Infection Prevention and Control
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 = Japanese journal of environmental infections (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.109-112, 2009-03-25
- 被引用文献数
- 4
2007年12月1日から2008年1月31日までの期間に,外来受診患者の喀痰材料から分離された<i>Mycobacterium chelonae</i> 20株と院内環境から分離された<i>M. chelonae</i> 2株について,パルスフィールドゲル電気泳動法(PFGE)およびenterobacterial repetitive intergenic consensus PCR (ERIC-PCR)を用いた遺伝子多型性解析を実施した.すべての患者由来株は,院内環境由来株のうち,外来に設置されている服薬用飲料水供給装置由来株と同じ遺伝子型を持つ<i>M. chelonae</i>と判定された.したがって,服薬用飲料水供給装置を汚染源とした<i>M. chelonae</i>による疑似アウトブレイクの可能性が強く示唆された.<br>
1 0 0 0 OA 日本郵船株式会社英文世界年鑑 : グリムプセス・オブ・ザ・イースト
1 0 0 0 OA 是を知らぬは親子の恥 : 男女必読
1 0 0 0 OA SPring-8利用者情報
- 出版者
- 高輝度光科学研究センター
- 巻号頁・発行日
- vol.16, 2011-05-25
- 著者
- 尹 亨建
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.9-14, 1997-05-31
第1報では韓国と日本の両国の伝統工芸品を対象に, 韓・日両国の20代を中心とした若者の美意識を把握するため因子分析を行ない, イメージ構造を明らかにした。第2報では, 韓国と日本の伝統工芸品に分け, 親密度による両国の人のイメージ構造の相違を明らかにした。本報では, 伝統工芸品の造形要素が両国の人のイメージ構造の相違にどのように寄与しているかを調べた。伝統工芸品の造形要素として重要と思われる「色彩」「材料」「形」「模様・装飾」を中心にして比較分析を行なった。「色彩」では, カテゴリー「材料自体の色+別な色」に対して日本人の反応が大きく, 「多彩な原色」「黒色+別の色」においても両国の差がみられた。「材料」については, 金属材料に対して違いが見られ, 日本人は人工的, 派手という評価を示し, 韓国人は, 軽快という評価を与えた。「形」では全般的に韓国人より, 日本人が大きく反応した。「模様・装飾」では, 韓国人より日本人は全体面積に対し模様・装飾の面積比が小さいものに高い評価を与えた。
1 0 0 0 OA 人は何故に貧乏するか
1 0 0 0 政官要覧
- 著者
- 政策時報社 [編集]
- 出版者
- 政策時報社
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA 理科物語 : 天界旅行記
- 著者
- 山田 貴志
- 出版者
- 東京学芸大学史学会
- 雑誌
- 史海 (ISSN:02886731)
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.69-71, 2012-06
1 0 0 0 IR MRアンギオグラフィーによる肝A-P shuntの検出
- 著者
- 高橋 健 佐藤 修 成瀬 昭二 牛嶋 陽 中村 敏行 山田 恵 古谷 誠一 建井 努 山下 正人 村上 晃一 飯沼 昌二 タカハシ タケシ サトウ オサム ナルセ ショウジ ウシジマ ヨウ ナカムラ トシユキ ヤマダ ケイ フルヤ セイイチ タテイ ツトム ヤマシタ マサト ムラカミ コウイチ イイヌマ ショウジ Takahashi Takeshi .Sato Osamu Naruse Shouji Ushijima you Nakamura Toshiyuki Yamada Kei Furuya Seiichi Tatei Ysutomu Yamashita Masato Murakami Kouichi Iinuma Shouji
- 出版者
- 日本医学放射線学会
- 雑誌
- 日本医学放射線学会雑誌 (ISSN:00480428)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.185-187, 1991-02-25
1 0 0 0 OA 医療政策・教育政策による人的資本蓄積のミクロ計量分析
- 著者
- 牛島 光一
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2013-08-30
本研究プロジェクトでは人的資本の蓄積に関する3件の研究を進めた。①子供の健康の評価と母親の教育水準の関係:教育水準の高い母親ほど子供の健康を評価する能力が高いかを調べた。教育水準の低い母親ほど病院に入院するような病気であっても子供を病院に連れて行っていなかったことを示した。②医療制度の導入が家計の予備的貯蓄に与えた影響:新たに導入された医療保障制度が家計の医療支出の不確実性を減少させることを通じて貯蓄行動を変化させることを示した。③健康投資としての居住地選択:環境政策が人々の健康投資行動に与える影響について研究を行った。持ち家率の高い地域ほど大気環境への限界支払意志額が高くなることが分かった。
1 0 0 0 OA 私の定義に関する諮問委員会
- 著者
- 宮地 政司
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測 (ISSN:04500024)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.189-190, 1958-04-01 (Released:2009-04-21)