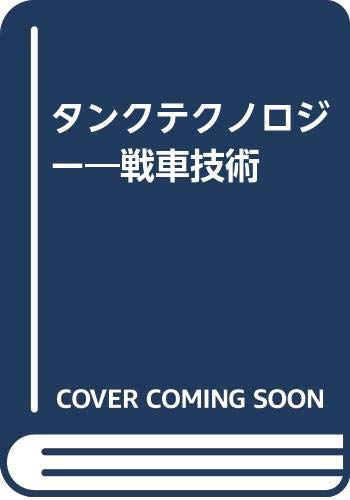1 0 0 0 タンクテクノロジー : 戦車技術
1 0 0 0 陸軍の衛生要員補充制度の成立過程 (特集 軍事と衛生)
- 著者
- 鈴木 紀子
- 出版者
- 錦正社
- 雑誌
- 軍事史学 (ISSN:03868877)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.111-126, 2010-09
1 0 0 0 陸軍衛生要員の育成と一年志願兵制度の創設
- 著者
- 鈴木 紀子
- 出版者
- 国士舘大学日本史学会
- 雑誌
- 国士舘史学
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.32-53, 2011-03
1 0 0 0 薬局のための法律講座 ペットによるトラブル、薬局の責任は?
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ドラッグインフォメーションpremium
- 巻号頁・発行日
- no.117, pp.56-58, 2007-07-10
今回は、患者が薬局内に同伴したペットが原因となり、ほかの患者に健康被害が生じた事例を取り上げる。ペットを伴ったまま薬局内に入店した患者に対し、薬剤師はペットの同伴を遠慮するよう求めたが、その交渉中に、犬アレルギーを持つ小児患者が両親に連れられて来局。
- 著者
- Phil R. CUMMINS 馬場 俊孝 堀 高峰 金田 義行
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.4, pp.498-509, 2001-08-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 2 2
By carefully analyzing the source process of the 1946 Nankai earthquake and its correlation with plate boundary structure, we attempt to explain the occurrence pattern of historical earthquakes in the Nankai Trough, in which great earthquakes tend to rupture separately either the western or eastern portions of the Nankai Trough. The source process of the 1946 earthquake consists of two major subevents, each corresponding to segments A and B, defined by Ando (1975), which have long been thought to correspond to units of earthquake rupture in the western Nankai Trough. Furthermore, rupture in each subevent begins near the eastern edge of the respective segment, where there are pronounced contortions of the plate boundary : a subducting seamount chain off Cape Muroto and a rapid change in subduction angle beneath the Kii Peninsula. We suggest that these seismotectonic features of the plate boundary shape control to some extent the pattern of great earthquake occurrence in the Nankai Trough.
1 0 0 0 OA 山の奥の奥まで入所勧奨は追いかけてきた : ハンセン病療養所「星塚敬愛園」聞き取り
- 著者
- 福岡 安則 黒坂 愛衣
- 出版者
- 埼玉大学大学院文化科学研究科
- 雑誌
- 日本アジア研究 : 埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀要 (ISSN:13490028)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.191-209, 2013-03 (Released:2013-03-15)
ハンセン病療養所のなかで60年ちかくを過ごしてきた,ある女性のライフストーリー。 山口トキさんは,1922(大正11)年,鹿児島県生まれ。1953(昭和28)年,星塚敬愛園に強制収容された。1955(昭和30)年に園内で結婚。その年の大晦日に,舞い上がった火鉢の灰を浴びてしまい,失明。違憲国賠訴訟では第1次原告の一人となって闘った。2010年8月の聞き取り時点で88 歳。聞き手は,福岡安則,黒坂愛衣,金沙織(キム・サジク),北田有希。2011年1月,お部屋をお訪ねして,原稿の確認をさせていただいた。そのときの補充の語りは,注に記載するほか,本文中には〈 〉で示す。 山口トキさんは,19歳のときに症状が出始めた。戦後のある時期から,保健所職員が自宅を訪ねて来るようになる。入所勧奨は,当初は穏やかであったが,執拗で,だんだん威圧的になった。収容を逃れるため,父親に懇願して山の中に小屋をつくってもらい,隠れ住んだ。そこにも巡査がやってきて「療養所に行かないなら,手錠をかけてでも引っ張っていくぞ」と脅した。トキさんはさらに山奥の小屋へと逃げるが,そこにもまた,入所勧奨の追手がやってきて,精神的に追い詰められていったという。それにしても,家族が食べ物を運んでくれたとはいえ,3年もの期間,山小屋でひとり隠れ住んだという彼女の苦労はすさまじい。 トキさんは,入所から2年後,目の見えない夫と結婚。その後,夫は耳も聞こえなくなり,まわりとのコミュニケーションが断たれてしまった。トキさんは,病棟で毎日の世話をするうちに,夫の手で夫の頭にカタカナの文字をなぞることで,言葉を伝える方法を編み出す。会話が成り立つようになったことで,夫が生きる希望をとりもどす物語は,感動的だ。 トキさんは,裁判の第1次原告になったのは,まわりから勧められたからにすぎないと言うけれども,その気持ちの背後には,以上のような体験があったからこそであろう。
1 0 0 0 OA 原告番号1番になって裁判を闘った : ハンセン病療養所「星塚敬愛園」聞き取り
- 著者
- 福岡 安則 黒坂 愛衣
- 出版者
- 埼玉大学大学院文化科学研究科
- 雑誌
- 日本アジア研究 : 埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀要 (ISSN:13490028)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.173-190, 2013-03 (Released:2013-03-15)
ハンセン病療養所のなかで70年を過ごしてきた,ある男性のライフストーリー。 田中民市(たなか・たみいち)さんは1918(大正7)年,宮崎県生まれ。1941(昭和16)年,星塚敬愛園入所。園名「荒田重夫」を名乗る。1968(昭和43)年,1988(昭和63)年~1989(平成元)年には,星塚敬愛園入所者自治会長を務める。1998(平成10)年,第1 次原告団の団長として,熊本地裁に「らい予防法」違憲国賠訴訟を提訴。2001(平成13)年,勝訴判決を勝ち取り,60年ぶりに本名の田中民市にもどる。2010(平成22)年6月の聞き取り時点で,92歳。聞き手は,福岡安則,黒坂愛衣,金沙織(キム・サジク)。なお,2010(平成22)年7月の補充聞き取りの部分は,注に記載した。 徴兵検査不合格の失意のなか,1941(昭和16)年4月に敬愛園に入所した田中民市さんは,同年7 月に「70人ぐらい一緒に収容列車で」連れてこられた,のちのおつれあいと知り合い,1943(昭和18)年の正月に結婚する。結婚にあたり,彼女には帰省許可がでたが,帰省許可が得られなかった民市さんは無断帰省をして,実家で結婚式を挙げたという。園に戻ってきて,一晩は「監禁室」に入れられたとはいうものの,療養所長の「懲戒検束権」が大手をふるっていた敗戦前の時代に,このように自分の意思を貫いた入所者がいたということは,新鮮な驚きであった。さらには,1,500 円という,当時としては大金をはたいて,園内の6畳2間の一戸建てを購入というか,「死ぬまでの使用権」を獲得したという。栗生楽泉園の「自由地区」に相当するようなことが,たった1つの例外措置であったとはいえ,ここ敬愛園でも実際にあったこともまた,耳新しい情報であった。 このように他の一般的な入所者と比べると相対的に恵まれた処遇を得ていたようにも見える民市さんが,1998(平成10)年の「らい予防法」違憲国賠訴訟の提訴にあたり,「原告番号1番」として,第1次原告団の団長を務めたのは,何故なのか。結婚して受胎した子どもを「堕胎」により奪われた無念さ,絶望の奈落に落とされた妻を案じて病棟に付き添った体験,みずからも「断種」を受け入れざるをえなかった憤り,これらの「悔しさ」を,民市さんはずっと胸に抱え込んだまま生きてきたことがわかる。ほんとの一握りの第1次原告がたちあがったことが,全国の療養所の入所者を巻き込み,2001(平成13)年5月11日の「熊本地裁勝訴判決」に結実したことを,民市さんは,いま,誇りとしている。 この語りをまとめるにあたり,星塚敬愛園に原稿確認に伺い,読み聞かせをしたとき,民市さんは「じっと聞いてると小説のごとあるね。アッハハハ。ほんと,ぼくの生きざまぜんぶ,書いてもらった感じで,ありがとうございます」と喜んでくださった。 民市さんは90代なかばになってもなおご健在で,わたしたちは2012年5月に青森の松丘保養園で開かれた第8回ハンセン病市民学会でも,フロアから元気に発言する民市さんの姿を見かけた。
1 0 0 0 中国高速公路及城乡公路网里程地图集 : 公路旅游必备
- 出版者
- 中国地图出版社
- 巻号頁・発行日
- 2012
- 著者
- 笠井 叡 萩尾 望都
- 出版者
- 青土社
- 雑誌
- ユリイカ (ISSN:13425641)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.7, pp.214-231, 2000-05
1 0 0 0 OA 六十余州名所図会 播磨 舞子の浜
- 著者
- 広重
- 出版者
- 越平
- 雑誌
- 大日本六十余州名勝図会
- 巻号頁・発行日
- 1853
- 著者
- 上野 千鶴子 渋谷 知美
- 出版者
- 文芸春秋
- 雑誌
- 諸君 (ISSN:09173005)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.8, pp.128-134, 2003-08
1 0 0 0 日本産Alucita属
- 著者
- 橋本 里志
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.111-123, 1984
Alucita属は広く全世界から知られ,100種以上の記載種から成る大きな属である.従来,わが国からは3種が知られていた.うち2種,ヤマトニジュウシトリバ(Alucita japonica)とアヤニジュウシトリバ(Alucita flavofascia)は日本からのみ知られ,残りの1種,ニジュウシトリバ(Alucita spilodesma)は東洋区を中心に分布している.今回,琉球列島から得られた2新種を記載すると共に,Alucita属の記載ならびに既知種3種の交尾器を図示し簡単な説明を与えた.また,日本産Alucita属を成虫の形質に基づいて,次の2つのグループに分類した.グループA:単眼を有すること,前翅のSc脈は基部より遊離すること,雄後翅にanal foldを持つことによって特徴づけられる.A.pusilla, A.japonica, A.spilodesmaの3種が含められる.グループB:単眼を欠くこと,前翅のSc脈とR1脈は基部あるいは基部から1/3の所で融合すること,雄前翅にcostal foldを持つことによって特徴づけられる.A.straminea, A.flavofasciaの2種が含められる.Alucita pusilla HASHIMOTOは白地にオリーブ色の斑紋を持つ,開張およそ7mmの小蛾である.本種は雄交尾器において,ヤマトニジュウシトリバ(A.japonica)に似るが,成虫の大きさによって容易に区別される.分布:西表島.Alucita straminea HASHIMOTOは成虫の色彩において,アヤニジュウシトリバ(A.flavofascia)に似るが,アヤニジュウシトリバから,頭部にオレンジ色の帯を持たないこと,前後翅に褐色を帯びた紫色の斑紋を欠くことにより区別される.分布:石垣島,西表島.
1 0 0 0 OA 扶餘や高句麗の官名「加」について
- 著者
- 田 鳳徳[著] 李 丙洙[訳]
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 史苑 (ISSN:03869318)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.43-56, 1975-03
1 0 0 0 IR 書評 川出良枝「貴族の徳、商業の精神 : モンテスキューと専制批判の系譜」
- 著者
- 森村 敏己
- 出版者
- 歴史学研究会
- 雑誌
- 歴史学研究 (ISSN:03869237)
- 巻号頁・発行日
- vol.700, pp.48-50, 1997-08
1 0 0 0 タックス・シェルターと市場の失敗
- 著者
- 吉村 政穂
- 出版者
- 日本税務研究センタ-
- 雑誌
- 税研 (ISSN:09119078)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.88-94, 2007-07
- 著者
- 津田 和夫
- 出版者
- 佐賀大学経済学会
- 雑誌
- 佐賀大学経済論集 (ISSN:02867230)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.51-89, 2009-03
- 著者
- 植田 敬子
- 出版者
- 日本女子大学
- 雑誌
- 日本女子大学紀要. 家政学部 (ISSN:0288304X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.153-163, 2009-02-26
1 0 0 0 IR 市場主義経済学と構造改革--市場の失敗,規制の失敗,理論の失敗
- 著者
- 廣瀬 弘毅
- 出版者
- 福島大学経済学会
- 雑誌
- 商学論集 (ISSN:02878070)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.2, pp.59-73, 2007-12
1 0 0 0 OA 市場の失敗と雇用格差 : 「既卒」差別と若年労働問題
- 著者
- 古屋 核
- 出版者
- 大東文化大学
- 雑誌
- 経済研究研究報告 (ISSN:09164987)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.17-25, 2008-03
- 著者
- 八田 英二
- 出版者
- IDE大学協会
- 雑誌
- IDE (ISSN:03890511)
- 巻号頁・発行日
- no.517, pp.38-41, 2010-01