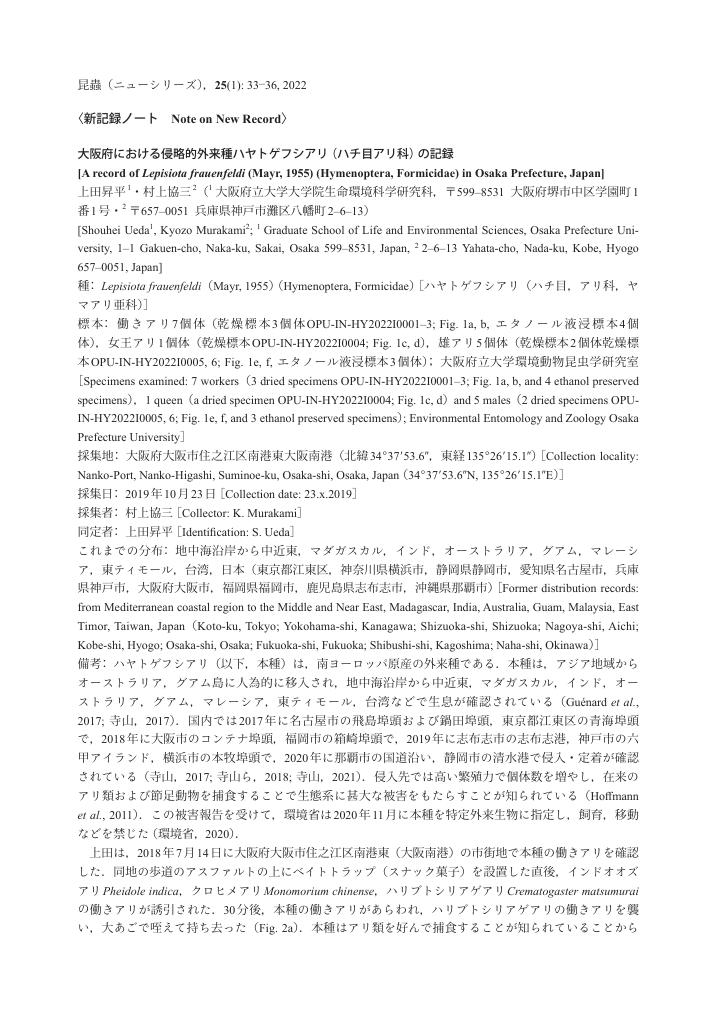4 0 0 0 OA レーシングドライバと一般ドライバの定常円旋回中の運転挙動の違いについての考察
- 著者
- 原中 喜源 栗原 亮
- 出版者
- Japan Human Factors and Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.268-276, 2007-10-15 (Released:2010-03-15)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
この実験では半径20mの定常円を旋回中のレーシングドライバと一般ドライバの運転挙動の違いを30km/hで定速旋回した場合とタイヤに横滑りを生じる速度域で走行した場合 (高速旋回) について比較検討した. その結果30km/h定速旋回中の各ドライバの最大横加速度の平均値は一般ドライバのほうが大きくなる傾向があり, 高速旋回では前輪の横滑りが発生する速度の平均値はレーシングドライバのほうが高いことがわかった. これらはカーブを同じ速度で走行していても運転技能の高いドライバほど車の運動状態は安定していることを意味する. また30km/h定速旋回では旋回軌道の修正は操舵により行われる傾向がすべてのドライバにみられるが, 高速旋回ではレーシングドライバはスロットル操作で軌道修正を行っていた. その理由としてレーシングドライバは車のサスペンション特性を利用する能力があるために実験車の運動性能を最大限に利用する操作がスロットル操作による軌道修正であったためと我々は考えた.
4 0 0 0 OA 大阪府における侵略的外来種ハヤトゲフシアリ(ハチ目アリ科)の記録
- 著者
- 上田 昇平 村上 協三
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.33-36, 2022-03-25 (Released:2022-03-25)
4 0 0 0 OA 海上国際条規
- 著者
- 俄爾社蘭 (ヲルトラン) 著
- 出版者
- 海軍参謀本部
- 巻号頁・発行日
- 1889
4 0 0 0 OA オッズ比と相対危険の関係
- 著者
- 横山 徹爾 田中 平三
- 出版者
- 社団法人 日本循環器管理研究協議会
- 雑誌
- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.36-39, 1998-01-30 (Released:2009-10-16)
- 参考文献数
- 6
4 0 0 0 OA 近代日本の日記帳 ―故福田秀一氏蒐集の日記資料コレクションより―
- 著者
- 田中 祐介 土屋 宗一 阿曽 歩
- 雑誌
- 国際基督教大学学報 3-A,アジア文化研究 = International Christian University Publications 3-A,Asian Cultural Studies
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.237-272, 2013-03-30
4 0 0 0 OA 明治・大正期におけるヨットの伝播と受容基盤
- 著者
- 佐藤 大祐
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.8, pp.599-615, 2003-07-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 2 2
本稿は明治・大正期の日本において,ヨットというスポーツがいかに伝播したのかを,ヨットクラブの結成とクラブ会員の社会属性,および当時の社会的背景に注目して明らかにした.その結果,ヨットは居留地外国人・駐日外交官から日本人華族・財界人へと受容基盤を変化させるとともに,外国人居留地から高原避暑地,海浜別荘地へと伝播し,定着したことがわかった. まず,ヨットは欧米列強の植民地貿易の前進基地である外国人居留地に導入された.横浜では,居留地貿易を主導した商館経営者や銀行・商社駐在員,外交官などの外国人によって,ヨットクラブが1886年に結成され,彼らの社交場として機能した.その後,ヨットは1890年代に形成された中禅寺湖畔の高原避暑地.に伝播し,ヨットクラブが1906年に結成された.この担い手はイギリスやベルギーなどの駐日公使をはじめとする欧米外交官であった.中禅寺湖畔では,東京における欧米外交官と日本人華族の国際交流が夏季に繰り広げられた.そして,ヨットは海浜別荘地である湘南海岸において,華族を中心とする上流日本人の間へ1920年代から普及していった.
4 0 0 0 12~19世紀の甲冑威糸類に用いられた赤色染料と媒染剤について
- 著者
- 小松 未来 西岡 文夫 齊藤 昌子
- 出版者
- 文化財保存修復学会
- 雑誌
- 文化財保存修復学会誌 (ISSN:13420240)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.25-40,図巻頭1p, 2005
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- Masahiro IWAKURA Kazuki OKURA Mika KUBOTA Keiyu SUGAWARA Atsuyoshi KAWAGOSHI Hitomi TAKAHASHI Takanobu SHIOYA
- 出版者
- Japanese Society of Physical Therapy
- 雑誌
- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.35-42, 2021-04-20 (Released:2021-04-20)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1 23
Objective: To estimate the minimal clinically important difference (MCID) of quadriceps and inspiratory muscle strength after a home-based pulmonary rehabilitation program (PRP) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Method: Eighty-five COPD patients were included. Quadriceps maximal voluntary contraction (QMVC) was measured. We measured maximal inspiratory mouth pressure (PImax), the 6-minute walk distance (6MWD), the chronic respiratory questionnaire (CRQ) and the modified Medical Research Council dyspnoea score (mMRC). All measurements were conducted at baseline and at the end of the PRP. The MCID was calculated using anchor-based (using 6MWD, CRQ, and mMRC as possible anchor variables) and distribution-based (half standard deviation and 1.96 standard error of measurement) approaches. Changes in the five variables were compared in patients with and without changes in QMVC or PImax >MCID for each variable. Results: Sixty-nine COPD patients (age 75±6 years) were analysed. QMVC improved by 2.4 (95%CI 1.1-3.7) kgf, PImax by 5.8 (2.7-8.8) cmH2O, 6MWD by 21 (11-32) meters and CRQ by 3.9 (1.6-6.3) points. The MCID of QMVC and PImax was 3.3-7.5 kgf and 17.2-17.6 cmH2O, respectively. The MCID of QMVC (3.3 kgf) could differentiate individuals with significant improvement in 6MWD and PImax from those without. Conclusion: The MCID of QMVC (3.3 kgf) can identify a meaningful change in quadriceps muscle strength after a PRP. The MCID of PImax (17.2 cmH2O) should be used with careful consideration, because the value is estimated using distributionbased method.
- 著者
- Gohei KATO Takehiko DOI Hidenori ARAI Hiroyuki SHIMADA
- 出版者
- Japanese Society of Physical Therapy
- 雑誌
- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)
- 巻号頁・発行日
- pp.E10153, (Released:2022-06-10)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4
Objective: This study aims to estimate the cost-effectiveness of combined physical and cognitive programs designed to prevent community-dwelling healthy young-old adults from developing dementia. Methods: The analysis was conducted from a public healthcare and long-term care payer’s perspective. Quality-adjusted life years (QALYs) and expenses for health services and long-term care services were described in terms of effectiveness and cost, respectively. A thousand community-dwelling healthy adults aged 65 years were generated through simulation and analyzed. The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of adults with preventive program intervention compared to those with nonintervention was simulated with a 10-year cycle Markov model. The data sources for the parameters to build the Markov models were selected with priority given to higher levels of evidence. The threshold for assessing cost-effectiveness was set as less than 5,000,000 Japanese yen/QALY. Results: The ICER was estimated as −5,740,083 Japanese yen (US$−57,400)/QALY. Conclusion: A program targeting community-dwelling healthy young-old adults could be cost-effective.
- 著者
- 石塚 千賀子
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.95-104, 2022-01-07 (Released:2022-01-07)
- 参考文献数
- 28
本ケースでは,小柳建設株式会社がマイクロソフト社との協業で複合現実(MR)技術をもちいて展開した新たなデジタル・サービス化をとりあげる。本技術により,工事の発注者,請負の施工者,設計者などの関係者が遠隔からも一堂に会し,実物大(ヒューマンスケール)で,工事の設計から竣工までの見たい場所を安全に歩き回り,意思疎通できるようになった。通常,デジタル・サービス化の多くは,顧客ニーズへのよりよい適応のために展開される。しかし,本ケースでは,経営者の内部顧客志向によってデジタル・サービス化が展開された。この内部顧客志向は,同社の経営理念そのものである。経営者は,偶然見つけたこの技術を,まさに自分たちのための技術だと直感的に確信し,リスクを覚悟で導入を即決した。デジタル・サービス化のパラドクスの乗り越えを可能にしたのは,迅速に顧客のネガティブな反応を察知し戦術転換できる組織体制にあった。経営陣は,本DXは経営理念実現のための手段のひとつと位置づけており,顧客体験の向上はもとより,業界のあたりまえとされてきた長時間労働の改善や,3Kイメージの払拭に挑戦している。
- 著者
- Mark L. LATASH Momoko YAMAGATA
- 出版者
- Japanese Society of Physical Therapy
- 雑誌
- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.1-11, 2022-04-20 (Released:2022-04-20)
- 参考文献数
- 96
- 被引用文献数
- 2
We review the current views on the control and coordination of movements following the traditions set by Nikolai Bernstein. In particular, we focus on the theory of neural control of effectors - from motor units to individual muscles, to joints, limbs, and to the whole body - with spatial referent coordinates organized into a hierarchy with multiple few-to-many mappings. Further, we discuss synergies ensuring stability of natural human movements within the uncontrolled manifold hypothesis. Synergies are organized within the neural control hierarchy based on the principle of motor abundance. Movement disorders are discussed as consequences of an inability to use the whole range of changes in referent coordinates (as in spasticity) and an inability to ensure controlled stability of salient variables as reflected in indices of multi-element synergies and their adjustments in preparation to actions (as in brain disorders, including Parkinson's disease, multiple-system atrophy, and stroke). At the end of the review, we discuss possible implications of this theoretical approach to peripheral disorders and their rehabilitations using, as an example, osteoarthritis. In particular, "joint stiffening" is viewed as a maladaptive strategy, which can compromise stability of salient variables during walking.
4 0 0 0 OA フリー・エージェントの分類と動向--労働者の視点から
- 著者
- 三島 重顕
- 出版者
- 京都大學經濟學會
- 雑誌
- 經濟論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.177, no.1, pp.34-55, 2006-01
4 0 0 0 OA 神経因性疼痛に対するカプサイシン軟膏の効果
- 著者
- 小佐井 和子 宇野 武司 小金丸 美桂子 高崎 眞弓
- 出版者
- Japan Society of Pain Clinicians
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.26-30, 1999-01-25 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 15
目的: 神経因性疼痛患者に0.05%カプサイシン軟膏を塗布し, カプサイシン軟膏の鎮痛効果と副作用を検討した. 対象と方法: 従来の治療法で除痛困難であった患者12名, 帯状疱疹後神経痛 (PHN) 群6名と神経外傷後疼痛 (外傷後疼痛) 群6名を対象とした. 塗布前, 塗布中, 中止後の痛みの強さを, 0~100の Visual Analogue Scale (VAS: 0=痛みなし, 100=耐えがたい痛み) で比較した. さらに睡眠, 気分, 日常動作の変化, および塗布中の副作用を調べた. 結果: VASの中央値はPHN群で塗布前45, 塗布中10, 中止後10であり, 外傷群で塗布前80, 塗布中40, 中止後50で, 両群とも塗布中および中止後は塗布前に比較して有意に低下した (p<0.05). 睡眠, 気分, 日常動作の改善がそれぞれ42%, 75%, 58%で認められた. 軽度の皮膚剥離を1名に認めた以外, 重篤な合併症は認めなかった. 中止後, PHN群では痛みは変化しなかったが, 外傷群では痛みは少し増強した. 結論: 0.05%カプサイシン軟膏は, PHNおよび外傷後疼痛の治療に有効であることがわかった.
4 0 0 0 IR メフメト 2 世時代初期の宰相たち
- 著者
- 今澤 浩二
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 人間文化研究 = Journal of Humanities Research,St.Andrew's University (ISSN:21889031)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.271-305, 2021-03-16
4 0 0 0 OA マスサイトメトリーを用いた癌性腹水中老化細胞の検出と細胞老化に着目した治療戦略
- 著者
- 安田 忠仁 石本 崇胤
- 出版者
- 日本サイトメトリー学会
- 雑誌
- サイトメトリーリサーチ (ISSN:09166920)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.27-32, 2022-07-13 (Released:2022-07-13)
- 参考文献数
- 11
Recent studies have revealed senescent non-malignant cells in the tumor microenvironment exhibit a secretory profi le under stress conditions; this senescence-associated secretory phenotype (SASP) promotes carcinogenesis and cancer progression. However, the role of senescent non-malignant cells in the metastatic process is not well-understood. We showed that fi broblast population shows p16 expression and SASP factors at high levels in the ascites of gastric cancer patients with peritoneal dissemination by single-cell mass cytometry (CyTOF). Moreover, we present the senolysis strategy in the tumor microenvironment based on the results of an in vivo validation. We identifi ed piperlongumine as the effective senolytic drug for senescent-fi broblasts. These fi ndings offer some notice toward a successful treatment targeting harmful senescent cells and provide the potential for clinical application for the future therapeutic strategy for combining conventional chemotherapy. progression. However, the role of senescent non-malignant cells in the metastatic process is not well-understood. We showed that fi broblast population shows p16 expression and SASP factors at high levels in the ascites of gastric cancer patients with peritoneal dissemination by single-cell mass cytometry (CyTOF). Moreover, we present the senolysis strategy in the tumor microenvironment based on the results of an in vivo validation. We identifi ed piperlongumine as the effective senolytic drug for senescent-fi broblasts. These fi ndings offer some notice toward a successful treatment targeting harmful senescent cells and provide the potential for clinical application for the future therapeutic strategy for combining conventional chemotherapy.
- 著者
- 松井 利仁 平松 幸三 宮川 雅充
- 出版者
- 公益社団法人 日本騒音制御工学会
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.367-374, 2012-10-01 (Released:2020-01-16)
- 参考文献数
- 20
航空機騒音が空港周辺住民のメンタルヘルスに及ぼす影響を明らかにすることを目的として,成田国際空港暫定平行滑走路(B滑走路)周辺において,精神健康調査票(GHQ-28)を利用した質問紙調査を行った。GHQ-28で神経症と判別された者の比率と騒音曝露量および騒音感受性との関連を分析した結果,騒音感受性が高い群において,住民のメンタルヘルスに影響が生じていると考えられた。さらに,騒音曝露群について,神経症と判別された者の比率と生活妨害との関係を分析した結果,夕方から夜間の時間帯(18∼23時)における生活妨害とメンタルヘルスとの間に,有意な関連が認められた。