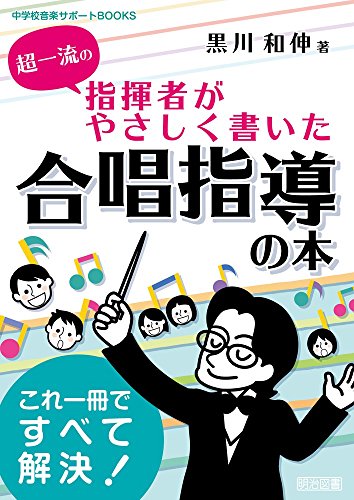3 0 0 0 OA 細胞環境における生体分子ダイナミクスのシミュレーション
- 著者
- 杉田 有治 優 乙石 Michael Feig
- 出版者
- 分子科学会
- 雑誌
- Molecular Science (ISSN:18818404)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.A0094, 2017 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 2
Atomic structures of proteins, nucleic acids, and their complexes are determined using X-ray crystallography, NMR, or cryo-Electron Microscopy. These structures are essential to understand their structure-function relationships. However, the experimental conditions are totally different from the actual cellular environments and it is hard to understand how biomolecules behave in such cellular environments, just using the atomic structures. We have recently built protein crowding systems in computers and carried out all-atom molecular dynamics (MD) simulations of the systems to understand biomolecular dynamics in the crowded environments. The largest simulations we have ever performed were the all-atom MD simulations of a bacterial cytoplasm using K computer. By analyzing the simulation trajectories, we observed that non-specific protein-protein and protein-metabolite interactions play important roles in biomolecular dynamics and stability in a cell. The new insight from the simulations is useful not only for basic life science in molecular and cellular biology but also drug discovery in future for introducing the effect of non-specific protein-drug interactions.
3 0 0 0 OA CNNを用いた高空間解像度衛星画像からの地物抽出
- 著者
- 藤田 藍斗 今泉 友之 彦坂 修平
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, 2016
3 0 0 0 OA 中国古代の軍事と民族-多民族社会の軍事統治-
本研究はまず(1)中国古代史における民族の問題-「漢民族」はいかにして形成されたのか、中国王朝はさまざまな帰属意識を持つ人間集団をいかにして統合したのか、新たな民族集団の流入が王朝にいかなる影響を与えたのか、など-について共同研究者間で討議したうえで、それら民族問題と軍事の相関関係について各自の研究課題を設定し、定期的に研究発表を行った。その過程で(2)中間年度に韓国・ソウル大学で国際シンポジウムを共催した。そこでの討議をふまえてさらに議論を重ね、(3)参加者全員の寄稿を得て成果報告書『多民族社会の軍事統治 出土史料が語る中国古代』を京都大学学術出版会から刊行するに至った。
3 0 0 0 OA 多変数量子解析
- 著者
- 鈴木 増雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.257-264, 1997-09-15 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 7
The purpose of the present paper is to formulate the quantum analysis of multivariate operator functions f({A_j}) by introducing auxiliary operators {H_j} satisfying the conditions that [H_j, H_κ]=0 , [H_j, A_κ ]=0 for j≠κ, and [H_j, [H_κ, A_κ]]=0. Then we have d^nf=Σ_<j1>...<jn> δ_H_<J1>・・・δ_H_<jn>f using the inner derivation δ_A : δ_AQ=[A, Q]=AQ-QA. The operator Taylor expansion formula is given in the form : f({A_j+x_jdA_j})=e^Σ_j^x_j^d_jf({A_j})=exp(Σ_jx_jδ_H_j)f({A_j})=Σ_nΣ_<j1>...<jn>x_<j1>・・・x_<jn>δ<j1>..., _<jn>f≡Σ_nΣ_<j1>..., _<jn>x_<j1>・・・x_<jn>f^<(n)>_<j1>..., _<jn> : dA_<J1>・・・dA_jn with dA_j≡[H_j, A_j]=δ_H_jA_j, and with the partial derivatives {d_j} with respect to {A_j}. Here, δ_<j1>..., _<jn> denotes an ordered partial inner derivation, and n!f^<(n)>_<j1>...<jn> denotes the n th derivative of f({A_j}).
3 0 0 0 OA くり込まれた指数積公式と量子解析 (量子情報とその周辺分野の解析的研究)
- 著者
- 鈴木 増雄
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1266, pp.146-149, 2002-05
3 0 0 0 場所の再概念化
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.19-19, 2011
1970年代の人文主義地理学によってキーワードとされた「場所place」は概念そのものの検討も含んでいたが,その没歴史的で,本質主義的な立場などが1980年代に各方面から批判された。1990年代にはplaceを書名に冠した著書や論文集が多数出版されたが,そこでは場所概念そのものの検討はさほどなされなかったといえる。本報告では議論を拡散させないためにも,検討するテクストをプラトンの『ティマイオス』および,そのなかのコーラ=場概念を検討したデリダの『コーラ』を,そしてアリストテレスの『自然学』および,そのなかのトポス=場所概念を検討したイリガライの「場,間隔」に限定する。プラトン『ティマイオス』におけるコーラとは,基本的な二元論に対するオルタナティヴな第三項だといえる。コーラは岩波書店全集では「場」と翻訳されるものの,地理的なものとして登場するわけではない。『ティマイオス』は対話篇であり,「ティマイオス」とは宇宙論を展開する登場人物の名前である。ティマイオスの話は宇宙創世から始まるが,基本的な種別として「存在」と「生成」とを挙げる。「存在」とは常に同一であるもので,理性(知性)や言論によって把握される。これは後に「形相」とも呼び変えられる。「生成」とは常に変化し,あるという状態のないものであり,思わくや感覚によって捉えられる。創世によって生成した万物は物体性を具えたもので,後者に属する。そのどちらでもない「第三の種族」として登場するのが「場=コーラ」である。コーラとは「およそ生成する限りのすべてのものにその座を提供し,しかし自分自身は,一種のまがいの推理とでもいうようなものによって,感覚には頼らずに捉えられるもの」とされる。その後の真実の把握を巡る議論は難解だが,ここにコーラ概念の含意が隠れているのかもしれない。いや,そう考えてしまう私たちの真理感覚を問い直してくれるのかもしれない。デリダはコーラ概念を,その捉えがたさが故に検討するのだ。「解釈学的諸類型がコーラに情報=形をもたらすことができるのは,つまり,形を与えることができるのは,ただ,接近不可能で,平然としており,「不定形」で,つねに手つかず=処女的,それも擬人論的に根源的に反抗するような諸女性をそなえているそれ[彼女=コーラ]が,それらの類型を受け取り,それらに場を与えるようにみえるかぎりにおいてのみである」。『ティマイオス』では,51項にも3つの種族に関する記述があり,それらは母と父と子になぞらえられる。そして,コーラにあたるものが母であり,受容者であり,それは次のイリガライのアリストテレス解釈にもつながる論点である。このコーラの女性的存在はデリダの論点でもあり,またこの捉えがたきものを「コーラ」と名付けたこの語自体の固有名詞性を論じていくことになる。アリストテレスのトポス概念は,『自然学』の第四巻の冒頭〔三 場所について〕で5章にわたって論じられる。トポスは,物体の運動についての重要概念として比較的理解しやすいものとして,岩波書店全集では「場所」と翻訳されて登場する。アリストテレスにおける運動とは物質の性質の変化も含むため,運動の一種としての移動は場所の変化ということになる。ティマイオスはコーラ概念を宙づりにしたまま,宇宙論をその後も続けたが,アリストテレスは「トポス=場所」を物体の主要な性質である形相でも質料でもないものとして,その捉えがたさを認めながらも論理的に確定しようとする。トポスには多くの場合「容器」という代替語で説明されるが,そこに包含される事物と不可分でありながらその事物の一部でも性質でもない。イリガライはこの容器としてのトポスの性質を,プラトンとも関連付けながら,女性としての容器,女性器と子宮になぞらえる。内に含まれる事物の伸縮に従って拡張する容器として,男性器の伸縮と往復運動,そして胎児の成長に伴う子宮の拡張,出産に伴う収縮。まさに,男性と女性の性関係と母と子の関係を論じる。この要旨では,デリダとイリガライの議論のさわりしか説明できていないし,これらの議論をいかに地理学的場所概念へと展開していくかについては,当日報告することとしたい。
3 0 0 0 屋外造園活動が在宅高齢者の活動能力に及ぼした影響について
- 著者
- 沖住 省吾 竹内 文夫 土屋 幸代
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.E1155-E1155, 2006
【はじめに】当通所リハビリテーションでは個別療法導入後、過半数の症例において日常生活自立度の維持・改善を認めたが、社会参加の向上には至らなかった事を第40回全国理学療法学術大会で報告した。そこで今回、屋外造園作業(以後、造園活動とする)を療法の選択肢として導入し、活動能力や社会参加におよぼした影響を検討したので報告する。<BR>【造園活動について】造園は利用者を交えながら、介助・監視下で種々の活動を実施するものである。活動の内容は、1、庭園整備:デザイン・造園、草むしり、芝刈り、枯れ草集め、石拾い、花壇作りなど。2、畑作業:菜園収穫、園芸、水撒き、木実の収穫など。3、生き物飼育。4、運動:庭園散策による歩行耐久性、不整地歩行、運動会などである。<BR>【対象および方法】追跡期間は、平成15年4月から平成17年4月までの約24ヶ月間であり、造園企画は平成15年11月に発足した。対象は通所リハビリテーション利用者のうち、個別療法を併用し且つ追跡できた75例である。この75症例中造園活動が併用できた症例は47名であった。活動能力の指標はBarthel index(以下BIと略)と老研式活動能力指標(以下活動指標と略)を用いた。活動指標は「自治会や老人会への参加」と「生きがいあるいは宗教」の2項目を加え15項目で評価し、BIと比較しやすいように百分率で表した。新たな療法が選択でき、期待される内容も変化したのでニーズの変化も合わせて調査した。<BR>【結果】75例のBIは改善27名36%、26名35%が維持され、21名28%が低下していた。屋外造園活動を併用した47名の内BIが低下した例は13%であり、その他は維持・改善の経過をたどった。更に造園活動併用者の内BI改善群を抽出するとBI平均79点から93点へと有意に向上し、活動指標も29%から38%に向上した。一方、ニーズ変化では次の特徴を示していた。造園活動前は活動性に関するニーズは皆無であり、シビレや除痛、麻痺肢の回復などの機能的ニーズが多くを占めていた。しかし、造園活動導入後は、屋外活動や趣味・余暇活動などが全ニーズの24%を占めるようになった。興味深いのは、造園活動の有無に関わらず、立ち上りや移動手段が全ニーズの30%以上を占め最も多かった事である。<BR>【考察】造園活動は、活動能力に加えて社会参加の向上、生きがい作りとしても好影響をもたらした。造園活動を開始する前は、室内の限られた環境での活動がほとんどであったが、活動範囲の拡大により運動量の増加と感情抑揚や動くことに対するモチベーションに変化をもたらしたものと考える。また、以前は環境安全面などに障壁があり、趣味や余暇活動をあきらめざるを得なかった境遇の人たちが多かったが、今回のアプローチ導入によって、これまで成しえなかった事が安全な環境と適切な介助量のもとで実行できるようになり、生活意欲や趣味・余暇活動に対する更なる動機付けに結びついたものと思われる。
- 出版者
- 日経サイエンス ; 1990-
- 雑誌
- 日経サイエンス (ISSN:0917009X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.8-11, 2017-05
超高速,省エネで世界トップクラスのマシンを続々開発「京」の100倍相当のエクサ級スパコンも視野にAIが人間超える「シンギュラリティー(特異点)」起こす道具に 横浜市金沢区にある海洋研究開発機構(JAMSTEC)横浜研究所。かつて世界最速を誇ったスーパーコンピューター「地球シミュレータ」が今もここで動いている。
3 0 0 0 OA 蜃氣棲的現象に就て
- 著者
- 藤原 咲平
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.12, pp.769-783, 1917-12-15 (Released:2010-10-13)
3 0 0 0 OA 屡氣樓的現象に就て
- 著者
- 藤原 咲平
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.11, pp.701-712, 1917-11-15 (Released:2010-10-13)
3 0 0 0 OA 縮合リン酸塩の1日摂取量とそれに影響する食品
- 著者
- 石橋 正博 山田 傑 北村 尚男 真島 裕子 一色 賢司 伊藤 誉志男
- 出版者
- 日本食品化学学会
- 雑誌
- 日本食品化学学会誌 (ISSN:13412094)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.93-96, 1996-03-29
- 被引用文献数
- 1
縮合リン酸塩のピロリン酸、ポリリン酸、メタリン酸の1日摂取量をマーケットバスケット方式で調査した。加工食品約340品目を(1)調味嗜好飲料、(2)穀類、(3)イモ類・豆類・種実類、(4)魚介類・肉類、(5)油脂類・乳類、(6)佐藤類・菓子類、(7)果実類・野菜類・海草類の7群に分け、それぞれの群の縮合リン酸含有量を測定し、各群ことの喫食量をかけて摂取量とした。(1)縮合リン酸の1日摂取量は、15.8mgでピロリン酸が7.2mg、ポリリン酸が3.8mg、メタリン酸が5.0mgであった。(2)摂取量の多いのは、5群の6.0mgと4群の5.1mgで、主な摂取源は、5群のチーズと4群の魚介類・食肉類であった。特に、チーズの種類と喫食量は摂取量に大きく寄与することが分かった。(3)地区別の比較では、東部地区と西部地区がやや多かった。東部地区の5群が特に多かったのは、チーズの種類による影響と思われる。(4)昭和58年度、昭和62年度、平成3年度、平成6年度の調査結果より、縮合リン酸の摂取量は増加傾向にある。(5)世代別の摂取量の比較では、高齢者、学童が成人に比べ多くなった。4群は各世代に摂取量の違いはあまりなかったが、5群はチーズの種類の影響でかなりばらつきがあった。その他、学童の6群と7群も他の世代に比べやや摂取量が多かった。
3 0 0 0 超一流の指揮者がやさしく書いた合唱指導の本
3 0 0 0 復印報刊資料. J21, 《紅楼夢》研究
- 出版者
- 中国人民大学書報資料社
- 巻号頁・発行日
- 0000
3 0 0 0 OA 福岡の祭りに見られる恵比寿神と磯良神
- 著者
- 吉田 修作
- 出版者
- 福岡女学院大学
- 雑誌
- 比較文化 : 福岡女学院大学大学院人文科学研究科紀要
- 巻号頁・発行日
- pp.六九-八七, 2004-03-31
- 著者
- 中村 尚史
- 出版者
- 川崎医科大学
- 雑誌
- 川崎医学会誌 (ISSN:03865924)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.1-11, 2014
思春期,青年期の適応障害患者において広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders,PDD)を基盤にもつ患者の割合を検討し,その場合,どのような臨床的特徴があるかを調査し,PDDの有無に関連する要因について検討した.DSM-IV-TR(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Fourth Edition,Text Revision)によって適応障害と診断された12歳以上30歳以下の患者58名を対象とし,以下の自記式質問紙を用いて臨床的特徴を評価した.精神症状の評価は,日本語版パラノイアチェックリスト(JPC:Japanese version of Paranoia Checklist),思春期の精神病様体験(PLEs:Psychotic Like Experiences),精神症状評価尺度(SCL-90-R:Symptom Checklist-90-Revised)を用いた.PDDの評価については,詳細な養育歴の聴取と,患者に対して自閉症スペクトラム指数日本版(AQ-J:Autism Spectrum Quotient-Japanese Version)を用いて,養育者に対しては,自閉症スクリーニング質問紙(ASQ:AutismScreening Questionnaire)を用いて総合的に判断し評価した.その結果,1)58名のうち,PDDと診断されたのは,32名(55.1%)であった.2)AQ-Jについては,PDDの有無に関してコミュニケーションが有意な関連性を示した.3)JPCについては,PDD群が,非PDD群と比較して総得点,確信度において有意に高い結果となった.PDDの有無に関して,確信度が有意に関連していた.4)SCL-90-RについてはPDD群では,恐怖症性不安,妄想,精神病症状,強迫症状,対人過敏,抑うつ,不安,その他の8項目において非PDD群に比較して有意に高かった.PDDの有無に関して強迫症状が有意に関連していた.5)各質問紙の総得点とPDDとの関連を見ると,JPCの総得点のみがPDDと有意な関連性を示した.思春期,青年期の適応障害患者では,PDDを基盤にもつと,被害妄想や,強迫症状など様々な精神症状を自覚する可能性があり,JPCなど質問紙も併用して,PDDの存在を念頭において診療を行う必要があることが示唆された.
- 著者
- 花岡 智恵
- 出版者
- 労働政策研究・研修機構
- 雑誌
- 日本労働研究雑誌 (ISSN:09163808)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.16-25, 2015-05
3 0 0 0 OA 琉球民謡:仲村渠節(上)
- 著者
- Naoko Horikoshi Hajime Iwasa Seiji Yasumura Masaharu Maeda
- 出版者
- THE FUKUSHIMA SOCIETY OF MEDICAL SCIENCE
- 雑誌
- FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE (ISSN:00162590)
- 巻号頁・発行日
- pp.2017-03, (Released:2017-12-12)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 27
The Fukushima Medical University conducted a mental health care program for evacuees after the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident. However, the mental health status of non-respondents has not been considered for surveys using questionnaires. Therefore, the aim of this study was to clarify the characteristics of non-respondents and respondents. The target population of the survey (FY2011-2013) is people living in the nationally designated evacuation zone of Fukushima prefecture. Among these, the participants were 967 people (20 years or older). We examined factors that affected the difference between the groups of participants (i.e., non-respondents and respondents) using multivariate logistic regression analysis. Employment was higher in non-respondents (p=0.022) and they were also more socially isolated (p=0.047) when compared to respondents; non-respondents had a higher proportional risk of psychological distress compared to respondents (p<0.033). The results of the multivariate logistic regression analysis showed that, within the participants there was a significant association between employment status (OR=1.99, 95% confidence interval [CI]:1.12-3.51) and psychological distress (OR=2.17, 95% CI:1.01-4.66). We found that non-respondents had a significantly higher proportion of psychological distress compared to the respondents. Although the non-respondents were the high-risk group, it is not possible to grasp the complexity of the situation by simply using questionnaire surveys. Therefore, in the future it is necessary to direct our efforts towards the mental health of non-respondents and respondents alike.