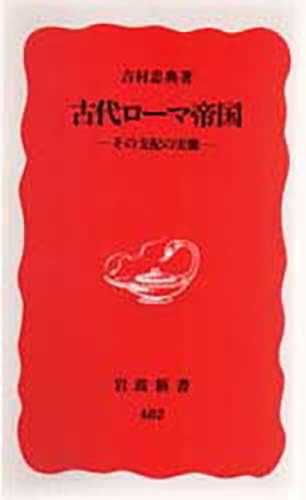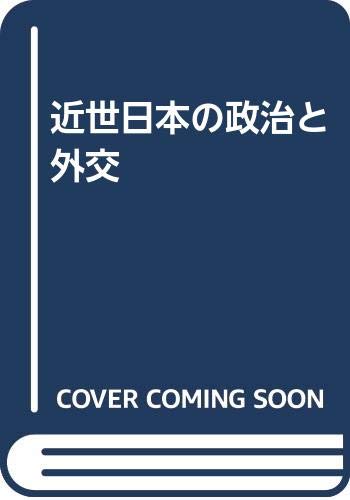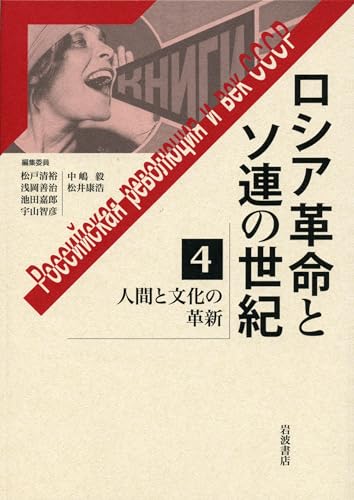3 0 0 0 伏見酒造業における酒造技術者の実践コミュニティ
- 著者
- 田崎 俊之
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.105-119, 2009-05-23
現在、日本酒製造の担い手は季節労働者(杜氏や蔵人)から社員技術者へ転換してきている。本稿では、京都市伏見の日本酒メーカーに勤める酒造技術者へのインタビューを通して、彼らがどのようなつながりのなかで技術の習得や継承を行なっているのかを明らかにし、伝統的な杜氏制度と社員体制との間の連続性と変化について検討する。また、分析に際しては実践コミュニティ概念を手がかりとすることで、フォーマルな組織の枠をこえた技術者仲間のつながりを把捉するよう努めた。社員技術者らは、日本酒メーカーの社員であるとともに、技術者たちが形成する企業横断型の実践コミュニティにも参加している。つまり、日本酒製造の担い手が企業に内部化されても、なお企業の内部では完結しない集合的な酒造技術の習得過程が存在している。他方で、社員技術者らの実践は個人的なつながりを基盤とした相互交流へと深化していた。これは、彼らが勤務先である日本酒メーカーをはじめ、技術者の団体やインフォーマル・グループなど複数の所属性をもつことによる。企業横断型の実践コミュニティは日本酒メーカーが当然求めるべき「企業の利益」と産地内での協調という「共同の利益」の両立にせまられており、社員技術者らは相互交流の複数の位相を用いることでこれを可能にしている。
- 著者
- 小松 孝徳 Takanori Komatsu 信州大学ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点 International Young Researcher Empowerment Center Shinshu University
- 雑誌
- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.6, pp.833-839, 2009-11-01
3 0 0 0 OA 実験古生物学的手法による古海洋環境指標の確立
- 著者
- 北里 洋
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.2, pp.258-273, 1998-04-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 87
- 被引用文献数
- 1 1 1
To analyze oceanic paleoenvironmental histories, paleoceanography has used various biological proxies such as characteristic species, molecular bio-markers, chemical components and others. Much of paleoceanographic information originates from skeletal remains and/or chemical compounds of marine organisms. Accordingly, we are always faced with the biological problem of so-called “vital effects”. Experimental paleontology is a research method to determine relationships between organisms and their biotic and / or abiotic environments through well-controlled culture experiments. This is one of the best ways to shed light into the “vital effect” black box.In this article, I review previous studies which have tried to solve paleontological problems through culture experiments using foraminifera. There are three different scales of experimental methods. First is a culture in a petri dish. This method is advantageous to observe the relation between individuals and environmental factors. Second is micro-and mesocosm experiments which tried to reconstruct a part of the marine ecosystem in laboratory. With this method one can examine interactions between organisms and biotic and/or abiotic factors. Third is in situ experiment in the sea using submersibles or benthic landers. These methods play the role of finding clues about, or proving the nature of, currentbiological proxies of paleoceanography. I strongly invite young scientists to work with experimental cultures for the better understanding biological proxies in paleoceanography. Several suggestions for future studies are also proposed in the text.
3 0 0 0 OA 「ひとつの変数の最大化」を抑制する共同体としてのダルク
- 著者
- 中村 英代
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.498-515, 2015 (Released:2017-03-31)
- 参考文献数
- 35
本稿の目的は, 薬物依存からの回復支援施設であるダルク (Drug Addict Rehabilitation Center : DARC) では, 何が目指され, 何が行われているのかを考察することにある.薬物問題の歴史は古く, 国内外で社会問題として存在し続けている. 薬物依存に対する介入/支援の代表的なものには, 専門家主導による司法モデルと医学モデルとがあるが, そのどちらのアプローチでもなく, 薬物依存症者自身が主導している介入/支援がある. それが本稿で考察するダルクだ. ダルクは, 薬物依存の当事者が1985年に創立して以来, 薬物依存者同士の共同生活を通して薬物依存者たちの回復を支援してきた. 薬物依存の当事者が運営している点, 12ステップ・プログラムを中心に据えている点, 日本独自に展開した施設である点にダルクの特徴がある.本稿では, 2011年4月以降, 首都圏に立地する2つのダルクを中心にフィールドワークとインタビュー (31名) を行ってきた. 調査の結果, ダルクとは, 我々が暮らす現代社会の原理とは異なる原理に基づいて営まれている共同体であることが明らかになった. 具体的には, 人類学者のG.ベイトソンの議論を補助線として, ダルクとは「ひとつの変数 (金, 人望, 権力など) の最大化」を抑制する共同体であることを, 結論として提示する.
- 著者
- 加瀬 嵩人 能勢 隆 千葉 祐弥 伊藤 彰則
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.J99-A, no.1, pp.25-35, 2016-01-01
近年,非タスク指向型の音声対話システムへの需要が拡大しており,様々な研究がされている.それらほとんどの研究は言語的な観点から適切な応答の生成を目指したものである.一方で人間同士の会話においては,感情表現や発話様式などのパラ言語情報を効果的に利用することにより,対話を円滑に進めることができると考えられる.そこで我々はシステムの応答の内容ではなく,応答の仕方に着目し,感情音声合成を対話システムに用いることを試みる.本研究ではまず,適切な感情付与を人手により与えた場合に実際に対話システムの質が向上するかを複数のシナリオを作成して主観基準により評価する.次に,感情付与を自動化するために,システム発話に応じた付与とユーザ発話に協調した付与の二つの手法について検討を行う.評価結果から,感情を自動付与することで対話におけるユーザの主観評価スコアが向上すること,またユーザ発話に協調した感情付与がより効果的であることを示す.
3 0 0 0 OA 地方自治体の政策形成と社会学者の役割
- 著者
- 玉野 和志
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.224-241, 2015 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2
本稿では地方自治体の政策形成に対して, 何らかの関わりをもってきた村落, 都市, 地域に関する社会学研究者の経験を検討することで, 政策形成に関与しようとする社会学者がふまえるべき教訓を導き出すことを目的とする. ここでは, 戦後農地改革の評価を行った福武農村社会学から地域開発政策への批判に及んだ地域社会学への展開, 自治省のコミュニティ施策に深く関与した都市社会学者の経験, そして近年の東日本大震災に関する日本学術会議社会学委員会の提言を取り上げる.そこから, 社会学者は政策の事後評価に関する地道な調査研究を蓄積することはもとより, 市民がより納得できると同時に, 政策の実施者である政府の意向をもふまえて, できるかぎりのことを模索することが求められることが教訓として引き出される. そのうえで, 政策形成に社会学が独自に貢献できるのは, 時間的・空間的に広がる人と人とのつながりに根ざした当時者の主観的な思いによって測られる, 歴史的・文化的な要因を数値などの客観的な表現で示すことであり, その結果, 人々がより納得できる実効ある政策の実現を可能にし, 民主主義の実質化に貢献することであることを明らかにする.
3 0 0 0 IR 民間機関による著作権保護 : 日本音楽著作権協会のゲーム理論的分析
- 著者
- 新井 泰弘
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 経済研究 (ISSN:00229733)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.17-27, 2012-01
本稿では音楽市場における民間機関の著作権保護についてゲーム理論的なフレームワークを構築し,作曲家が楽曲の違法利用を防止するために自発的に著作権協会を組織した場合,社会厚生にどのような影響を与えるか考察を行った.日本音楽著作権協会(JASRAC)が現実に作曲家との間に締結している信託契約を考慮に入れ,作曲家の自発的参加と協会内における利潤分配交渉を含む2段階ゲームを定式化することで次の結論を得ることができる. まず,取締費用がそれほど高くなく,著作権協会に参加する作曲家のパフォーマンスの差が十分大きい場合,著作権協会の存在により社会厚生が増加することが示せる.次に全作曲家が著作権協会に参加するならば,著作権協会が楽曲使用料を統一に設定する方が,著作権者に楽曲利用料を決定させるよりも社会的に望ましい事が示せる.We consider non-governmental copyright protection in a music market in a game theoretical framework. Music composers voluntarily form a non-governmental association to prevent illegal uses of music and to impose music fees collectively. We find that the formation of an association increases social welfare when differences in composers' abilities are sufficiently large. We also show that a uniform pricing rule, as currently employed by the association in Japan, is more desirable from the social point of view than a non-uniform pricing rule whereby members can set music fees individually to maximize their private profits.
3 0 0 0 IR 深澤七郎の小説『楢山節考』とフランツ・アルトハイムの『小説亡国論』
- 著者
- 大木 文雄 ダールストローム アダム
- 出版者
- 北海道教育大学
- 雑誌
- 釧路論集 : 北海道教育大学釧路分校研究報告 (ISSN:02878216)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.69-77, 2003-11-30
深潭七郎の『楢山節考』は、典型的に日本的な作品なのであるが、その作品が外国人にも理解され感動を与えることができるかというところから拙論のテーマは発している。筆者はこの小説『楢山節考』を、昨年平成14年度後期から今年平成15年度前期にかけて、北海道教育大学釧路校の外国人留学生のための授業「日本文化論」の教材にも使ってきた。この小説をこの授業の教材に取り上げたそもそもの理由は、勿論この小説が戦後の日本文学を代表する決定的な作品であり、日本文化を勉強しようとしている彼ら外国の学生たちにとってこの小説は最適の教材と思っていたからである。しかしそれと同時に筆者にはもうひとつの期待があった。それは外国の彼らも一体にこの小説にショックを受けるであろうか、そしてこの小説に感動するであろうかという一縷の望みを内に孕んだ密かな期待であった。そしてその期待は実現した。しかしその感動の源泉は一体どこからくるのであろうかというのがこの論文のライトモチーフである。拙論では特にハンガリーの神話学者カール・ケレーニーイ(Karl Kerenyi 1897-1973)の根源神話(Urmythologie)を援用しつつ、ドイツの古代史学者フランツ・アルトハイム(Franz Altheim 1898-1976)の著書『小説亡国論』を分析しながら、この『楢山節考』を比較検討している。スウェーデンのアダム・ダールストローム君は、国費研究生として北海道教育大学釧路校で日本文化を研究してきた。とりわけ彼はこの『楢山節考』に関心を待って筆者の指導を受けた。彼の論文には意味深いものがあると思われるのでここに補遺の形で掲載することにした。
3 0 0 0 OA あて : 羅漢柏
- 著者
- 仁瓶平二, 辻敬二 編
- 出版者
- 石川県山林会
- 巻号頁・発行日
- 1917
3 0 0 0 OA アジア地域における定額制音楽配信サービス-ユーティリティモデルによるコンテンツ配信
- 著者
- 森沢 幸博
- 出版者
- 埼玉女子短期大学
- 雑誌
- 埼玉女子短期大学研究紀要 (ISSN:09157484)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.151-171, 2007-03
3 0 0 0 古代ローマ帝国 : その支配の実像
3 0 0 0 OA 日本沿岸海域の風況・波浪マッピング
- 著者
- 間瀬 肇 Tracey H. TOM 池本 藍 志村 智也 安田 誠宏 森 信人
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.I_115-I_120, 2014 (Released:2014-10-01)
- 参考文献数
- 6
地球温暖化対策およびエネルギー安全保障の観点から,再生可能エネルギー利用のさらなる進展が必要である.風力エネルギーは風速の3乗に比例して増加するが,経済性の向上には風況の良い場所の選定が重要となる.経済性の目安としては,ハブ高さ80mにおいて年間平均風速が7m/s以上とされている.陸上においては,全国風況データ,500mメッシュで解析した風況マップや風配図が提供されているが,日本沿岸海域においては,詳細な風況・波浪マップはまだ提供されていない.本研究は,今後の洋上風力発電施設の設置場所選定に役に立つように日本沿岸海域の風況・波浪マップを作成し,風と波の概況を把握するものである.
3 0 0 0 OA ヒノキ科樹木の核形態学的研究
- 著者
- 長野克也 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1990
3 0 0 0 天才の発見 : 名編集者マックスウェル・パーキンズとその作家たち
- 著者
- 永岡定夫 坪井清彦著
- 出版者
- 荒地出版社
- 巻号頁・発行日
- 1983
3 0 0 0 近世日本の政治と外交
- 著者
- 藤野保先生還暦記念会編
- 出版者
- 雄山閣出版
- 巻号頁・発行日
- 1993
3 0 0 0 人間と文化の革新
- 著者
- 松戸清裕 [ほか] 編
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2017
- 著者
- Hsiao-Fan YEH Ruey-Lin CHEN
- 出版者
- Japan Association for Philosophy of Science
- 雑誌
- Annals of the Japan Association for Philosophy of Science (ISSN:04530691)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.39-60, 2017 (Released:2017-11-07)
- 参考文献数
- 29
This paper proposes an experiment-based methodology for both classical genetics and molecular biology by integrating Lindley Darden's mechanism-centered approach and C. Kenneth Waters' phenomenon-centered approach. We argue that the methodology based on experiments offers a satisfactory account of the development of the two biological disciplines. The methodology considers discovery of new mechanisms, investigation of new phenomena, and construction of new theories together, in which experiments play a central role. Experimentation connects the three type of conduct, which work as both ends and means, occurring in a circular way and constituting an overall process of scientific practice from classical genetics to molecular biology.
3 0 0 0 小笠原産高等菌類 I
- 著者
- 本郷 次雄
- 出版者
- 国立科学博物館
- 雑誌
- 国立科学博物館専報 (ISSN:00824755)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.31-41, 1977
1976年11月10日より11月29日の間, 小笠原諸島の菌類調査を行なったが, そのさいの採集品のうち, 分類学的もしくは生物地理学的に興味深いもの10種をここに報告する。 1) Anthracophyllum nigrita (LEV.) KALCHBR.ネッタイカタハ(新称)だいだい色∿かば色, 皮質のヒラタケ型の菌で, ひだの組織はKOH液で青緑色に変わる。熱帯∿亜熱帯性. 2) Mycena chlorophos (BERK. & CURT.) SACC.ヤコウタケ熱帯∿亜熱帯性の発光菌である. 3) Xeromphalina tenuipes (SCHW.) A.H.SM.ビロウドエノキタケ(新称)ややエノキタケに似るが, 茎だけでなくかさの表面も微毛におおわれる。熱帯∿亜熱帯に広く分布。筆者は屋久島でも採集したことがある. 4) Lepiota subtropica HONGOムニンヒナキツネガサ(新種)ナカグロヒメカラカサタケL.praetervisa HONGOなどに近縁の小形種。 5) Ripartitella brasiliensis (SPEG.) SING.ニセキツネノカラカサ(新称)外観はカラカサタケ属Lepiotaに似ているが, 胞子が細かいとげ状突起におおわれる点, ならびにシスチジアがザラミノシメジ型である点はきわめて特徴的である。従来は北米∿南米からのみ知られていた種類で, 分布的にも興味深い。熱帯∿亜熱帯性。 6) Panaeolus tropicalis OLA'Hアイゾメヒカゲタケ(新称)子実体が帯緑青色に変色すること, および厚膜のシスチジアが存在することがいちじるしい特徴である。近縁のP. cyanescens (BERK. & BR.)SACC.に比し胞子が小形である。広く熱帯に分布. 7) Psathyrella stellatifurfuracea(S. ITO & IMAI) S. ITOキラライタチタケ故伊藤・今井両博士によって小笠原(父島)から記載された菌であるが, 原記載が簡単なためここに英文記載を補足した. 8) Rhodophyllus glutiniceps HONGOアイイッポンシメジ(新種)ウスムラサキイッポンシメジR. madidus (FR.) QUEL.に似るがずっと小形で, かさは粘液におおわれ, 茎は白い。 9) Suillus granulatus (FR.) O. KUNTZEチチアワタケリュウキュウマツとともに持ち込まれたもので, 本来の小笠原の種類ではない。 10) Lactarius akahatsu TANAKAアカハツ前種と同様にリュウキュウマツとともに移入されたものである。L. semisanguifluus HEIM & LECLAIRにきわめて近縁で, もし両者が同一種であることが判明すれば, 学名としては田中氏のものを用いるべきである。
3 0 0 0 OA 日本住宅雑作図案五百種
3 0 0 0 故訓匯纂
- 著者
- 宗福邦 陳世鐃 蕭海波主編
- 出版者
- 商務印書館
- 巻号頁・発行日
- 2007