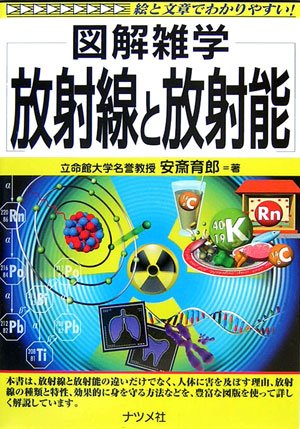2 0 0 0 OA ロシアの政治・社会情勢と市場化の展望
- 著者
- 袴田 茂樹
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 比較経済体制学会会報 (ISSN:18839797)
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, no.33, pp.40-44, 1995-11-01 (Released:2009-07-31)
2 0 0 0 IR 雪関智〔ギン〕と「主人公」論争
- 著者
- 野口 善敬
- 出版者
- 九州大学中国哲学研究会
- 雑誌
- 中国哲学論集 (ISSN:03856224)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.42-72, 2000-10
2 0 0 0 IR 明末に於ける「主人公」論争 : 密雲円悟の臨済禅の性格を巡って
- 著者
- 野口 善敬
- 出版者
- 九州大学文学部
- 雑誌
- 哲學年報 (ISSN:04928199)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.149-182, 1986-02-28
2 0 0 0 IR 『うつほ物語』私見 : 仲忠の主人公性は何か
- 著者
- 髙橋 諒
- 出版者
- 慶應義塾大学国文学研究室
- 雑誌
- 三田國文 (ISSN:02879204)
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.1-13, 2018-12
一, 作り物語の主人公 : 『落窪物語』を端緒に二, 『源氏物語』における秘密三, 後期物語における秘密四, 仲忠の主人公性おわりに
2 0 0 0 IR 疎外と孤立 : 古代物語における主人公と読み手
- 著者
- 奥村 英司
- 出版者
- 鶴見大学
- 雑誌
- 鶴見大学紀要. 第1部, 日本語・日本文学編 (ISSN:18826970)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.1-17, 2015-03
2 0 0 0 IR 自らの不在を語る : "A Slice of Life"の語り手兼主人公
- 著者
- 中田 晶子
- 出版者
- 南山大学短期大学部
- 雑誌
- 南山短期大学紀要 = Journal of Nanzan Junior College (ISSN:02879484)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.43-60, 2018-03
2 0 0 0 IR 『浮世物語』における主人公の機能と巻第二の断層
- 著者
- 松本 健 Matsumoto Ken
- 出版者
- 筑波大学比較・理論文学会
- 雑誌
- 文学研究論集 (ISSN:09158944)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.46(17)-62(1), 2005-03-31
一、 はじめに 「浮世物語」をめぐる先行研究の多くは、前半から後半への流れにおいて見られる様相の変化に注目している。「浮世物語」ははじめ、矮小滑稽に設定された主人公の批判されるべき振る舞いを描くハナシが展開されているのだが、 ...
2 0 0 0 流離の意味-物語の主人公 : 『源氏物語』須磨巻を読む(読む)
- 著者
- 阿部 好臣
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.8, pp.60-65, 2000
2 0 0 0 IR 「小説神髄」研究-7-構成と主人公
- 著者
- 亀井 秀雄
- 出版者
- 北海道大學文學部
- 雑誌
- 北海道大学文学部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.p89-133, 1992-09
2 0 0 0 IR 作者・話者・主人公・<私>そして言語--ホメ-ロスからベケットまで
- 著者
- 近藤 正毅
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- no.255, pp.p61-82, 1993
- 著者
- 長谷川 政春
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.53-61, 1989
『古事記』が語るヤマトタケル伝承のうちに、双生児という二個体における分身関係と両性具有の少年英雄という一個体内における分身構造との、原型的な<分身>の在りようを確認し、それが物語文学の上で展開されている様相を論じた。『石清水物語』における男色関係や主従関係、また『源氏物語』における乳母子の存在などから語り手の構造へ。『虫愛づる姫君』や『貝合』の女主人公たちの両性具有性と<分身>の問題に言及した。
- 著者
- Tatsuhiko Nishimura Kiyotaka Kabata Akiko Koike Masateru Ono Keiji Igoshi Shin Yasuda
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.395-402, 2016 (Released:2016-06-30)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 1 3
Soft rush (Juncus effusus L. var decipiens), known as igusa, is locally cultivated as an edible organic crop, and the dried powder is applied to the processing of unique foods in Japan. The current study investigates the anti-inflammatory effects of edible soft rush using lipoxygenase and hyaluronidase assays, and an activated macrophage cell model in vitro. Matcha green tea powder was tested for comparison. Hot-water and ethanol extracts of soft rush as well as matcha showed comparable lipoxygenase inhibition, with IC50 values of 123 to 145 µg/mL. For the hyaluronidase assay, IC50 values of the samples were 1.16 mg/mL or more. Macrophages cultured in the presence of hot-water and ethanol extracts of soft rush showed strongly suppressed nitric oxide production (IC50 of 120 µg/mL and 35.2 µg/mL, respectively) compared to matcha in a lipopolysaccharide-activated cell model. These results support the potential usefulness of edible soft rush powder for anti-inflammatory purposes.
2 0 0 0 OA 自衛官と文官の協働にみる組織変化の考察 ―陸上自衛隊における参事官を事例として―
- 著者
- 池上 隆蔵
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.72-92, 2019-06-30 (Released:2022-03-14)
- 著者
- 下山 肇
- 出版者
- 実践女子大学
- 雑誌
- 実践女子大学美學美術史學 = Jissen Women's University Aesthetics and Art History (ISSN:09122044)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.(1)-(13), 2018-03-05
2 0 0 0 OA <研究論文>明治初中期の女子教育といけ花、茶の湯、礼儀作法 : 遊芸との関わりを通して
- 著者
- 小林 善帆
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 = NIHON KENKYŪ (ISSN:24343110)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.51-89, 2022-03-31
本稿は、明治初中期、いけ花、茶の湯が遊芸として捉えられながらも、礼儀作法とともに女子教育として高等女学校に、条件付きで取り入れることを許容された過程を考察するものである。手順としてまず教育法令の変遷を遊芸との関係から確認し、次に跡見学校、私塾に関する教育・学校史資料の再考、続いて欧米人による記録類や、欧米で開催された万国博覧会における紹介内容をもとにして、検討を加えた。 教育法令の変遷と遊芸との関係を見ると、1872年「学制」頒布においていけ花、茶の湯は遊芸と捉えられ、教育にとって有害なものであり不要とされた。このことから茶の湯研究が、1875年跡見学校で学科目として取り入れた、としていることは考え難い。いっぽう、1878年のパリ万国博覧会、1893年のシカゴ万国博覧会において、いけ花や茶の湯が女子教育として位置づけられた。それは1879年のクララ・ホイットニーの日記や1878年のイザベラ・バードの紀行からも窺えることであった。 また改正教育令が公布された1880年、「女大学」に初めていけ花、茶の湯が、余力があれば学ぶべき「遊芸」として取り上げられた。さらに1882年、官立初の女子中等教育機関の学科目「礼節」のなかに取り入れられたことは、いけ花、茶の湯が富国強兵という国策の女性役割の一端を担うことになったといえ、ここで女子の教育として認められたと考える。 そのいっぽうで1899年、高等女学校令の公布においていけ花、茶の湯は学科目及びその細目にも入れられなかった。しかし同年、福沢諭吉は『新女大学』で、いけ花や茶の湯は遊芸であっても、学問とともに女性が取り入れるものと説いた。 そして1903年、高等女学校においていけ花、茶の湯は必要な場合に限り、正科時間外に教授するのは差し支えない、との通牒が出された。遊芸を学校教育で課外といえども教えてよいかの是非が問われ、「必要な場合に限り」「正科時間外」という条件付きで是となったのであった。
2 0 0 0 IR 「協働」の法言説 : 自治基本条例における展開を中心に (米沢広一教授 退任惜別記念号)
- 著者
- 阿部 昌樹
- 出版者
- 大阪市立大学法学会
- 雑誌
- 法学雑誌 (ISSN:04410351)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.702-660, 2016-08
2 0 0 0 OA ポイント・マージを用いた航空管制処理方式に対するシミュレーション分析
- 著者
- 阪本 真 屋井 鉄雄
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.I_1089-I_1101, 2019 (Released:2019-12-26)
- 参考文献数
- 20
航空需要の増加に伴い,首都圏空港は更なる機能強化が必要とされている.海外では,従来の管制運用方式とは異なる先進的な管制運用方式の導入によって空港の機能強化が達成されている.本稿ではPoint Merge System(以下,PMS)と呼ばれる運用方式に着目し,従来の研究には見られない管制指示音声データを利用した分析により,PMSにおける管制指示及び航空機挙動の特性を定量的に明らかにした.次にこの結果を踏まえて先行研究で開発した基礎的なシミュレータの改良を進め,羽田空港にPMSを導入した場合の効果について基礎的な検討を行った.
2 0 0 0 OA 岡山県人名辞書
- 著者
- 高見章夫, 花土文太郎 編
- 出版者
- 岡山県人名辞書発行所
- 巻号頁・発行日
- 1918