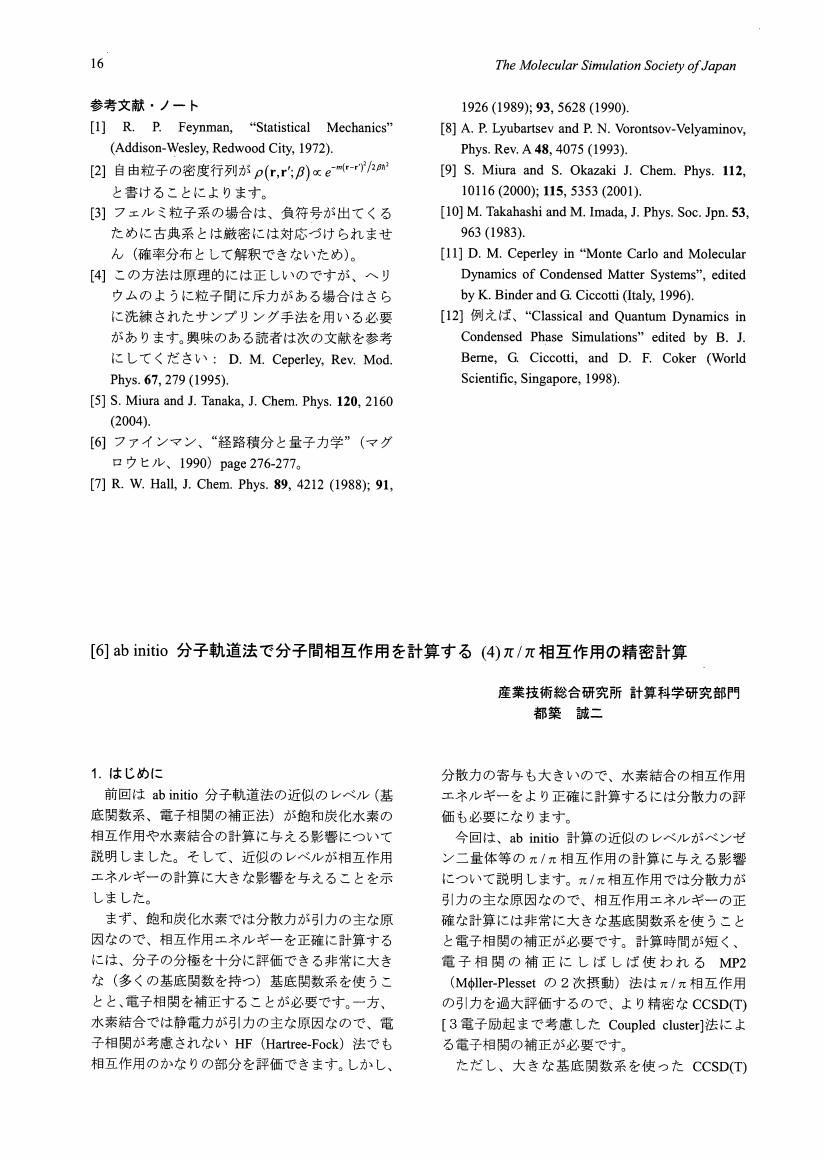2 0 0 0 OA 浦島説話の変遷
- 著者
- 下澤 清子
- 出版者
- 奈良教育大学国文学会
- 雑誌
- 奈良教育大学国文 : 研究と教育 (ISSN:03863824)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.27-37, 1980-05-31
2 0 0 0 OA 文部省検定西洋史受験準備の指導
- 著者
- 都築 誠二
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.30, pp.18-21, 2005-04-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 斎藤 みほ
- 出版者
- 日本子育て学会
- 雑誌
- 子育て研究 (ISSN:21890870)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.42-55, 2019 (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 29
本稿は、日本の子育てにおいて進行しつつある「子育ての社会化」に着目し、その現状と課題について概観した上で、「社会化」のあり方を見直そうとするものである。 現在の日本で「子育ての社会化」が提言される場合、子育ての責任の一端を担うべき「社会」はたいてい、政府や地方自治体といった公的機関、公的システムとして捉えられている。つまり、子育てを家庭内での私事から、自治体などの公的領域が担うべき公事へと転換する方向で進められてきた。しかし、そこには子育てを「私/公」といった二元論的観点から探ることによる問題と行き詰まりが生じている。本稿では、「私/公」という観点を脱する一つの方途として、子育てを「共同化」という形で社会化した、共同保育所について見直し、当時の記録から父母や関係者たちが育児を共同化する過程を検討した。結果、そこには「自分の子もよその子もいっしょに」という親たちの「よその子」も含み込むような私事的意識の領域の拡張とその意識の相互化を軸とした、「子育ての/による社会化(共同化)」、すなわち私事/公事の二元論を超えた「共事」(コモン)としての子育てという可能性が示された。
- 著者
- 都築 誠二
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.29, pp.16-20, 2005-01-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA 政策をめぐる地方自治体とJ リーグクラブの官民パートナーシップ形成の機能と課題
- 著者
- 日下 知明
- 出版者
- 鹿屋体育大学
- 雑誌
- 学術研究紀要 = 学術研究紀要 / 鹿屋体育大学 (ISSN:13426613)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.31-40, 2022-09
研究ノート
2 0 0 0 OA 性に関する危険な出来事の被害体験が防犯意識に与える影響―楽観主義バイアスの視点から―
- 著者
- 笹竹 英穂
- 出版者
- 日本犯罪心理学会
- 雑誌
- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.33-44, 2014-01-31 (Released:2017-07-30)
- 参考文献数
- 22
女子大生の防犯意識は,性に関する危険な出来事の被害体験によってどのような影響を受けるのかについて,楽観主義バイアスの視点から明らかにすることを目的とした。性に関する危険な出来事の被害は,変質者に出会うということに限定した。楽観主義バイアスは,被害にあう確率を他者と比較するという楽観主義バイアス(頻度)と,被害にあった場合の結果の重大性を他者と比較するという楽観主義バイアス(程度)の2つを設定した。そしてそれぞれの楽観主義バイアスを直接法および間接法によって測定した。中部地方の女子大学生329人に対し,平成21年1月に調査を行った。その結果,被害体験がある場合には楽観主義バイアス(頻度)が低くなるが,防犯意識の形成にまでは至らないことが示された。また防犯意識を従属変数にし,被害体験と楽観主義バイアス(程度)を独立変数にした分析では,直接法では被害の有無にかかわらず,楽観主義バイアス(程度)が高いと防犯意識が低いことが示された。同様の分析において間接法では交互作用が認められ,特に被害体験がある場合には,楽観主義バイアス(程度)が高いと防犯意識が低いことが示された。
- 著者
- Yudai Tamura Yuichi Tamura Yu Taniguchi Ichizo Tsujino Takumi Inami Hiromi Matsubara Ayako Shigeta Yoichi Sugiyama Shiro Adachi Kohtaro Abe Yuichi Baba Masaru Hatano Satoshi Ikeda Kenya Kusunose Koichiro Sugimura Soichiro Usui Yasuchika Takeishi Kaoru Dohi Saki Hasegawa-Tamba Koshin Horimoto Noriko Kikuchi Hiraku Kumamaru Koichiro Tatsumi on behalf of the Japan Pulmonary Hypertension Registry Network
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-22-0098, (Released:2022-10-08)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3
Background: Portopulmonary hypertension (PoPH) is one of the major underlying causes of pulmonary arterial hypertension (PAH). However, PoPH, especially treatment strategies, has been poorly studied. Therefore, this study evaluated current treatments for PoPH, their efficacy, and clinical outcomes of patients with PoPH.Methods and Results: Clinical data were collected for patients with PoPH who were enrolled in the Japan Pulmonary Hypertension Registry between 2008 and 2021. Hemodynamic changes, functional class, and clinical outcomes were compared between patients with PoPH treated with monotherapy and those treated with combination therapies. Clinical data were analyzed for 62 patients with PoPH, including 25 treatment-naïve patients, from 21 centers in Japan. In more than half the patients, PAH-specific therapy improved the New York Heart Association functional class by at least one class. The 3- and 5-year survival rates of these patients were 88.5% (95% confidence interval [CI] 76.0–94.7) and 80.2% (95% CI 64.8–89.3), respectively. Forty-one (66.1%) patients received combination therapy. Compared with patients who had received monotherapy, the mean pulmonary arterial pressure, pulmonary vascular resistance, and cardiac index were significantly improved in patients who had undergone combination therapies.Conclusions: Combination therapy was commonly used in patients with PoPH with a favorable prognosis. Combination therapies resulted in significant hemodynamic improvement without an increased risk of side effects.
2 0 0 0 OA 天下りによる大学の研究費獲得と大学発ベンチャー企業に関する実証研究
- 著者
- 藤野 真衣 大江 秋津
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR MANAGEMENT INFORMATION (JASMIN)
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.87-90, 2022-01-31 (Released:2022-01-27)
本研究は天下り人材が社会にもたらす利益や、大学の研究力向上に与える影響は何かという研究課題を持つ。大学に天下りした希少な人材である官僚が持つ独自のネットワークが大学の研究力に与える影響やそのメカニズムを明らかにする。また、大学の研究成果を発信する大学発ベンチャー企業の創出に与える影響も実証する。分析には、2017年4月1日から2019年3月31日までに国公立大学へ再就職をした国家公務員の人事データを利用した。その結果、天下りの大学の研究費獲得能力や大学発ベンチャー企業設立への影響が実証された。天下りの有効性を実証したことは、天下りに対する公平な評価の一助となる実務的貢献と言える。
2 0 0 0 OA 産科病棟におけるケタミン塩酸塩使用症例:その有効性と安全性について
- 著者
- 三宅 麻由 衣笠 万里 西尾 美穂 松井 克憲
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.31-36, 2021 (Released:2021-05-10)
- 参考文献数
- 21
ケタミン塩酸塩は日本では麻薬に指定されているが,われわれは産科病棟に常備して緊急時に使用してきた.2007年1月から2018年12月までに同病棟でケタミンによる静脈麻酔を行った32症例について,その有効性と安全性を評価した.22例は胎盤用手剥離術施行例であり,出血量は平均1,096mLであったが,輸血例はなかった.それ以外は分娩後子宮出血止血処置が3例,腟裂傷・血腫の止血処置が4例,III度およびIV度会陰裂傷縫合が3例であった.計5例に輸血を要したが,その後の回復は良好であった.ケタミン使用量は30~80mg(平均43mg)であり,単独でも良好な鎮痛・鎮静効果が得られ,血圧低下・呼吸停止・誤嚥はみられなかった.またケタミン投与後の授乳による新生児への影響は認められなかった.ケタミンは有効かつ安全な麻酔薬であり,母体救命の視点から緊急時にはただちにアクセスできることが望ましい.
2 0 0 0 OA 過密環境がマウス免疫能に及ぼす影響
- 著者
- 塚本 和正 町田 和彦 稲 恭宏 栗山 孝雄 鈴木 克彦 村山 留美子 西城 千夏
- 出版者
- 日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.827-836, 1994-10-15 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 6 9
動物の過密飼育(crowding)は,心理社会的なストレッサーとされているが,従来の方法は飼育面積を一定にし,個体数のみを変化させているため,個体数の増加と1匹あたりの占有スペースの狭少化という2つの要因が複合されたものであるといえる。そこで本研究ではケージ内の個体数とケージのサイズの両方を変化させるという方法をとり,免疫能に及ぼす影響を追求した。またケージ内の動物の構成メンバーの変化が及ぼす影響についても検討を加えた。実験1ではマウスをまずケージあたり4匹ずつに分けて14日間馴化飼育し,その後ケージあたり4匹(Control群),小スペースあたり4匹(Crowding-I群),ケージあたり16匹(Crowding-II群)の計3群に無作為に分け7日間飼育を行った。結果は以下の通りであった。(1) 体重に群間で有意差は認められなかった。(2) 総白血球数に有意差は認められなかったが,Crowding-II群にリンパ球百分率の有意な低値,そして好中球百分率および絶対数の有意な高値が認められ,ストレッサーの継続負荷による白血球構成比の変動が示唆された。(3) 好中球NBT還元能ではCrowding-II群に低値を示す傾向が観察され,細菌貪食能ではCrowding-II群に有意な低値が認められた。一方Crowding-I群では,NBT還元能,貪食能ともにCrowding-II群ほどの低下は認められなかったが,いずれもControl群とCrowding-II群の中間の値を示す傾向がみられた。これらの結果から,個体数の増加によるマウス相互間の心理社会的要因の複雑化がストレッサーとして重要な意味をもつことが示唆された。実験2ではマウスをまずケージあたり5匹ずつに分けて14日間馴化飼育し,その後ケージあたり5匹(Control群),小スペースあたり5匹(Crowding-(1)群),ケージあたり20匹(Crowding-(2)群)の3群に分けたが,Control群とCrowding-(1)群はケージ内のマウスの数と構成メンバーは馴化飼育と同一にし,ケージへの移動のみを行った。群分け後2日目に抗原としてSRBCを腹腔投与し,7日間飼育を行った。結果は以下の通りであった。(1) 体重にはいずれの時期も有意差は認められなかった。(2) 特異免疫反応として測定したPFCおよび抗SRBC抗体価は,群間に有意差は認められなかった。なおマウスの産生した抗体はIgMであると考えられた。(3) 血漿中のIgM濃度に有意差は認められなかったが,Crowding-(1)群が高値を示した。またIgG濃度では,Crowding-(1)群に有意な高値が認められた。(4) 好中球NBT還元能は,エンドトキシン刺激時では有意差は認められなかったがCrowding-(2)群が低値を示し,細菌刺激時ではCrowding-(2)群に有意な低値が認められた。また好中球の細菌貪食能においてもCrowding-(2)群に有意な低値が認められた。一方Crowding-(1)群はControl群に比べて,有意差は認められなかったがいずれも高値を示した。このように,マウスの構成メンバーを変えず飼育面積の狭少化のみを施して過密にした場合は,同様にマウスの構成メンバーを変えなかった対照群に比べ,免疫能が亢進する傾向が観察された。一方ケージ内の個体数を増やして過密にした場合は,条件設定は実験1とは異なるが,好中球機能の顕著な低下が認められた。本研究は7日間という短期間のストレス負荷の結果であり,今後より綿密な実験デザインを設定し長期間の検討を行いたいと考えている。
- 著者
- 中出 孝次 佐久間 豊 梶島 岳夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.893, pp.20-00366, 2021 (Released:2021-01-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
To clarify the mechanisms underlying airflow-induced vibrations of high-speed trains running through tunnels, large-eddy simulation of a large-scale flow structure around a simplified 6-car train model was conducted. Since actual trains run on one of the double track lines, the position of the train model was made to deviate from the tunnel center and hence the gap between one of the sides of the train and the tunnel wall is narrower than that of the other side. A train running in the open air was also calculated for comparison. The results of this study shed light on the generation mechanism of the pressure fluctuations acting on the side of high-speed trains as follows. Firstly, in the open air, the air velocity in the space between the underbody and the ground gradually decreases from the head toward the tail of the train. Thus, the air velocity is slower than that on both sides of the train, which generates shear flows near the bottom edges of both sides of the train. The shear flows cause large Karman vortex-like vortices (staggered Karman vortex street), which in turn lead to a meandering airflow beneath the underbody of the train. Secondly, in the tunnel, the air velocity not only in the gap between the underbody and the ground but also in the narrower gap between the side of the train and the tunnel wall gradually decreases from the head toward the tail of the train. In the same mechanism as the open air, a meandering airflow is generated throughout the side and underbody of the train and causes pressure fluctuations along the side of the train. Finally, it is demonstrated that the wavelength of pressure fluctuations along the side of the actual train can be estimated from the present LES results.
- 著者
- 桃原 一彦
- 出版者
- 沖縄国際大学社会文化学会
- 雑誌
- 沖縄国際大学社会文化研究 (ISSN:13426435)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.1-30, 2007-03