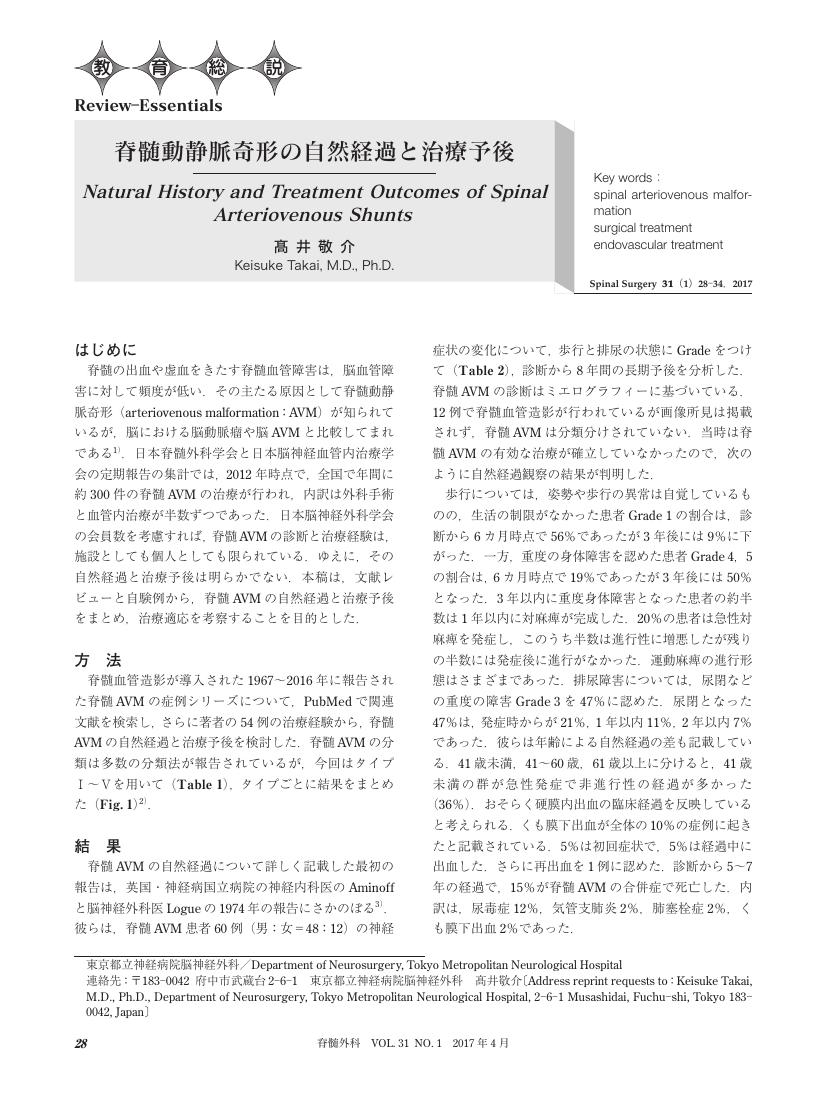2 0 0 0 OA 青森県鉱泉誌
- 著者
- 青森県警察部衛生課 編
- 出版者
- 青森県警察部衛生課
- 巻号頁・発行日
- 1920
2 0 0 0 乱数生成による量子コンピュータの統計的評価
- 著者
- 田村 賢太郎 鹿野 豊 レイモンド ルディー
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 日本計算機統計学会シンポジウム論文集 (ISSN:21895813)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.23-26, 2020-11-28
- 著者
- Kazumasa Oura Keita Taguchi Mao Yamaguchi Oura Ryo Itabashi Tetsuya Maeda
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.7735-21, (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3
Takayasu's arteritis is an inflammatory disease of unknown etiology that causes stenosis, occlusion, or dilatation of the aorta and its major branches, the pulmonary arteries, and the coronary arteries. The incidence of extracranial carotid artery aneurysm in patients with Takayasu's arteritis is reportedly 1.8%-3.9%. We herein report a patient with Takayasu's arteritis who presented with transient left hemiplegia immediately after neck massage. Carotid ultrasonography revealed a thrombus within the fusiform aneurysm on the right common carotid artery. We speculated that fragmentation from the intra-aneurysmal thrombus was caused by neck massage.
2 0 0 0 OA トンネル覆工コンクリートに生じるひび割れの発生メカニズムに関する実験的研究
- 著者
- 高山 博文 増田 康男 仲山 貴司 植村 義幸 Narentorn YINGYONGRATTANAKUL 朝倉 俊弘
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F (ISSN:18806074)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.132-145, 2010 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 16
NATMで施工された覆工コンクリートでは,トンネル天端付近において軸方向に伸びるひび割れがしばしば確認されている.このひび割れは地圧によるものと類似するため,維持管理段階における健全度評価を困難なものとしている.本研究では,このひび割れの発生メカニズムを明らかにするため,実際の坑内環境と施工条件を模擬した模型試験とそのシミュレーション解析を実施した.この結果,吹付けコンクリート面の凹凸などによる外部拘束がない現在の覆工コンクリートにおいて,ひび割れの発生に寄与すると考えられるコンクリート自身が発生させる内空側と地山側との収縮量の差(内部拘束)を数値解析で適切に表現するためには,「湿気-応力連成解析」を行う必要があることを示した.
2 0 0 0 IR 《模型千円札》理論の形成主体に関する考察 : 赤瀬川原平著作の分析を中心に
- 著者
- 河合 大介
- 出版者
- 成城大学大学院文学研究科美学・美術史専攻
- 雑誌
- 成城美学美術史 = Studies in aesthetics & art history (ISSN:13405861)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.1-15, 2018-03
2 0 0 0 OA 最近巡洋艦の發達
- 著者
- A.K.
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会雑纂 (ISSN:24331023)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, pp.146-148, 1934 (Released:2018-02-25)
2 0 0 0 OA デカルト哲学における「客象的レアリタス」について
- 著者
- 村上 勝三
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.28, pp.116-126, 1978-05-01 (Released:2009-07-23)
2 0 0 0 OA 気管支喘息の病因
- 著者
- 光井 庄太郎 鹿内 喜佐男
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.198-212,241, 1969-03-30 (Released:2017-02-10)
According to the histories of the patients with bronchial asthma the factors involved in the occurrence of asthmatic attack were investigated and the following results were obtained. 1. Analysis of the season and occurrence of asthematic attack studied on 237 cases revealed that 55 had the attack in autumn, 52 regardless of the season, 31 in winter and 25 in both spring and autumn. 2. Of 685 asthmatics, the causes of the first asthmatic attack were presumed in 464 cases. They were common cold occurred in 245 cases, revealing the highest incidence, inhalation of sea-squirt substances in 80, pneumonia in 22, acute bronchitis in 17, fatigue in 14, cold and pregnancy in 11 each. Of 673 asthmatics, the causes or the inducing factors of asthmatic attack after the onset of bronchial asthma were presumed in 567 cases. They were related to: 1) physical conditions in 352 (common cold and influenza in 229, fatigue in 126, overeating in 34, psychic tension in 24, bathing in 19, etc.);. 2) weather in 222 (cold in 84, rainy day in 63, cloudy day in 33, sudden change in weather in 29, humid day in 21, etc.); 3) dust in 173 (sea-squirt substances in 83, house dust in 78, cotton wool in 9, etc.); 4) smoke and offensive odor in 91 (cigarette smoke in 38, smoke of mosquito stick and smoke of broiling fish in 9 each.) 5) food and drink in 79 (wine in 30, vegetable foods in 26, animal foods in 20, fatty foods in 9, etc.) ; 6) drugs in 9 (ACTH in 3, aspirin in 2, etc.) ; 7) animals in 6 (contact with domestic. animals in 4, furs and feathers in 2) ; 8) plants in 5 (newly-bult house in 3, pollen in 2); 9) molds in 5 (aspergillus in 2, other molds in 3). 3. The causes or the inducing factors of asthmatic attack above mentioned were studied as follows: l) those relating to the psychic and physical conditions were investigated from the view-point of the autonomic nervous function and the endocrine glands; 2) those relating to the infection of the upper respiratory tract were investigated from the view-point of bacterial allergy; 3) those relating to the inhalants and ingestants were investigated by the skin test with these substances; and the significant results were obtained from each of them. 4. The incidence rate of positive reaction in the intradermal test was 51.2% with house dust antigen, 41.8% with Paspat, 21.6% with ragweed pollen antigen, 15.5% with the mixed antigen of crab, lobster and oyster, 15.5% with sea-squirt antigen (except sea-squirt asthma patients), 11.8% with mixed antigen of cat hair and dog hair, 11.2% with yam antigen.
2 0 0 0 IR 『逢魔ヶ刻動物園』が描く変身の妄想的世界
- 著者
- 諸井 克英 古性 摩里乃 Moroi Katsuhide Furusho Marino
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- 総合文化研究所紀要 = Bulletin of Institute for Interdisciplinary Studies of Culture Doshisha Women's College of Liberal Arts (ISSN:09100105)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.256-263, 2018-07-27
研究ノート
2 0 0 0 OA 脊髄動静脈奇形の自然経過と治療予後
- 著者
- 髙井 敬介
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.28-34, 2017 (Released:2017-07-08)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 明治期日本と在外窮民問題
- 著者
- 鈴木 祥
- 出版者
- 外務省外交史料館
- 雑誌
- 外交史料館報 = Journal of the Diplomatic Archives (ISSN:09160558)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.21-36, 2020-03
2 0 0 0 IR 戦間期における京都花街の経済史的考察
- 著者
- 瀧本 哲哉
- 出版者
- 京都大學人文科學研究所
- 雑誌
- 人文学報 = Journal of humanities (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- no.115, pp.193-222, 2020
戦間期の京都には花街(貸座敷免許地)が16か所あり, 京都府内外から大勢の遊客が花街を訪れていた。全国的にみた京都花街の特異性は, 人口や工業生産額との対比でみて娼妓数が他府県と比べて際立って多いことである。当時の京都は「繊維の街」であったが, 「遊廓の街」でもあったのである。1920年代前半に芸娼妓数が急増し, 遊客数や遊興費も増加して, 花街はおおいに賑わった。その背景としては, 府内の繊維産業の業況回復に伴って遊客の遊興費支出額が増加したこと, 1928年(昭和3年)の昭和の大礼による観光客の増加が遊客数の増大につながったことが挙げられる。戦間期の京都府内の花街は, 芸妓主体の花街と娼妓主体の花街(遊廓)に分化していく過程にあった。芸妓主体の花街は, 1930年代に入ってから芸妓数が減少し, 遊興費も落ち込んで地盤沈下していった。一方, 娼妓主体の花街(遊廓)では, 1930年代前半も郡部を中心に娼妓数や遊客数の増加が続いた。京都花街の経済的な位置付けをみると, 芸娼妓は毎月多額の賦金や雑種税を京都府に納付していた。その金額規模は, 商工業者等に課される京都府税の3割前後にまで達しており, 不況期には芸娼妓の税額が府税落ち込みの下支えの役割を果たした。そして, この恩恵を享受していたのは専ら京都府民である。また, 花街が吸い上げた遊興費は, 1920年代前半には京都府歳入総額にほぼ匹敵する規模にまで達していた。さらに, 花街では数多くの芸娼妓が稼業を営んでおり, 衣装代などの多額の支出を行っていたことから, 呉服商など関連業界は大きな恩恵を受けていた。このように, 花街は消費経済の主要な事業体として京都経済に組み込まれており, 地域経済の循環の一翼を担っていた。芸娼妓は賤業と蔑まれながらも, 納税などを通じて京都経済の発展に寄与していた。京都府民も間接的に芸娼妓から搾取していたのである。
2 0 0 0 IR 師団の立地と遊廓移転をめぐる地域社会と市政 : 日露戦後期の豊橋市の場合
- 著者
- 松下 孝昭
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
- 雑誌
- 史林 = The Journal of history (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.2, pp.304-333, 2020-03
平時における軍隊の立地と遊廓との関係性を解明するため、日露戦後期に愛知県豊橋市で起きた遊廓移転問題を研究対象とする。豊橋市では、大口喜六市長が師団の誘致に成功すると、市街地中心部にあった遊廓を、市費を投じて東郊に移転させる計画を立て、貸座敷業者や反市長系会派の反対を制して実施に移した。次いで市長は、師団と共存しうる都市に改造するための道路整備事業を推進するが、これは、停車場・兵営・新遊廓の三点を結ぶことが目的となっていた。新遊廓では、貸座敷業態の比率が高かった地区から移転してきた業者らが中心となって組合を組織し、他市から移転してきた業者らを組み込みながら、廓内の秩序を形成していった。以上の豊橋市の事例は、平時の軍隊と遊廓との関係性を論じるにあたり、軍隊と共存して地域振興を図ろうとする地元首長や議員らの動向を重視する必要性があることを示している。
2 0 0 0 IR パピアメント語におけるヴォイスとその周辺
- 著者
- アルミロン パトリシオ バレラ アルミロン パトリシオ バレラ ALMIRON Patricio Varela
- 出版者
- 東京外国語大学語学研究所
- 雑誌
- 語学研究所論集 (Journal of the Institute of Language Research)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.419-427, 2021-03-31
2 0 0 0 OA 原子力市民委員会の目指すもの
- 著者
- 吉岡 斉
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.188-189, 2014 (Released:2019-10-31)
2 0 0 0 OA [大阪市]社会部報告
- 著者
- 大阪市社会部労働課 編
- 出版者
- 大阪市社会部労働課
- 巻号頁・発行日
- vol.第65号 大阪市住宅年報(昭和元年), 1935
- 著者
- 土屋 靖明
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.88, pp.51-66, 2003-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 46
Le but de cet article est de dégager un principe de la théorie du devenir humain dans la philosophie bergsonienne, et par ailleurs, de souligner le discours sur le pragmatisme (particulièrement celui sur William James) chez Bergson. Les conceptions de la vie, du devenir, du changement de la réalité spirituelle, de l'effort spirituel, de la pluralité et de l'inventivité qui sont examinées dans cet essai sont des idées importantes pour la philosophie bergsonienne elle-même. Et Bergson montre son intérêt pour ces thèmes dans son discours sur le pragmatisme.Dans le bergsonisme et dans l'interprétation bergsonienne du pragmatisme, l'humain est la réalité spirituelle, soit en d'autres mots, l'âme et l'esprit. La réalité spirituelle vit; elle est en devenir continuel et se transforme et évolue par un effort d'esprit intime. Une telle théorie du devenir refuse le but comme point final. La finalité dans la théorie du devenir est le devenir indéfiniment soi-même, ou encore la pluralité qui signifie des évolutions divergentes. La pluralité du devenir se manifeste dans la faculté inventive. Le pragmatisme (dans l'interprétation de Bergson) vise des inventions scientifiques reflétées dans des utilisations pratiques. Le bergsonisme est tourné vers les créations artistiques reposant sur leur propre inspiration. L'utilisation pratique et l'inspiration artistique sont le produit d'un effort spirituel.
2 0 0 0 OA 民約論
- 著者
- ジャン・ジャック・ルソー 著
- 出版者
- 有斐閣
- 巻号頁・発行日
- 1920
2 0 0 0 OA 民約論
- 著者
- 戎雅屈・蘆騒 (ジャン・ジャック・ルーソー) 著
- 出版者
- 有村壮一
- 巻号頁・発行日
- 1877