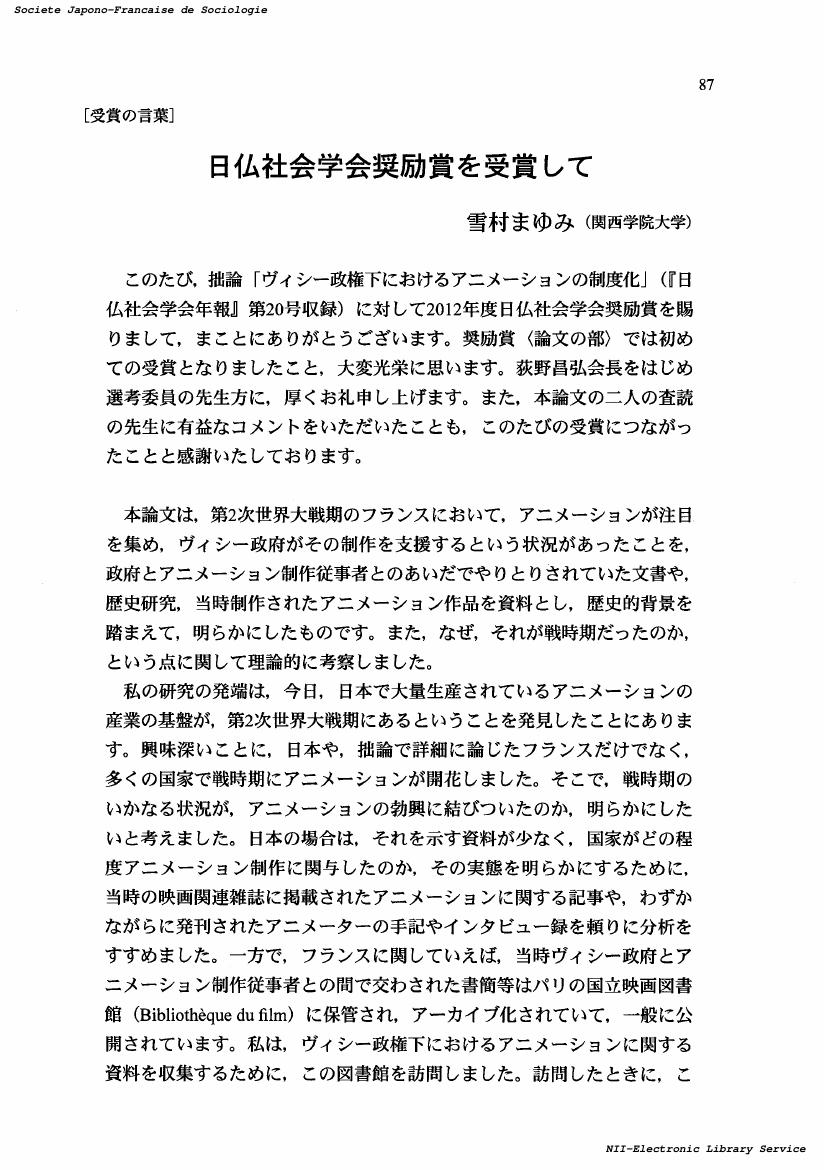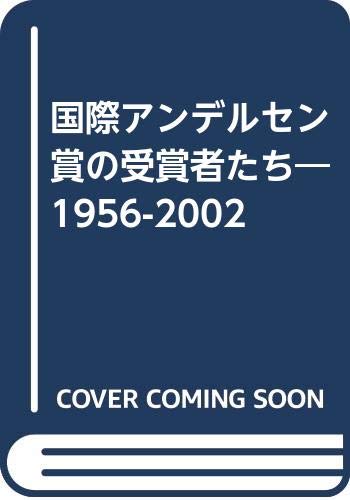1 0 0 0 OA 日仏社会学会奨励賞を受賞して(受賞の言葉,日仏社会学会奨励賞)
- 著者
- 雪村 まゆみ
- 出版者
- 日仏社会学会
- 雑誌
- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.87-89, 2013-03-31 (Released:2017-06-09)
1 0 0 0 OA 1歳児クラスの保育室での遊びにおける環境構成の要素 ―保育者と仲間の存在に着目して―
- 著者
- 齊藤 多江子 増田 まゆみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.9, pp.657-666, 2018 (Released:2018-10-27)
- 参考文献数
- 27
The aim of this research is to study the effects of dividing a childcare room into several small spaces which provide a calm environment suitable for play, with a specific focus on how one-year old children moved in the newly-partitioned room. We examined the characteristics and background of the movement of children by paying attention to situations where childcare teachers or other children were present or not. It became clear that the presence of childcare teachers and other children in the partitioned childcare room had an influence on the way children in the one-year old class chose to play. In addition, in order to carefully plan the provision of a calm environment suitable for play for children in small spaces, the perspectives that are considered to be important are, (1) a place where childcare teachers and children's peers are present and, (2) play contents that make use of a small space.
- 著者
- 宇佐美 まゆみ
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.4-22, 2008-08-31 (Released:2017-05-01)
本稿では,これまで,いわゆる「ポライトネス研究」としてまとめて言及されることが多かったものを,その目的の違いによって,「ポライトネス記述研究」と「ポライトネス理論研究」に分けて整理し,従来明確に区別されることなく論じられてきた両者を含む「ポライトネス研究」の約30年間の流れを,その違いを明確にする形で概観する.「ポライトネス記述研究」とは,各個別言語におけるポライトネス,敬語体系や敬語運用の研究,それらの比較文化的研究などを指し,「ポライトネス理論研究」とは,言語文化によって多岐・多様にわたるポライトネスの「実現(realization)」の基にある動機とその「解釈(interpretation)」のプロセスを,統一的に説明,解釈,予測しようとする「理論(theory,principle)」に重点をおいた研究である.それぞれの意義と役割,問題点などを確認した上で,本稿では,後者の「ポライトネス理論研究」のほうに焦点をあて,Brown&Levinson(1978/1987)のポライトネス理論が普遍的であるとして提唱されて以降,他の研究者から提起された問題点や,普遍理論追究のために重要だと考えられる新しい捉え方のポイントをより具体的にまとめる.その上で,「ポライトネス理論研究」の今後の課題をまとめ,これまでに指摘されてきた様々な問題点を克服する形で構想されている「対人コミュニケーション理論」としての「ディスコース・ポライトネス理論」(宇佐美,2001a,2002,2003)の最新の構想の一部を提示する.
1 0 0 0 IR 文化財保護のグローバル化と地域の文化資産のカテゴリー化 : 日本の世界遺産条約批准の影響
- 著者
- 雪村 まゆみ
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Sociology, Kansai University (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.1-15, 2020-03
近代国家成立とともに、各国の文化的生産物は、文化財として国内法あるいは慣習によって保護されてきた。本稿では、世界遺産条約といった国際的な文化財保護制度の枠組みが浸透するなかで、それらがいかに変化するのか、また、新たな批准国の参画は、世界遺産条約にいかなるインパクトをもたらすのか、という問題について考察することを目的とする。そのために、まず、2節では、日本が世界遺産条約に批准するプロセスについて、国会議事録等を資料として考察する。次に、3項では、日本が世界遺産条約に批准してすぐに開催された「木造建築」のオーセンティシティを議論する「奈良会議」に至る経緯と、そこで議論された文化財のオーセンティシティの解釈について考察する。また、4項では広島の原爆ドームが世界遺産に登録されるプロセスを分析し、日本国内の文化財保護行政の変更点を示す。さいごに第5項では旧閑谷学校の世界遺産登録運動のプロセスを分析することで、戦略的に文化財のカテゴリー変更が推し進められる実態を明らかにする。以上のことより、国際的な文化財保護の制度化は、他者の文化との交流を促すため、不可避的に各文化の価値基準の変化を引き起こすことが明らかとなった。本稿は、2018年度-2019年度科学研究費助成事業・研究活動スタート支援「世界遺産制度が地域の文化財保護におよぼす影響」(研究代表者:雪村まゆみ、課題番号 : 19K20933)による研究成果の一部である。
1 0 0 0 IR 医療福祉相談室における看護師の役割
- 著者
- 三平 まゆみ 深沢 紀代美 高野 和美 山岸 春江 山崎 洋子
- 出版者
- 山梨大学看護学会
- 雑誌
- 山梨大学看護学会誌 (ISSN:13477714)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.21-24, 2003
医療福祉相談室(以下,相談室)における看護師の役割を明らかにするために,相談室の看護師が関わった相談者150人の初回相談時の主な相談内容を調査した。相談者で一番多かったのは看護師70人(46.7%)で,内容としては医療器具に関する事38件(25.3%),在宅療養27件(18.0%),退院に向けて25件(16.7%)の相談であった。相談解決のために,当院の医療スタッフ,市町村役場,保健所,訪問看護ステーション等の関係職種に協力を求めた。相談室における看護師の役割として,医療用消耗品の選定・情報提供を行う事,病状や家庭事情に合わせた社会福祉資源を検討する事,病院内外を問わず関係職種との連絡調整を行う等の役割があることが示唆された。
1 0 0 0 国際アンデルセン賞の受賞者たち : 1956-2002
- 著者
- 国際児童図書評議会編著 さくまゆみこ 福本友美子訳
- 出版者
- メディアリンクス・ジャパン
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 資料のユニバーサルカラーデザイン (特集 色彩による情報提供)
- 著者
- 三浦 まゆみ
- 出版者
- 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 = The journal of Information Science and Technology Association (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.113-118, 2021
1 0 0 0 七わの白ん鳥 . 月にのぼったアカナー
- 著者
- 梶原まゆみ文 石部虎二絵 . 松谷みよ子文 儀間比呂志版画
- 出版者
- 世界文化社
- 巻号頁・発行日
- 2004
1 0 0 0 資料のユニバーサルカラーデザイン
- 著者
- 三浦 まゆみ
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.113-118, 2021-03-01 (Released:2021-03-01)
資料のユニバーサルカラーデザインというテーマで,わかりやすく読みやすい資料作成の具体的な手法をまとめた。色の見え方は誰もが同じではなく色覚異常や高齢者の加齢による色覚変化などによりさまざまな色覚特性があり,見にくい配色のパターンがあるため,それを踏まえて色を選定することであらゆる人にとって快適なカラーデザインとなる。また,色の三属性,トーン,配色によるイメージ表現,色の機能的効果(誘目性,明視性,可読性,識別性)といった色彩学の基本の解説と共に,対象者や目的別の資料作りを効率よく作成する色使いを5つのポイントとして紹介している。
1 0 0 0 OA タラの芽がラットの生体に及ぼす影響
- 著者
- 開元 多恵 渋谷 まゆみ 前田 英雄
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.5, pp.309-314, 2010 (Released:2010-11-29)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
コレステロールを添加した高脂肪食を投与し,タラの芽摂取がラットの血清および肝臓の脂質に与える影響を調べる目的で実験を行った。タラの芽は凍結乾燥し,粉末は600μmのふるいを通し,一部はエチルアルコールによる抽出に用いた。タラの芽粉末,抽出物,抽出残渣は別々に高脂肪食に添加し,20%カゼイン食(普通食)と比較した。Sprague-Dawley系雄ラット(4週齢)は食餌によって5群に分け,4週間飼育した。5%タラの芽粉末およびエチルアルコール抽出物や抽出残渣を添加しても摂食量や体重増加,血清中の肝臓や腎臓機能を表す指標についても差は認められず,添加による影響はほとんどないと考えられた。高脂肪食での飼育により,肝臓の脂質含量は顕著に増加し,血清のHDL-コレステロールは低下したが,タラの芽粉末あるいはアルコール抽出残渣を添加した群では,肝臓のトリアシルグリセロールの増加が抑制された。これらの結果からタラの芽には肝臓の脂質代謝に有効な成分が含まれている可能性が示唆された。(オンラインのみ掲載)
1 0 0 0 OA 患者と家族の意思決定における看護職の役割(患者の意思決定と家族の役割)
- 著者
- 近藤 まゆみ
- 出版者
- 日本医学哲学・倫理学会
- 雑誌
- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.96-100, 2008-10-22 (Released:2018-02-01)
1 0 0 0 OA 樹木年代学的手法による山地流域のニホンジカ生息密度・分布域の時間的変化の再現
- 著者
- 櫻木 まゆみ 丸谷 知己 土肥 昭夫
- 出版者
- 一般社団法人日本森林学会
- 雑誌
- 日本林學會誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.147-152, 1999-05-16
- 被引用文献数
- 3
九州山地の大藪川流域(520ha)において, シカの生息密度や分布域の変化を樹木年代学的手法により再現した。幼齢造林地における枝葉被食木率と糞粒密度との関係やこれまでの研究例から, 樹皮被食木率が過去のシカ生息密度の指標として有効であることを示した。林齢と糞粒密度の関係から, 4〜10年生の幼齢造林地がシカの環境収容力が高いことを明らかにした。流域における1982〜1991年の幼齢造林地の増加は, 樹皮被食木率の増加と一致していた。1992年以降の幼齢造林地の減少により樹皮被食木率はさらに高くなった。この結果から, 幼齢造林地の拡大は環境収容力の増大とそれにともなうシカの集中を引き起こしたこと, さらに生息密度の増加とその後の幼齢造林地の減少によって, 採食圧が高まりシカが流域全体に分散したプロセスが明らかにされた。造林の規模や配置がシカの生息密度や分布域の変化に大きく影響していることから, 被害地におけるシカの増加プロセスを明らかにし, その各時期に対応した被害防止対策の必要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 小中学校における屈折検査
- 著者
- 野原 雅彦 高橋 まゆみ
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.115-120, 2001-07-15 (Released:2009-10-29)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
小中学校での眼科学校健診において、オートレフラクトメーター使用による屈折検査を導入し、屈折分布や変化を検討した。対象は長野県小県郡丸子町の小中学生1719名で、キヤノン社製RK-3Rを用いて各眼3回以上測定し、その平均値を使用した。等価球面度数は、小学校1年生+0.09D±0.61D(平均±標準偏差)、2年生-0.17D±0.69D、3年生-0.33D±0.82D、4年生-0.50D±0.92D、5年生-0.62D±1.12D、6年生-0.99D±1.55D、中学校2年生男子-1.09D±1.61D、2年生女子-1.34D±1.39D、3年生男子-1.33D±1.75D、3年生女子-2.07D±2.17Dであった。乱視度数は、学年や男女差はなく0.4~0.6Dであった。学年が進むにつれて近視化していき、標準偏差も大きくなった。中学生では女子の方が近視化傾向が強かった。また教諭の測定した裸眼視力が良好でも、屈折異常が大きくある者がみられた。学校健診において屈折検査を導入することで、屈折状態を把握し適切な指導を行うことができ、有用と思われた。
- 著者
- 高島 まゆみ
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.11, pp.1930-1931, 1990-11-20 (Released:2017-11-29)
- 著者
- 前田 まゆみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.11, pp.855-864, 2005
本研究は, 米国で多く問われているmedical malpractice crisisを前提に踏まえ, 日本での医療訴訟の増加を危惧し, その解決策のポイントをさぐるため「医療訴訟の系統的分類」の構築を目的とした.特に, 近年注目されている心身医学領域を中心に調査した.判例の分析から, 一系類型として医療過誤判例の法的争点に関わる分類と, 二系類型として心身医学領域の事案内容による分類を行った.これをもとに, 判例分類表を作成し, 問題点やポイントがわかるシステムとした.また, 判例の勝訴数や, 分類から導き出される訴訟回避のポイントを提案し, 医療側の倫理的な視点として検討を試みた.
1 0 0 0 村落運営と長老衆--甲賀北内貴の十人衆
- 著者
- 関沢 まゆみ
- 出版者
- 日本民俗学会
- 雑誌
- 日本民俗学 (ISSN:04288653)
- 巻号頁・発行日
- no.168, pp.p30-46, 1986-11
1 0 0 0 IR 名筝「山下水」考
- 著者
- 宮崎 まゆみ
- 出版者
- 宮崎大学教育文化学部
- 雑誌
- 宮崎大学教育文化学部紀要 芸術・保健体育・家政・技術 (ISSN:1345403X)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.62-46, 2002-03
A Koto Yamashitamizu owned by the Kishu-Tokugawa House in the old times, is now stored at the National Museum of Japanese History. This Koto has a passed down tradition claiming that it has been made by the Kishu-Tokugawa House in 1788, in imitation of the Ya,nashitamizu owned by the Shogunate. It may safely be said that this beautifully decorated Gakuso (Koto for Gagaku, Japanese traditional music) features the essence of all Koto decorating techniques in Edo (Tokugawa) period. Furthermore, the elaborate designs and techniques applied to this Koto include gold and silver lacquer works of crab-image and gold and silver inlayed works at the instrument's head and tail, and ebony plate and inlayed decoration works of autumnal colour leafs, rocks and flowing water images at its side. That is to say, this Koto is not only beautifully decorated, but also displays several rare and significant characteristics - elaborate crab-image design rarely seen on a Koto, rare gold inlayed work techniques, and side-decorations very rare for a Gakuso during Edo period. The author was appointed a member of the museum's Experts' Appraising Committee when the museum purchased this Koto in January 1991. And at the time, from the above reasons, the author presumed that there exists special reasoning regarding the making of this Koto, but the details remained uncovered. However, Professor Mitsumasa Yamamoto of the museum reported at the committee that there is a short description on the Koto Yamashitamizu owned by the Shogunate in Tankai (1776- 1795) by Tsumura-Souan. ###Then a while later, by coincidence, the author discovered descriptions on the Koto Yamashitamizu derived from Kino-Tsurayuki's waka (Japanese traditional short poems) entitled Yamashitamizu, in Mimibukuro (1781-1815) by Negishi-Morinobu, Ichiwa-Ichigen (1779-1820) by Ohta-Nanpo, and archive documents (1975) by Imaizumi-Chiaki (a member of Saga feudal clan, and also the traditionist of Tsukushi-Goto). By analyzing and organizing the contents of these descriptions, and studying over the matter together with the existing Koto Yamashitamizu that was owned by the Kishu-Tokugawa House in the old times, it was ascertained that during the Edo period, there existed at least three Yamashitamizu Kotos in relation to the same one tradition. ###The following assumption may be made on the first Koto - It was brought along with Kazuko, the daughter of the second Tokugawa Shogun, Hidetada, when she married to become Chugu (Empress) of Emperor Gomizunoh in 1620. Later, it was given by Kazuko to the daughter (a Princess) of Fushiminomiya Sadakiyo, when the Princess married the fourth Tokugawa Shogun, Ietsuna. Thus it was again brought to Edo with her. However, it's whereabout was lost when the Princess passed away in 1676. Then at around 1712, it was found in an antique ware shop in Ueno. Kuroda-Naokuni, who later became a Roju (Shogunate's Council of Elders), purchased the Koto from the shop-it is uncertain whether he knew about its background history - , repaired it, and seeing its outstanding beauty, presented it to the eighth Tokugawa Shogun, Yoshimune. Thus the Koto was restored to the Shogunate, and presumably owned by the wife of the tenth Tokugawa Shogun, Ieharu, at around 1771 . ###The second Koto was made by the Kishu-Tokugawa House in 1788, in imitation of the above masterpiece Koto handed down in the Shogunate. The Koto was then made a family treasure. ###The third Koto is said to be Kino-Tsurayuki's Yamashitamizu Koto that Imaizumi-Chiaki saw at the antique ware shop in 1875. However, after analyzing the observational reports by Chiaki, a presumption is derived, that it is unlikely that this Koto is the traditional instruments handed down in the Shogunate or the Kishu-Tokugawa House.###This paper consists of the study leading to the above conclusion, a research report on the Koto Yamashitamizu owned by the Kishu-Tokugawa House in the old times now stored at the National Museum of Japanese History - the report was re-examined in order to complete this article - , a Japanese translation of lchiwa-Ichigen originally written in classical-Chinese, and a reproduction of Imaizumi-Chiaki's record archives, etc.
1 0 0 0 OA ヴィシー政権下におけるアニメーションの制度化
- 著者
- 雪村 まゆみ
- 出版者
- 日仏社会学会
- 雑誌
- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.65-84, 2011-03-31 (Released:2017-06-09)
Le gouvernement de Vichy a financierement aide les producteurs des films d'animation. Afin de maintenir une autonomie menacee par la presence des Nazis, le gouvernement de Vichy a eu l'idee de promouvoir la collaboration plus poussee avec les colonies francaises. On voit bien, dans certains films d'animation comme "la Nuit enchantee", l'exemple de cette collaboration ; un petit francais essaie de chasser un monstre geant qui symbolise les Allies. C'est ainsi que par le recours au film d'animation, le regime de Vichy a essaye de montrer au grand public son ideal qui devrait masquer l'incertitude a laquelle il s'affrontait dans la mesure ou le film d'animation a ete considere comme un moyen d'expression pertinent pour decrire le changement provoque par la guerre ou l'invasion violente. Cet article a pour objectif de montrer pourquoi le gouvernement de Vichy a choisi le film d'animation par rapport a la position dans laquelle il se trouvait.
1 0 0 0 OA 慢性期めまい平衡障害患者における転倒リスクの評価 ~複数の評価ツールによる検討~
- 著者
- 荻原 啓文 加茂 智彦 田中 亮造 加藤 巧 遠藤 まゆみ 角田 玲子 伏木 宏彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.218-229, 2020-08-31 (Released:2020-10-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 5
This study was aimed at (1) determining the risk of falls in patients with chronic dizziness/vertigo using the Timed Up and Go test (TUG), Dynamic Gait Index (DGI), Functional Gait Assessment (FGA), and Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale, and (2) investigating the correlations and agreements among the measurements results of assessment by the aforementioned methods in these patients. A total of 52 patients with dizziness/vertigo were included in the study, and the risk of falls in these patients was evaluated by the TUG, DGI, FGA, and ABC scale. We analyzed the correlations and agreements in the fall risk assessed by the aforementioned methods using Spearman's rank correlation and kappa statistics. Of the 52 patients, 11 (21.2%), 26 (50%), 29 (55.8%), and 18 (34.6%) patients were assessed as being at a risk of falls by the TUG, DGI, FGA, and ABC scale, respectively. The results of the assessments by the above methods showed significant good correlations and agreement. However, the kappa coefficients for some results were low (TUG-DGI: k=0.423, TUG-FGA: k=0.351, TUG-ABC scale: k=0.299, DGI-FGA: k=0.885, DGI-ABC scale: k=0.385, and FGA-ABC scale: k=0.294). Risk factors for falls in patients with dizziness and vertigo include disturbances of psychological balance and gait. Multiple methods to assess the fall risk may yield more accurate results than assessment by one method alone.
1 0 0 0 日仏社会学会奨励賞を受賞して(受賞の言葉,日仏社会学会奨励賞)
- 著者
- 雪村 まゆみ
- 出版者
- 日仏社会学会
- 雑誌
- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.87-89, 2013